
ブツ群(2010s best music) 前
周りに感化されつつも着手しない悪癖を克服すべく書いた。いわゆるベストアルバム記事であり回顧録である。選ぶ基準はよく再生していた、ただ一点のみ。2019年は記憶が新しすぎて何も思い浮かばないため未選。以下、年を遡りながら書いている。
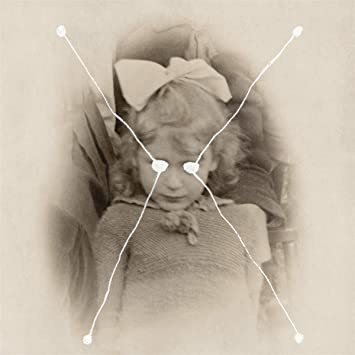
Current 93 / The Lights Leaving Us All (2018)
リリース日に開かれたロンドン公演を観に行ったこともあり、バンドの10年代の作品では最も印象深い一枚となった。スティーヴン・ステイプルトン(Nurse With Wound)によるサイケデリックなミックスが顕著だった時期とは違い、シンガーとしてのD.Tibetの魅力を引き出すための徹底したバッキングが冴える。その瞬間に燃え尽きるノイズを封じ、歌い手から別の歌い手へと受け継がれるフォークを選んだことが正解であると改めて示した作品だった。書物がそうであるように、音楽と歌も永い時間にわたって残され、継がれていくものなのだ。10年代という括りも大して意味をなさなくなるだろう。先のロンドン公演時、開場する前に道でTibetとすれ違ったことも良い思い出だ。

Mary Ocher / The West Against The People (2017)
ベルリン在住、音楽だけでなく映像やZINEでもメッセージを放ち続けるMaryの快作。ヴォルフガング・ミュラー(Die Tödliche Doris)や、本作には不参加だがフェリックス・クビンらと組むところが彼の地のアーティストらしい。音楽はコスモポリタン的背景もうかがわせる折衷タイプで、レコメン系と称するのが一番早いかな。ゼノフォビアを主題にした歌など、自分ができる抵抗に取り組み続ける姿勢にこそ刺激を受ける。2019年に対面できたことは大きかった。
Sunshower / Arcadia (2017)
bandcampで見つけた一枚で、このEP以外の詳細はまったく知らない。所謂和製アンビエント再評価に感化されてのものか、元来こうしたテイストなのかもわからない。一期一会という感じが気に入っていて、今も詳細をあえて調べないようにしている。大貫妙子と関係はないはずだ。
シンセでひたすらノスタルジックなコードを響かせ続ける姿勢は強引さすら感じるのだが、嫌いになれないのは自分もゼロレベルでこうした音を求めていたということかな。

Salami Rose Joe Louis / Son of a Sauce! (2016)
カシオの純朴な音色と複雑なビートが繰り出す世界はチル時々不思議の『MOTHER』シリーズ的世界観。ビーフハートが好きという事実もあり、The Residentsとそう遠くない、枝分かれした西海岸サイケの未来の一つに思えて仕方ない。ビートがより先鋭的になる次作以降も良いが、やっぱりデモテープ感が愛らしい本作が一番。クロージング「hookie wookie」は泣けるぜ。拙著でインタビューしているので、よかったら読んでほしい。

Matt Elliott / The Calm Before (2016)
歌メロ主軸、低音の利いた声など共通点を持つレナード・コーエンの遺作と迷ったが、こちらを載せた。The Third Eye Foundation名義やCOILトリビュート『The Dark Age of Love』でも見せていた進歩的頽廃は健在だ。2000年代の作品よりも簡潔になっているのはTEFの反動なのか。直系とは言い難いかもしれないが、自分にとってはCOILから得た情動を蘇らせた数少ない音楽の作り手だ。
Michael Arthur Holloway / Guilt Noir (2016)
ムード重視でノアールのサントラ風ジャズ。40年くらい前に出てても違和感がないほどだ。保守的といえばそうだし、時流と距離を置くために足掻いているようにも見える。
2016年はbandcampやApple Musicなどで「最新の音楽」を探してみたが、結局リリース日が新しいという入り口しか通れなかった。借り物競争的に音楽を聴くのは大変なのだ。同年は不意の出会いと縁のようなものを大事にしようと改めて確認できた年であり、この作品は指針的存在となっていた。

GRIM / MAHA (2015)
GRIMは作品すべてに独自の不文律が通底している。小説における文体、個人と対峙した時のムードが恋しくなると同じで、音源単位で評価してもGRIMという体験へと帰結する。本作は発売から少し遅れて手に入れたものだったか、2013年作『Love Song』と2012年の小長谷淳氏ソロ『Organ』に匹敵する感嘆の一枚だった。強固なノイズと神聖さを携えたメロディがもたらすコントラストは、人の持つ原始的な欲求が相対ではなくつがいとして存在していることを突きつける。ロジックで説明づける前の本能的な反応、理解できないが笑えてしまう生理反応を経た時、自分がまだ死んでいなかったと安堵する。解読不能だがメッセージであろう叫びが描く原始の曼荼羅は、音楽で世界を変えられずとも、変わり続ける世界に屈しない音楽と場があることを証明している。

Robert Haigh / The Silence of Ghosts (2015)
2015年内だけでも300回は再生していたと思う。ロバート・ヘイによるピアノ・ミュージックで、Sirenから出していた過去数枚のアルバムと同じ趣向、同じメンタリティだが、一番記憶に残るのはこれだ。Andrew Chalkとの差異があるならば、在りし日の思い出に耽る余韻さえないところだろうか。河原で石を拾っては各々の形を見比べるような、そんな無為のひと時が音で表されている。吉村弘などの和製アンビエント再評価に鈍感だったのは、結局ヘイのような作家がいたからかもしれない。

Neon Indian / Vega INTL. Night School (2015)
ちょうど『ホットラインマイアミ2』を吐くほど(マジで)遊んでいた時期と重なったこともあり、音にも目にもレトロウェイヴに浸る時期があった。本作はvaporwaveとSuicideの出会いといえばいいのか、ボイド・ライスとの縁からもうかがえる60年代米国ひいてはワイルドサイド(とチャイナタウン)への憧憬が、16bitビデオゲームと80sフィクションに抱くノスタルジアと混ざり合う。見知らぬ過去と見知った過去のコラージュがもたらす、現代版サイケデリアとでも呼ぶべきだろうか。

Hair Stylistics / Dynamic Hate (2013)
2012~3年は今以上に金がなく精神的にもどん底だったので、見聞きしていたもの含めて思い出したくないのが本音である。それほどに強くこびりついている悔恨または怨念と同化する『Dynamic Hate』は、痛みを癒やすことで、その傷の存在を担保する絶望のウェザリングだ。Raimeのようなインダストリアル派とは対照に、湿っぽく有機的なビートも新鮮に聞こえた記憶がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?


