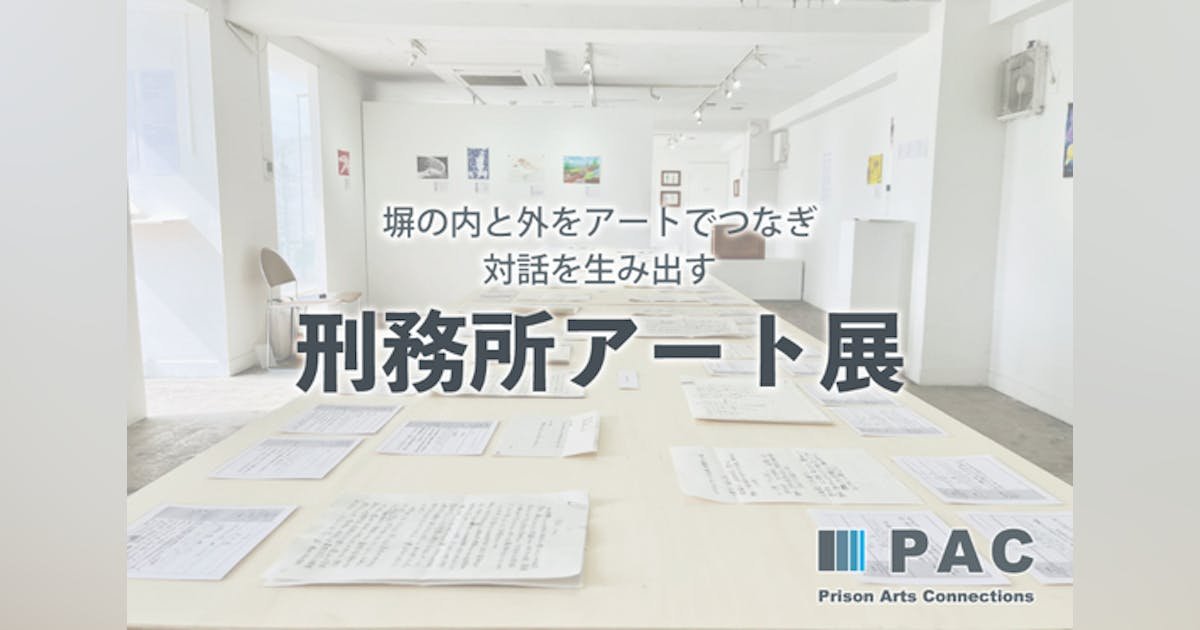暴力の連鎖ではなく、修復、回復に向かおうとする場を-「刑務所アート展」のクラウドファンディングに寄せて
はじめに
芸術家の父のもとに育ち、アートが幼いころから身近にありました。成長するにつれて、だれかを傷つけたりだれかに傷つけられたりすることがあり、少しずつ身近な加害や被害について考えるようになりました。だから刑務所もアートも、わたしの日常からそう遠くない地続きのものとしてあって、それなのに刑務所はわたしたち塀の外にいる人間からすると通常あまりにも遠い隔たったところです。
しかし塀の中にいる人たちも当然ながら生身の肉体と感情をもった人間です。人は人との対話を必要とします。他者とのコミュニケーションがあってこそ、感じ考え、自分を掘り下げ、他者を知り社会を知り、回復に向かっていったり日々を生きていったりすることができます。
そんな思いをもって、12月1日からクラウドファンディング「刑務所の内と外をつなぐ対話を生み出す『刑務所アート展』開催にご支援ください!」を実施しています。
このプロジェクトは、塀の内と外とで断絶されたコミュニケーションの回路をつなぎ直す営みだとわたしは考えています。その回路として、だれしもの側にアートがあったなら。たとえ塀の中にいて使える画材が限られていても。そうした制約の中から、いったいどんな作品が生まれてくるのでしょうか。それを通してわたしたちはどのようなコミュニケーションができるでしょうか。
「加害者の支援って必要なの?」
とはいえ、「加害者の支援って必要なの?」というのがみなさんの率直な感想かもしれません。罪を犯して被害者を傷つけた人たちなのに、と。
わたしはこの領域(加害者支援)に仕事としてかかわるようになってから1年ほどが経ちますが、正直に言って、葛藤の連続でした。ではなぜわたしがかかわり続けているのか。
加害と被害のはざまで揺れ、「このまま加害者支援を続けていいものか」と悩んでいたとき、このプロジェクトの呼びかけ人である風間勇助さんが、
「ぼくはこの領域に携わるようになってから、加害と被害という二項対立ではなく、『だれにどのような回復が必要か』という視点で考えるようになりました」
という言葉をかけてくださいました。暴力の連鎖ではなく、修復、回復に向かおうとする場を、小さくてもつくり続けたいと願う風間さんを、わたしは応援しています。
さらに言えるのは、加害と被害は連鎖していて、加害者のうち元被害者である人は少なくないこと、そして被害者を増やさないためにも加害者の回復が必要だということです。
そしてわたしは、加害は他人事ではないと考えています。わたしたちは日常のなかでちょっとずつ人を傷つけたり人に傷つけられたりして生きています。たまたま運がよくて刑務所に入らず済んでいるだけだと思うのです。このプロジェクトが、みなさんとわたしたちと、対話する契機となることを願っています。
「たまたま運がよくて刑務所に入らず済んでいるだけ」とは?
先ほどわたしは、「わたしたちは日常のなかでちょっとずつ人を傷つけたり人に傷つけられたりして生きています。たまたま運がよくて刑務所に入らず済んでいるだけだと思うのです」と書きました。「それってほんとうに?」「どういうこと?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
このnoteを普段から読んでくださっている方はご存知だと思いますが、私は持病のために当時4歳の息子を児童養護施設に預かってもらっていたことがあります。そのとき児童養護施設で育つ子どもたちについて学んだり、実際に児童養護施設で育った人の話を聞いたりしました。それを通して、社会にはさまざまな環境に生まれ育つ子どもたちがいることをリアルに想像することができました。
大人から信用してもらうことができずに社会に不信感を持っていたずらを繰り返すうちに次第に法に触れる行動を起こすようになった人、子どものときの養育環境によって社会における善悪の基準が育たず、それが犯罪だと知らないまま罪を犯してしまった人、育ててくれる保護者がおらず施設でもうまくやれなくて友だちの家を転々として思春期を過ごしていた人。ほんとうに、さまざまな人たちがいました。
その人たちが罪を犯してしまったとして、それははたしてその人だけの責任なのでしょうか。私にはその人たちと息子が違う人間だとは到底思えませんでした。もし環境が違えば、私の息子だって、私自身だって、罪を犯したかもしれません。
加害者にならずに済むのであればそれに越したことはありませんが、もしも加害者になってしまったとき、再び被害者を生んでしまわないためにも、その人自身が回復して生きていく必要があります。たったひとり孤立していては、それはむつかしく、人とのつながりが必要となります。
「刑務所アート展」は、アートを通して人とのつながりを感じてもらい、コミュニケーションの回路をつくろうとする試みです。
アートは再犯率を低下させる?
この項では、クラウドファンディングページ本文からの引用をご紹介したいと思います。
アメリカやヨーロッパでは、刑務所でアート・プログラムを行うことは珍しくなく、専門的な非営利組織も多くあります。
かの有名な刑務所映画の名作『ショーシャンクの空に』の主役であった俳優のティム・ロビンスは、実際の刑務所で演劇のワークショップを行う活動 「Actors’ Gang Prison Project」を行っています。再犯率の低下や違反行為の減少などの効果も指摘されています。
※参考記事:”名作「ショーシャンクの空に」には続きがあった!? ティム・ロビンスが仕掛ける社会貢献、刑務所ドラマの第二章とは?”(一般社団法人インプロ即興コメディ協会)
アートプログラムが、再犯を防ぐ、犯罪からの離脱を促す効果があるといった実証研究は多く存在します。私も研究を進める中においては、刑務所にアートを持ち込む理由として、この「再犯防止」というのが説得材料になるだろうと思います。
刑務作業が必須でなくなる「新たな拘禁刑」が議論されている現在、日本でもアート・プログラムが教育として取り組まれる可能性はゼロではありません。実際、少年院においては情操教育として表現活動が行われる例は少なくありません。
第1回刑務所アート展へ訪れた被害者遺族からの感想
受刑者たちの表現が、被害者の方を再び傷つけるのではないか。そのことは、社会からも起きうる反応であり、私も常に「こんな展覧会をやっても大丈夫なのかな」と不安を感じながら、考えてきました。
今回のクラウドファンディングの呼びかけ人・風間勇助さんは、本文に上記のように書いています。実際に第1回刑務所アート展へ足をお運びくださった被害者遺族の方からの感想を本文から抜粋してご紹介します。
「自分も事故の直後は許せない気持ちでいっぱいでした。それでも時間が経ってくると少し変わってくる思いもあって...。加害者の相手はまだ刑務所にいるのですが、最近会ってみたいという気持ちが少しあったりします。他の家族は会うなんてまだ考えられない状況だと思うのですが、加害者や犯罪をした人がどういう気持ちでいるのか知りたくて展示に来てみて、たくさんいろんなものを知ることができて、本当に貴重な展示でした。」
また風間さんは加害者支援に悩みながら携わる中で、原田正治さんに出会いました。
原田さんは、自身の弟さんを保険金目当てで殺害された被害者ご遺族の方です。加害者である長谷川敏彦さんと面会した経験を著書『弟を殺した彼と、僕。』(ポプラ社、2004年)に綴っています。長谷川敏彦さんが生前に原田さんに向けて送っていた絵を、この著書に書かれていたことや原田さんへのインタビューをもとに、前回の刑務所アート展において展示させてもらいました。
加害者との対話を望む被害者遺族の方もいる。それは、事件直後には難しいことでも、時間が経ってから、変わってくる思いや考えがある(実際、原田さんが長谷川さんに会うことになったのは事件から10年後です)。これは、司法の仕組みの中では扱うことのできないものです。
またそれは、マスコミが事件直後の過熱報道の中で固定化してしまう被害者遺族像とも異なります。そもそも、事件は個別に大きく異なるものであり、一括りにはできないものです。
表現やアートといった活動は、個別に異なるものに目を向け、長い時間の中で変わる思いや考えに丁寧に寄り添い、マスコミとは異なる方法で社会が一緒に向き合う場をもたらすと考えます。
クラウドファンディングは、問いを投げ、対話し、輪を広げていくプロセス
わたしは加害者支援の領域に広報という形でかかわるようになって1年ほどが経ちますが、被害者がいる、傷ついた人がいる、という歴然たる事実にひるんでしまいそうになるときもあります。
被害当事者の中には、加害者を支援すること、アートを介して加害者の回復をと願う活動に不快感や嫌悪感を覚える人もたくさんいることだろうと思います。そういう方たちを刺激してしまうことが怖くて、クラウドファンディングの話が出たとき、ひるみそうになりましたし、ひとり悩みました。
しかし加害者にもまた傷つきがあること(加害と被害が連鎖していること)、加害や被害が他人事とは思えないこと。そして発起人の風間勇助さんの使う「回復」という言葉が心に引っかかり続けて、加害や被害という二項対立ではなく、回復という地平にたって活動を続けていくことを心に決めました。
クラウドファンディング公開後2日間は特に怖かったです。もちろんすぐに支援してくださった方もいらっしゃいましたが、もし支援金が集まらないとしたらそれは加害者支援に理解がない証左だと捉えて、勝手に傷ついたりもしました。
だけれど次第に、このクラウドファンディングを実施すること自体が、問いを投げ、対話し、輪を広げていくプロセスなのだと気づきました。
中にはご自身が被害当事者の立場でありながら、複雑な思いを抱えて、それでもなおこのプロジェクトの趣旨と意義に理解を示して支援くださる方もいらっしゃいます。その方の知性のたまもので、心から尊敬しますし、ありがたいですし、この思いをしかと受け止めて一日一日やっていかねば、と思っています。
2024年1月15日まで、第2回「刑務所アート展」展示会の開催および、カタログやグッズ、Webギャラリー等のコミュニケーション媒体の制作、持続可能な運営体制づくりの資金を集めるため、目標250万円のクラウドファンディングを実施しています。ぜひ、プロジェクトページをご覧になって、ご支援ください。どうぞよろしくお願いいたします。
Prison Arts Connections 運営メンバー 黒木萌
いただいたサポート費はよい文章を書くために使わせていただきます!