
2-16 ブレてもいい、悩んでも、迷ってもいい。本当のことが知りたい。
博士 つまり忖度で守られてきた〈会の根本体制〉が危機に瀕している、と。
チェ もちろん依然として忠実に疑問を持たず、あるいはナチュラルに思考に蓋をして、忖度を体現しつづける会員も少なくありません。特に後期青年部世代から、壮年婦人部世代はそうです。「学会にとって、都合の悪いことは知ってはならないし、広めてもならない」と表向きは三猿(さんざる)を決め込んでいますが、処分された全国幹部の醜聞(しゅうぶん)や、現役の執行部メンバーがひた隠しにする事案まで、かなりの人が知っています。都市伝説のように聞いた人もいれば、リアルな情報をつかんでいる人もいます。
博士 チェ・ゲバラ似の男さんも、そのひとりではないですか。
チェ 様々な情報が入ってはきますが公開できる情報は、限られています。正直な話、学会員さんが聞いて喜ぶようなことは多くありませんので。学会の現状を正視して、組織の今後や〈自分の広宣流布〉を考えるきっかけになるであろうこと、その中でも確度の高いウラがとれたことだけを、言葉を選んで伝えています。
博士 知ることも、それを伝えることも闘争なんですね。
チェ 闘争です。「知らずにいれば良かった」と思うことだらけです。そういうものにぶち当たるたび、取材・調査・研鑽をして、なるべく余計な忖度を抜いて、考えを形成しています。
博士 お話を聞いていると、本当のことを知ったうえで忖度するのが、いまの組織体質の癌(がん)であると感じます。
チェ いま組織に本当に必要なのは、大本営発表を黙って受け入れる忖度ではなく、心からの敬意です。敬意は〈リアルな責任感〉から生まれます。学会の役職が上だから言うことを聞く。それではただの虚構です。あるべきは〈リアルな責任感〉を持つ人が〈リアルな責任感〉を持っている人を尊敬すること。〈リアルな責任感〉について池田先生の指導を引きます。
「自分が一人で全責任を担おうとすれば、協力してくれる人がいることのありがたさが、身に染みてわかるものだ。そうなれば、決して人に対して傲慢にはなれないはずである」〈新人間革命4巻 凱旋の章〉
近年、幹部に上がるのは結果を出す力がある人間、ビジョンや考えをしっかり持っている人間より、より上の幹部が扱いやすい従順な人間になってきています。だから何も聞かず、察して動く人が幹部になり、この体質が強化されてきました。
従順という性質は逆らわない、組織を動かしやすいという点では長所です。しかし事の正邪や善悪を考えたり、また師匠の意図(こころ)を深く汲んでいくという点においては短所になりかねません。大切なのは適材適所のバランスです。「やっぱり、あの人は凄いな」と率直に抱くのが敬意、それを生み出すのが価値創造です。そのためには、リアルな情報が必要なんです。
博士 21世紀最大の歴史学者・梅原猛は「自由とか自己決定ということは、たいていの人間には重荷なのである。そういうときにある絶対者から『これはこうだから、こうしろ』と命じられれば、人間は容易に従うものである。そういう社会においては、神のようにまつりあげられている人がいる」〈将たるゆえん〉と言っています。池田SGI会長は絶対者と言って差し支えない存在(カリスマ)であったことに議論の余地はありません。
その人がいなくなった、出てこなくなった。それは大きな喪失感でしょうし、喪失したと認めることすら困難でしょう。かかる状況においては、いまだにトップダウンで活動する方が、安心できる人も少ないと考えるのが自然です。
チェ・ゲバラ似の男さんの考えは、学会員の皆さんに理解されるのでしょうか。
チェ どうでしょう。理解されるかどうかは、考えていません。私の話をどう解釈するかは、各人の自由です。理解されないとしても、広宣流布員(みんな)が何かを考えるきっかけになればじゅうぶん。御の字です。
私自身も、多くの友人との対話、また本部職員、除名された元会員、現役の幹部への取材をするなかでショックを受けたり落胆したり、何度も考えがぶれました。「こんなことが許されて良いのか」と怒りに震え、おかしいことを白日(はくじつ)に晒してやろうと息巻いた時もありました。「除名されるのではないか」とガタガタ怯えた夜もあります。そして「これからは、こういう風に活動するのが良いのではないか」と考えては、既にそのような活動をはじめている人たちに取材もしました。その中で、少しずつ希望を見いだしてきています。
それらを、22世紀最大の歴史学者である博士に対話という形でぶつけて、創価学会だけでなく、人類と宗教の歴史という大きな観点から見て、〈現在(いま)〉はどのようなフェーズであるのか、その価値観を磨きたいのです。
博士 光栄です。私も歴史学をひもときながら、忖度無しで疑問点をぶつけます。
歴史とは、「そもそも、何であったのか」を研鑽し「最後は、どうなるのか」を考える学問です。
1930年に創立された創価学会は91年の歴史があり、日本の新宗教では伝統的な部類に入りますが、世界宗教としては草創期であると言えます。現在、絶対的・永遠と思われていることも、時代や価値観の移り変わり伴い、解釈や意味合いが変わっていくことは間違いありません。まして現代の情報交換のスピード、テクノロジーによる人の暮らしぶりの変容を考えれば、ほんの3~5年先、あるいは数ヶ月でも大きく変わっていると考える方が自然でしょう。
チェ 同感です。30年前であれば10年かかった変化が、今は1年で起こってもまったく不思議ではありません。
〈変わっていくもの・変わらなければいけないもの〉と、〈変わらないもの・変えてはならないもの〉の見極めを、この対話で成し遂げたいと考えています。引き続き宜しくお願いします。
(つづく)
ここから先は
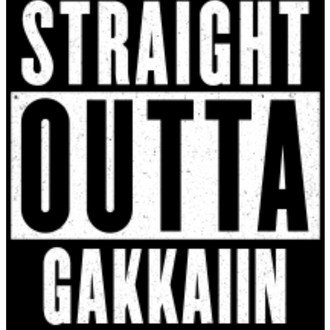
歓喜を取り戻す創価学会論 ストレイト・アウタ・学会員
学会活動が、おもんなくなった(異和を感じた)人が、学会活動をおもろくしていくための本。有料だけど、無料部分だけ読んでも学会員には有益と自負…
なにぶん、いい加減なことは書けないテーマゆえ、記事を書くための取材、調査、また構想から執筆、編集までかなりお金と時間と労力をかけております。 サポート、記事、マガジンの購入は本当に助かります。いただいたお志で、更に精度の高い文体を提供できます。本当にありがとうございます。
