
狂犬病ワクチンはどうなの? その6 … 世界統一基準に沿わない(?)法的接種義務
前回、狂犬病の場合はウイルスに対する抗体があっても、病気の感染から守られているとは言えないとの主張をご紹介しました。アメリカ獣医師会は、この根拠として4本の論文を提示しています。その中の最も新しい物を見てみました。
抗体検査の手法に疑義を唱える勢力の存在
ジョージワシントン大学(GWU)のジェフリー・ベソニー教授らが2010年に発表した「狂犬病の抗体について」と言う論文がそれです。これは、アメリカ国立医学図書館が保有する論文を「PubMed(パブメド)」という国立衛生研究所が運用する無料検索エンジンで探してまとめたものです。対象となった論文は、1975年から2008年までに発表されたものだそうです。

結論として、狂犬病ウイルスから体を守ることにおいては、抗体が中心的な役割を担うことは認めています。ただし、生体内で実際に生じている免疫反応はとても複雑で、現在の抗体検査で分るのは「多くの場合、病気を防ぐしくみの部分的なものに限定される」としています。
ベソニー教授はまた、WHO(世界保健機構)などが認めている抗体検査の方法(RFFIT法:迅速蛍光焦点抑制試験法)が抗体価を計る「Gold Standard (黄金律)*」としながらも、命に関わるリスクがある狂犬病に関する検査と評価の方法には慎重であるべきだとしています。 (* 診断や評価の精度が高いものとして広く容認された手法)
余談になりますが…、
本当に余談ですが…、
GWUは政治の中心である首都・ワシントンDCにある大学です。

場所柄、政治家や官僚などの経験者が教鞭をふるっていることでも知られています。ロビー活動などに関する知見も豊かでしょう。

犬の狂犬病ウイルスに対する免疫というテーマが、獣医学で世界的に有名な、例えばカリフォルニア大学デービス校などからでなく、GWUから出されている事実には興味を感じます。
興味を感じます…
あくまで、「興味」ですが
世界中で採用されているWHO基準
GWUが疑問視する抗体検査・評価手法ですが、何度もご紹介したようにWHOは有効としています。狂犬病ウイルスに対する抗体価を測定し、0.5 IU/mL(IU: 国際単位)以上あれば狂犬病ワクチン接種後の適切な免疫応答と判断できるとしています。この場合の検査方法がRFFIT法です。

べソニー教授らが主張するまでもなく、免疫は「細胞免疫」や「免疫記憶」など抗体以外の働きも複雑に関わっているのは知られています。ですが、RFFIT法での抗体価測定は人間に接種する狂犬病ワクチンの認証においても認められています。新薬の効果やリスクを調べる治験では、被験者(人間)に狂犬病ワクチンを接種し、その後、採血します。RFFIT法による抗体検査で0.5IU/mLの基準を満たせば、そのワクチンには予防効果があると判断されます。
最も慎重に判断されているはずの人間の場合も、狂犬病ウイルスに対する抗体検査は確立されていると考えられると思うのですが…
日本もWHO基準を使用
日本も同様です。世界的な製薬会社の日本法人であるグラクソ・スミスクライン株式会社が2019年に人間用の狂犬病ワクチン「ラビピュール」の製造販売承認を厚生労働省から取得しました。その際も、有効性などに関して行った試験は全てこのRFFIT法による抗体検査で評価されています。

「WHOはRFFIT法にて狂犬病ウイルスに対する中和抗体価を測定し、0.5IU/mL以上あれば狂犬病ワクチン接種後の適切な免疫応答レベルとしている。(中略)狂犬病ウイルスに対する中和抗体価が<0.5 IU/mLに減少した場合のみ、追加免疫が推奨される(原文ママ)」 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構が公表している「乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチンラビピュール筋注用 臨床に関する概括評価」より)
政治や行政で有名なGWU
「世界保健機構」であるWHO
2つの権威ある、でも、主な活動分野がまったく違う組織の判断が一致していない…
賛否両論を検証したうえで
グラクソ社の資料は人間に接種する狂犬病ワクチンに関するものですが、ワクチンの有効性と再接種の必要性は抗体検査によって判断するのが世界の常識のようです。詳細を読み込んでいませんが、新型コロナ用ワクチン評価でも、常に「(中和)抗体価」が効果測定に使われています。
確かにGWUのベソニー教授が主張するように、命に関わる狂犬病の場合はその効果の検証には慎重な判断が必要だとは思います。でも、以前ご紹介したウィスコンシン大学のシュルツ教授らによる論文は、実際に犬を使って感染するかどうかを確認した「攻撃試験」の結果に基づくものです。
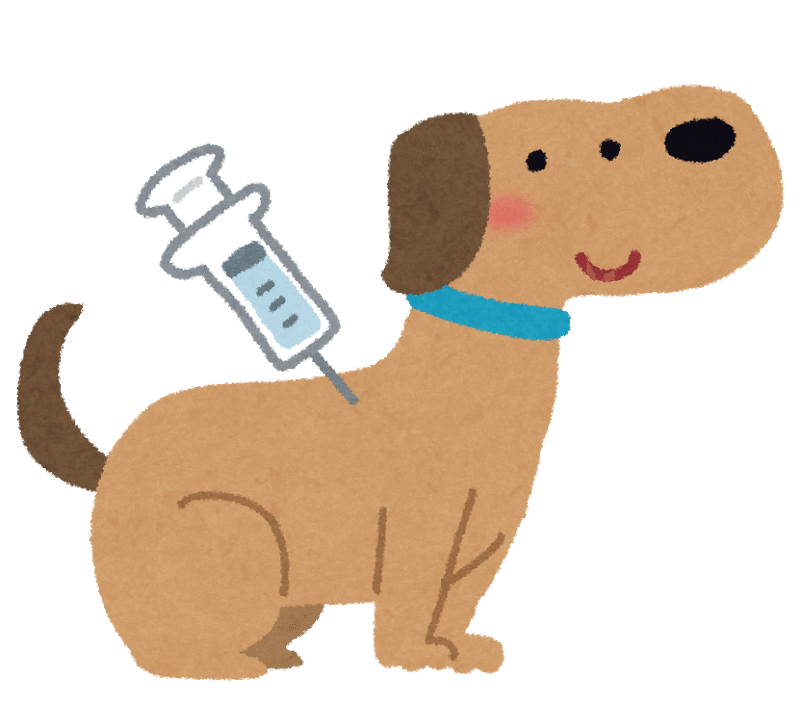
ラボ(研究室)などの実験環境(in vitro)だけでなく、より重要とされている生体試験(in vivo)でも検証された結果です。一方、ベソニー教授の(極)慎重論は文献リビュー(literature review)に留まります。

自然科学分野では、in vitro <<< in vivoが常識だそうです。文献レビューのみでin vivoベースの論文と議論できるのかな???
この辺は、今後お勉強したいと思います。

ここから何を感じるか(ひょっとしたら何も感じないか)は人それぞれだとは思いますが…
最後に1つ、とても興味深い噂を
ということで、これまで以下のポイントについてご紹介してきました:
• 狂犬病の怖さ
• 予防の大切さ
• 狂犬病予防法の功績
• 日本と北米の法規制
• 必要かつ最低限にとどめるべきワクチン接種
• 抗体検査の有効性についての主張
• 抗体検査への反対意見
次回はもう1つ、北米で言われている興味深い話を1つご紹介します。
とても、興味深いです

