
20200316 アカデミスト学会に参加してきました(ヒマラボ賞も提供したよ)
ヒマラボのモリタです。
楽しみにしていました3月14日のアカデミスト学会。オンラインでのトライでしたが、最高に面白かったです。
最初の発表が「超新星爆発」からですもんね。異分野から集結してるとはいえ、斜め上。
物理系のパートから始まって、これは難解かなと思っていたらすごくわかりやすい。生物系パートはより具体的な未来やロマンを感じさせ、社会実装パートは、実装へのトライが実際に触れてみたいという思いを呼び起こさせました。人と人との関係パートは、ヒトや社会に迫る研究に触れ、物理や生物系との対比で好奇心を大きく揺さぶられました。
アカリクさんのnoteにも振り返りが(体制とコメントすごい!)
全てにおいてですが、アウトリーチの修行でも積まれているのかと思うくらい皆さん発表がわかりやすかったですね。専門的な学会とはまた別の資料を作られたという方も多くいらっしゃいましたし、academistでのクラウドファンディングにトライされた方は伝え方の洗練もされていたのでしょうか。
ちょうど良い平易さの発表が多く、これは高校生にも聞いて欲しかったです。アメリカやインドネシアなど海外にいる研究者の話も聴けるチャンスでした。
(尾花先生のご発表なんかはSSHなんかの高校だとすごくいいような。泥臭い実験のトライも併せて伝わると高校生は勇気と希望を抱きそうです)
当日の様子はToghetterからも。
(先ほど見ると伊藤先生がTwitterで後から質問に全部返されていたり。ハッシュタグも引き続き追っかけてみてください)
ヒマラボ賞
アカリク賞、Beyond Next Ventures賞と協賛企業賞がありましたが、ヒマラボからは、石北直之先生の「プチイノベーション『聴診アップ』」をヒマラボ賞に選出しました。
いやはや、めちゃくちゃ悩みました。
今回は、着想から成果までのプロセスにポイントをおきました。
ヒマラボでは、学術機関や研究所に所属していない方が個人的な好奇心や課題感からテーマを持ち寄って研究的な活動に臨まれています。またその内容をどんどんアウトプットして形にしていくことも推奨しています。
今回石北先生の聴診アップの研究プロセスは、声にならない患者の声をより明確にしたいという思いからスタートし、実践的な開発プロセスの中にも研究的な姿勢を絶やさず、アウトプットを残されていました。実際にモノや製品を作り上げたということを評価しているのではなく、このプロセスそのものがヒマラボの目指すものとは相似形だなと感じたからです。
スネルの法則に関する御発表をされた大上先生も、プリズムを覗く中で「あれ?この法則って他にも適用できるんだっけ?」という非常に素朴な個人的関心からスタートし、法則自体に疑問を投げかけながらその問いに応えようとする。ちょっとした疑問をどんどん研究的に深めていく姿勢も素敵で。個人的な好奇心が爆発していた泉先生、「大学を辞めてフリーの研究者でいきます」という言葉から発表が始まった伊藤先生、「すべては知的好奇心からです」と言い切った土田先生もシビれました。ヒマラボの理念や方向性から見た際に合致する研究が多く、本当に本当に悩みました(2回目)。
サイエンスDJ
最後に、今回のアカデミスト学会での体験は何に近いかなと考えたときにラジオかなあと。
ゲストが語り、Slidoやチャットに来たコメントを選んでファシリテーターの道林さんが振っていく様子。これはまるで研究者をゲストに招いて、視聴者からのお便りを片手に番組を進めるラジオのDJのよう。サイエンスDJ道林さんがそこにいました。
ラジオのメタファーを踏まえるとどんなことが考えられそうでしょうか。
・ 少しBGMがあっても良い?
・ファシリテーターは複数でもよい?
・ファシリテーターにファンがつく?
・休憩時間に協賛企業のCMが入ってもよい?
・早朝や深夜帯にコアなファンがつく?
・事前に何かテーマを提示してコメントやお便りを募集する?(おすすめの学術書など)
・発表の前にファシリテーターと発表者の簡単な対話から始まる?(自分の曲を流す前の簡単なアーティストとの曲紹介の会話など。聞こえてますか確認もできる)
・別学会に参加中の研究者も参加してくる?(ライブ会場から参加するアーティストのように)
・今まさに実験しているところも中継できる?
・いいコメントをする「コメント職人」が現れる?
などなど、いわゆる学会とは異なるものかもしれませんが、オフラインとは異なった楽しむ場を作るヒントがありそうでした。どの程度くだけてしまってもいいのかということはありますが、ヒマラボで実験したい。
オンライン学会はこれからですよね
オンラインということで自宅から参加していました。子どもが隣の部屋にいても大丈夫だったり、モバイル環境でも充分やれたり。(こんな感じで参加していました)
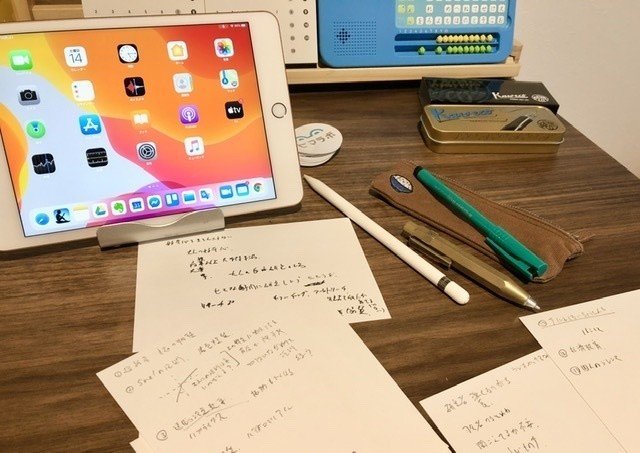
オンラインの学会をオフライン学会のあり様に近づけていくべきかなど、色々な議論はあれど、私はオンラインでどう楽しめるものを作れるかには引き続き力点を置いていきたいです。オンラインでのあるべき姿とはどのようなものか。
ヒマラボのヒントになることも満載で凄く楽しめました。
主催されたアカデミストの皆さま、ご発表&ご参加された皆さま、協賛企業の皆さまに感謝します。最高。
それでは今日もリサーチカルチャーを醸しましょう!
************************************
モリタヤスノブTwitter: @domino613
ヒマラボのホームページ(福岡大学の学生が作ってくれました): https://himalab.jp/
Facebookグループ: https://www.facebook.com/groups/HimaLabo/
*ヒマラボの設立経緯はこちらです
************************************
リサーチカルチャーを醸成する事業資金にあてさせていただきます!よろしければ是非です!
