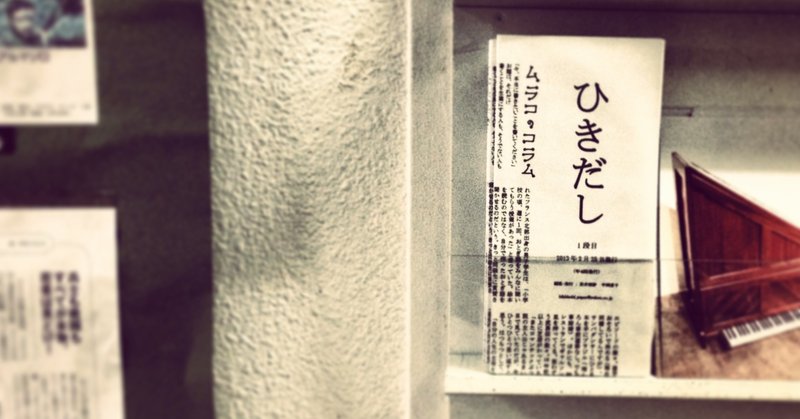
【紙のムラコのコラム】ロマンチックの本質
〈フリーペーパー 1 段目(2013 年 2 月 25 日発行)「ムラコのコラム」の再録。筆者の職業は当時のまま〉
ロマンチックの本質
姜 尚美
昨年の秋、雑誌の取材でフランスを訪れた。かの地へは学生の頃に留学し、その後何度か行き来して、最後に訪れたのは通過のフランがユーロになる直前だった(ユーロ換算電卓付きキーホルダーなるものが配布されていた)から、およそ 10 年ぶりの渡仏である。
そんなひさびさのフランス滞在で、今さらながらに気づいたことがある。留学生の時分にはまったく意識にのぼらなかったのだが、社会人になり、編集・ライター業を生業として多少の年月を重ねた今、あらためてフランスの人々と話してみると、「なんておしゃべりがうまい人たちなんだろう」と感心してしまったのである。
おしゃべりとは言っても、イタリア人(もとい私の知るイタリア人)のようにやたらと言葉数をかせぐタイプをはまた違い、「物語力」があるというか、たった 2、3 センテンスでで気の利いた「お話」に仕上げてくる。
ライターの立場から言えば、これほどありがたいものはない。普通、話し言葉をそのまま原稿にすると間延びして読みづらいので、切ったりつなげたり要約したりに心を砕くわけだが、彼らの場合、聞いた話をそのまま文字にしても、実におもしろく「読ませる」のである(具体的にはクウネルと言う雑誌の 2013 年 1 月号掲載『街のじまんは、4 つの耳をもつビスケット』をご覧ください)。
彼らの「物語力」はいったいどこで養われるのか。
そういえば留学時代、何か面白いことが起こると、決まって物真似まじりで説明してくれたフランス北部出身の男子学生は、「小学校の頃、週に 1 回、おとぎ話をみんなに聞いてもらう授業があった」と言っていた。絵本を読むのではなく、自分で作ったおとぎ話を聞かせるのだという。きっと同級生に賞賛された良い思い出があるのだろう。「お話を作るのってめちゃくちゃ楽しいんだよ。ぼくはその授業が大好きだった」と目を輝かせるのだった。フランスのすべての小学校にそのような授業があるのかは定かではないが、少なくとも彼にとっておとぎ話は「自分で作るもの」としてインプットされている。そんなふうに育った彼は、今頃、自分の子供に、自作のおとぎ話を語り聞かせているに違いない。
ラクレット(グリルチーズをゆでじゃが芋などにのせて食べる料理)の会に参加した時には、語学力×話題力の圧倒的欠如で沈黙のオブジェと化していた私に、隣に座っていたパリ出身の男性が、こんな一言を浴びせた。
「持ち寄りパーティーには、自分の料理を持ってこなくちゃ」。つまり、自分から話題をふらなくては会話は始まらないよ、と。地球の裏側から来た留学生にもっとかけるべき言葉があるだろうと思ったが、当然言い返す語学力もなく、ゆで芋の皮を次々にむきあげることで「私も参加してしています感」を出すしかなかった。まあ、今にして思えば、その発言からは、彼らも生まれつきおしゃべり上手なのではなく、努めてそう振る舞っているのだということが見てとれる。
また、誕生日会やナイトパーティーなどで、彼らがことあるごとに「スケッチ」と呼ばれるミニコントを披露していたことも思い出される(本屋さんに台本が売っているらしい)。もちろん観客は身内だけ。なのに役を演じることに照れがないというか、よくそこまで真剣に演じられるなあ…という感じで、その姿には「フランス人たるもの、スケッチのひとつやふたつ演じられて当たり前」という自負すらただよっているのだった。
しかし、真に彼らの「物語力」に圧倒されるのは、何といっても恋のなれそめを聞く時だろう。のぼせそうなほどトゥー・マッチなエピソードの数々。進学先や就職先を恋人とおそろいで決める(理由=一緒にいたいから。同棲しているんですが)。お祭りで踊っていたサンバダンサーにひと目惚れし、薔薇 100 本を手にブラジルへ飛んでプロポーズ(もちろん事前連絡なし。でもサプライズ成功で見事結婚)。ほかにも、詩を贈る、歌を贈る、レストランでギャルソンが指輪をのせたお皿を持ってくる。思わず目こすり、耳うたがう武勇伝の数々。10 年前はそれがなぜか必要以上に芝居がかっているように感じられ、「またロマンチックぶっちゃって…三文小説の主人公じゃあるまいし」とどこか冷めた目で見ていたのだが、今、彼らの「物語」をひとつひとつ思い返すと、素直にいいな、と思う。はつらつとして、まぶしい。
「自分の人生の主役を演じるのは、ほかならぬ私」ということに、照れたり冷めたりしない人たち。人生という、たった一度しかないドラマの台本を自由に描いて、演じる力。「物語る力」はそのまま「生きる力」なのだと、おしゃべり上手な彼らに学ぶのである。
帰国してから、ふと「ロマンチック」という単語をフランス語の辞書で引いてみたら、「小説的」という意味であった。
今号のムラコ=(かん・さんみ/編集者・ライター)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
