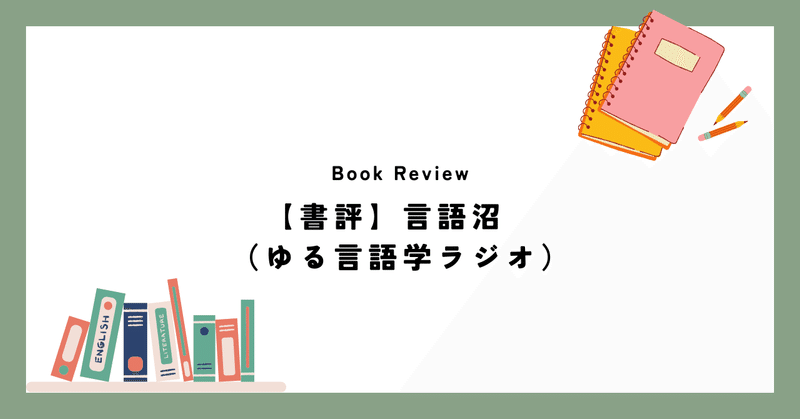
【書評】言語沼 (ゆる言語学ラジオ)
ぼくはわりと語学に興味がある方で、大学の時専攻を決める段階で結構最後まで言語学ゼミに進むか迷ったりしてました。
語句を覚える時も「この言葉の語源は何だろうか?」ということを記憶のとっかかりとして覚えてます。(例:ストア派ってストイックの語源なのか。だから禁欲主義なんだな)
で、この本はその言語の魅力にどっぷりとハマった人による対話篇です。
著者のお二人
語り手は言語オタクの水野大貴さん。
小学校で難読漢字にハマり、中学校で辞書を読むことに夢中になり、高校では英語の語源や英文法に魅せられるという、半生をどっぷりと言語沼に浸かってきたお方。
大学でも言語学を専門として、その後出版社に就職し編集者として勤務。
生粋の言語マニア。
聞き手は言語学素人の堀元見さん。
慶応義塾大学理工学部卒、情報工学を専攻。
作家としても活躍し『教養悪口本』、『ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金律』などを著している。
言語学素人と名乗ってはいますが多方面への深い知識を有し、本書や二人で行っているチャンネル「ゆる言語学ラジオ」でもうんちくを随所に挟み込み、ペダンチストっぷりを存分に発揮している
言語の奥深さ
本書の章タイトルを紹介すると
「のこと」沼
「バテる」沼
「えーっと」沼
「あいうえお」沼
「パンパン」沼
「を」沼
という感じ。
一見するとおもしろそうなそうでもなさそうな、というラインナップ。
しかしひとたびページをめくると……
「やまかわ」と「やまがわ」の違いは?
「ヘリコプターで山を登った」は変?
「お」は「い」より大きい
「えーっと」と「あのー」はどう違う?
といった、普段は気にもしないような、しかしながらよくよく考えてみると「あれ? なんでだろう?」という知識がいっぱい。
言語学の面白さは、「話者として使っているのに。どれが正しいのか感覚的にわかるのに。それなのになぜか説明できない」ところにあるような気がします。
「ドク」+「カエル」は「ドクガエル」なのに「ドク」+「トカゲ」は「ドクトカゲ」であり決して「ドクドカゲ」にはならない。
日本人なら「確かにそうだ」とは思うものの、なぜと言われると説明できない。
その面白さをプロローグではフェルマーの最終定理のたとえます。
題材が身近にあり、正誤判定も容易にできるのにその証明過程がわからない。これはフェルマーの最終定理よりもずっと身近で面白いコンテンツであると。
どこまでも深い言語沼
本書は六つの章に分かれており、それぞれ興味深い言語的知識と脇道にそれたうんちくで楽しませてくれるのですが、これは言語沼という氷山の一角でしかないのです。(沼なのか氷山なのかややこしい)
まだまだ言語学の面白さはこんなもんじゃない、まだまだ言語沼に浸りきった気がしないという方は彼らのyoutubeチャンネル「ゆる言語学ラジオ」をのぞいてみるとよいでしょう。
水野氏による言語学のさらなる深淵と、堀元氏によるうんちくの興味深さがこれでもかと味わえるはず。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
