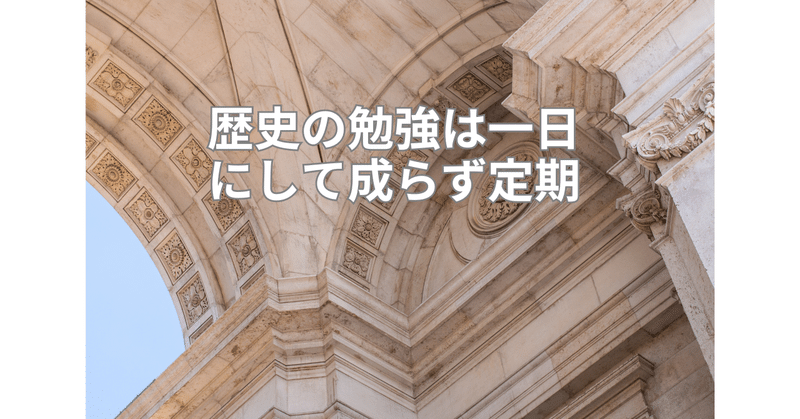
歴史の勉強は一日にして成らず定期
今月下旬に行われる歴史能力検定の世界史2級のための勉強をしています。
ぼくは歴史が好きなのですが、決して得意ではないです。
普通ならこれって謙遜になるのでしょうが、ぼくは本当に得意ではないのです。
とはいえ、歴史能力検定については昨年日本史2級と世界史3級をダブル受験してどちらもなんとか合格できたのですが、実は点数はかなりギリギリで、合格ラインから+1,2問程度の余裕しかありませんでした。
十分すごいじゃんと思うかもしれませんが、実は世界史については結構長いこと勉強していまして、それでもなかなか身につかずに記憶から消えていってしまうんですね。
都合3年ほど勉強して悟ったこと
世界史については、勉強しなおそうと思ってから約3年が経過しようとしています。これは高校生の学生生活と同じ長さ。さすがに時間がかかりすぎでしょう。
なぜ勉強しても身に付かないか。
それは「結果を急ぎすぎた」というのが一つの理由だと思いました。
最初に、石井貴士氏の『1分間世界史1200』という本で勉強してみました。
これは、表題通り高速で世界史の用語を覚えてしまおうという、魅惑のライフハック系参考書です。
石井氏は1分間シリーズという短時間で成果を出すための学習書を何冊も出版されています。こちらはその世界史版。
結論から言うとこれはぼくには無理でした。
やり方が悪いのか性格が不向きなのか根気が足りないのか。
とにかくぼくはこの本では一切世界史の用語を定着させることができませんでした。
多分ですがその大きな理由は「ぼくが世界史が好きだから」だと思います。
この本は「理屈なんてどうでもいいからとにかく用語を詰め込んで点数アップ! 合格ライン達成!」というタイプの本です。
・暗記が得意で
・歴史が嫌いで
・一時的にでも覚えられればいいや
という人にはとても効果がある本のような気がします。
ぼくは真逆の人間だったのでちょっと無理でした。
次に試してみたのは天下の山川出版、その『書きこみ教科書 詳説世界史B』です。
普通の教科書ではなく用語が空欄になっていて、書きこむことによってはじめて完成するという形式になっているものです。
なお、空欄の答えはページ下部に記載されていて答え合わせは容易にできます。
で、これもですね。教材としてはいいのですが、書きこみに飽きてしまいました。
また、書きこむことによってアウトプットができるのは良いのですが、書きこむことは一回しかできない。
赤ペンで書いてシートで消して答えるという記憶法にも使えそうですが、じゃあ普通の教科書でもマーカー弾いてできそうです。
しかしながら
・字がキレイ
・定期考査のために勉強する
・本に書きこむのが抵抗ないタイプ
という人には結構おすすめだと思います。
ぼくはどれも真逆なんですよねー。
その他、スマホの一問一答アプリを使ってみたり、エリア別になっているもの、教科書より優しいとうたった参考書など、両手の指で足りないくらいの参考書や問題集やアプリを使って勉強しましたがなーかなか覚えられない。
と半ば絶望しかけていたのですが現在使っている参考書がなかなか良さそうなのでこちらをご紹介。
河原孝哲著『ものがたり世界史 古代~近代/近代~現代』
2分冊になっておりしかもそれぞれ700ページ弱という大ボリュームの参考書です。
テーマ数も上下各80テーマで、合計160テーマ。
本署の構成は、各時代からタイムスリップしてきた当時を知る先生が現代の女子高生に講義するというスタイルになっています。
語り形式なので教科書のような堅苦しさはなく、名講師のように興味深いエピソードを随所に挟んでくれます。
各テーマの後にコラムが載っており、世界史への興味をさらに深堀りしてくれます。
はっきり言って分量はかなりあります。手に持っていても重たいです。
この分厚さだけで手に取る気が失せてしまう人も大勢いるでしょう。
ですが、読んでみると今までの勉強が何だったのかというくらい面白いし頭に入ります。
なぜか?
それは物事のそれぞれにちゃんと理屈をつけてくれるからです。
戦争を仕掛ける理由、農民たちが反乱を起こす理由、海上貿易が栄えた理由、どれもきちんと説明してくれています。(一部わかりやすさのために誇張がある、ということを前書きで断ってありました。が、それはやむをえないことだと思います)
というわけで少しばかり分厚い本ですが
・ページ数の多い本に抵抗がない
・テストには出ないようなエピソードに興味がある
・時間がかかろうとも理屈を一緒に覚えたい
という人にはとても良い本だと思います。
これはぼくにばっちり当てはまったのでした。
結局は暗記の下支えとなるのは「面白さ」のような気がしています。誰かに話したくなるような、そんな面白さがないとぼくの頭からはすぐ消えてしまうのでした。
勉強というのは本来あくせくしながら頭に大量の情報を詰め込むものではなく、生きた知識を自らの血肉にしていくものだったと思います。
特に歴史はこれまでの人類が歩んできた道のりを追体験するような学問ですから、じっくりと一歩一歩味わうように踏みしめるのが一番おいしい楽しみ方なのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
