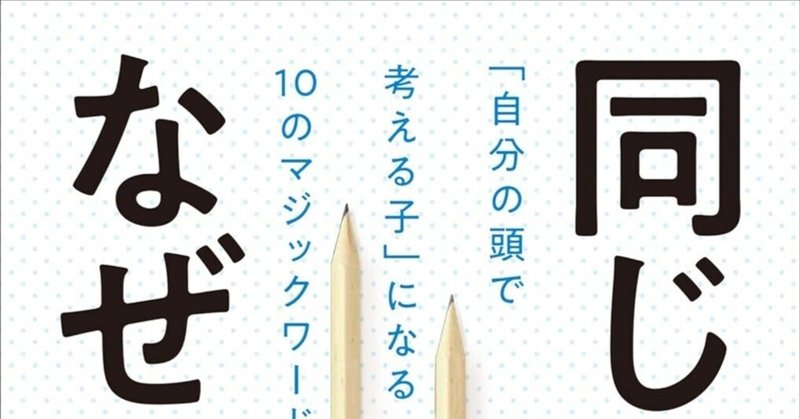
【書評】同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか?
Amazonのプライム会員特典「プライムリーディング」で読んだこちらの本。
『同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか?』
こちら、ぼくが普段から感じていることを上手く表現してくれていてとても参考になったので紹介します。
著者情報
石田勝紀
◆(一社)教育デザインラボ 代表理事
◆Yahoo!ニュース公式コメンテーター
◆Voicyパーソナリティ
1968年横浜生まれ。教育者、著述家、講演家、教育評論家
20歳で起業し学習塾を創業。これまで直接指導した4000人以上の生徒に対し「学びの法則」という日常生活の習慣化によって学力、成績を引き上げるのみならず、社会に出ても活用できるスキルとマインド双方を習得させてきた。現在は子育てや教育のノウハウを、「カフェスタイル勉強会〜Mama Cafe」、執筆、講演活動を通じてお伝えしている。国際経営学修士(早稲田大学)、教育学修士(東京大学)、都留文科大学元特任教授。書籍は23冊出版
学びの3つのタイプ
学びには3つのタイプがあるといいます。
【タイプ 1】 学んでいるように見えるが、学ぼうと思っていない人
【タイプ 2】 授業中・仕事中だけでしか学ばない人
【タイプ 3】 寝ているとき以外、日常すべてが学びになっている人
タイプ1の子は授業を受けていても頭を働かせず、受動的に黒板の文字を書き写すだけ。先生の言葉は基本的に右から左へ受け流します。
「面白いな」と思った瞬間だけスイッチが入るが、そのため知識は断片的になってしまい一過性の体験として終わってしまう。
タイプ2の子はまじめに授業を受けテスト勉強もまじめに努力します。
このタイプの子は「両立」という言葉をよく使います。つまり勉強とその他のことを分けて考えている。また、努力することを是としトップをとれない自分を責める人が多いようです。
タイプ3の子は勉強しているとき以外の時間も学んでいます。テレビを見ている時も友達との登下校の時も親とコミュニケーションをとっている時も、ゲームをしている時でさえ学びの時間にしてしまうのです。
タイプ3のような子について以前ぼくは同じような趣旨の記事を書き、それを「しあわせのくつを履いている」と表現しました。
戦闘以外の時にも経験値を得ているという比喩です。
頭のOSバージョンアップ
著者はこのタイプの違いを「頭のOSのバージョンが違う」と表現します。
OSが古いと新しいソフトを入れてもすぐにフリーズしてしまいますが最新のOSならばサクサク動いてくれます。
この場合のソフトというのは学校の勉強で言えば科目の事などです。
OSが最新であれば学年が上がるたび「中1数学」「中2数学」といったソフトをちゃんとインストールして動かせますが、OSが古いままではきちんと機能せず不具合を起こしたまま使用することになってしまいます。
ではタイプ1や2の子はタイプ3のような子には一生かなわないのか?
そんなことはありません。
どうやら後天的にタイプ3のような子になる方法があるのです。
著者は「頭のOSは後天的にバージョンアップしていける」と説きます。頭のOSの正体はすなわち「考える力」です。
考える力を意図的に伸ばしていくにはどうすればよいのでしょうか?
10のマジックワード
頭脳のOSをアップデートするには①疑問を持たせる②まとめさせる、という二つのアプローチが必要となります。
そのために考えられたのが10の声かけ「マジックワード」です
【アプローチ①疑問を持たせる】
1 「原因分析力」をつくる→「なぜだろう?」
2 「自己表現力」をつくる→「どう思う?」
3 「問題解決力」をつくる→「どうしたらいい?」
【アプローチ②まとめさせる】
4 「抽象化思考力」をつくる→「要するに?」
5 「具体化思考力」をつくる→「たとえば、どういうこと?」
【5つの補助的なスキル】
6 「積極思考力」をつくる→「楽しむには?」
7 「目的意識力」をつくる→「何のため?」
8 「原点回帰力」をつくる→「そもそも、どういうこと?」
9 「仮説構築力」をつくる→「もし~どうする(どうなる)?」
10 「問題意識力」をつくる→「本当だろうか?」
こういった問いかけをしていくことで自ら思考するという習慣をつけていく。すると脳のOSは次第に進化していくというのです。
それぞれの問いかけについては詳しくは本編を読んでいただきたいのですが、まずは二つ三つずつ実践していくのが良いでしょう。
ぼくが気になったのは4と5の「具体化」「抽象化」です。
頭の良い人は例外なく具体と抽象の行き来が上手です。
人間は知らないものを理解するためには具体的なイメージが必要で、知っているものを整理・保管するためには抽象化が重要になります。
それができない人が抽象的なものを抽象的なまま理解しようとして失敗しているのでしょう。
よくある例が「数学の公式を意味わからないまま丸暗記して、必要な場面でうまく使えない」といった事例でしょう。
抽象化ができるとどうなるか
具体化と抽象化は平たく言うと「違いを見つけること」と「共通点を見つけること」です。
「足が短いのがダックス」「耳が広がっているのがパピヨン」とするのが具体化で、「ダックスもパピヨンもイヌの仲間」とするのが抽象化です。
著者は抽象化が上手くなると争いやいじめがなくなると書いています。
人種間やクラスメイトで違いを見つけて別の存在と考えるのではなく、多少の違いはあれども共通点の持つ人間なのだという意識を持つことで世界は平和になる、というと大げさですがそういった趣旨を述べています。
おわりに
頭のOSをバージョンアップすることは必ずしも幸福になることとイコールではありません。
考えることが得意でなくても愛嬌や行動力や我慢強さなど、幸せになるための道具はいくらでもあります。
ですが、考えるということは視野を確実に広げてくれるものだと思います。
なるべく大きな視野を持って、それから自分がどうやって生きるべきかを考えていければ理想的な生き方に近づくのではないですか、と思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
