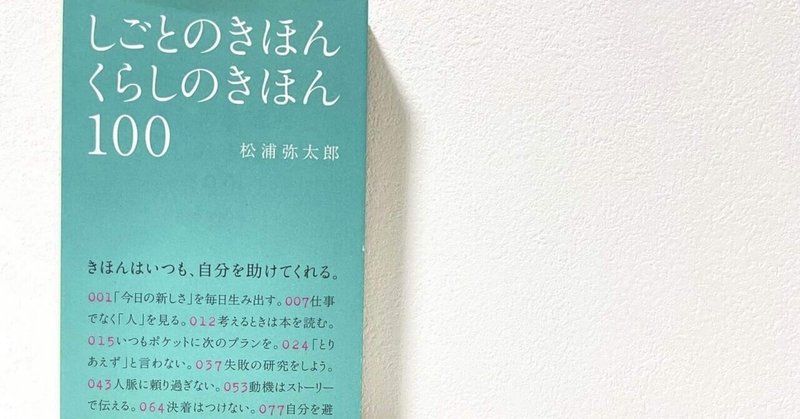
しごとのきほんくらしのきほん100/松浦弥太郎
〈しごとのきほん〉
ユニークで、楽しく。
「すべての人が「もっともだ」と言い、「全員一致で大賛成」なんて、つまらない気がします。正しいことはいくらでも言えるし、間違っていると声高に責めるのは簡単。しかし、お互いの不完全さ、ユニークさ、人間らしさを見せ合ったほうが、もっと仲良くできるのではないでしょうか。人でも商品でも、面白くて楽しくないと、興味を持ってもらえません。「きちんとしている」からはみ出す愛しいユニークさを、僕らは魅力と呼ぶのです。」(p.13)
仕事でなく「人」を見る。
「どんな仕事でも、いつも「人」をイメージしましょう。目の前にいてもいなくても「人」のために知恵を絞りましょう。接客業でなくても、あらゆる仕事の先には人がいます。新しいものを生み出し、人とどう関わるか。その関わりを、どう改善し、さらに新しくするか。生産、接客、改善。この3つを繰り返すことが仕事の基本です。「この先に、人がいる」こう考えたら、どうすべきかが見えてきます。」(p.21)
考えるときは本を読む。
「「考える」とは、簡単そうで難しい。一人になり、静かなところに行ったとしても、雑念が邪魔をします。そんなときは本を読みましょう。文章に集中し、本の世界に入り込むことをきっかけに、集中力を高める。すっぼり入り込んだら、ふっと本から離れて考えごとを始めます。しばらく考えてくたびれたら、再び本に戻る。こんな読書と思考の散歩をしましょう。慣れてくれば膝の上に本を置くだけでも散歩ができるようになります。」(p.31)
たくさん、繰り返し、読書する。
「「とにかく読む」という行為を基本中の基本としましょう。文字のなかでも特に本を繰り返し読みましょう。たくさんの量を読みましょう。読書とは受動的に見えて積極的なこと。人の人生の疑似体験であり、本を読まなくなると退化してしまいます。読書とは、状況を把握し、精度の高い客観的な意思決定のためのトレーニングです。迷った時、不安な時は、本を読んでみましょう。」(p.33)
種をまく。
「今日一日を生産的な日にすることが仕事です。何かをかたちにしたり、達成したり、生み出したり、「やることリスト」をクリアするのは大切なことです。それと同時に、種をまいておきましょう。毎日、稔りを収穫するには、毎日、種まきが必要です。今すぐかたちにならないもの、役に立つかどうか不確かなことを、少し多めにやっておく。遠い日の大きな稔りのために、毎日の種まきという投資をしておきましょう。」(p.39)
しっかりと向き合う。
「なんにせよ、ものごとにどう向き合うかで、自分に入ってくることは違ってきます。まっすぐに向き合っているか、ちょっと斜めなのか、横にいるのか。自分でいくらでも調整できるから、ついつい外してしまいがちですが、まっすぐ、正面から、しっかり向き合うことを心がけましょう。まともに向き合わずにいる姿勢は相手に伝わり、不安に思わせたり、傷つけたりしてしまいます。」(p.45)
「とりあえず」と言わない。
「ささいなことではあるけれど、この言葉を使わないようにすると、すてきになれると思うのです。「とりあえず」とは、つまるところベストでもべターでもないため、ネガティブな印象があります。会議の結論から飲み物の注文まで、「とりあえず」ですませる習慣を、なくしていきましょう。」(p.55)
早い返事は福を呼ぶ。
「「返事は早く」を大原則としましょう。打てば響くような俊敏さをもつよう、日頃から自分を整えておきましょう。「一日考えてからお返事します」というのでは、チャンスは逃げてしまいます。運の良さはタイミングの良さとつながっているから、早い返事が肝心なのです。」(p.57)
売り物は自分。
「何を作るのでも、何をするのでも、何を売るのでも、みんな同じです。仕事で大切なのは、自分という人間を信用してもらい、自分という人間に価値を見出してもらうこと。「ものを売るより、まずは自分を売れ」とは使い古しの言葉だけれど、それだけに真実です。信用さえしてもらえれば、どんな仕事でもうまくいくでしょう。」(p.61)
まじめさに逃げない。
「「とにかくまじめです」をアピールポイントにしているのなら、ちょっと考えたほうがよさそうです。まじめさとは標準であり土台。そこに自分の知恵、工夫、能力、がんばりで、どんな色をつけていくかが、仕事をして価値を生み出すということです。まじめさに逃げ込まず、一歩踏み出す積極性をもつ。はじまりは、そこからです。」(p.63)
自分の限界を作らない。
「自分のキャパシティを知ることは大切ですが、キャパシティと限界は違います。物理的な時間、体力、持てるもの、つきあえる人といったキャパシティの限界を知り、セーブすることは必要ですが、能力の限界を決めてしまうと、できることもできなくなります。自分のキャパシティについては大人のように、能力については育ち盛りの子どものように扱うのが、ちょうど良いバランスです。」(p.71)
一石二鳥に注意。
「「一石二鳥だな」と思ったら、手を出さないと決めておく。これはマナーであり、自分を守る知恵です。チャンスは重なって起きるもので、「こっちとあっち、両方手にしても誰にも責められない」というシーンが訪れます。でもそれは、宇宙のテストで、試されているときでもあります。一
石二鳥はたかが二鳥。桁外れの大成功をしている人は、一つしか取らないたしなみを知っています。」(p.77)
読み終えた新聞のたたみ方。
「新聞が古新聞になるのは、読む人がいなくなったとき。自分が読み終えても次に読む人がいるならば、まっさらな新聞でなければなりません。何をやるにしても、その先には人がいます。次の人が気持ちよく読めるように、会社でも家でもホテルのロビーでも、新聞をきれいにたたんで戻すこと。ゴミを捨てるときは集める人を、トイレを使うときは次に使う人を、困らせないように思いやること。ささやかだけれど、忘れてならないことです。」(p.95)
考えてから口を開く。
「考えながら、話していませんか?言いながら、考えていませんか?言いたいことは何なのか、自分がわかっていないのに見切り発車で話し始めるのは、コミュニケーションのマナー違反です。仕事の指示、連絡、報告、提案。何にしても「自分が言いたいこと」をしっかりと自覚して、準備
を整えてから話しましょう。」(p.49)
動機はストーリーで伝える。
「前に進んでいくときになくてはならないのは、動機というエンジンです。「なぜこれをやるのか」という動機をはっきりと伝えなければ、人は一緒に進んでくれません。なぜこれをやるのか、ストーリーを語りましょう。ボタンの掛け違いが起きないように、背景まで語りましょう。人を動かすものは感情です。要点だけまとめたリストでなく、思いを込めたストーリーを語ってこそ、動機がちゃんと伝わります。」(p.113)
ほめる、たたえる、認める。
「仕事の仲間、上司や部下、チーム。人と一緒にやっていくなら、とにかくいいところを見つけてほめ、今やっていることをたたえ、過去にしてきたことを認める。ほめ言葉、たたえる言葉、認める言葉をはっきりと表現する。これがチームワークの極意であり、人間関係の基本です。どんな人でも、ほめられると元気がわいてきます。」(p.123)
「正しさの城」で孤立しない。
「ポリシー、理念、主義を大きな旗のようにかかげ、自分の城を築いてしまうと孤立します。独自の考えは大切ですが、正しさにこだわり、流儀にしがみつき、違う意見をかたっぱしから否定すると、人とかかわるゆとりが削ぎ落とされてしまいます。孤独とは、誰もが持って生まれた宿命ですが、孤立とは、自分から関係を断ち切る行為。孤立した城の末路は、たいてい悲劇と決まっています。」(p.133)
自分一人でできることはない。
「若い頃は多かれ少なかれ、なんでも自分一人でやろうと思い、なんでも自分でできると勘違いしています。ところが時を経るごとに「自分一人でできることなんて一つもない」と気がつきます。すると自分都合で物事を考えなくなり、人に何かを押しつけなくなり、人の思いや気持ちに耳を傾けられるようになります。人の力を借りなくては、自分という存在は成り立たない。この事実をしっかりと知っておきましょう。」(p.141)
いつも発信源であれ。
「自分で見つける。自分で工夫する。自分から発案する。この3つは、誰かから必要とされる「価値ある存在」になるための基本姿勢です。プログやSNSをやっていてもいなくても、自分の経験から生まれた知恵を、いつでもさっと取り出し、前向きなコミュニケーションをとりましょう。情報
があふれている時代だからこそ、自分で集めた情報、知恵を絞った工夫、惜しみない発案が、貴重な一次情報となります。」(p,143)
私を主語にして話す。
「プロジェクトや世の中の動きについて話し合うとき、自分の意見の主語は自分にしましょう。「私はこう思う」「僕はそれをやってみた」と、きちんと主語を入れましょう。いろいろな情報があり、さまざまな人の意見を取り入れやすい時代だから、ついつい「〜は○○なんですよ」などと主語を抜いて話してしまう。聞く人は「それはあなたの意見?それとも新聞に書いてあったこと?」と混乱してしまいます。主語をつけて話すことで、信頼と責任が生まれます。」(p.149)
朝こそ、ゆったりと過ごす。
「朝は忙しく、みんな効率を求めます。走ったり勉強したりしたいし、何もしない場合も素早く支度しようとします。これを当たり前としているのなら、朝こそゆったり過ごしましょう。パンとコーヒーだけでも、時間をちゃんととって食べる。家族と話したり、物思いにふけったり、何か書いたりする。朝、1時間ゆったりするだけで、1時間多く眠るよりリラックスし、一日が活性化します。」(p.157)
大切なことは午前中に。
「成功している人や、すごい人は、口を揃えてこう言います。「重要なことは午前中に終わらせなさい」。よく言われることだからこそ、普遍の真理。肝に銘じておきましょう。集中力のある午前中に、大切なことを終えておく。午後になると体は疲れるし、意思決定の能力も落ちるもの。年齢を重ねれば重ねるほど、このルールを守ることです。」(p.159)
自分を避難させる場所をもつ。
「自分に立ち返り、自分を落ち着かせる場所。じっくり何かを考えたり、リラックスしたりする場所。自宅の部屋でも公園のベンチでも、本屋さんでもカフェでも、のんびり歩ける道でもいい。そんな「自分を避難させる場所」をもちましょう。人はそれほど、タフな生き物ではありません。ときには避難場所で、じっとしていていいのです。」(p.161)
勝ち負けから距離を置く。
「「人がやっていることは、やらない」こう決めてしまうと、勝ち負けの渦に巻き込まれずにすみます。ライバルが多く競争の激しい仕事は刺激的だし、高め合うことは大切ですが、勝ち負けで工ネルギーを消耗することも事実。誰もいない道なき道をゆけば、勝ち負けとは無縁でいられます。コンディションが整った状態で、自分が目指す場所に歩いていけます。人がひしめいていたら「どうぞどうぞ」と譲ってしまいましょう。」(p.195)
勇気を出して逃げる。
「何事からも逃げず、最後までやり通すのは、大切な基本姿勢です。そのうえで、「逃げる」というカードを捨てずにおきましょう。逃げなければいけないときは、勇気を出して逃げましょう。格好悪くても、弱虫と笑われても逃げる。義理を欠いても、誰かに嫌われても逃げる。用心深く状況を見極め、生き物としての勘を働かせ、そっと歩いて逃げることです。自分が命拾いをするばかりか、大切な人を守ることもあるはずです。」(p.197)
運を味方につけること。
「いつも笑顔であること。徹底して前向きであること。人に与えつづけること。運を味方につけたいのなら、この3つを守りましょう。実力は大事だし、努力は欠かせない。でも、時には運も必要です。運に味方をしてもらうために、「笑顔、前向き、与える」を基本としましょう。」(p.203)
君はそれがやりたいかい?
「やるか、やらないか。何かを頼まれたとき、誘いを受けたとき。もしも迷いが生じたら、計算で答えを出してはいけません。損か得か、お金になるかならないか、キャリアに役立つか、義理があるか。そんな計算はやめにしておきましょう。目を閉じて自分に聞きます。「君はそれをやりたいかい?」。答えがノーならすぐ断る。「やりたい!」なら、無謀でも、リスクがあっても、先行きが見えなくても、大きく息を吸って飛び込みましょう。」(p.207)
〈くらしのきほん〉
人よりも早く見つける。
「みんなが、「あ、待ってました!」という気持ちになるものを、すっと差し出す。そのためには、人より早く見つけましょう。ちょっと先のうれしいこと、欲しいもの、足りないものを先回りするには、超能力などいりません。よく見て、思いやりを持つことです。たとえばホームパーティで料理と飲み物と音楽の用意は誰でもしますが、さらに、くたびれたときのために、クッションを用意しておく。そういう何かを、早く見つける達人になりましょう。」(p.229)
好かれること。嫌われること。
「「好かれる」と「嫌われる」はセット。そう思っておきましょう。みんなに好かれたらハッピーですが、ありえない話。自分を好きだと言う人が10人いたら、嫌う人も10人います。そういうものだと思っておくと、SNSで伝わってくるコメントや、心ない噂話に振り回されずにすみます。人の好き嫌いはまた、すぐに変わるもの。愛憎ではないのですから、深く考える必要るないことです。」(p.231)
親切を深めていく。
「家族や友人、仕事仲間であれば、呼吸のごとく日常的に、親切にしたいもの。でも、その親切がルーティン化してはいませんか?単なる習慣になり、すでに親切ではなくなっていることもあるかもしれません。「もっと親切にするには、どうしたらいいのか?」と常に意識しましょう。親切とは心の働き。踏み込んで深めていかないと、心からの親切にはたどり着けません。」(p.235)
手放すという智恵。
「手に入れることに夢中になって、手に入れたものは、しっかり握って手放さない。それではだんだん息苦しくなってきます。モノや服であれば、「1つ買ったら1つ処分」。さらにモノ以外のことにも、同じルールを当てはめましょう。勉強、趣味、社交、友人など、すべて楽しく、有益なことであっても、全部を抱え込んだら、自分が壊れてしまいます。」(p.239)
相手に寄り添う。
「大切な人に何かをしてあげたい。そんなとき、やさしい言葉、親切、思いやりある行動、はたまた贈り物を考えるかもしれません。でも、悲しんでいるとき、やさしい言葉は届かないもの。傷ついているとき、親切は負担になるかもしれません。だから何もせず、距離を保ち、寄り添うことが一番という場合はたくさんあります。ただ寄り添う。ずっと寄り添う。しばらく会っていなくても、心は寄り添う。慎ましくて美しい贈り物です。」(p.245)
控えめであること。我慢すること。
「「自分」というのは、誰にとっても最大の関心テーマなのでしょうか?どうしても自分の話がしたい、つねに自分が前に出たい、誰でも自己顕示欲をもっています。それでもちょっと抑えて、控えめになりましょう。ときには我慢して、相手を優先しましょう。ただし、控えてばかりだと無責
任な傍観者になってしまうことがあります。さじ加減が難しいから、いつも気をつけましょう。」(p.255)
否定しないこと。
「「神さまになりなさい」と言っているように響くかもしれません。それでも、否定しないこと。ノーで始めないこと。シャッターをおろさないこと。頭から否定をするとは、ぷつんと糸を切るようなふるまいです。否定はまた、争いごとの種になります。どんなことでも、素直に聞いてみる。その意見を受け入れないのは、「違うな」とわかってからでも遅くはありません。」(p.257)
自分よりも優れた人と付き合う。
「自分よりも優れた人たちと付き合うのは、実はとてもしんどいこと。背伸びをしないといけないし、自分の欠けている部分を突きつけられるし、その差を現実として受け止め、縮めるべく努力をしなければなりません。それでも背伸びの付き合いは、自分を伸ばすための最良のレッスン。居心地いい仲良しの輪では味わえない緊張感が、自分のレベルをあげてくれます。たとえ古い仲間と別れることになっても、思い切って飛び込みましょう。」(p.261)
コレクションではなくセレクション。
「コレクションは、たくさん集めることがうれしい。セレクションは、一生けんめい選ぶことが楽しい。モノはもちろんのこと、すべてはセレクションです。たとえば、「なんでもいい」とコーヒーばかり飲むより、自分のその日の体調や気分と相談して、慎重に飲み物を選んだほうが、おいしくいただけます。常にちゃんと選ぶ、セレクションという意識を大事にしましょう。」(p.281)
察する。
「大人のたしなみであり、日本人らしい思いやりであり、なんとも美しいマナーです。言葉で確かめなくても理解する。そっと相手を慮る。そんな、「察する大人」を目指しましょう。口に出してはっきり訊ねるのではなく、「今はそっとしておいてほしいんだな」察する。込み入った話をしていたら「自分は席を外したほうがいい」と察する。察する大人になれば、その場にふさわしい振る舞いがわかるようになります。」(p.295)
声をかけよう。
「言葉を交わさなくてもコミュニケーションがとれるから、いつのまにか声をかけあうことが忘れられています。家族、近所のコミュニティ、職場。用があってもなくても、話があっても特段なくても、声をかけましょう。「元気?」「気持ちがいい天気!」「最近どうですか?」なんでもいいので、逐一、声をかけあう。これは「あなたのことをちゃんと気にしていますよ」というサインです。声をかけることで、相手が救われることもあるし、自分が救われることもあります。」(p.297)
年下にも年上にも、きれいな言葉で。
「親しくなるとは、「なんでもOK」になることではありません。とくに気をつけたいのが、言葉遣い。堅苦しいほどていねいな言葉と、無礼なくらいカジュアルな言葉の中間がないのは、残念なことです。言葉遣いは心遣い。どんなに親しくても、相手への敬意を忘れずに話しましょう。年上の人に気を使え、ということではありません。年上でも年下の人でも、きれいな言葉づかいを自分のべーシックとしましょう。」(p.305)
言葉の取り扱い方。
「本物の大人になるには、言葉の取り扱いを慎重に。信頼される人とは、口が堅い人。話したことが全部漏れてしまうとしたら、恐ろしくて何も話せなくなります。何気ない話が時として大きくなったり、ねじ曲がったりするから要注意です。安心できる人は、知っていることをひけらかさない人。よく知っていても黙って聞いてくれる人は、知惠と包容力を感じさせます。」(p.307)
「でも」と言わない。
「「でも」を言う癖は、悪気はなくても厄介です。「あの店はいい」と教わったとき、「でも、こっちの店はすごい」とは、相手の話をまるごと受け止めるのではなく、自分が知っていることをカチンとぶつける。そんな癖があれば直しましょう。すてきな人は、年を重ねるほど素直になり、どんな話も感心して聞きます。いいものがあると聞けば試し、いい映画があると聞けば見に行きます。この素直さから、たくさん得るものがあります。」(p.315)
相手の意見を聞く。
「優先すべきは、自分が話すことより、相手の話を聞くことです。耳を傾ける姿勢から、さまざまな可能性がひらけます。教えてもらえたり、信用してもらえたり、自分のためになるのです。聞き上手とはまた、人間関係をよくするための秘訣です。」(p.319)
安易にプライベートに触れないこと。
「個人的なことに干渉したり、 家族について相手が答えに困るような質問をする人がいます。 「親しいのだから立ち入ったことを聞いてもいい」と思うのでしょうか。 なぜ聞きたいかといえば、ただ知りたいから。 単純な興味で悪意はなくても、 美しくありません。 すてきな人は、門が開いていても入らない節度をもっています。 プライベートには安易に触れないこと。 ちらりと見えても見て見ぬふりくらいで、 ちょうどいいのです。」(p.323)
静かであること。
「大人とは静かであるべきです。 大声で話すのは、レストランや料理屋では無作法ですし、セルフサービスのカフェでさえ、がさつな感じがします。どしどし歩く、バタンとドアを閉める、 がちゃんとコップを置く。 擬音がつく動作は慎むこと。 エレベーターのボタンを押すとき、公共交通の自動改札機にICカードをタッチするとき。静かであるかどうかで、印象がずいぶん違います。」(p.327)
頭ではなく心を使う。
「頭を使うスイッチと心を使うスイッチ。いつも両方をオンにしておきましょう。 頭の使い方にはある種の教科書のようなものがあり、慣れれば上手に使えるようになります。 いっぽう、心の使い方は誰も教えてくれません。 目の前のことを良く見ること。目に見えない人の気持ちも良く見ること。その試行錯誤で、少しずつ心が使えるようになっていきます。 ついつい頭ばかり使ってしまうから、意識して心を使う暮らしがしたいものです。」(p.345)
わかることと感じること。
「「わかる」というのは頭で理解すること。「感じる」とは心で受け止めること。 大切なのは、わかることと感じることのバランスです。 頭では納得できても、感じる部分ではなんとなく信用できないなら、ちょっと疑ったほうがよさそうです。逆に、 自分が相手に伝える側の時は、 「わかる」だけで押し通さず、「感じる」部分にうったえかけるような表現をしていきましょう。」(p.347)
トラブル・イズ・マイ・ビジネス。
「生きることに慣れてきたら、 2つの力をもらえます。 困ったことを避ける技術と、困ったことを乗り越える能力を。どちらを使うかは自分次第。 できれば逃げず、乗り越える能力のほうを使いたいものです。「トラブル・イズ・マイ・ビジネス」困ったことをなんとかするのが役目だと腹をくくれば、3つ目の力が手に入るかもしれません。」(p.353)
1つだけにする。
「時間を組み合わせのパズルのように見なして、空きスペースに次々とやるべきことを詰め込む。「ついでに何かをする」というやり方が、あらゆる場面で増えています。 効率的でいい面もありますが、1つのことだけに集中して時間を使うほうが、経験として自分のなかにしっかり残ります。人に何かを伝えるときも、あれもこれもと欲張るより、1つに絞ったほうが確実に伝わります。」(p.359)
3時のお茶を楽しむ。
「どんなに忙しくても、1日1回、仕切り直しをする。それが3時のお茶です。 朝が早い職人は、「10時と3時のお茶」 と言います。 家族のお弁当作りなど、 朝早くから働いている主婦は、同じく2回でもいいでしょう。会社で働いていると9時
がスタートなので、3時だけでちょうどいい。 手を止めて、15分でも30分でも仕事を中断し、飲み物を味わい、おやつを少し。 3時のお茶を落ち着いて楽しむと、もうひと頑張りできます。」(p.371)
時には動かない。
「新米の宇宙飛行士がチームに入ったときは、動かないことが大切だそうです。 すでにチームのやり方があり、優秀な人がそれぞれ役目をこなしている。そこに張り切って自分流を持ち込むと、 迷惑になるというのです。 それに倣い、 引っ越し、転職、習い事を始めるなど新たな人間関係に入っていくときは、しばし動かずにいましょう。 自己アピールのような提案はやめ、絶対に必要な下働きを地味にこなす。 時には動かず、様子をみましょう。」(p.377)
大人の教養は歴史と宗教。
「大人の教養として身につけたいのは、歴史と宗教。2つは密接に絡み合っており、 人間の本質を学ぶ最良の師です。 旅をしても、 そこの歴史と宗教を知っていれば得るものが多くなります。歴史に比べて宗教は敬遠されがちですが、 たとえば聖書は、世界で最も多く読まれている書物。 お話仕立てのものから、スマートフォンのアプリまでいろいろあるので、教養として読んでみるといいでしょう。」(p.393)
うまくいかなかったことを振り返る。
「うまくいかなかったこと、それは実は、もっと上手になれる手がかりです。 うまくいったことより、失敗を振り返ったほうがたくさんの気づきがあります。焦がしたパンケーキから新しいレシピが生まれます。 「誤解を招くことを言ってしまったのはなぜ?」とよく考えれば、思いやりが育まれます。 気づきを数多く得た人のほうが幸せです。」(p.395)
スタイルを持つ。
「暮らし、仕事、生き方。 すべてについて、一貫した自分の信念をもっている人は魅力的です。言葉を変えれば、「自分のスタイル」をもつということ。 スタイルは固定ではありません。 宝物を手入れするように、絶えず磨いていくものです。 より良いスタイルができると生き方の質が上がり、人から好かれ、社会との関係性も深まるでしょう。」(p.407)
人を嫌いにならない。
「誰にでも苦手な人はいます。 虫が好かないというのもあるでしょう。 しかし 「嫌い」という箱に分類してしまうと、その人を否定することになります。 人間関係は、いつ、どうなるかわからないもの。誤解に気づいたり、思いがけないことで助けてもらったりするかもしれないのです。 「嫌い」と断定せず、手前で止める。 苦手くらいにとどめる。この癖がつくと人を嫌いにならなくなります。」(p.409)
不自由があたりまえ。
「「せっかくの外出なのに、電車が遅れている!」こんなふうに苛立つ人がいますが、おかしなことです。 本来、歩くべきところを電車で行けるようになっているだけで奇跡だし、 時間通りに運行されるのも奇跡。もともとは不自由があたりまえなのに、何かが整っていないと文句を言うのは愚かなことです。「自分の思うままにはならない」と受け入れてこそ、 自分のなかで化学反応が起きて、学び、気づき、思考、工夫が生まれます。」(p.411)
美しきものとは、腕を組んで歩く老夫婦。
「初めての恋も、すばらしい愛も、かけがえのない結婚も すれちがった恋愛も、男と女のつながりの全部のなかで一番美しいものは、腕を組んで歩く老夫婦。 ダイヤモンドの美しさでもなく、格好良い車の美しさでもなく、人と人が一緒に丹念に磨き上げ、支えあう美しさがそこにはあります。」(p.415)
自分の船は自分で漕ぐ。
「家族がいても会社に勤めていても、みんな自分の船を持ち、 一人で漕いでいます。 「誰かが漕いでくれる」とオールから手を離して待っていたら、流されてしまいます。 自分の船は自分だけの船。会社に明け渡してしまうのは、 人生の面白さを手放すのと同じです。 誰かの船に引っぱってもらおうとしたら、大切な人の船もろとも 沈んでしまうかもしれません。 それぞれが漕ぐ小さな船が一緒に進む。 そんな独立精神をもちましょう。」(p.421)
忘れられないために。
「たしかに生きた証しとは、人の記憶に残ること。突き詰めていくと、どれだけ人の役に立てたか、助けることができたか、感動を与えられたのかということでしょう。 どんなにおいしい料理も役立つ工夫も、誰とも分かち合えなかったら、 たまらなくさびしい。 ものをつくるとき、何かを考えるとき、「これは人の役に立つだろうか?」と自問しましょう。 そのうえで行動に移せば、いつか人の記憶に残ることができるはずです。」(p.423)
きれいごとを大切に。
「「そんなの、きれいごとだよ。 現実はそうじゃない」と考えたり言ったりすることがあります。 わからなくはないけれど、やっぱり、きれいごとは大切です。「こうあると美しい」という理想や、「こうだったら素晴らしい」という希望。 それがすぐに手に届かない夢であっても、むつかしい課題だったとしても、紙に書いて形にする。 これだけで実体のあるものになり、いつかそのとおりになる。 「きれいごとだ」と口にするのは、 「あきらめます」という宣言です。」(p.425)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
