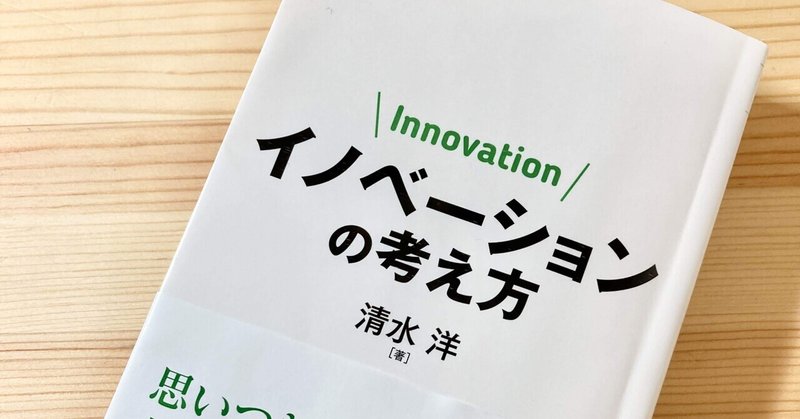
イノベーションを体系的に捉える
一般名詞になったイノベーション
「SDGsや社会課題の解決に向けたイノベーション」、「…業界・領域でのイノベーションの実現」など、いまや多くの企業が様々なイノベーションの実現をビジョン、戦略や統合報告書などで謳っています。そして、私自身も過去経験したことがありますが、社内でも上層部から「イノベーションを起こせ!」と各部門に新規事業の開発などの発破がかけられたりしていませんでしょうか?
しかし、そもそもイノベーションとは、企業の大方針や上からの指示で起こせたりするものなのでしょうか?また、イノベーションという言葉が何を指すのか、画期的な新商品の開発になのか、旧来のビジネスモデルの刷新なのか、新しい技術革新なのか、使う人、企業によっても少しずつ意味合いや定義が異なったりします。
イノベーションを体系的に捉え直す
このように企業現場で日常的に使われるようになったイノベーションを改めて体系的に整理して捉え、その実現に向けての示唆を与えてくれるのが、今回紹介する清水 洋 著『イノベーションの考え方』になります。
そもそもイノベーションとは何か?その定義から始まり、イノベーションの種類やタイプ、イノベーションの担い手や組織毎の得手不得手、イノベーションを実現していく上でのポイントが、コンパクトながらも豊富な学術研究をもとに深く解説されています。
イノベーションの定義
まず、本書ではイノベーションを「経済的価値をもたらす新しいモノゴト」と定義して議論をスタートします。ここでの「新しいモノゴト」は事業に限定されるものではなく、社内の仕組みでもビジネスモデルでも何でも構わないとして、イノベーションの対象が製品サービスに限らないことを指摘します。ここから、イノベーションの大まかな分類として、プロダクトイノベーション(製品やサービス自体に関わるもの)とプロセスイノベーション(生産、提供方法や社内の仕組みなど)が導き出されます。
そして、産業や事業の初期にはプロダクトイノベーションが求められ、業界標準となる製品・サービスの仕様やデザインが確立された段階(ドミナントデザイン)からはプロセス・イノベーションの重要性が高まるため、自社の事業、製品サービスがどの段階にいるかをよく見極める必要があると言います。
さらに、イノベーションの別の整理の仕方として、創造的破壊をもたらす急進的なラディカル・イノベーションと改良を積み重ねる漸進的なインクリメンタル・イノベーションを挙げ、ラディカルは新しくて小さな組織、インクリメンタルは大きくて古い組織が得意としやすい傾向にあることが述べられています。
一口にイノベーションと言っても、このように少なくともプロダクト・プロセス、ラディカル・インクリメンタルの4種類の整理があり、事業のフェーズによって求められるイノベーションが異なることに加えて、企業の特性によっても得意不得意が分かれるため、それらを考慮した上で必要、最適なイノベーションを追求していくことの重要性が指摘されています。
イノベーションの担い手
先に挙げた企業特性の新しくて小さな組織、大きくて古い組織はそれぞれスタートアップ、大企業と捉えることができます。本書では、もう一歩踏み込んで、個人としてのアントレプレナー(とイントレプレナー)の資質や要素、さらにはアントレプレナーシップ溢れる人材をいかにマネジメントしていくかについて、これまでの学術研究をもとに紹介されています。
実践に向けた示唆
以上のように、本書は既存の中堅中小、大手企業に所属する方、スタートアップで働く方、さらには後半では政策担当者にとっても参考となる内容となっていますが、特に示唆に富むのが次の3点になります。
1. イノベーションはやらされ感ではできない
至極当たり前のことであるにも関わらず、意外と中堅大手の企業現場では置き去りにされている点ではないかと思います。
最近はさすがに減ってきているかもしれませんが、ともすると既存事業の中で実績を上げてきた社員が新規事業開発のプロジェクトチームのメンバーとしてアサインされたりします。
もちろん、その方も期待に応えようと頑張りますが、往々にして行ってしまいがちになるのが、既存事業のように、いかに目標を達成していくか、逆算と積み上げで発想しがちになります。ややもすると、プロジェクトの当初から落とし所(経営層が納得してくれるゴール)を探したりします。
しかし、新規事業は既存事業と異なり、分かりやすい落とし所はありませんし、そもそも落とし所を見定めた時点で、おそらくイノベーションにはつながらないと思われます。
そのため、本当にイノベーションを実現したい場合には、仕事の範囲を超えて、そのテーマに強い問題意識を持っているメンバーなどをアサインすることが重要になってきます。このよう点が非常に説得力を持って語られています。
2.どの種類のイノベーションも大事
次に、一般的にはプロセスよりもプロダクトイノベーションのほうが分かりやすく、注目されやすく、またインクリメンタルよりもラディカルイノベーションのほうが重要視されがちです。しかし、本書では事業のフェーズや組織特性などを踏まえながら、それぞれのイノベーションの必要性や重要性を指摘している点が特徴と言えます。
なんとなく上から発破をかけられるとラディカルなプロダクトイノベーションを考えなければと思いがちですが、一度立ち止まって改めて関わっている事業のフェーズを踏まえて、本当に求められているイノベーションは何かを考えることができると思います。
3.新しいモノゴトを経済的な価値につなげる
3点目が最大のポイントになると思いますが、多くの新規事業は何らかの新しさを持っているから新規事業な訳ですが、新しいだけでは価値につながらず、経済的な価値につなげていくための戦略的な行動の重要性が本書では指摘しされています。
戦略的な行動の中でも特に指摘されているのが、価値を規定される側ではなく、規定する側になるということです。例えば、顧客は何らかの製品・サービスをそれ単体で使用することは少なく、複数の製品・サービスとともに活用して自身のニーズを満たしたり、課題を解決します。この時、新規開発した自社の製品・サービスが顧客のニーズや課題のボトルネックを解決するものになっているかどうかが重要だと言います。その立ち位置を取ることができれば、経済的的な価値、高い収益性につなげることができます。逆にその位置を取ることができなければ、顧客にとっての重要性が高くないので、収益につながりにくくなります。
なお、しばしば「アイデアは良かったけど、早すぎた」といったことが新規事業開発の場面で言われることがありますが、上述した一緒に使用する他の製品・サービス、一般的に補完財と呼ばれるものや製品サービスの活用の前提となる社会的な制度が整っていない場合に起こり得ることが言及されており、補完財や制度面への気配りの必要性も指摘されています。
以上のように、イノベーションを考える上で見過ごされがちになってしまう点や具体的にどのようなイノベーションを志向するか、さらにいかに経済的な価値につなげていくか、これらを日々の業務の中で一度立ち止まって俯瞰的に見直す機会を与えてくれる一冊かと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
