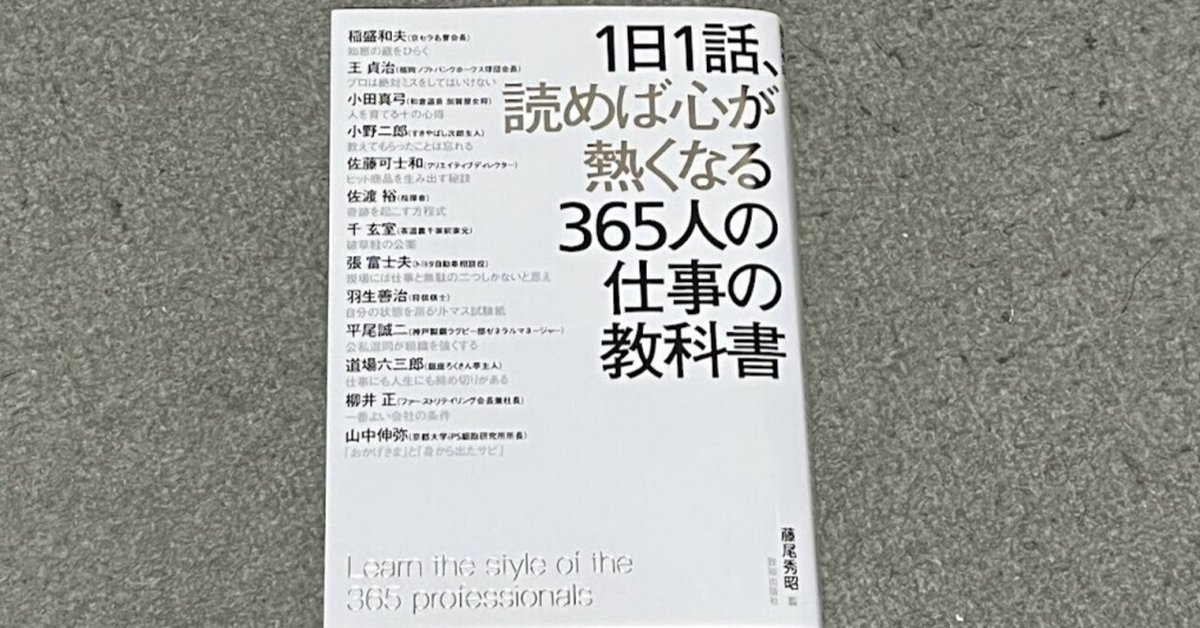
【書籍】腹を括る勇気ー水野彌一と京都大学アメフトの変革
『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』(致知出版社、2020年)のp190「6月6日:腹を括れば、自分がなくなる(水野彌一 京都大学アメリカンフットボール部前監督)」を取り上げたいと思います。
水野彌一氏の人生と指導哲学は、多くの転機と深い洞察に満ちています。彼が昭和43年に大学院を卒業し、アメリカに留学したことは、彼の人生における最初の大きな転機でした。アメリカンフットボールを本場で学ぶことを決意した彼は、スポーツ指導に対する全く新しい視点を得ることになります。留学前、彼は体育会系の厳しい訓練と指導が、選手を強くする唯一の方法だと信じていました。しかし、アメリカでの経験は彼の考えを根底から変えました。彼は、個々の選手の能力を最大限に引き出し、組織として機能することの重要性を学び、スポーツ指導の新たな理解を深めたのです。
私は昭和四十三年に大学院を卒業した後、本場のアメフトを学ぼうとアメリカへ留学しました。これが一つの転機になりました。それまではいわゆる体育会のシゴキをやって、普通じゃない、特別な選手をつくることがスポーツの指導だと思っていましたが、アメリカはそうじゃなかった。集めてきた選手に自分たちの戦術を教えて、組織で試合に勝つと。その大切さを学びました。
この留学経験は、帰国後の彼の指導スタイルに大きな影響を与えました。昭和49年、京都大学アメリカンフットボール部の監督に就任した彼は、関西学院大学との試合で以前とは比べ物にならないほどの健闘を見せるチームを作り上げました。これは、彼がアメリカで学んだ指導法を実践している証であり、京都大学アメフト部の新たなスタートとなりました。しかし、勝利は容易には得られず、彼はさらなる挑戦に直面します。経済的な理由からスズキインターナショナルへの就職を選んだ彼は、そこで再びスポーツにおける新たな教訓を学びます。関学アメフト部を全国制覇に導いた鈴木智之氏のもとで働きながら、彼は「表面的な技術に頼るな」という教えを受け、真のフットボールの本質を追求するようになりました。
昭和57年には、彼の人生と指導哲学におけるもう一つの大きな転機が訪れます。副将の突然の死は、彼に人生の儚さと、親子の深い絆の価値を痛感させました。この出来事は、彼に「自分をなくす」ことの重要性を教え、自己中心的な考えを捨てさせました。彼は、自分自身をチームとその目標に捧げることで、真の意味での勝利が得られるという新たな理解に至りました。この哲学は、チームが勝利を重ねるきっかけとなり、彼は選手たちにも「腹を括る」ことの大切さを伝えるようになりました。
もう、彼は帰ってきません。ならば自分も人生を捧げないとフェアじゃないだろうと。
それで、「自分をなくそう」と思いました。それまではやっぱり「自分が強くする」「自分が日本一にする」と、自分が強かったんです。でも、もう自分はどうでもいいと腹を括りました。それからです、すっと勝ち出したのは。
だから私は京大生に「腹を括れ」といつも言っているんです。腹を括れば自分がなくなる。そうすれば、逆に自分が自由になるんです。自分に制限をかけているのは自分でしかないですから。
水野氏の話は、スポーツ指導に限らず、人生における挑戦と成長、自己超越の重要性を示しています。彼の経験は、自分自身の限界を超え、より大きな目的のために自己を捧げることの価値を教えてくれます。アメリカ留学から始まり、京都大学アメフト部の監督を経て、副将の死に至るまで、彼の人生は、自己を超えた目標に向かって努力し続けることの重要性を強調しています。彼が選手たちに伝えた「腹を括れ」というメッセージは、自分の制限を超えて成長すること、そしてその過程で真の自由を見出すことの象徴です。水野氏の人生と指導哲学は、スポーツの枠を超えて、人間としての成長と自己実現の模範を提供しています。
人事の視点から考えること
水野氏の経験から得られる教訓は、人事の専門家が組織内で直面する多様な課題に対して、深い洞察と具体的な行動指針を提供します。これらの教訓を基に、人事領域における実践的な応用をさらに詳細に掘り下げてみましょう。
チームビルディングの進化
水野氏がアメリカで学んだ組織で勝つためのアプローチは、現代の組織においても重要な意味を持ちます。従来の個々のスキルや才能の単純な集約ではなく、チームとしてのシナジーを最大化することが求められています。人事部門は、従業員の多様性を理解し、それぞれの強みを活かしながらも、全員が共通の目標と価値観を共有する文化を築くことが重要です。このプロセスには、定期的なチームビルディング活動、クロスファンクショナルプロジェクトの推進、オープンなコミュニケーションチャネルの確立などが含まれます。
リーダーシップの深化
「自分をなくそう」という水野氏の考え方は、リーダーが自己中心的な視点を超え、組織やチームの利益を優先することの重要性を示しています。これは、リーダーシップ開発において、自己認識、感情知能、他者への共感といったスキルの重要性を強調します。人事部門は、リーダーがこれらのスキルを身に付け、実践できるように支援するためのプログラムやワークショップを提供する必要があります。また、リーダーがチームメンバーの意見や感情に耳を傾け、包容力のあるリーダーシップを展開する文化を促進することも重要です。
人材育成の新たな展開
水野氏の体験は、人材育成における個人の尊厳と成長の重要性を浮き彫りにします。社員一人ひとりが自己実現を目指し、その過程で組織の成長に貢献できるような環境を作ることが、人事部門の役割です。これには、キャリア開発プランの個別化、メンタリングやコーチングのプログラム、そして継続的な学習とスキルアップの機会の提供が含まれます。また、社員が自らのキャリアパスを探求し、新たな挑戦を経験するためのサポート体制を整えることも、人事が果たすべき重要な役割です。
組織文化の深化
水野氏の「腹を括る」というメッセージは、組織文化の核となるべき価値観を示しています。自己を超えた大きな目標に向かって努力する姿勢は、組織のミッションやビジョンと密接に結びついています。人事部門は、このような価値観を組織のDNAに組み込むために、日々の業務、コミュニケーション戦略、報酬や認識のシステム設計において、これらの価値観を反映させる必要があります。組織が一丸となって目標に向かうためには、社員一人ひとりが自分の役割を理解し、組織全体の成功に貢献することを誇りに思う文化を育むことが不可欠です。
まとめ
水野彌一氏の体験談から学べる教訓は、人事管理の多くの側面に深く関わっています。チームビルディング、リーダーシップ開発、人材育成、そして組織文化の構築という4つの主要な領域において、具体的な戦略と行動指針を提供します。これらの教訓を実践することで、組織は持続可能な成長を実現し、変化するビジネス環境の中で競争力を保つことができるでしょう。水野氏のように、深い洞察力と自己犠牲の精神に基づくリーダーシップは、組織内のあらゆるレベルでの人々の心を動かし、組織全体を前進させる力を持っています。
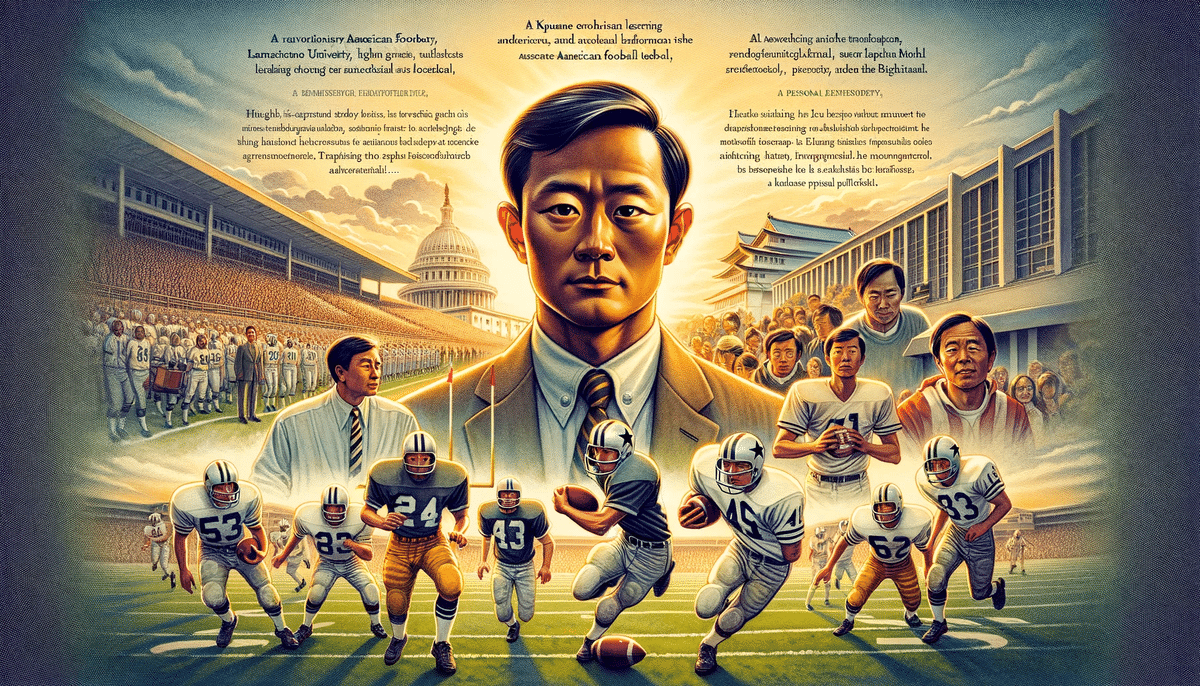
水野彌一氏の変革の旅を象徴的に表現しています。日本での大学院生活から始まり、アメリカにおけるアメリカンフットボールの学び、そして京都大学アメフト部の革命的な監督へと成長するまでの過程が描かれています。画像は、彼のアメリカへの出発、アメリカンフットボール技術の学びと観察、日本への帰国、そしてライバルに対する顕著なパフォーマンスをリードする様子を捉えています。日本の大学から海を越えてアメリカのフットボールフィールドへ、そして日本のスタジアムへと、彼の成長と文化交流を反映した場面の移り変わりが特徴です。柔らかく温かみのある画風で、チームワーク、リーダーシップ、個人的な変革、そして献身というテーマに焦点を当てて、水野氏の感情的、哲学的な成長が強調されています。この画像は、彼の教えとチームおよび個人の哲学への影響の本質をダイナミックでインスピレーションに富んだ方法で示しており、彼の経験がもたらした深い影響の感覚を伝えます。
1日1話、読めば思わず目頭が熱くなる感動ストーリーが、365篇収録されています。仕事にはもちろんですが、人生にもいろいろな気づきを与えてくれます。素晴らしい書籍です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
