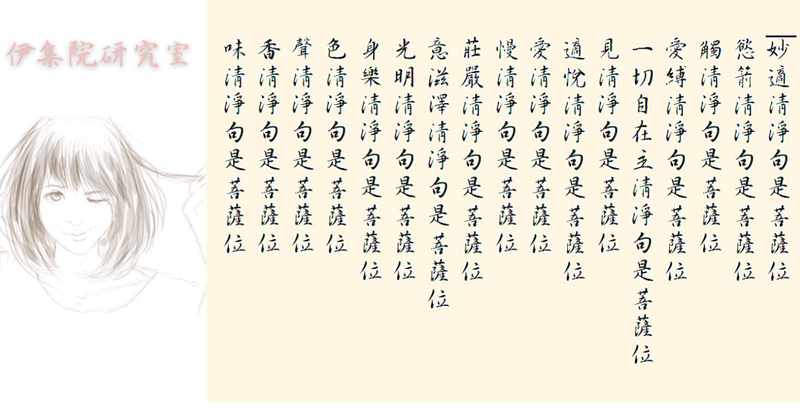
密教という、巨大な「真意」を追求してみる@苦行するだけで、それが描けるのか、実践的に考えてみるのだ。 講座「仏教と日本の関わり」はいかに?
実は、ずっと構想していたことなんですが、
あたし自身、「信仰」というものは
いったい何なのかという事を解明してみたいという
大きな命題を持っているんでございます。
(ちょいと大袈裟なんですがね(・-・*) )
で、仏教に限らず、いろんな「信仰」をテーマに
これからずらずら書こうと思ってはいるんですが。
その前にどうしても
通らなきゃいけないかも知れないかな
というテーマがあるのです。
それは、空海の思想との邂逅であり、対決です。

日本の仏教の成立期、その時代において
言ってみれば3人の「巨人」がおります。
それは誰かというと、まずは厩戸皇子、つまり聖徳太子です。
そして弘法大師空海、もう一人が伝教大師最澄でございます。
もちろん、行基とか鑑真の名も挙げられましょうが、
「体系的」な日本仏教の基礎を作った方々が、
このお三方だと言うわけです。
もちろんこの時代をさらに下ると、
新仏教というような「中興」期がありまして、
馴染みの深い、法然、親鸞、道元、日蓮などは
これにあたるのですが、
実はこの方々のルーツは比叡山。
つまりは最澄につながるわけで、この事から言えば
始めに述べたお三方が
日本仏教の基礎だと考えるわけです。
まず聖徳太子ですが、この方は
とにかく古代日本における
仏教経典研究の第一人者です。
聖徳太子が生きた7世紀の日本。
飛鳥時代ですが、
この時代は東アジア全体で外交から内政までの
微妙な舵取りを求められる時代でした。
聖徳太子は、この政治の舵取りの理念を
仏典に求めたわけですが、
実を言うと当時の東アジア国際社会における「文化の尺度」として、
自国がいかに「仏教化」かつ「律令化」されているかに
トレンドがあったわけなんですな。
つまり、仏教を知ると言うことは
この当時「最新鋭」のアイテムを手にした
「先進国」の証しであったというわけなんでございます。
したがって、聖徳太子が政治家としてこれに取り組み、
それを体系化させたのは、敏腕政治家として
ごく当たり前のことだったと推察されます。
聖徳太子が著した「三経義疏」は、
法華経・勝鬘経・維摩経の解説本で、
言ってみれば「仏教哲学」の大本として体系化したと言う事です。
ただ、これは民衆への教化というより、
政治理念の確立であったと
とらまえることが妥当でありましょう。
このあと、わが国における仏教は、
言ってみれば「政治ツール」の役割を担うことになり、
言ってみれば旧態然の保守派に対する
対抗策であったともとられます。
ただ、教条的・原理主義的な律令体制に対する
道義的な安全弁としてとらえられたというのが、
この3つの経典の内容からはうかがい知られます。
「義疏」とは、「解説」という意味です。
聖徳太子は僧ではありませんでしたが、
こういった仏典の解説を行ったわけです。
それゆえ、その後の古代日本は律令制度の充実と共に、
仏教が鎮護国家のアイテムと見なされ、その隆盛を見るわけです。
そして、仏典を学ぶということは、
上流階級のたしなみとして
当然のように優遇、奨励されたというわけなんですな。
ここにおいての仏教の立ち位置としては、
信仰と言うより教養という意味合いが
強かったのではないかと考えられます。
ある意味では、
中世ヨーロッパのカトリック教会のような
「権威」というものに変化していったと考えられるわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
