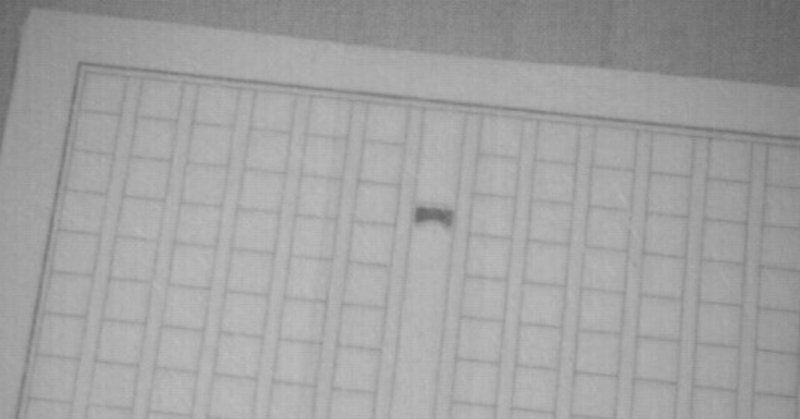
夏の終わりのじゆうけんきゅう(3)
かくして自らの身体をはった自由研究でお茶を濁したぼくだったが、クラスのなかにはやはりどうしても夏休み最終日に間に合わなかった友人たちがいた。
男女合わせて五人ほどだったろうか。
夏休みが開けた初日にそれぞれ研究の模造紙や工作を持ち寄り、詳しい内容は端折って、どんなことをしたのかだけを教室の端っこの列からひとりずつ順番に発表することになっていた。
ぼくは『アシナガバチにさされてからなおるまでのけんきゅう』をしました、といった。どこからか小さな笑い声が起きた気もしたが、気にすることはない。
クラスのなかに何人か、
「持ってくるのを忘れました」という生徒がいた。
誰もが、あゝ間に合わなかったのだな、あるいは、今晩泣きながら何か作るのか、気の毒に。と思った。
ひと夏かけて完成した自慢の研究や工作を忘れて来る生徒などいるはずがないからだ。
先生はそうした生徒に「そうか。ならば明日か明後日持って来なさい」とだけいった。
大人には、相手が100%嘘をいっているとわかっていても「そうですか」と収める場合があって、しかもその状況には大人のあるいは社会の事情的な、ときにはもっとシンプルな様々なパターンがあることを、ぼくはずっとあとに自分が大人になったときにはっきりと知ったのだけれど、そのときの先生の「一日二日待ってあげる優しさ」もきっとそういうことのひとつなのだろう、と子ども心にぼんやりと思っていたのだった。
Aくんも何もしていないクチだった。
「どうするん?」帰り道、すでに自由研究を完成させていたぼくは余裕を見せながら訊いた。
「昆虫採集でもするわ」とAくん。
「そんな簡単にはでけへんで」
ぼくは自分が蜂に刺された時のことを思い返しながら反論したが、Aくんは、すでに目処はついているというようなことをいった。
「ほんまかいな、まあ、がんばってくれ」
正直いって悪い予感しかしなかった。
翌朝、Aくんは固形石鹸の詰め合わせが入っていた赤い色の空き箱を、胸の高さに水平に掲げるようにして持ってきた。箱の大きさは下敷きと同じくらいか。
箱の上蓋に貼られた紙に「こん虫さいしゅう 〇年〇組 〇〇A雄」
よく見ると明らかにあとから書き足したように「家のちかくの」とあった。
「見る?」
Aくんが箱を手渡してきた。
見たくなかった。自分のなかのなにかが「見るな」と叫んでいた。
箱の底面に段ボールや厚紙を敷かずに箱に直接虫ピンを刺しているようで、箱の底から0.5ミリほど飛び出た針の先が指にザラザラチクチクと当たって不快極まりない。
「中、見てみ」
Aくんに即されて嫌々箱の蓋を開けてみた。
見知った(とはいえ正式な名称は誰も知らない)虫が箱の底に虫ピンで留められていた。簡単にいえば、その辺の石をごろんとひっくり返したときにガサガサと現れる連中である。
カナブンを艶消し黒にして小さくしたような甲虫がいた。
「べんじょむし」
と、Aくんの下手な字で書いていた。
その隣りは、べんじょむしを縦に伸ばしたようなフォルムで艶消し黒の
「ほそいべんじょむし」
その隣りは、怪獣ツインテールのようなフォルムでお尻にハサミがついている。黒光りした心底気持ちの悪いやつだった。
「はさみべんじょむし」
と書いていた。
(昆虫採集というより、べんじょむし採集やんけ)
といおうとしたのだが、その隣りの虫は、同じように艶消しではあるもののきちんと虫のフォルムをしている。ざっくりいえば、真っ黒い蜂であった。
「べんじょばち」
とあった。
要するにいつもより何分か早く起きたAくんは、家の近くの石をひっくり返して目についた虫を闇雲に捕まえてきたのだった。
話は絶叫の展開へ つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
