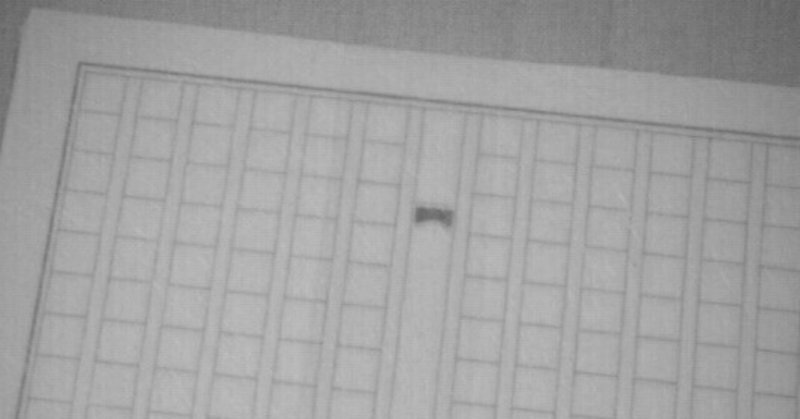
夏の終わりのじゆうけんきゅう(4 最終回)
一日遅れで提出する自由研究は、教卓とは別に教室の前にある先生の机の上に置いておくことになっていた。
Aくんは先生の言いつけ通り「家のちかくのこんちゅうさいしゅう」の箱を先生の机の上に置いた。
さっそくそれを見ていた他の男子が「どれどれ?」という感じで、蓋を開けてなかを覗く。
すると、その男子は「うっ」という声にならない声を漏らすのと同時に、大きな声で「おいおいみんな見てみ」と他の男子を呼んだのだった。
さて、前回(3)の最後に、箱のなかに「べんじょばち」がいたということを書いたが、実は書き漏らしていた『重大な事実』がある。
べんじょばちの横に、ムカデをそのまま小型化したような足がたくさんある最高に気持ち悪い虫が「げじげじ」として虫ピンで留められていて、さらにその横には、得体のしれないミミズのような生き物が「わからない」と記されて磔にされていた。
もはや虫ですらない。
さらに空いたスペースには付け合わせのようにしてダンゴムシが五、六匹、様々な体制で留められていた。
が、それはいい、としよう。
何よりも重大な事実とは、箱のなかの連中の何割かは、己の不運を嘆くかのように、まだカサカサと動いていたのである。
男子たちは、そこら辺にいる女子に手招きをした。
次の瞬間、教室を震わせるような女子たちの絶叫が響いたのだったーーー。
ここまでぼくやAくんの昭和のお馬鹿小学生男子の話を書いてきたわけだが、実はその年の自由研究にまつわる忘れ難いエピソードがもうひとつある。
夏休みが開けた初日、自由研究の詳しい内容を端折ってどんなことをしたのかだけをひとりずつ発表する時間があった、と書いた。
そのときに「やったけれど持ってくるのを忘れました」といった生徒がAくんを含んで四、五人いたとも書いた。先生はそんな生徒たちに「ならば明日か明後日持って来なさい」といった。
忘れがたいエピソードとは、その四、五人のなかにBさんという女子がいて、Bさんは自分の番になったときに、さっと立ち上がると、
「忘れました。自由研究をするのを忘れました」
と、いったのである。
教室中に音にならない「えっ?」が広がり、一瞬時間が止まったようになった。
(そんなことがあるのか)というよりも(そんなことが通用するのか)という驚愕の目でぼくたちは先生とBさんを交互に見た。
先生は一瞬、間を置いたものの「そうか」とだけいって、次の生徒を指した。そして入れ替わるようにBさんは着席したのだった。
Bさんは夏休みの間に他所から転入してきたわけでもないし、夏休みの間に大きな病気をしたという様子でもない。もしかしたら「自由研究どころではない家庭の事情」のようなものがあったのかとも思ったが、どうもそんな雰囲気でもない。一見、普段と変わらない様子だったのである。
ただBさんは起立している間、ぎゅっと両手の拳骨を握りしめて、唇を噛んでいた。
そのあとBさんがどうなったのかわからない。
ぼくたちの知らないところで、ひとり職員室に呼ばれて先生からこっぴどく叱られたのか、あるいは当時のお約束のように親も学校に呼ばれて、親子ともども「生活態度」について話し合い、何日かかっても必ず提出をするという約束をさせられたのか。
当時の学校と教師は「正しいこと」という名において、Bさんとその親をけっして許すことはないであろうことは、三年生のぼくたちでさえ恐怖心を以って理解、予感していたのだのだった。
しかし、と 改めてあの日のことを想う。
先生はあとでBさんに自由研究をしなかった理由を聞いたかもしれないが、結果的にBさんを許し、改めての提出を強いることもなかったのではないか。(実際に、のちにBさんが何かを提出していたという記憶はない)
そして、Bさんは、自分ではもうどうしようもないくらいに追い詰められた状況からようやく救い出されたのではないか。
当のBさん自身、何か特別な考えや意思があって自由研究を拒んだのではなく、誰もが抱く「面倒だな、嫌だな、やりたくないな」という気持ちが、ちょっとした何かが切っ掛けとなって、いつしか自分でも手に負えない(大げさに言えば、もはや頭や手先が思うように働かない)ほどに巨大で屈強なものになってしまったのではないだろうか。
そして、あのときの先生といえば(今、ぼく自身が当時の先生よりもはるかに年長となって思えば)、何十年にもわたる長い教員生活のなかの一年、二年、あるいは三年。教師として、ひとりの人間として、心が重く苦しく辛い時期だったのではないだろうか、と想像してみる。
人間長く生きていれば、どんな人生にも多かれ少なかれそうした「しんどい何年間」があるものだ。
もしかしたら先生は、当時先生という生活を続けるなかで、Bさん(ひとりの生徒の)自由研究どころではないという精神的に切迫した状況で、なかば投げやり的に「いいよ、いいよ」ということになったのかもしれないし、当時先生を疲弊させていた要因のひとつが、学校社会の上から下から強要される「正しいこと」の執行だったのだとすると、無意識にそうしたものからBさんを護ろうとしたのかもしれないな、と思う。
Bさんの「忘れました。自由研究をするのを忘れました」という言葉と、先生の「そうか」という言葉の「間」(ま)に、その答えががあったのではないのだろうか、そんな風に思うのである。
ずいぶんと脈絡のないふらふらした文章になってしまったけれど、「夏休みの自由研究」というワードで、半世紀が過ぎた今でもふと脳裏に浮かぶのは、Aくんの突拍子もない自由研究とともに、
人間とはいかに不完全で弱く愛おしいものかを写し撮った一葉のモノクローム写真のような、あの日のBさんと先生の姿なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
