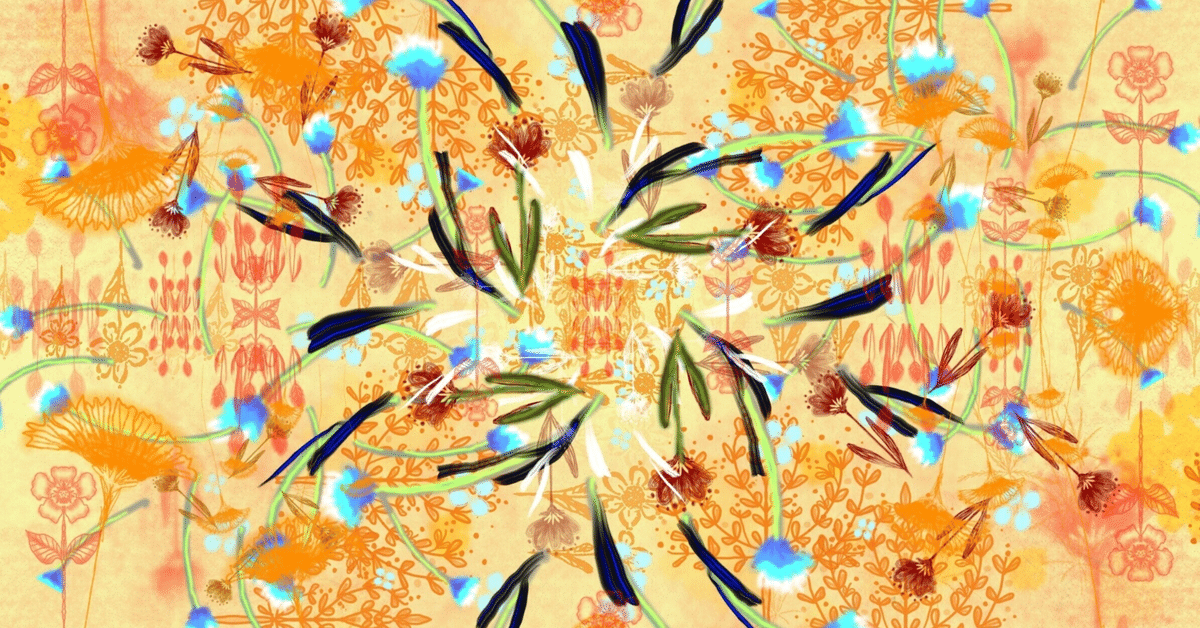
2022年、読んでよかった本
今年は9月くらいまでが本当に多忙だった。毎月の日系の大手メディアへの連載の執筆やプログラミングコンテストの準備等が重なって、ほとんど一人になれる時間はなかった。が、忙しくなると現実逃避としてなぜかはかどるものが読書。実は去年よりも本が読めたのではないかと思う。というわけで、読んで印象に残った本をおぼろげな記憶ベースで書き記していく。
なお、例年している言い訳になりますが、読んでから時間が経ったものも多く、かなりおぼろげな記憶を元に書いています。内容の誤認などは当然あるので、気になった本はポチッとして確かめてください。
バブルの経済理論
今年は経済状況が大きく動いた1年だった。ここ数年、日頃トレーディングをそれなりにしているので、自分が扱う商品のマーケット自体は頻繁にウォッチしているが、年初から今年は波乱の予感だと感じていた。去年の年末くらいから金利はじわじわ上がっていたので既定路線だったが、コロナによる全世界的な物流の制限や意外に労働者が戻らないアメリカの労働市場の状況をはじめとした供給不足からインフレになった。インフレになり、年末には10年以上続いた日本の異様な金融緩和が終わりを告げた。ちなみに某戦争はインフレとはあまり関係がなかったと思われる。
マーケットは眺めているので個々のマーケットの動きはそれなりに把握できていたかもしれないが、マクロ経済政策や金融政策についてはキャッチアップできていなかったので本書を読んでみることにした。本書を読んだ結果、ゼロ金利近傍では人の行動が変わり、それが当局(というか、ケインズ的な世界線というべきか)の想定外の動きをしていることや、新フィッシャー主義と呼ばれる主義主張があることなどを知った。MMT くらいで止まっていた私のマクロ経済に関する知識がアップデートされた。
この本を読んだ9月ごろに、その時点でおそらく近々金融政策は修正され、政策金利は上がるのだろうと思った。新フィッシャー主義の主張は雑にまとめると、フィッシャー方程式「名目金利 = 実質金利 + 期待インフレ率」のうち、名目金利を 0% とおくと、日銀の想定では「0% = -2% + 2%」であったが、実際はゼロ金利近傍では人の行動が変容し、「0% = 2% + -2%」、つまり期待インフレ率が-2%(実質デフレ)が起きているのではないかというものだ。これはたとえば、銀行は利下げが起きると利益をむしろ圧迫されるので、貸し出しが渋る結果につながるとか、一般の家計について言えば、資産ポートフォリオに債券だけでなく貨幣つまり現金が加わるとか、さまざまな「想定外」の行動が発生するためだ。
利上げは国債の償還額を実質増やすことになるので、一見直感に反するかもしれない。利上げにより増税が起きるのではという声もある。が、おそらく今の高すぎる国債の自国保有率(95%くらいでしたっけ)を85%程度に下げれば1%の実質利下げになるので、次の一手としてはそれを狙ってくるかもしれない。
で、結果10年債の YCC 変動幅調整が入り、事実上日銀が政策を軌道修正した。来年は日銀総裁も変わる。その準備だったのだろうと思っている。マイナス金利はあと2年くらいは続きそうという予測もあるが、いずれにせよ金利がちゃんと正常化されるのはよいことだ。
関連書籍として、「経済学者は政策による社会実験の責任を取らなくていいので好き勝手言えるが、日銀の政策担当者は何を考えているのだろう?」というのを知りたくなって、下記の書籍を最近読んでいる。次の総裁候補として取り沙汰される中曽さんの一冊。おもしろいです。
「みんな違ってみんないい」のか?
ディスカッションしようとすると「人それぞれだよね」という意見を表明しがちで、それ以上踏み込もうとしない大学生の話が、以前どこかのメディアに上がっていた。こうした「人それぞれだから踏み込まなくていいよね」は現代人の一つの病と言える。これは一見賢そうな態度だが、単に対話を拒絶して自分を守っているだけで相手の価値観を理解しようとしていない態度とも言えるため、知的に高度な行動であるとは言えない。本当に知的な態度を取るなら、自分の主張に対して相手の引っ掛かっているポイントを対話で探って、落とし所を見つける行動を取るべきである。
雑に本書の論旨をまとめると「みんなちがうというほど人は違うわけではないことを、進化生物学などの知見から説明」「道徳的な正しさと正しい事実が何かを勝手に決めてはならない」「対話をして合意をとってよりよい正しさを見つけていきましょうね」といったところだろうか。
私はこの本の論旨に基本的に同意するし、こうした相対主義や懐疑論はたしかに新しい視点を生み出すこともあると言えばあるが、基本的には何か新しい概念を生み出したりはしないし、社会を前に進めたりはしないと思っている。だから対話をして合意をしましょうね、というのは合理的な標榜だ。
ただ、現代社会で問題になっているのは「対話拒否」の方なように思う。対話拒否される時代状況の中で「対話しましょうね」というスローガンを掲げるのはたしかに重要だが、対話拒否を望む相手をどう対話のフィールドに引っ張り出すかの方法論の方が求められているように私は思った。そもそも異なる価値観が可視化され、全面的にそれらがぶつかるようになったのが最近の話ではあるから、この状況自体が歴史が浅いと言える。今後検討が進みそうではある。
教養としてのラテン語の授業
ラテン語は大学の授業でとった。今でも少し読める。装丁がきれいだったので買ったがよかった。
ラテン語は今となっては役に立っている。とくに役に立っているのは英語を使う時だ。英語はさまざまな地域の言葉を柔軟に取り入れてしまったので、結果ラテン語由来のものも結構多い。ちなみに英語のスペルと発音が一致しないことへの文句をよく目にするが、これには理由がある。一致しない単語はだいたいが外国語から輸入された(多いのはフランス語由来のものだ。ノルマンコンクエストというイベントがあったことを思い出してほしい)ものだからだ。
「今となっては役に立っている」と書いたのは、当時大学生だった私は選択を間違えたからだ。哲学の文献を読む際にはたしかにラテン語の知識は役に立ったが、それより必要だったのは古典ギリシャ語の授業をとることだった。
肝心の本の内容だが、ラテン語の名言をきっかけにしてローマ帝国の与太話とキリスト教関連の与太話から導かれる人生訓が説かれるといったものだ。ラテン語の文法解説などはほとんどなされないので注意が必要。「教養としての」の部分に太字がつくイメージだ。いわゆるヨーロッパ社会を支える(といったとき、だいたい東欧は含まれないのだが)リベラルアーツと呼ばれる概念を体感するにはいい一冊な気はした。
資本主義だけ残った
これは教育がよくないとは思うが、政治学などを専攻にしなかった人々は「政治体制というのは世の中に一つしかあるべきではない」と考える傾向にあるのではないかと最近感じている。ところが、政治体制というのはこれまでたくさん移り変わってきたし、ポリビオスという人は政治体制というのはそもそも移り変わるものだと昔述べているくらいなのだ。要するに相対的な存在なのだ。そして、今でさえ民主主義はかつての輝きを失い、多くの国は専制的な政治体制を敷くようになりはじめている−–近年新しく採用される政治体制のほとんどは、実は専制政治なのだという研究結果すらある。
経済体制も同様に、これまでいくつか制度が考案されてきたし、ある種壮大な社会実験がされてきた。ところが経済体制だけは、現代では資本主義だけが残り他の体制は見る影もなくなった。しかし一方で、資本主義にもやはり流儀がいくつか生まれることになった。本書では、それぞれの流儀を分析し資本主義がどのように進化していくかを考察する。
政治体制は違えども、たとえば日本も中国も資本主義を採用していることは事実だ。ただ、形が違う。日本はリベラル資本主義というものに分類でき、中国は政治資本主義というものに分類できると本書は説く。およそ想像がつく通り、政治資本主義は政策の立案から反映までが早い。リベラル資本主義は遅い。一方で、政治資本主義は賄賂や不正などの腐敗が進みやすい。
採用する社会システムが異なる相手は確かに怖い存在かもしれないが、こうしてカテゴライズすることで冷静に客観視できるようになる。本書を通じて新しい視点を手に入れられたと感じた。
まとめ
これ以外にも数十冊読んだと思う。今年は経済状況が大きく動いていると感じていたこともあり、比較的経済に関する本を多く読んだ。来年はもう少し幅広いジャンルの本を読みたいと思う。最近遺伝子編集が話題なのでそのあたりとか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
