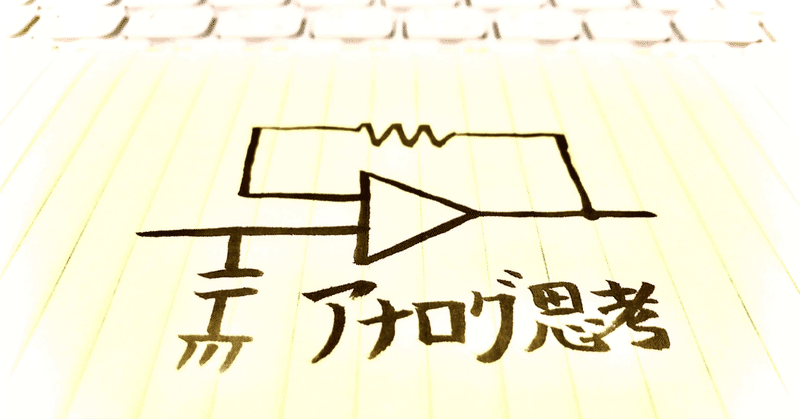
チャンネルディバイダーとパッシブネットワークで分割共振は制御できるのか?
マルチウェイのパッシブスピーカーユニットをパワーアンプで駆動する場合、ユニット間の周波数分割の方法として大きく2つあります。
アクティブ方式(チャンネルディバイダにより入力信号を帯域分割し、帯域分割された信号でパワーアンプとスピーカーユニットを駆動する)
パッシブ方式(入力信号とパワーアンプまでは1系統で、スピーカーユニット内のパッシブネットワーク(受動素子(LCR)で構成されたLPF, HPFなど)で、パワーアンプの出力を帯域分割して、スピーカーユニットを駆動する)
こちらの記事は2wayのパッシブネットワークを調整している記事で、参考になります。
パワーアンプからするとパッシブネットワークは負荷となり、特に低域のLPFは大きな負荷となります。
通常、設計目標として、スピーカーユニットの周波数応答ができるだけフラットになる周波数領域だけを透過するフィルターを構成します。逆に言うと周波数特性がフラットで無い周波数領域は、入力電気信号に対して、出力機械信号(音波)の応答が非線形となっています。
したがって、電気系のフィルターで不要周波数帯域を減衰させることで、機械系の線形応答が得られることが前提になっています。
しかしながら、分割振動は機械系の非線形応答なので、単純な線形フィルターでは、必ずしも意図した効果が得られない場合があります。
そこで、ノッチフィルターなどの付加的なフィルターで非線形応答を制御することになります。
ここで、盲点だと思われるのは、パワーアンプからすると非線形負荷がさらに増えることになることです。なぜなら、完全な線形特性の受動素子はそもそも実際の部品としては入手できないからです。
これまで、チャンネルディバイダもパッシブネットワークもいろいろ試してきましたが、パワーアンプの評価用のスピーカーシステムとしては、フルレンジか、それにHPF(fc=4kHz, -12dB/oct)とツイーターをアドオンしたシンプルな2ウェイが無難という結論です。
4kHzというのはピアノの一番右側の鍵盤の基音となる周波数なので、これより高い周波数は通常人間の聴覚としては倍音として認識されます。
また、スピーカーユニットごとに動的な周波数特性は大きく異なるため、チャンネルディバイダでアクティブに周波数分割する場合はLinkwitzフィルタ(-24db/oct)が無難で、それより浅くても深くてもつながりに違和感が出やすくなります。
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
