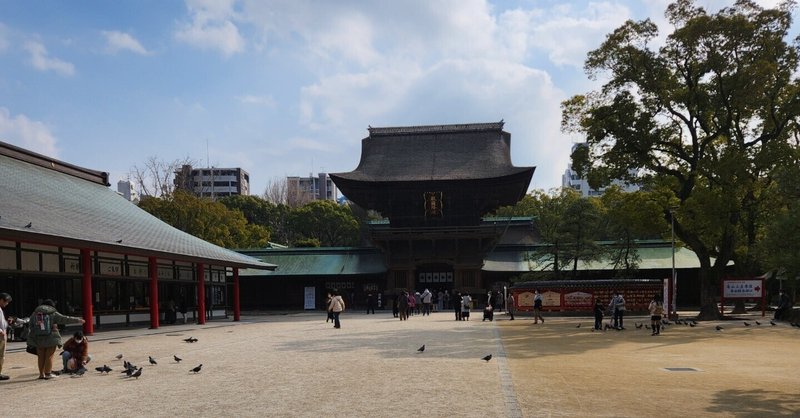
介護事業経営調査委員会での数値を見ての私見①
令和5年2月1日、介護給付費分科会において介護事業経営調査委員会が開催され、その資料により私見を述べる。
他の介護コンサルタントで、こうした資料をただ説明している方々もいらっしゃるが、私はそこにあまり意味を感じない。
なぜなら、そもそも「説明するにあたり、自分の考えがない説明は全く意味が無い」と思っているからである。
ここでは「令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要」を基礎として、税理士であり、介護コンサルタントである私なりのあくまでも私見を述べる。
まず前提として、「利益率」と「収支差率」の話をする。
一般的に企業の損益計算表においては、いくつかの利益を示しているが、ここでは「税引き後当期純利益」を想定、「利益率」として話を進める(①)。
また、介護事業は介護保険収入が収入の大部分を占めている。確かに国保連を通じて請求のやり取りが行われるので入金時期はズレるが、これは現金主義とも言えるので収支、つまり「収支差率」を用いる(②)。
つまり、会計的には、違和感があるものの僅少の差違とし①の利益率と②の収支差率の細かい部分を捨象して比較を行う。
企業①・・・利益率 3~4%
(全ての企業の大まかな平均値と置く)
介護②・・・収支差率 3.0%(全サービス平均 令和3年度決算)
介護時期は、全サービス平均 令和2年度決算で3.9%であったので、令和3年度では前年対比▲0.9%ということとなる。
まあ、これだけ見ると全サービス平均では、①と②を比較すると、現時点、一般的な企業と介護事業者では、適正な利益水準に収斂しているとも思える。
では、次に個別の介護サービスの数値を見ることにしよう。ここでは、前年対比に関係なく、令和3年度決算が、特に収支差率が4%以上の介護サービス事業に着目する。
(令和3年度決算)
介護医療院・・5.8%
訪問介護・・・6.1%
特定施設入居者生活介護・・・4.0%
居宅介護支援・・・4.0%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・・・8.2%
認知症対応型通所介護・・・4.4%
小規模多機能型居宅介護・・・4.7%
認知症対応型共同生活介護・・・4.9%
看護小規模多機能型居宅介護・・・4.6%
この介護サービス事業を見て感じることがありませんか?
つまり「政策誘導」されている介護サービス事業は、当然のことながら、概ね「収支差率が高い」ことである。
たとえば、介護医療院は、介護療養型医療施設等からの転換の経過期間のため、収支差率は高いのだ(とは言っても介護医療院のカテゴリーができたらのが平成30年4月なので加算や収支差率も低下傾向にある)。
地域密着型サービスも、もちろん注目されている。
では、上記、サービスのうち、政策誘導に当てはまらず、収支差率が4%以上の介護サービスについては、この収支差率がなぜ出てくるのか、他の介護サービスと何が違うのか、その説明や理由が必要なはずである。
さもなくば、次回介護報酬改定では厳しい事象が起こるかも知れない。よって、業界団体としても、今後介護報酬分科会において、業界団体へのヒアリング等において、しっかりした取り組みが必須である。
反面、他の介護サービスはある意味、収支差率がある程度絞り切れており、今後は「収支差率に対する給与費割合」という論点の検討とならざるを得ないだろう。
次回ブログでは、この話の続き、給与費割合の論点から②として、この話を継続することとする。
今回もブログ「旗本雑居帳」をお読み頂き、ありがとうございました。次回のブログもお楽しみに❗👍️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
