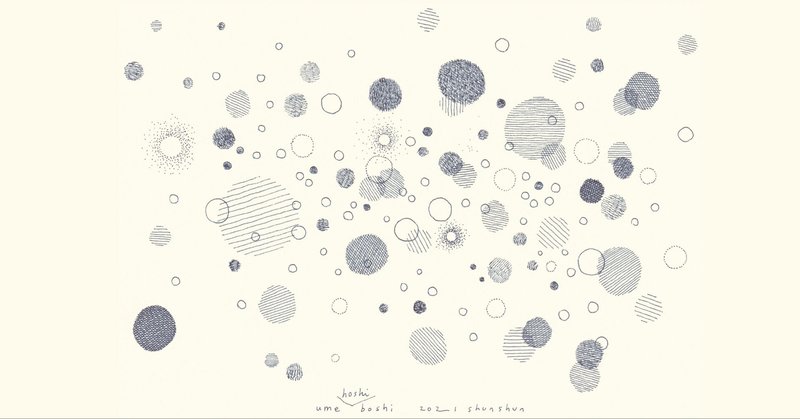
vol.33 「梅干先輩」芒種 6/5〜6/20
今年も梅農家を営む知人に梅干し用の南高梅を注文した。梅が届いたらすぐさま大きなザルに広げて黄色くなるまで追熟を待つ。数日経つと、青梅は次第に色づき、ポッと頬を染めたように赤みを帯びてくるものもある。そうなってくると、部屋中が甘酸っぱいような、なんとも言えない芳しい香りに包まれていく。
梅干を漬け始めるようになったのはいつ頃からだろう?震災があった年は途切れてしまったけれど、それを除けば10年以上は続けている。食べたいから作っているのはもちろんだが、梅しごとの作業自体が好き…いやもっと単純に追熟の時のあの香りに出会うために、毎年続けているようなところがある。
以前にとある雑誌の連載ページに梅しごとの話を書いたことがきっかけで、ご近所の方と梅干作りの話になったことがあった。お相手は人生の大先輩。しかも男性の方。どの品種の梅を使うか、塩はどんなものを使うか、赤紫蘇の有無や他にもいろいろ。私自身は塩の種類や塩分濃度を変えたりということはあっても、やり方は一度覚えたままで毎年続けているだけだったから、その方が実験をするように梅干作りを楽しんでいらっしゃるお話がとても興味深かった。甕がいくつもあると伺ったけれど、一体何kgの梅を漬けているのだろう?後日、梅干ではないが甘く漬けた梅のシソ漬けを戴いた。香りが良く、程よい酸味が爽やかで美味しいこと、美味しいこと。私にとっての梅干先輩。先輩が仕込んだ甕がいくつも並ぶ様子を想像しているだけで豊かな気持ちになっていく。
ある朝、自宅からin-kyoに向かって歩いていると、梅干し先輩とバッタリお会いしたことがあった。
「おはようございます」
しばし立ち話。もちろん話題は梅干のことである。
「梅干のことなら乗松祥子さんという方の本が図書館にあるから一度読んでみるといいですよ。私はとっても勉強になって参考にしているんですよ」
早速、図書館で本を借りて勉強、勉強。道端で梅干作りのことで会話ができて、そして新しい扉が開いていく。年代も性別も超えて、共通の話題があること、しかもそれが梅干という日常的なことが、なんだかたまらなく平和に感じられて嬉しかったことを覚えている。
祖母が元気だった頃は、毎年自宅の梅の木から採れた梅の実を使って梅干を漬けていた。祖母の梅干は赤シソを使わない塩だけで漬けたもの。茶色くて梅干本来のしっかりとした酸っぱさで、子供の頃はなかなか好んで食べることはなかった。塩の分量も塩分濃度をちゃんと測っていたかどうかは定かではない。塩が入った容器には、いつもホーローでできたレンゲを入れたまま使っていたので、おそらく祖母は梅の大体の量に対して「レンゲ何杯分」といった測り方をしていた気がする。今さらながら、あの頃祖母にもっと聞いておけば良かったなぁとか、あれはどうしていたのだろうと思うことが多くなっている。いつどのタイミングで土用干しをするのか。パーセントといった数字的なものを超えて、それでもブレないような味が定まったときに、その人ならではの味というものが出来あがっていくのでしょう。祖母も私にとっては梅干の大先輩。祖母の味ともまた違う味。私が目指す味とはどんなものだろう?
今の家の庭にも梅の木があるが、しばらく手入れもされていなかった梅の木は、なかなか実をつけないまま、春先になるとかろうじていくつかの花だけを咲かせている。本来だったらこの梅の木に成る実で梅干を漬けたいところだけれど、それは叶わずにいる。先の梅農家の知人は、東京でお店を営んでいた頃に出会っていた人で、縁あって移住をした和歌山県で梅農家に就農し、農薬も肥料も使わずに自然栽培で梅を育てている。ここ数年はそこで大事に育てられ、収穫された南高梅を使って梅干を作っている。その梅の実には斑点があったり、大きさが揃っていないなど、欠点もあるけれど、自然栽培という安心感と、育てている人を知っているからか、あばたもえくぼよろしくその姿も含めて愛おしい。実際にはこれまで使っていたどの梅よりも香りも味わいも良く、実は好みのやわらかさで仕上がってくれる。
我が家の梅の実、知人が育てる梅。三春の隣町の西田町には高田梅という品種の梅の産地があるからその梅を使ってと、いつかはそれぞれ甕を変えて、梅干先輩のように仕込んでみたいという夢もある。たかが梅干、されど梅干。作業自体は単純なものの、やればやるほど奥が深い。梅干先輩は今年は果たしてどんな実験をするのだろう?お天道様のご機嫌を伺いながら、今年も無事に土用干しができることを願っている。
梅干というと、深くシワが入った祖母の手の甲を思い出す。「梅はその日の難逃れ」ということわざの通り、自分で作った梅干に上白糖を少しかけて、毎朝ひと粒をおいしそうに食べていた祖母の姿も。上白糖こそかけて食べることはしないけれど、この時期のお弁当には毎日のように梅干を入れて炊いたご飯をつめて、仕事場に持参している。私の手の甲に深いシワが刻まれる頃には、私の味というものができあがっているのだろうか。まだまだ、まだまだと梅干先輩たちの背中を追うようにしていることも作り続けている理由のひとつ。ひょっとしたら梅の香りはその気持ちを助けてくれているのかもしれない。そうやっていつの間にかここ数年が過ぎている。
