イカとロケットの同じところは? 「異なるものの中から同じをみつける」ことと創造性
さっそくですが、イカとロケットの同じところは何でしょうか?
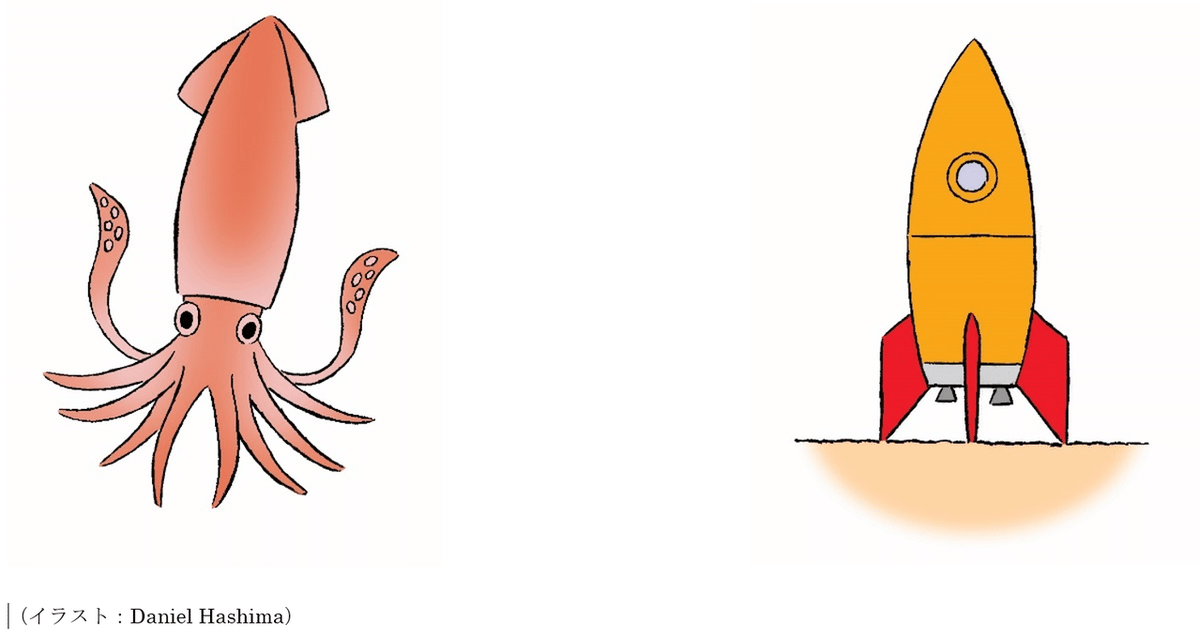
イカは海にくらす生きものです。香ばしいイカ焼きやお刺身や煮物、イカ墨のパスタなど、食べ物としても身近です。一方、ロケットは人工衛星などを載せて宇宙まで飛んでいくものです。
イカは生きものだけど、ロケットは人間が作ったもの、イカは食べられるけど、ロケットは食べられない、イカはくにゃくにゃだけど、ロケットは硬い。大きさも全然違っていて、あまり似たところはありません。
一見なんの関係もなさそうですが、移動の方法に着目してみると……。
イカが敵から逃げるときは、勢いよく体の中から液体(吸い込んだ海水)を噴き出して、その反作用によって進みます。イカは敵の注目をそらすために墨も吐くので、逃げるときの原理が見た目にもわかりやすいですね。
一方、ロケットは内部で燃料を燃焼させ、その燃焼ガスを勢いよく噴射し、その反作用によって進みます。
どちらも、内部から勢いよく流体(液体、気体)を噴き出して、その力の反作用によって動きます。そのしくみは「同じ」なのです。

このように、性質や大きさが違う異なるものの中にも、ある観点から見れば「同じ」を見つけることができるのです。
「だから?」
じつは、この「異なるものの中に同じを見つける」ことは、あらゆる発明において行われている、と考えるのが「等価変換創造理論(Equivalent Transformation Theory =ET理論)」です。
ET理論は、「創造」に共通するプロセスを解明し、体系化した理論で、市川亀久彌が65年前に提唱しました。"創造性の科学"として、工業的な発明や開発だけでなく、芸術や社会の構造、さらには歴史的な展開の過程までを視野に入れた理論です。
ET理論では、創造の過程をこのような式で表しています。「等価方程式」と言います。

「こんな記号の集まりなんてムリ」という人も多いので、多少アバウトに日本語の図にします。

簡単に言い表すと、
① ある観点において、参考になるものAを見つける。
② Aの中からAに固有なものを捨て、ある観点での本質を抽出する。
③ その本質に必要なものを加えてBを作り出す。
となります。
つまり、どんな発明でもまったくなにもないところから何かをつくりだすのではなく、必ずすでにある何かをどこかに受けついでいるのです。
「創造的活動とは、過去より受け継いだものの中から、なにがしかのものを捨てさり、かつ、これに現時点で獲得できる別の新しい要素を導入して、改めて全体を再構成していくこと」
(市川亀久彌著『創造性の科学』より)
わかりやすい例を紹介します。
1950年代の日本でのこと。印刷会社で働いていた岡田良男さん。社内では紙を切る仕事が多く、カミソリで切っていたのですが、すぐに切れなくなっていたそうです。
当時、路上の靴職人はガラスの破片を使って靴底を削っていて、切れ味が悪くなるとさらに割って新しくできた鋭利な部分を使っていたそうで、それを見た岡田さんは、ふと、戦後、進駐軍の兵士が持っていた板チョコのことを思い出して、ある発想を得たそうです。
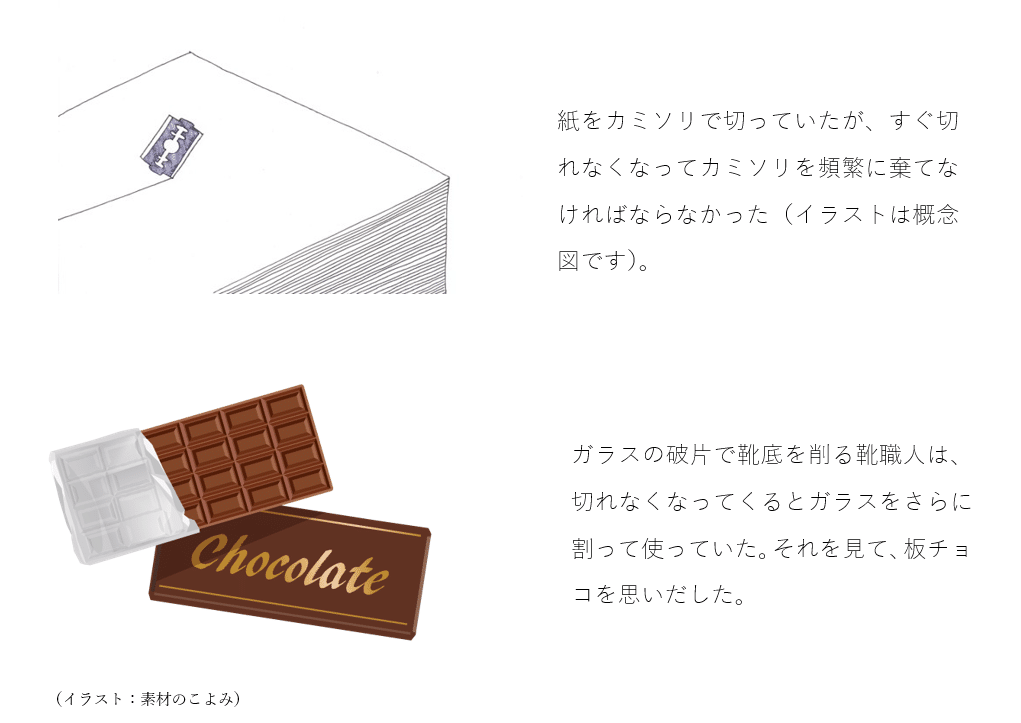
岡田さんが発明したものは何だと思いますか?
それは、「次々に折って使う刃」でした。
そうです。このようにしてカッターナイフは発明されたのです。
岡田さんの会社はオルファという会社になりました。
オルファのサイトにはこのエピソードが掲載されています。
https://www.olfa.co.jp/birth_of_olfa_cutter/index.html
カッターナイフの発明の過程をET理論で考えてみましょう。
さきほどの図に当てはめると、こうなります。

① 「簡単に折れる」という観点で、板チョコがAになることを見つける。
② A=板チョコの中から、板チョコに固有なもの(材料や味、作り方など)を捨て、「簡単に折れる」という観点での本質=「溝がついている」を抽出する。
③ その本質に必要なもの(刃を持つためのカバーや、刃を固定するものなど)を加えてB=カッターナイフを作り出す。
新しいものをつくり出すという意味では、重要なのは①と②の過程です。なかでも、何か課題があるときに、Aが見つけられれば(①)、ざっくりとしたBのアイデアは浮かんでいるはずです。
その観点での本質を抽出することで(②)、Aそのものから離れてBを作り出すための準備が整います。③はアイデアの仕上げの段階です。
カッターナイフの例で言うと、「カミソリがすぐに切れなくなって頻繁に捨ててしまわなければならない」という困りごとを抱えていた岡田さんが、板チョコが自分の課題解決に使えると見つけたこと(板チョコをAとしたこと)が、カッターナイフ(B)の発明に決定的でした(岡田さんの場合、板チョコを見つける前段階として、靴職人がガラス片を割りながら使っているという情報に触れていたことが板チョコを思い出すきっかけになりました)。
岡田さんは、口の中で溶けるとか、甘いとか、茶色いとか、さまざまな特徴が一体となったチョコレートそのものを思い出したのではなく、「簡単に折れる」という観点で板チョコを思い出したからこそ、カッターナイフを生み出すことができたのです。
では、このような創造過程と「異なるものの中に同じを見つける」は、どうかかわっているのでしょうか。
たとえば、イカとロケットの中に「同じ」を見つけることは、それぞれから「ある観点での本質」を抽出し、それが「同じ」ことを見つけているのです。
発明や開発の場合は、すでにあるなにか(A)と、これからつくろうとしているもの(B)との間の同じ「ある観点での本質」を見つけているとも言えます。
ですから、「異なるものの中に同じを見つける」力は、発想力、ひいては創造力の基礎的な力なのです。
ET理論では創造性は天才や偉人だけでなく、「だれもが創造性を持ち、人間とは創造的な活動に生きがいを見出すものである」という人間観を打ち出しています。
創造的活動とは、
1.主体的(自発的)な活動であり、
2.結果(未来)が予想できず、
3.努力が実を結ぶ活動
のことを指します。
だとすれば、創造的活動とは、「人が主体的に自分らしく生きること」と言い換えることもできます。だからこそ、創造性を伸ばすことは子どもにとっても大人にとっても大事なことだと考えます。
そんな思いから、「異なるものの中から同じを見つける」を中心に、創造性について書いていければ、と思っています。
*** *** *** *** *** ***
「等価変換理論」については、おいおい紹介できればと思いますが、以下のサイトや本などもあります。
●入門書:『改訂・増補版 創造性の科学――図解・等価変換理論入門』市川亀久彌著
1970年より20年あまり版を重ねたロングセラーの入門書を2005年に改訂・増補。

オンデマンド出版でお求めいただけます。
四六判272ページ(5,500円+税)
冒頭の52ページはカラーでさまざまな「同じ」や「発見」「発明」を視覚的に展開。
●『図解でわかる等価変換理論―技術開発に役立つ70のポイント』(等価変換創造学会著 日刊工業新聞社)
四六版162ページ(2,200円+税)
実際の開発事例の解説を中心に、技術開発力を高めるトレーニングなど。見開きごとに図解。
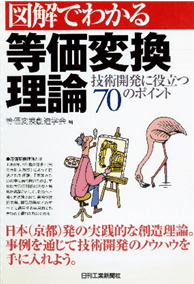
●実践的な開発や問題解決の通信講座もたくさんの方に受講していただいています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
