
Happy Women's Map 茨城県古河市 日本で最も名声を高めた女流文人画家 奥原 晴湖 女史 / The Most Renowned Female Literati Painter, Ms. Seiko Okuhara

「里に入りてまた一聲(こえ)や杜鵑(ほととぎす)」
"Entering the village, another cry of the cuckoo"
奥原 晴湖 (本名 池田 せつ子)
Ms. Seiko Okuhara
1837 - 1913
茨城県古河市 出身
Born in Koga-city, Ibaraki-ken
奥原 晴湖女史は日本の代表的な男装の女流文人画家です。彼女の「詩書画一致」の作品は幕末から明治の激動の世にいきる人々に熱狂的に支持されました。
Ms. Seiko Okuhara is the most renowned female Literati Painter in Japan. Her "Harmony in Verse, Script, and Brushwork" were enthusiastically supported by the people living in the tumultuous times spanning the end of the Edo period to the Meiji. She is acclaimed alongside Noguchi Shohin as a pair of distinguished female Southern-style painters of the Meiji era.
「墨吐煙雲楼」
せつ子は、古河藩士の父・池田繁右衛門政明、蘭学者を伯父にもつ母・きくの間に生まれます。幼い頃より男勝りの性格で、薙刀・剣術・柔術・絵筆の上達早く、まわりの男子から恐れられながら藩の儒者・茅根一鴎に漢学・和歌・俳句・茶道を学びます。10歳から叔父である古賀藩家老で蘭学者の鷹見泉石のもと学問を学び、17歳から古賀藩の南画家・枚田水石に書画を学びます。「古賀で話せる者は泉石隠居ただ一人だ」。文金高島田の二十歳前後の娘が70歳を過ぎた白髪の老学者を相手に天下の形勢を論じます。せつ子は男達からの縁談また口説きを切り捨てては投げ飛ばし、名文・名画を片っ端から模写しながら生涯独身を決意。江戸で画家として身を立てようと考えるようになりますが、古賀藩は女子が単身で江戸はもとより旅に出ることを禁じていました。29 歳のとき、猛反対する家族を説得、気心の知れた侍女・おでんを伴い、叔母の嫁ぎ先である奥原家の養女となって江戸に出ます。文人墨客の住む上野の下谷に居を構え、「墨吐煙雲楼」と看板を掲げ、「晴湖」と号します。
「不忍池集」
せつ子は自筆書の扇子を名刺代わりに、先輩書家・画家らのあいさつ回りを始めます。外見の美しさと覇気縦横の筆力と談論風発の応対ぶりが評判となり、同年の暮れに不忍池の三河屋で盛大なるお披露目会を開催します。詩人の大沼枕山・鱸松塘・上村蘆洲、書家の関雪江・高斎單山・山内香溪、画家の鈴木鵞湖・松岡環翠・坂田鴎客・福島柳圃・服部波山など25名もの大家の参加と合筆「不忍池集」を受けます。せつ子は他人の書画会にも努めて顔を出しながら、「どうです。私のところで一杯やりませんか。」男達と対等の交際をするために大いに酒を飲みます。父からの支援金25両が尽きると、兄から米を送ってもらい、さらに質屋通いをして着物を次々と酒代にあてます。そして、清の画家の鄭板橋を発掘して研究、豪快洒脱な即興書画で人気者となります。「私の書も画も自己流です。鄭板橋のほうが私に似てきたのでしょう。」
「容堂攻略」
明治維新の混沌時代、知識階級の中で文人画が流行。特に大権政家の山内容堂の一面風流文雅の雅宴へ参会しようと文人墨客が先を争います。せつ子もようやく招待を受けると、当日主席する先輩大家をひとりひとり手土産とともに訪ねてまわり、自分の席順を最上席にすること、ならびに自分の画を褒めるよう約束をとりつけます。会の当日、他の出席者が勢揃いして着席した頃、せつ子は鮮やかな黄八丈の2枚重ねの上に黒ちりめんの羽織とだるまがえしの粋な髪型で参上。一同のどよめきの中を最上座に着席。会が始まると、せつ子は得意の啖呵とダイナミックな筆また先輩大家の援護評価で容堂を圧倒します。「御(あんた)はすこぶる才子と聞くが本当か。」「私がもし男ならば、朝に立てば天下を料理し、野にあれば大富豪になるものを、残念ながら女と生まれたために絵筆を舐って末席を汚しております。」容堂はじめ木戸孝允の贔屓を得たせつ子は、皇后の御前揮毫の機会を得、南画家として一躍有名になります。総勢300人以上の門人を抱えながら、鷲津毅堂・小長井小舟・市河萬庵・川上冬崖らと雅会「半間社」を結成、文人画の研究と隆盛に尽力します。
「繍佛草堂」
男子の断髪廃刀令が出ると、女子の断髪は禁止じられるも、44歳のせつ子は持病のためと申し立て散切り頭にします。黒羽二重で五つ紋の男羽織に仙台袴、男の様に振舞います。おびただしい数の来客と揮毫依頼に、せつ子の借家は大豪邸に、せつ子の体は相撲取りのように、せつ子の筆はますます豪宕無類となります。清湖は一度筆を取ると渾身の気力奔しらせ、誤字脱字を気にも留めず次々と書きあげます。「学問ない奴はほんとの字を書いたって読めない。読めるものは少しぐらい間違っていても通じる」。やがて、岡倉天心とフェノロサが始めた新日本画運動が盛り上がって美術学校創設に発展。文人画非芸術論におされ、せつ子ら文人書家・画家らは人々から顧りみられなくなります。せつ子は55歳の時に、埼玉県熊谷の草深い川上村に画室付きの住宅「繍佛草堂」を建て、同じく散切り頭の女弟子・晴嵐(せいらん)と共に隠棲します。「紅塵避け、俗物避けだよ。真に用のある人は草を分けても訪ねてくる」。2人で長期にわたって北越方面松島、東北方面、関西方面を旅をしながら風光また名書画を研究の資とします。日露戦争がはじまると、せつ子のもとに俄かに揮毫依頼や訪問客が増え、門前の草は踏み絶やされます。一変して神韻で雄渾蒼潤な書画を描き続けながら、せつ子は77 歳の生涯を閉じました。
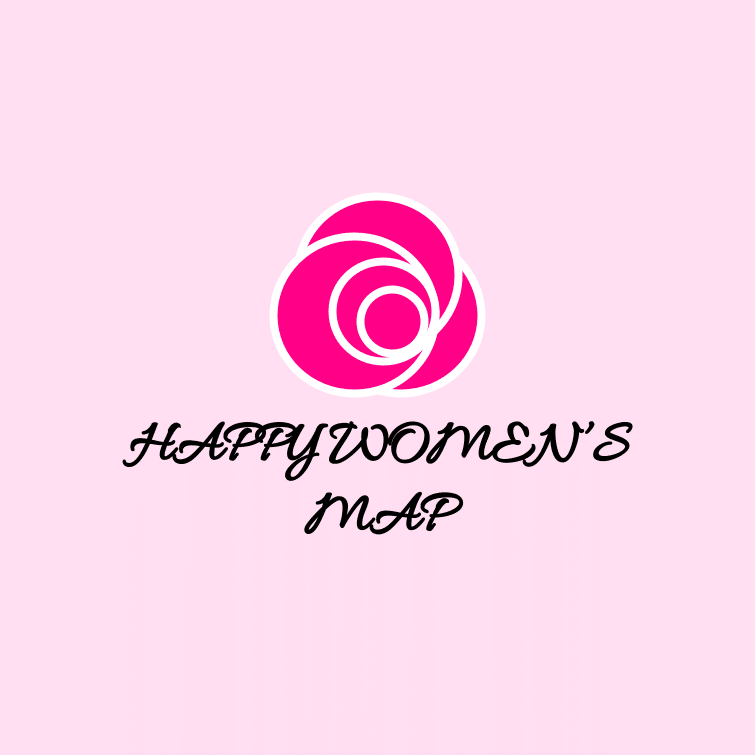
Share Your Love and Happy Women's Story!
あなたを元気にする女性の逸話をお寄せください!
Share your story of a woman that inspires you!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
