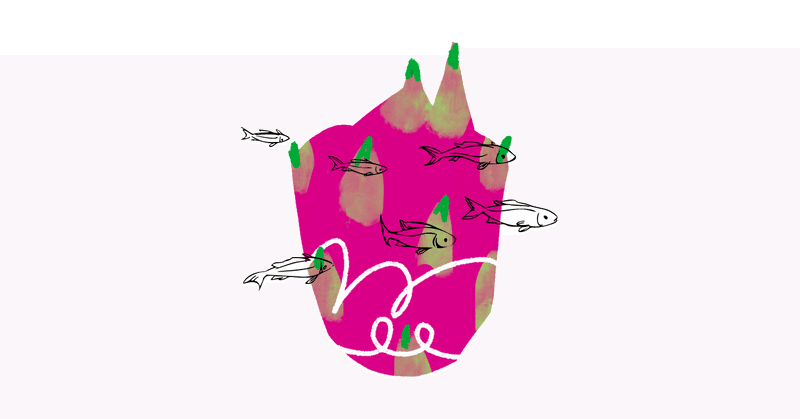
民族浄化思想のいま
医師であり
当時内務省衛生局予防課長で後の同省予防局長の高野は
大正15年5月財団法人中央社会事業協会発行の「社会事業」において
「民族浄化のために」と題する論考を掲載した
そこには次のような記述がある
以下は読みやすく若干修正した文章である
「らい病はだれしも忌む病気である。見るからに醜悪無残の疾患で、これを蛇蝎以上に嫌いかつ怖れる。」
「こんな病気を国民から駆逐し去ることは、誰しもねがうところに相違ない。民族の血液を浄化するために、またこの残虐な病苦から同胞を救うために、慈善事業、救療事業の第一位に数えられなければならぬ仕事である。」
「要するに、らい予防の根本は結局らいの絶対隔離である。この隔離を最も厳粛に実行することが予防の骨子となるべきである。」
日本において
堂々と かつ 意識的に
感染症対策を理由とした
「民族浄化」が語られた論考である
いまの視点でみれば
この論考の「ヤバさ」がわかるだろうか?
「差別はいけない」ことは当然のはずである
ハンセン病患者及びその家族に対する差別もまた
当時の誤りを反省して
いまに至っているはずであった
しかし日本社会が「頭で知識として理解した」だけでなく
身体性を伴って
「人間に対して、やってはいけない」と理解していたかどうかは
かなり怪しいと思う
この3年間
世論は一部の医師・専門家による恐怖の刻印と
報道による強力な後押しを受けて
上記論考と同様の、あるいは類似の
対応を現実に採用したと思う
そこでは
患者個人を尊重したり
患者に対して本人の望む医療を提供したりする努力以上に
患者を「隔離」し
患者以外の人々が「うつされない」という
安心・安全が選択されてきた
家族であってさえ
看病することを拒否する例は多々あった
「うつさない優しさ」は「うつされない正しさ」を生み出した
具合が悪そうな人に手を差し伸べるという
人として当然に思われることを
「感染するおそれ」によって否定した日常…
冒頭に紹介した「民族浄化」ということばは
ハンセン病患者を大量殺害するという意味では
もちろん使われていない
むしろハンセン病から
患者(とその家族)以外の人々を
守るという意味合いが強い
その結果として
厳格な隔離政策は世間にいっそうの差別をもたらし
そうした差別がさらに隔離政策を推進させた
無らい県運動は盛り上がり
人々は互いに疑心暗鬼となって
「患者狩り」をした
それにより身体的に精神的に
どれほど多くのハンセン病患者が涙し
どれほど多くのハンセン病患者が殺されたことだろう
知識は頭だけで「わかった」としても意味がない
「差別はダメだ」と正解を解答欄に書き込んだとしても
表面上の問題でしかない
知識は身体に叩き込まねばならない
この3年間
日本社会が歩んできた道には
上記論考と相通じる「恐怖」「空気」「正義」が
通底している
「県をまたぐな」「他県ナンバーですが地元民です」
「○○県で患者は○○人です」
日々繰り返される差別的思考の再生産は
いまだ継続している
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
