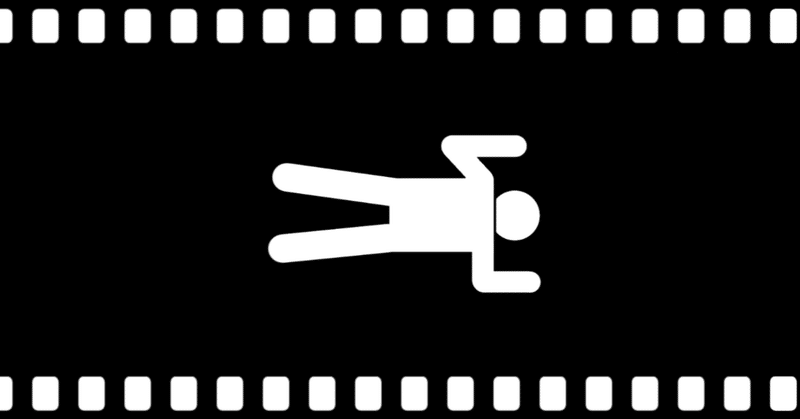
【小説】 穴に落ちる既視感 ②
ガードレールに腰かけてため息をついて既視感を感じながら、この既視感を追い払うにはどうしたらいいのか私は真剣に悩み始めた。
既視感の反対はなんだ。新しいこと、未知のことか。
五十七年間の人生ではじめてのことをやってみたらどうだろうか。それでどうなるかはわからないが、新しい体験の興奮で、しばらくは既視感連鎖から抜け出せるかもしれない。
でも…それでも既視感が起きたら、どうしよう?いやいや、今は考えるまい。
手っ取り早く、未知の体験といったらなんだろうと私は近くのコンビニエンスストアに入って行った。
「いらっしゃいませえ」間延びした声で、顎の辺りまで伸ばしたさらさら髪の男が言った。
「煙草が欲しいんだが…」
べつに照れるようなことでもないが、私は今まで一度も煙草を吸ったことが無い。今どきの若者ならともかく、私が子供時代はほとんどの大人(ほぼ男性だが)は煙草を吸っていたのだが。
「何番にしますかあ」
さらさら髪の言葉に私はたじろいだ。そうだ、銘柄を決めていなかった。いまどきの煙草は番号制なのか?
「ここにある、番号をおっしゃってくださーい」
見れば、彼のうしろにはずらりと並んだカラフルな煙草ケースがあり、ひとつひとつ番号が振ってある。
「ええと、じゃあその水色の…十六番」
「はい、十六番」
「ライターはあるかな」
「そこにあるんでとってきてもらえますかあ」
さらさら髪が、後ろの棚を指さす。赤、青、紫などの派手な色の百円ライターが箱に入れて売られていた。
店の外に出るとさっそく銀色のフィルムを破って、苦労して一本取り出しライターで火をともした。その瞬間、目の前にKの顔が浮かびあがった。いや、目の前にKが立っていたのだ。
「あれ、君、いつ戻って来たの?」
「先生、ここは禁煙ですよ」
「あ、そうか。いまどきはコンビニの前でも吸えないのか」
「いやいや、そうじゃないですよ。ここ、穴ですから」
「穴?」
そう聞き返した瞬間、足の裏から地面の感触がなくなっていた。
「うわあ」
足を踏み外した感覚などなかったのに、私は落下していた。突如、道路に地割れが起きたのか。無我夢中で手足をばたつかせるものの、どこにも手掛かりはなくただ落ちていく。穴は相当深いのか、なかなか地面に着地しない。深ければ深いほど、落下した時の衝撃は大きいに違いないと思ったとき、また既視感に襲われた。
私はたしかに穴に落ちたことがある。空中でもがく感覚、五臓六腑が浮き上がるような、どうにもならない情けない恐怖。しかし私はこんな大変なことを忘れていたのか?
「たすけてくれえ」
叫ぼうとした瞬間、またしても烈しい既視感に襲われそうになって私は口をつぐんだ。なぜか落下する恐怖よりも、既視感に襲われる感覚のほうが恐ろしかった。
そのうちに落下速度はだんだんとゆるやかになった。それもまた既視感があったが、最後には水に浮いているような具合で、痛みもなく穴の底に着地することができたときはさすがにほっとした。
穴のなかは真っ暗だった。幸い、ここには既視感がない。
「おうい」
頭の上に向かって叫んだが、答えはない。声は穴の先を抜けて行く感じがしなかったので、相当に深いのだろう。
そろそろと歩いてみる。穴の大きさは六畳間程度だろうか。地面は踏み固めた土のようで周囲の壁はつるりとして硬い。よじのぼれるようなとっかかりは何もない。
ため息をつきながらも、私はもしかすると、これは夢なのかもしれないと思い始めた。そうでなければ、説明がつかない。コンビニの前にこんなに大きな穴があるのもおかしいし、穴に落ちる既視感もおかしい。もしかすると、自分は今までに何度も穴に落ちる夢を見ていたのかもしれない。
私は穴の底に腰かけて、目を閉じた。そうしていれば夢から醒めると思ったのだ。だが、眠気もやってこないし、夢からも醒めない。
穴に落ちる、ということについて私は考えてみた。
考えあぐねるというのは、穴に落ちることに似ている。あるいは、すねた子供が押入れに隠れるように、私は穴というメタファーに逃げているのかもしれない。
今まで書いた作品の中で、誰かを穴に落としたことがあってそいつに復讐されているとか。自分のことだから、適当な穴を書いて適当に落としてそのまま死なせてしまったのに違いない。
勢いよく立ち上がると、何かがつま先に当たった。さっき歩き回ったときには穴には何もなかったはずだが。触れると、金属の感触がある。どうやら携帯電話らしい。やはりここはメタファーだの夢ではなく現実だ。これで助けが呼べる。そう思った瞬間、手の中の携帯電話が、びるびると鳴りだした。
なんとか通話ボタンを押す。
「もしもし?」
若い女の声だ。
「もしもし、あの、今私は…」
「まだいたんですか」
「まだ?」
「私の黄色いバッグに落ちたでしょ」
「え?」
「こまります」
これは、あの自転車の女か。なぜあの女が。
「いや、違うんです。私は…今、穴に落ちてしまっていて…」
「とにかく、こまりますから」
それで、電話は切れてしまった。
「ちくしょう」
私は穴の底で一人毒づいた。だが、これはKの携帯ということはわかったぞ。そう言えば、穴に落ちる直前目の前にいたのはKだった。あのとき、携帯電話も一緒に落ちたのかも知れない。それならKが探しに来るだろう。いや、そもそも私が落ちたのをやつは見ているはずなのだ。とすれば、Kが助けを呼んでいるはずだ。
また電話が鳴った。
「もしもし!」
「あー。やっと出たー」
先程とは違う、女の声だった。
「どちらさまですか、いやそんなことはどうでもいい。助けて下さい!」
「なに?何言ってんの?なんか声、へんだよ。爺くさいよ。風邪ひいてんの?」
「いや、私はこの電話の持ち主じゃないんだ、私は」
「えー、だれー」
「斎藤権田裕といいます」
「だれ?」
「作家です、いや、そんなことはいいから」
「ていうか、あいつ携帯落としたんだ。だから言ったのに、あいつ携帯の扱い適当過ぎるんだよねー」
「とにかく、助けてくれ」
すると、女にかわって男の声がした。
「もしもーし。僕の携帯持ってるのって、あなたですかあ?」
「その声は、Kか。助けてくれ、私だ」
「私って言われても、私はあなたを知りませんがあ」
「君は私の担当だろう」
「私はあなたの担当ではありませーん」
「まだ名前も言っていないぞ」
「言わなくてもわかりますよー。だって僕の担当は〇〇〇さんですもん」
「誰だよそれは」
「知らないんですか、今をときめく作家さんなのに」
「今をときめくなんて、そんな言い方」
「えー、じゃああなたならなんて言うんですかあ」
「いや、わからんが。今はそんなことわからんよ。それよりも今日、君と僕は喫茶店で打ち合わせしただろう。新しいシリーズ物のことで。君はハーブティを飲んだ。覚えてないのか」
「飲んでませんよ、ハーブティなんか」
「あれ、じゃあ違うものだ。何だったか忘れたが。それで電話がかかって来たんだ。君は外に出て電話をかけて、電話を落して、ほら自転車が走って来たから」
「なんだかよくわかんないな。もっと正確に思い出してくださいよ」
「思い出したくたって、こんな状況じゃ無理だよ。穴の中にいるんだぞ」
「ほんとうに?」
「本当だ」
「じゃあ、どんな穴か言ってみてくださいよ。どんな状況で落ちたのか。それから新しいシリーズってどんなものか。それについて、僕がなんと言ったのか」
なんと言った?そう言えば、何も覚えていない。Kが携帯電話を落とす。それを自転車の女が拾う。戻ってきたKはなんと言った?二人はどうやって別れた?店から家までどう歩いた?まるで覚えていない。
酷評されたのだろうか。それでがっくりして穴に落ちたのか。受けとめられなかったのか。それで忘れてしまったのか。そんなのはいやだ。既視感よりも、そんな忘却はもっといやだ。
「穴は穴だ」
しぼりだすように、ひとこと私は言った。
「それだけ?やっぱり信用できないなあ。ともかく僕の携帯、返してくださいね」
電話は切れた。もう、助けはこない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
