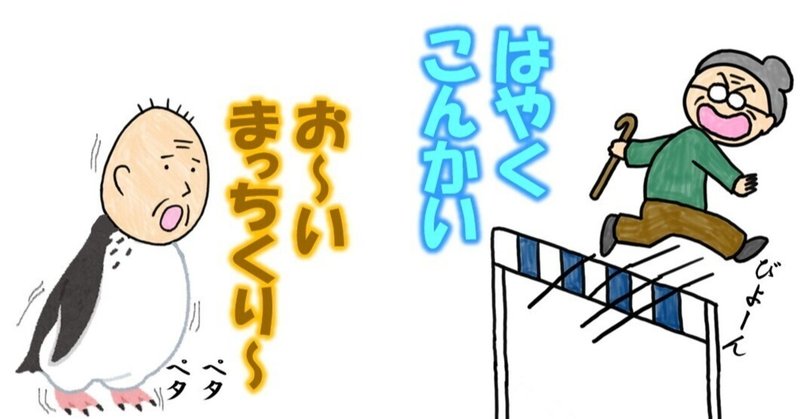
ペンギン歩きは認知症の初期症状
◆老化は徐々に忍び寄る
久しぶりに旧友に会って、その変貌ぶりに驚くことはありませんか。
「おおっ、老けたな~」
の言葉が口をつくのを、ぐっと我慢しなければなりません。
もし、言ってしまったららどうなるでしょう。
「お前こそ」と返されるでしょう。
何十年もかけて老け顔になっていくため、
自分も同居家族もその変化に気づきません。
それと同様、認知機能も少しずつ衰えていくため、
自覚できるのは、認知症がかなり進んでからでしょう。
早期発見に、良い方法はないのでしょうか。

◆歩き方で分かる
認知症の早期発見の手がかりの一つが「歩き方」です。
歩くのは足なので、手がかりでなく「足がかり」と言うべきでしょうか。
失礼な言い方ですが、お年寄りは「ヨボヨボ」歩いてる印象はありませんか。
認知機能が低下すると、ふらつくために歩き方が不安定になります。
それでヨボヨボした歩きになります。
歩行の速度も遅くなります。
谷口優博士は「ペンギン歩き」と称しています。
その特徴をあげてみましょう。
・とぼとぼ小股で歩いている
・手の振りが小さい
・うつむいて前かがみになっている
・だれかと一緒に歩いていると、遅れることが多い
「ペンギン歩き」になるのは、筋力が弱ったからでなく、
ふらふらするためです。
「立ちくらみ」や「めまい」の経験はありませんか。
倒れるのではないかと不安になり、前かがみになります。
ムリに歩こうとすると、ヨボヨボ歩きになります。
◆ペンギン歩きは前頭葉の衰え
認知症に向かうと、なぜ歩行に変化が起きるのでしょうか。
歩く時にふらつく原因は、脳の前頭葉にあります。
前頭葉に前頭前野という領域があり、
計画を立て、実行する機能があります。
また、歩行を維持する働きがあります。
認知症の場合、前頭前野の血流が低下していることが明らかになってきました。
つまり、「認知機能」と「歩行」は、一緒に衰えていくのです。
◆大股で歩こう
理論からすると、運動神経抜群な認知症患者はいないことになります。
認知症を予防するには、前頭前野を鍛えることが重要です。
前頭前野の働きが弱くなるとペンギン歩きになるので、
その逆をすればよいでしょう。
つまり、大股で歩くと前頭前野が鍛えられ、
認知機能がアップすると谷口博士は提唱しています。
若いころ、日に少しでも前に進もうと努力してきたことでしょう。
認知症予防に、1cmでも2cmでも、足を前に出して歩きましょう。

参考文献
1)青柳由則:『認知症は早期発見で予防できる』, 文藝春秋,2016
2)谷口 優:『認知症の始まりは歩幅でわかる』,主婦の友社,2021
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
