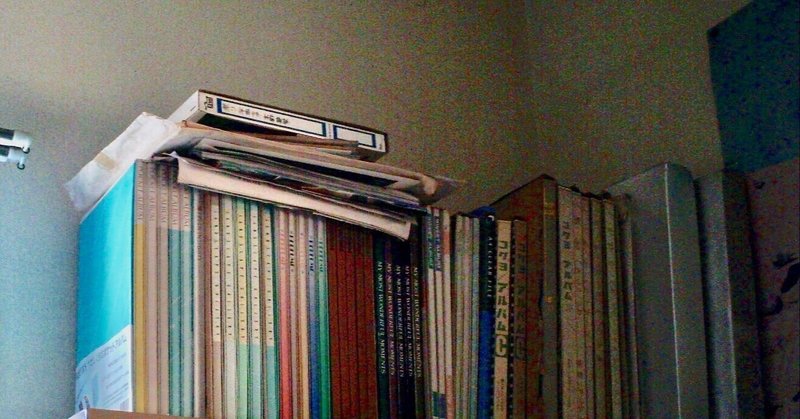
思い出を生活史に ー自分史からはみ出た思い出は小さな歴史
はじめに
自分史を書いているが、どうしても思い出に踏み込んでしまいがちである。自分の定義では、自分史は、”妻子孫(子々孫々)に捧げる私の歴史”である。個人的な思い出は、その枠からはみ出してしまうし、世の中でも思い出は自分史に含めていない。しかし、その思い出は個人のものではあっても、時代や生活環境を反映していると思われ、広く後世に伝える価値のあるもののような気がして、筆を執った。私の経験では、同年代であっても暮らした地域によって記憶が異なる。すなわち、経験が異なる。そうではあっても、いやそうであるからこそ、個人個人が思い出を記すことが大事な気がする。
いわゆる歴史(大歴史)は、学者がその時代の政治経済社会を総括したものであり、一般人が経験した卑近な出来事(小歴史)は抜け落としている。ここに書くのは、自分史を記す中ではみ出してしまった生活の記憶(記録)であり、大歴史と自分史の間を埋めるものである。
しつこいようだが、この生活史は、飽くまでも私個人が経験した出来事を基にした記録(記憶)である。
はじめに(追補)
はじめにに追補というのも変な話だが、いわば言い訳である。内容は三つある。一つ目は自分以外、具体的には父母のことについても書くということ、二つ目は自分の記憶や記録では不十分なので調べたことも書くということ、三つ目はまとまった話にならず漫談になるだろうということである。
父母については、ウェブサイト「自分史を作ってみよう!」にも書いたのだが、始まりは父母にならざるを得ないからだ。
調べることについては、本来は図書館にまで行くのが良いのだが、時間的な関係、コロナ禍の関係、加えてそこまでのものではないのでネットサーフィンになるだろう。
漫談になることについては、私自身の性格もあるが、トピック別になるのであちこちに飛ぶのはやむを得ないだろう。
父と母
上記のウェブサイト「自分史を作ってみよう!」にも書いたのだが、作家の年譜などでは、生年月日と生誕地に加え、父母の名前と父の仕事、何人目の子供のことから書き始められていることが多い。しかし、私の場合にはそのように書きにくい。当時の父の仕事について、詳しくは知らないからだ。米国製品を主に官庁のだれかれに売り歩いていたのは知っていたが、それをどこでどのように入手していたかを知らない。時々、東京に行っては仕入れてきてはいた。アメ横とのつながりはあったが、他からも仕入れていたのだろう。法律違反の入手であったことが分かったのは、新聞に記事が載ってからだ。何でこんな話しを書くかというと、私の父は1900年生まれであり、戦後、45歳を超えていて正業につきにくかったのではないか、と思われるからだ。もっとも、その気になれば正業につけたかもしれないのだが、男性も女性も平均寿命が60歳代だったから無理と思ったのだろう。80歳代になった今では考えも及ばないが。数年前のことだが、兄から代々木のワシントンハイツに父と一緒に行ったという話しを聞いた。今では、何をしに行ったのか想像できる。
そう言えば、上の話とは離れるが、小学校の時に、父の最終学歴を書いてくるようにと書類を渡されたことがあった。父は蔵前の高等工業*卒(あるいは中退)と書いておけと言われた。しかし、これも信用できない話しだが、そも学校が父親の学歴を知る必要があったのだろうか。今でもこんなことが行われているのだろうか。疑問である。
*蔵前にあった東京高等工業学校(現在の東工大)の事ではないか?
豆腐を買う
小学生になってから良くお使いに行かされた。豆腐を買いに行くのも私の役目であった。兄がどうであったか分からないが、ある時期は私だけであったような気がする。秩父市(埼玉県)の東町の十三番(札所;慈眼寺)の近くに住んでいた。豆腐屋は十三番を抜けると直ぐの所、御花畑駅(秩父鉄道)に行く細い小路の直ぐ脇にあった。平豆腐店である。豆腐は水を含んでいて柔らかい物だから、鍋を持って行った。時期は昭和30年(1955年)から昭和35年(1960年)。この時代、街では、みんなこんな生活をしていた。(リヤカーを引きながら、ラッパを吹いて来た事を知らせる豆腐屋を知ったのは後年の事で、当時その音を聞いた記憶は薄い)
最近、冨田均さんという人が書いた「東京私生活」(作品社、2000年刊)を読んだら同じ事が書いてあった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
