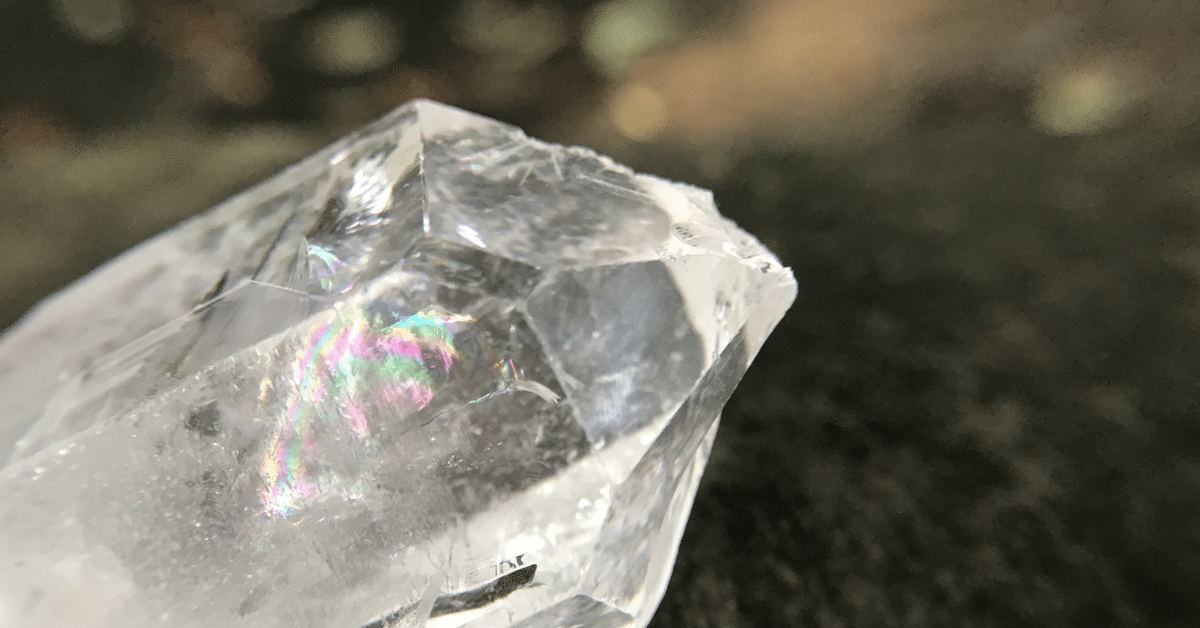
タカラノツノ 第8話 #創作大賞2024#ファンタジー小説部門
《くまざむらい》
気がつくと、タカは大きな部屋にねかされていた。頭のてっぺんがずくずくと熱を持っていたみ、あのできことが夢などではない、と教えてくれた。けれどもそれいじょうは何も考えられなかった。タカは高い熱にうなされぐらぐらする頭のいたみをかかえて、ふたたびふかいねむりに引きずりこまれた。
次に目がさめると、おどろいたことに、そこにいたのはくまざむらいだった。タカのきおくでは、殿さまといっしょにいくさ場に出陣したはずの男だった。こわばりついたくちびるをようやっとひらいて、タカは「どうして?」とだけ聞いた。くまざむらいは、そんなタカに水をのませてから、城の守りが手うすになりはじめているから、殿さまから兵の一部をひきいて一度、城にもどるように命令(めいれい)されたのだと答えてくれた。そこで、あのさわぎに出くわしたのだという。くまざむらいは部下の兵たちも使ってさわぎをおこした者たちをいさめ、事のてんまつを聞き出し、気を失ったタカをここにはこんだのだ。
「ざんねんだったが占い師はあのまま、死んでしまったよ。そして、お前の角はもう何者かに持ちさられたあとだった。」といたましそうにタカの頭を見ながらそうむすんだ。
そうだったのか、とタカはぼんやり思うだけで、かなしむ気力(きりょく)さえなかった。いたみで頭にふれることもできなかったが、角がおられてなくなったことは見なくてもわかった。そのけがのせいで、こうやって話ができるまでに、タカは何日も高い熱にうなされていたのだそうだ。
タカがはこびこまれたのは、やしろではなく、城の中でも使用人(しようにん)が使うへやの一つだった。今度のさわぎで何人かは城をにげ出してしまったため、空いたへやがあったらしい。城からはなれたやしろは、もうあぶないだろう、とくまざむらいが取りはからってくれたのだった。人手がないので、タカをつきっきりで手当てできる者はいなかったが、水と食べものだけは何かしら毎日さしいれられたので、それだけは自力で食べた。けれども起き上がれるようになるまでには、さらに何日もかかってしまった。
それからも、ただじっとよこたわるだけの日々が何日かすぎた。タカはその間、角がなくなった頭にさわっては、天じょうやかべをかわるがわる見つめては、これからのことについて、はげしく考えをめぐらせていた。
あのさわぎで、タカがいくさ神でないと思う者は一気にふえたはずだ。角もおられてしまった。こうなってしまうと、またいつ、あの男たちのようなれんちゅうが城におしかけて来るかわからない。
それとどうじにあの時、あの男たちの一人が言った言葉が思い出された。(「タカラノツノさまなんて言われてその気になって、おれたちは汗をながして取ってきたえものを、ずっとこいつにみつぎものとしてさし出してきたが、こいつはいくさ神なんかじゃなかったんだ!」)。そこにはまんまとだまされた者の、くやしさとかなしみがにじみ出ていた。たとえどんなにタカにそのつもりがなかろうと、殿さまとぐるになって、民をだましたにくむべき者として、タカは男たちの目にうつったのだ。
だったらタカはあの時、そのかなしみとにくしみを、もっとしっかり自分の身に引き受けるべきだったのだろうか。
やっぱりちがう、とタカは心の中でその考えにかぶりをふった。
タカははじめこそ、鬼とうたがわれてむりやり城につれこまれたが、いくさ神にしたて上げられたのは、殿さまがたやすくいくさをするためだった。タカは、だまされた者でこそなかったが、“つごうよく利用された者”であることにまちがいはなかった。それをタカがひとりで引き受ける、というのはおかしい。どう考えてもタカがこれいじょう、この城にいる理由は見つからなかった。
かあちゃんと捨丸にも何が起こっているかもしれない。ならばもう、いっこくもぐずぐずしていられない。
今日にでもここを出るのだ―。
そこまで考えたとき、ひょっこりとくまざむらいが顔を出した。今日も、ほんのみじかいあいだだったが、タカのぐあいをたずね、早く体をなおせ、とだけ声をかけてすぐに立ちさっていった。城の守りもいそがしいだろうに、タカを助けてくれてからずっと、くまざむらいは何かとタカに気をつかってくれた。
タカの方も、何もかもじじょうを知った上で自分を助け、けがをなおす場をあたえてくれたこの男がそばにいてくれることで、ずいぶんと気持ちがやすらいだ。くまざむらいがいなかったら、タカは今ごろどうなっていたかわからない。かんしゃしてもしきれないものを、タカはこの男からもらっていた。にげるにしても、せめてくまざむらいには、何もかもを話してから行きたかった。
それなのに、タカの中の別のところでは一つの疑問(ぎもん)が頭をもたげはじめた。
考えても考えても、くまざむらいには今のタカをここまで守るだけの理由がどこにも見当たらなかったからだ。神ではないと、大ぜいの人たちの前でふれまわられ、今や角さえ持たないタカに、いくさ神としては何の価値もない。むしろ、たまたまいあわせたというあのさわぎの時、そのままタカを捨ておいて、いくさ神は殺されました、と殿さまに言った方が、あとくされもなかったはずだ。タカを助けたところで、いくさで負けそうなこの時に、けがの手当てをほどこし、城の食料(しょくりょう)をわけあたえているのだ。その上、もしかして今でも、「インチキのいくさ神を出せ!」とさわぐ、この前のようなれんちゅうをおいはらっているのかもしれない。くまざむらいにとっても城にとってもそれは、重荷(おもに)にしかならないはずだった。
考えればふしぎなことばかりだ。ひょっとしてタカをさらってきて、いくさ神にまでされてしまったことを、くまざむらいはひそかにあわれに思ってくれたのだろうか。けれど、その気持ちだけでここまでするのでは、あまりにもわりにあわないのではないか。なぞはふかまるばかりだった。
くまざむらいのにらみがきいているのか、あるじのいない城は、はたらく者たちの話し声がたまに聞こえるだけでどこまでもしずかだった。うっかりすればまるでいくさなど、どこにもないかとかんちがいしてしまいそうなほどだった。
さいわいなことに、ふたたび足かせがタカにつけれられることはなかった。城にもどってからも、ろくに起き上がれないと思われてか、いくさのせいでそこまで手が回らないのか、それとももう、そのひつようがないと思われているのか…。おかげでタカは自由に城を歩きまわることができた。
人が話すのを聞いたことがあるだけだったが、城には敵(てき)におそわれた時、殿さまやその家族がこっそりにげ出すためのぬけ道や、ぬけ穴がかならず作ってあるということをタカは思い出した。ためしに城中を歩きまわってみたが、そのたびに手ぶらで帰るはめになった。そんなものがかんたんに見つかるようには作られているはずもなかった、とタカはがっかりした。城の外にくらべて、城の中はそれほどきびしい見張(みは)りはいなかったが、それでも人にあやしまれないように、となると、そのぬけ道が見つかるにしても、それまでに何日も、あるいは何週間もかかりそうだった。そもそも城につれて来られた時と、出陣(しゅつじん)前のきとうの時いがいは、ほとんどやしろにとじこめられていたタカだ。ただでさえ、城の中をよくわかっていなかった。これではいつまでたっても城から出られないだろう。
しかし、やしろなら、とタカは思った。
自分で自分のことをいくさ神ではない、とはっきりと知った時から、タカの中には、いつかはここをにげなくては、という思いが強くなった。もちろん、足かせがとどくはんいではあったが、殿さまのいくさのるすのあいだに、タカもまたあちこちに、はずせるかべや、てんじょうや、ゆかを作った。ほんとうは、城の外まで出られる穴をほりたかったけれど、そこまではかなわない、ととちゅうであきらめた、ほりかけの穴もいくつかあった。
その時の自分を思い出してタカは、ふと自分を夜中におそった者たちのことをせめられるすじあいではないな、と思いついて、ひにくまじりにわらった。
でも、これなら使えるかもしれない。
そうときめたタカは、その夜、よけいに一枚、ねまきを持ち、かわぶくろに布切れを入れ、まかないどころにむかった。そこでは、めしのしたくをするために、つねに種火(たねび)があったからだ。タカは油(あぶら)をしみこませたぬのに火をうつし、かわのふくろに入れた。そうやって火を持ち歩くことは、もともと猟師として山をかけまわっていたタカにはお手のものだった。そして着物をぬぐと、ひえた灰(はい)を体中にぬりたくった。次に、いくさがない時に、さむらいたちが剣(けん)や槍(やり)や弓(ゆみ)などをれんしゅうする、たんれん場に行った。そこで、まとに使う人形を取ってきて、自分のきものをきせた。それからやしろに向かい、縁(えん)の下から、ゆかのいたをはずして、中にしのびこんだ。中にはきとうに使う、こうろと小さなたいまつがおかれた護摩壇(ごまだん)があった。今でこそ使われていなかったが、そこに種火をうつすと、たいまつはいきおいよくもえた。あとはそれほどむずかしくなかった。さいだんのまわりには、ししゅうをした、かざりぬのがたくさんかけられていたし、自分のきものをきせた人形にも、火は、いきおいよくついた。それからタカはほりかけの穴にひそんで、じっと時をまった。
ほどなく、「火事だぞ!」とさけぶ声と、ばたばたとたくさんの足音がやしろにあつまってくるのが聞こえた。火を消そうと、城とやしろを行き来する、人のながれができはじめた。じきに、門の方からも何人かは火を消そうとかけつけてくるはずだ。タカは穴からはい出し、黒々した木のかげにかくれて門までたどりついた。そこには火事のようすを見に、すでに人だかりができはじめていた。のこった門番たちは、そんな人たちを押しとどめながら、同時に火事にまぎれて外から敵が入って来はしないかとひっしに目をこらしていた。そのため、後ろからこっそり堀(ほり)におりた小さなかげには気づかなかったのだ。
堀をわたりきると、タカは人のけはいを感じない場所をさがして、ようじんしながら堀の石垣(いしがき)をのぼった。さいごに、人がいないことをたしかめて、タカはぐいっと自分の体をおし上げた。けれど、けがと熱ですっかり弱っていたタカにとっては、それだけでも大しごとだった。大きく息(いき)をはきだし、タカはしばらくのあいだ、城のへいの中の、あわただしく火消(ひけ)しのさしずをしているおさむらいたちの声を聞きながら、その場でよこたわっていた。人形を使って小ざいくはしたが、焼けあとをしらべれば、タカがやけ死んだのではないことなど、すぐにわかってしまう。少なくとも夜明け前には、どこか人目のつかないところににげなければならない。しかし、ここでこんなにつかれてしまうようでは、すぐには遠くまではいけない。ならば、近くの森か山ににげこむしかなかった。追っ手が来たとしても、そこでのかくれんぼがっせんに持ちこめれば、タカは勝てる。それから捨丸とかあちゃんのいる、黒森山をめざすしかない。おもい体をひき起こし、歩きはじめたタカは、そこで強いしせんを感じて、びくり、と足をとめてふりかえった。
やぐらの上のくまざむらいと、タカの目ががっちりとたがいをとらえ合った。
しまった、とタカはきもをひやした。これでけいかくはしっぱいだ。タカはかんねんした。
だが、くまざむらいはまるでタカにきょうみなどないように、ふいと目をそらすと、そのまま大声で火消しの水を持ってくるよう、さむらいたちに命令するのだった。それをどうとらえていいかわからないまま、タカはやみをもとめて走った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
