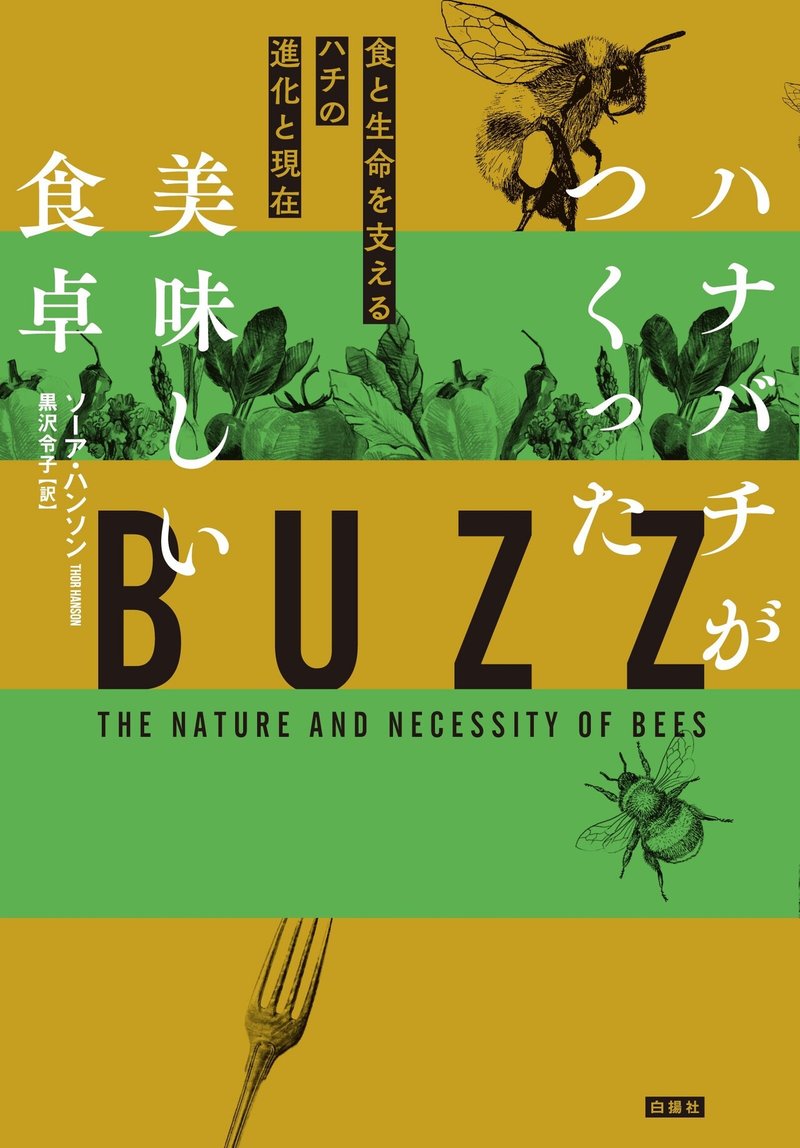人間の食物の3分の1はハナバチのおかげ『ハナバチがつくった美味しい食卓』試し読み
トマト、ナス、キュウリ、カボチャ、リンゴ、ブルーベリーなどなど、私たちが食べる作物の多くは、ハナバチが花粉を運んで受粉させてくれるおかげで手に入ります。おいしい食事のために必要不可欠な存在なのに、ハナバチのことはあまり知られていません。
特定の花と共進化した驚きの生態、古代人類との深い関係、世界各地でハナバチが突然消え、農業が立ちゆかなくなる現在の危機……発見の詰まった面白くてためになる本書から、第1章の冒頭をお届けします。
■ ■ ■
第1章 菜食主義のカリバチ
(第1章を一部抜粋したものです)
そのとき私は広い砂利採取場の向こう側へ向かっていたのだが、その羽音を耳にすると無視するわけにはいかなかった。珍しいチョウの採集を頼まれていたので、本来ならば捕虫網とメモ帳を手にして、その白いチョウが飛んでいるのが見えたところへ走っていくべきだった。しかし、足元の地面でブンブンという羽音が聞こえると、チョウどころではなくなってしまった。これが自然研究の問題点なのだ。自然界は驚異に満ちあふれているので、特定の課題に集中して取り組むのがきわめて難しいのである。私は「目標に集中しろ」と自分に言い聞かせた。この助言は『スター・ウォーズ』のエピソードからもらった。大混戦となった最後の戦闘に出たルーク・スカイウォーカーたちが、デス・スターを爆破するために小さな排気口に狙いを定めようと苦心していた場面の言葉だ。しかし、私にはジェダイの騎士のような集中力はなかった。依頼主には申し訳なかったが、チョウはまたの機会ということにした。
かがんでよく見ると、何千匹にも上るカリバチに囲まれているのに気づいた。黒と金色のツルリとした体が、焚火から飛び散る火の粉のように、四方八方へせわしく動き回っている。しかし、火の粉と違って、カリバチたちは最終的には地面に開いている小さな巣穴のそばに必ず降りてきた。これほど大きな集団営巣地(コロニー)は見たことがなかった。私はアドレナリンがほとばしり出るのを感じた。カリバチに刺される危険に直面したからではなく、巣を見つけて胸が高鳴ったからだ。ハナバチに興味のある人にとっては、適切なカリバチの巣を発見するのは時を遡るようなものだと言えるかもしれない。私が間違っていなければ、足元の地面にある小さな巣穴から、ハナバチがなぜ、どのように進化したのかを解明するのに役立つ、きわめて重要な手がかりが得られるはずだからだ。私は捕虫網もメモ帳もチョウのことも忘れて地面に腹ばいになると、間近から観察し始めた。
すると一匹のカリバチが一〇センチほど離れた砂利混じりの土の上に降りると、目で追えないほどすばやくジグザグに行ったり来たりし始めた。そして、特定の砂場に的を絞ると突然とまり、前脚を前に突き出して地面を掘り始めた。掘った土を後脚の間から後ろの方へ飛ばす様子は、ちょうどイヌか、股の間からボールを投げるショットガンスナップを練習している小さなアメフト選手のようだ。他のハチも皆この行動をくり返しているので、私のまわりの地面は跳ね上がる砂で振動しているように見えた。古い巣穴の修理をしているものもいれば、新しい巣穴を作っているものもいたが、どの個体も別々に作業をしていた。イエロージャケットやホーネットと呼ばれるスズメバチ科の身近なカリバチとは異なり、一心不乱に地中に巣穴を掘るこの小さなハチは、洗練された紙製の巣も造らないし、キャンプ場で人を脅かすようなこともしない。また、女王に率いられた巨大な組織集団で暮らすわけでもない。このハチは単独性で、営巣に適した生息環境を利用するために集まっているだけなのだ 。このハチはアナバチの仲間だとわかった。アナバチ科という名は今日でも広く知られているものの、一八〇二年に命名されたあとで、実際には多様な種を含んでいることがわかってきた。アナバチ科の学名(Sphecidae)はカリバチを意味するギリシャ語(sphex)に由来する。このことからわかるように、当時の昆虫学者はこのハチがカリバチの生態を完璧に体現しているので、「カリバチらしいカリバチ」という学名がふさわしいと考えたのだ。しかし、私が顔を地面に近づけてまで見たいと思ったこのハチの生態は、リンネ式分類法ができるよりもはるかに古い時代にできあがったのだ。恐竜が全盛期を迎えようとしていた白亜紀の中頃に、アナバチの勇敢な仲間が最もカリバチらしい習性の一つを捨てて、その後まもなくハナバチに進化したのだ。
私が観察していた個体は突然穴を掘るのをやめると、目の前から飛び去ってしまった。よく見ると、そのアナバチは巣穴の一部を掘りだしてしまっていた。それが自分の巣穴なのか、他の個体の巣穴なのかは知る由もない。少し待ってみたが、そのハチは戻ってこなかった。そこで、手で砂を払いのけてみると、とても細いトンネルがやや下向きに掘られているのがわかった。さらに掘り進めると、トンネルの壁が内側に崩れ始めたので、長い枯草の茎を差し込んでトンネルの奥を探ってみた。地面から一〇センチほど下で、トンネルは小さな部屋に突き当たって行き止まりになっていたが、そこには私が見たいと思っていたもの、つまりハエの死体が入っていた。それは夏の日に窓辺から追い払うようなごく普通の黒いハエだった。この死んだハエは、昔の昆虫学者が「カリバチらしいカリバチ」と命名したこのアナバチの特徴を示していた。このハチは、自分の子供に与える餌を常に探し回っているハンターなのである。私のまわりで巣穴を掘っていたハチは、ハエを専門に狩る「スナバチ(サンドワスプ)」と呼ばれているアナバチ科の一種である。同じアナバチ科でも、他の種はアブラムシからチョウやクモまで何でも狩る。針で刺し殺したり麻痺させたりした獲物を巣穴に蓄えておき、幼虫はそれを(生きていようと死んでいようとお構いなしに)貪り食って成長するのだ。身の毛もよだつやり方だが、非常に効果的で、一億五〇〇〇万年以上にわたってカリバチがとってきた基本的な戦略である。しかし、それを変更すると、さらに大きな成功を収めることになった。
レフ・トルストイからポール・マッカートニーまで、著名な菜食主義者は屠殺場に反対し、肉を食べないライフスタイルは健康にも環境にも有益だと訴えてきた。菜食主義の活動家は、ハナバチの歴史に目をつければ、より説得力のある根拠を手に入れられるだろう。菜食主義はハナバチの生き方を変えただけでなく、まったく新しい生き方を創り出したからだ。ハナバチの遠い祖先は、食物を動物質から花がもたらす栄養に切り替えることで、ほとんど手つかずで増え続けていた資源を発見したのだ。その資源はきわめて便利でもあった。通常、カリバチの成虫は、自分用の食物とはまったく異なる食物を幼虫のために捕えなければならない。だが、ハナバチには一ヵ所で食料がすべて手に入るという利点がある。質の高い花が与えてくれる甘い蜜は成虫自身の食料になり、タンパク質たっぷりの花粉は、巣に持ち帰って幼虫を養うことができるからだ。ハエやクモのような狡猾な獲物は捕まえるのが難しかったり、危険を伴うことがあるが、花はその場を動かないだけでなく、やがて魅力的な色彩や香りで場所を知らせるようになった。カリバチからハナバチに移行した時期やくわしい過程についてはまだ結論が出ていないが、それがうまくいったことは誰もが認めている。今ではハナバチの種数はアナバチの三倍近くに上っているのだ。
巣穴を慎重に塞ぐと、私はアナバチの集団営巣地をあとにしてチョウの調査に戻り、その日の午後はアブラナの黄金色、ムラサキツメクサ(レッドクローバー)の赤、ルピナスやアルファルファの紫色の花が咲き乱れる斜面で過ごした。これほどたくさんの花が咲き乱れている中にいると、花に栄養を頼るという考えは当たり前のように思われる。しかし、ハナバチが進化した世界では、一か八かの先駆的な適応以外の何ものでもなかったのだ。白亜紀と言えば恐竜を思い浮かべるかもしれないが、当時と現代の違いは爬虫類がたくさんいたことだけではない。幼虫を花粉で育てた最初のハナバチは、私たちが知っているような野の花が咲き乱れる草地のある環境で子育てをしたのではないのだ。当時は花自体が花弁や色彩といった花らしい形質を進化させている最中だったのである。初期の花は目立たない小さなもので、ソテツシダやソテツの仲間、それに針葉樹が優占していた当時の植物相の中では端役に過ぎなかったことが化石記録からわかっている。ハナバチが進化した理由を考えるためには、当時の世界を明確に理解することが必要なのだが、たいていの復元作業で重視されるのは大型爬虫類で、植生ではない。恐竜の本を調べたが、唸り声を上げている恐竜の背景には、ハナバチは言うまでもなく、花らしいものすらほとんど見当たらなかった。
ハナバチが進化した場所を思い描くのに苦心していると、どのようにして進化したのかという疑問がすぐに浮かんできた。当時は花が小さくてめったにないものだったのなら、ハナバチの祖先はなぜわざわざ花を探し求めたのだろうか? 何がきっかけとなって食性が大転換し、ハナバチは菜食主義者になったのだろうか? 最初のハナバチはどのような姿をしていたのだろうか? カリバチからハナバチに進化するまで、どのくらい時間がかかったのだろうか? このような昆虫の進化に関する疑問に行き当たったときは、昆虫進化の本を著した当人に聞いてみるのが一番だ。
著者のマイケル・エンゲルは、私がハナバチの進化について問い合わせると、「それは驚くべきできごとだが、データの裏付けがあまりなくて謎だらけなんだ」と述べ、「下品な言い方をすれば、ションベンをチビッた程度の化石記録しかないのさ」と続けた。
マイケルは、カンザス大学が所有している倉庫にある研究室から私の問い合わせに答えてくれた。五〇〇万点に上る大学の昆虫標本コレクションは、二〇〇六年に主任学芸員ともどもこの倉庫に移された。それまではキャンパス内にある豪壮な古い建物の一つに保管されていたが、それでは場所を取りすぎると大学側が考えたからだ。電話をしたとき、マイケルは「エンゲルだ」とぶっきらぼうに答えた。仕事中にかかってくる電話にうんざりしているようだった。それも無理はない。学芸員の仕事の他に、二つの大学で教授を務め、アメリカ自然史博物館の研究員と九誌に及ぶ科学誌の編集者も兼ねている。これまでに発表した論文は査読を経たものだけでも六五〇本を超え、さらに『昆虫の進化』という専門書を共著で出版している。私がマイケルにハナバチの進化について問い合わせてみようと思ったのは、この権威ある本の共著者だったからだ。研究対象は多方面にわたるが、そのなかでもハナバチが専門だった。教授がハナバチの権威なので問い合わせの電話をしたと伝えると、マイケルの声は急に明るくなり、他の仕事のことはすっかり忘れてしまったように、二時間近くも長電話で話し込んでしまった。
「最初の原プロトビーハナバチを探すためには、一億二五〇〇万年ほど時代を遡る必要がある」とマイケルは語った。しかし、残念なことに、紛れもなくハナバチと特定できる最古の化石が出現するのはその五五〇〇万年後なので、進化過程の真ん中に大きな空白があるのだそうだ。この状況をよい方向に捉えるなら、これほど化石記録がないことは、少なくともハナバチが進化した生息場所を示唆しているのかもしれない。化石が特に少ない場合は、たいていもっともな理由があるからだ。
「原ハナバチに適した生息地は、おそらく化石が最も残りにくい場所だったのだろう」とマイケルは述べた。初期の花の多くと同様に、ハナバチも乾燥した暑い環境で進化したことを示す証拠がいくつか挙がっている。今日でもハナバチの群集が最も豊かなところは、生物の多様性がきわめて高い湿潤な熱帯ではなく、地中海沿岸やアメリカ南西部のような乾燥地域である。白亜紀の陸地の大部分は似たような環境だったと思われるが、そうした場所やそこに生息していた生物のことはほとんどわかっていない。化石ができあがるためには、そうした環境に欠けているもの、つまり水が必要になるからだ。植物を含め生き物が化石として残るためには、できれば酸素が欠乏して腐敗が進みにくい場所で、短時間のうちに堆積物に覆われる必要がある。こうした条件を備えた場所は湖沼や河川、浅海の底のような水の中だ。したがって、私たちが思い描く遠い過去のイメージやその研究は、古生物学が「保存のバイアス(偏り)」と呼ぶものの影響を受けていることになる。つまり、最も湿潤な環境の生物相が、古生物に関する知見を支配しているのだ。そうした環境では、動植物が化石として残りやすいからである。もちろん、例外もある。突発的な洪水や火山の噴火後に、乾燥した地域で形成された化石だ。しかし、こうした化石もハナバチの起源を特定する手がかりにはほとんどなっていない。
「実に難題だよ。ハナバチの特徴を備えた化石を見つけようとすると、行き詰まってしまう。見つかったとしても、もうすっかりハナバチになってしまっているんだ! カリバチからの進化過程について何一つわからない。八方ふさがりなのさ」とマイケルは述べた。
問題は菜食主義というハナバチを特徴づける性質そのものにある。花粉を食べることは行動であって身体的特徴ではないし、行動によって特に質のよい化石ができるわけでもない。食性が変わったという確かな証拠が化石から得られるのは、花粉の収集や運搬に役立つ独特な毛などの形質が進化したあとになってからなのだ(長髪で花が好きな菜食主義者と言えばヒッピーが思い起こされるので、ハナバチは冗談交じりに「ヒッピー・ワスプ」と呼ばれている。ハナバチの重要な進化形質を覚えておくのにこのあだ名は意外と役に立つ!)。原ハナバチの外見はカリバチの親戚のようだったに違いないし、その後もしばらくの間はその状態が続いたのではないか。そして、今でもハナバチの仲間の一部が行なっているように、胃の中に花粉を入れて巣に持ち帰り、吐き戻していたと思われる。そうなると、実際に「原ハナバチ」の化石を発見する可能性はきわめて低く、偶然見つけたとしても、それだと気づく可能性はきわめて低いだろう。
「確証を得るには、巣の化石が必要になるだろう」と、マイケルはつぶやくように言った。その巣には花粉が入っていなければならない。さらに欲を言えば、餌を与えている最中に化石化したメスバチも一緒にいれば言うことはない。「もしそんな化石が見つかったら、どこだろうが貯金をはたいて航空券を買って見に行くね!」とマイケルは笑いながら付け加えた。
科学者としてデータを求めるマイケルの熱い思いと、証拠に裏付けられた仮説と単なる推測を峻別しようとする熱意が、電話での会話を通してはっきり伝わってきた。ハナバチは白亜紀中期にいたアナバチ科の祖先から進化した菜食主義者である。これまでにわかっていることはこれだけだ。そのことを私が了解すると、マイケルはその一線を越えて「もしかしたら」「こうだったら」「おそらく」という推測や憶測、仮定の領域に快く踏み込んでくれた。ハナバチがたどったかもしれない初期の進化の可能性を教えてもらう相手として、彼以上の適任者は見つからないだろう。「こんなことに貴重な時間を無駄遣いする人間はめったにいないからね」とマイケルは皮肉っぽく言ったが、彼がこれまで精力的に発表してきた幾多の研究結果は無駄などではない。二〇〇九年にはリンネ協会からバイセンテナリーメダルを授与された。これは四〇歳以下の生物学者を対象とした最も権威ある賞である。しかし、大学四年生のときに出会った偶然の機会がなければ、マイケル・エンゲルは一生涯ハナバチに関わることがなかったかもしれない。
「私は昆虫少年ではなかったんだ」とマイケルは昔を振り返る。だが、いつも細かいところによく気がついた。小さなものを描くのが好きだったので、細部まで正確に原寸大で描けるように、高価な極細のペンを欲しがって母親を困らせたそうだ。のちにカンザス大学の医学部進学課程で真剣に学んでいたときに、化学の教授に卒業研究には違うことをやってみてはどうかと言われた。「まわりと違った方が医学部の出願に有利になるのではないかと言われたんだ」。マイケルは先生の助言に従って、著名なハナバチ専門家のチャールズ・ミッシュナーの研究室を訪ねた。それ以来、そこに居続けていると言えるだろう。ハナバチの分類学は細かなことをきちんと扱うのが好きなマイケルの性に合い、難解な進化の謎解きも楽しかった。研究の取り組み方について尋ねると、「誰もやっていない研究ならば、やってみたくなる」と話してくれた。このようなへそ曲がりの性質だったので、偉い昆虫学者が昆虫の化石記録を十把一絡げに「何の役にも立たない」と一蹴したと聞くと、マイケルはすぐに初期のハナバチと昆虫の進化全般に興味を持った。コーネル大学の大学院を修了し、アメリカ自然史博物館で研究員をしたあと、ミッシュナー教授の後任に抜擢されてカンザス大学に戻り、一九四〇年代に遡るハナバチ研究の伝統を受け継いだ。これまでに発表した論文は、トビムシやアリからシロアリやクモ、チャタテムシまで多岐にわたるが、専門はハナバチとその進化である。マイケルほど数多くのハナバチの化石を調べた(そして、それについて考察した)人物はまずいないと言っても間違いはないだろう。
「カリバチの仲間の一部が花蜜を食べ始め、そのときに偶然、体についた花粉を巣に持ち帰るようになったというのが私のお気に入りの仮説なんだ」と、まだ憶測気分のついでに話してくれた。花の上にいたハエなどの昆虫を捕らえるようになり、その獲物の体に花粉がついていたり、獲物自身も花粉を食べていたという可能性もある。いずれにしても、巣の中に頻繫に花粉が運ばれてくるようになると、幼虫が肉と一緒に花粉も食べる機会が生じた。そして、最初は偶発的に運ばれていた花粉が、やがて意図的に集められるようになると、花粉だけを利用する花粉食へと(マイケルの言葉を借りれば)「一気に移行する」。
「花の上で過ごす時間が長くなったとたんに、メスは大きな危険を避けられるようになった」とマイケルは述べ、狩りに比べると花粉集めの方が危険が少ないと指摘した。「狩りは危険を伴うからね。獲物は自己防衛するだろうし、ハチの羽がやぶれたり、口器が損なわれたりすれば、命すら危うくなる」。自然選択は花粉食のハチにすぐに有利に働いただろう。花粉を集める平和な生き方で、個体の寿命は延び、子孫の数も増えることにつながるからだ。そして「気がついたら、もうハナバチになっていたのさ」とマイケルは締めくくった。
マイケルが描き出すカリバチからハナバチへの移行のシナリオは直感的で説得力があるが、その後に起きたことについてはもう少し慎重だった。現生のハナバチの解剖学的特徴については、専門家の意見が一致している。最もハナバチらしくない種でも、翅脈の細かいところまで共通点が見られ、花粉の運搬に便利な枝分かれした毛が少なくとも数本は生えている。しかし、現在知られている最古のハナバチの化石にはすでにこうした特徴が見られるので、それ以前の化石記録がないと、こうした形質が進化した時期や理由を知ることはできない。花粉を運んだことを示す枝分かれした毛の起源さえも明らかではないと、マイケルは指摘した。枝分かれした毛は、最初は飛ひ 翔筋の保温などの体温調節のために進化したのかもしれないし、ハナバチが砂漠のような乾燥地で進化を遂げたのならば、気門の周辺から水分が失われるのを防ぐために進化したのかもしれない。マイケルが夢見ているような完璧な巣の化石や、進化過程の空白を埋めてくれる太古のハナバチの化石が見つかるまでは、こうした疑問の多くは解明されないだろう。幸い、ハナバチの進化の概要を知るために、各形質の起源を突き止める必要はない。ハナバチの化石が現れ始める年代までに、ハナバチは祖先のカリバチから分かれて、別個の多様性豊かなグループを形成し、繁栄を極めていた。さらに、初期に毛が少なくて不便だったのを補うかのように、ハナバチはとても美しい姿になったので、人間がアクセサリーとして身につけることもあった。
マイケルと共に『昆虫の進化』を執筆したデイヴィッド・グリマルディは以前、自分の研究には、生きている昆虫を捕まえる繊細な捕虫網と、昆虫化石を取り出す鋼鉄のロックハンマーという二つのまったく異なる道具を使いこなす必要がある、と述べていた。とはいえ、ハンマーの扱いも細心の注意を要する。特に化石が琥珀の中に取り込まれている場合にはなおさらだ。琥珀は針葉樹のようなヤニの多い樹木の樹脂が化石化したもので、太古の森林が洪水に見舞われたり、短時間のうちに堆積物に覆われたりしたときに、琥珀を含む堆積層ができる。琥珀には、琥珀色という名のもとになった暖かみのある赤みを帯びた黄色からバタースコッチのような黄褐色や黄色、さらに緑や青色までさまざまな色が見られるので、琥珀の発掘作業を行なっていると、ステンドグラスを発掘しているような気になる。ガラスは向こう側を見るために作られたが、琥珀がすばらしいのは中に入っているものが見られる点だ。普通の化石では生物が平たく押しつぶされてその輪郭だけしかわからないが、琥珀はもともとはべたついた樹脂なので、その中に閉じ込められた生き物は、立体的に細部まで完璧に保存されているのだ。顕微鏡で見るような微細な特徴さえも明確に見える。有名な事例では、琥珀の中で見つかった白亜紀のサンドフライと呼ばれる吸血性のハエ類の保存状態が非常によかったので、その腹の中に爬虫類の血球と、既知の病原体が含まれているのがわかったほどだ。この化石記録から、人間やその他の現生動物と同様に、恐竜も昆虫が媒介する病気に悩まされていたことが明らかになった。
最後までお読みいただきありがとうございました。私たちは出版社です。本屋さんで本を買っていただけるとたいへん励みになります。