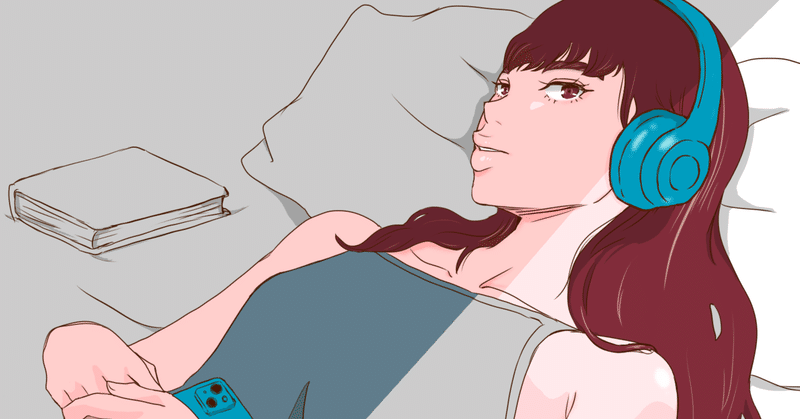
バレリーナの狙撃術
映画館の椅子に座ったとき、足もとでカタン、と小さな音がした。
何かを落としたんだろう、と探したけれど、何も落ちていない。貴重品はすべて巣の中の雛鳥のようにきちんとバッグにおさまっていた。
でも私はたしかに何かを落としたんだと思う。iPhoneとか、サイフとか、自分の心とかより、もっと大切な何かを。
それは体重が何グラムか軽くなってしまったような、はっきりと身体的に感じられる欠落だった。ちょうど耳がひとつなくなったみたいな。映画から得られるものでは埋めることのできない何かが、確実に私からこぼれ落ちたのだ。
映画を観たあとはどこかで食事をするつもりだったけれど、外は予想外の暗さだった。家路を急ぐことにする。まだ人通りの多い時間帯ではあるが、油断は禁物だ。最近は都心にも熊が出る。先日も六本木に3匹の殺人熊が出没し、大暴れの果てに14人の老若男女を殺害したばかりだ。今どきの熊は人を食べない。ただ無惨に殺して、熊専用のタブレットのようなものに死体との自撮りを写し、軽やかな足取りで去っていく。熊の世界にも新時代の波が押し寄せているのだろう。
厄介なのは、無闇に熊を射殺してしまうと「可哀想」との声が全国各地から上がるようになったことだ。阿呆としか言えない意見で、まともな社会であればいちいち相手をするはずもない戯れ言だが、阿呆の増えすぎた現代においては無視できない思想となっている。むしろ一大勢力といって良い。世の価値観はあるとき突然、昨日までの歴史がまるで存在していなかったかのように一変する。近い将来、熊を殺すことは禁忌となり、熊を異常なほど有り難がって、熊の餌となることを進んで受け入れるのが人間として当然の義務、みたいな風潮が蔓延したって、何の不思議もない。
ところで、その日の私は10センチのメタリックなピンヒールを履いていた。熊の出現率が激増しているというのに。私は浮かれていた。それほど楽しみにしている映画だったのだ。エンドロールが終わった瞬間に内容をすべて忘れてしまったけれど。まあ、そういう映画も悪くない。少なくとも上映中は現実以外のものを見られたわけだから。
いざとなったらピンヒールを両手に装着すれば、熊の目ぐらいは潰せる。本気になったら、それはもう稲妻のように素早く動くことができるのだ。私は。
とはいえ、その時点の私は呑気なものだった。しかもマナーが悪かった。歩きスマホでSNSを開き、最新の話題をチェックする。TwitterがXと名称を変えて早数か月。その前後でタイムラインの様子が変わったとは思えない。芸能事務所の問題や、ガザ地区の惨状や、「私はこんなにまともなのに、変な人が変なこと言ってくるんですけど!」の言い合いや、美男美女の写真とかイラスト、猫、廃墟、お説教漫画、過剰な罵り合い、過剰な褒め合い、街角の暴力の切り取り動画、赤ちゃん、赤ちゃんと猫、大袈裟なタイトルのわりにどれも似たような味の料理レシピ、AIを使用したおもんな画像大喜利、薄い格言、濃い陰謀論、学者の粗探し、河童の川流れ、世代間論争、格差問題、昭和は良かった・クソだった、チンピラの言動に対する無闇な称揚、寿司屋のマナーに関するマウントの取り合い、オタクのマナーに関するマウントの取り合い、マナー講師の〈マナー創造力〉の根源たる〈マナ〉は大気中に満ちています、みたいなの。そんなのがずらずら並んでいるだけ。
歩きスマホのまま私は新宿駅に突入し、この複雑怪奇な魔窟で一切迷うことなく、誰にもぶつかることなく、ぶつかりおじさんにぶつかられることもなく、白線の内側にて、スッと雅やかに立ち止まる。
電車を待っていると、熊が出たぞ! と叫ぶ声がした。
えっ、とさすがにスマホから顔を上げるのと同時に、ま、私が殺されることはないだろう、と高を括ってもいた。
いくら殺人熊でも、いっぺんに100人も200人も殺したりはしないはず。呂布じゃないんだから。
これだけ人の多い時刻の新宿駅であれば、私とは無関係の善良な市民が数人殺されたあたりで、山手線の各駅に常駐しているスナイパーが出てきて、あっさりと熊を殺してくれるはずだ。
何らかの理由でスナイパーの出動が遅れたとしても、猟友会とか、警察とか、自衛隊とか、熊殺し系YouTuberとか、そんなのが出てきてくれるだろう。
しかし私の目算は甘かった。
群衆は阿鼻叫喚とはならず、むしろ半透明となって、ほとんど私をすり抜けるように整然と駅から撤退し続けている。不思議と体が接触しない。群衆が私の人生にとって意味を持ったことなど一度もないから、これはいつも通りとも言えた。
必然的に私と熊が対峙することになる。
誰もいなくなった新宿駅のホームで、いつしか巨大な殺人熊と私は一対一だった。
その距離、約5メートル。
熊は柔道家が試合開始直後にやるような感じに、両手を上へと伸ばした。
次の瞬間には「鮭を獲る熊の置物」の鮭の部分に私が位置しているんだろうな、と確信せざるを得なかった。
ピンヒールを両手に装着して熊の目を潰す?
5歳児でももっとましなことを言うだろうに。
私はすっかり腰を抜かしていた。
絶望すら今の私には贅沢だ。せいぜいが呆気に取られている、といったところ。
そのとき突然、横合いから大きな「土」みたいな字が飛んできた。
何ごとかと思ったが、それはきれいな「土」みたいな姿勢で跳躍する人間だったのだ。
そいつは私と熊の中間地点に降り立った。
そして熊と向き合うと、すぐさま部首の「こざとへん」みたいなポーズを取る。「防」の字の左側ね。βでも、まあ良いでしょう。
こざとへんの姿勢のまま、そいつは目だけで私を振り返った。
「大丈夫ですか?」
女。に見える。まだ若い。ように見える。二十歳ぐらいだろうか。体は細く、格好はバレリーナだ。白を基調として青を効果的にあしらったベル型のチュチュ。白いタイツ。金色のトゥシューズ。髪だけはまとめておらず、豊かな栗色の巻き毛を駅構内の雑然とした風にさらしている。
そう、そいつはバレリーナだった。
跳躍時の「土」みたいなポーズも、静止状態の「こざとへん」みたいなポーズも、バレエでよく見る姿勢だ。
バレリーナは突然動き出した。
優雅な身のこなしで、飛んだり跳ねたりした。
バレエだ。
時が止まっているように感じられたが、実際には世の理に従って数秒が動いていたはずだ。
私も、そしておそらく熊も、完璧に見とれてしまった。
バレリーナが再び静止したとき、それはいかにもバレリーナ然とした佇まいに見えたが、今度のはいわゆるフィギュアスケートにおける軽めのイナバウアー、のような姿勢だ。
その手には、黒いショットガンが握られている。
私は驚いた。
熊も驚いただろう。
いつの間に?
どこから取り出したんだ?
私と熊の混乱をよそに、バレリーナは引き金をひいた。
体を反らせて背面で銃を構えているため、照準など取りようもないだろうに、バレリーナの放った無数の弾丸はすべて熊に命中した。弾が発射され続けているあいだ、発砲音は一切せず、かわりに聞き覚えのある華麗なワルツが流れていた。
なんという曲なのかは思い出せない。
バレエを踊ったりするのには丁度良いだろう。
音楽が止むと、巨大な熊の死骸が私の眼前に転がっていた。
踊ったあとに、これほど重たい静寂で迎えられるバレリーナもいないだろう。
バレリーナが私に近づいてくる。まだ動けずにいる私の手を取り、ゆっくりと立ち上がらせてくれた。
向かい合うとずいぶん小柄だ。
165cmの私より、10cm以上は低そう。バレリーナとしては致命的かもしれない。
その手にショットガンはすでになかった。
手品のように忽然と消えている。
幻だったのか?
しかし熊は確実に絶命している。
「熊殺し!」
と叫ぶ声が聞こえた。そちらに目をやる。向かいのホームの人だかりから発せられたようだった。
「可哀相だ!」
「なにも殺すことはなかったじゃないか!」
「熊も人も、命の重さに変わりはない!」
「おまえらは死刑だ!」
口々に非難の声があがっている。
自分たちが殺されるところだったというのに。
群衆はしだいに興奮の度合いを高めている。熊よりよほど危険な雰囲気を漂わせはじめた。
だがタイミング良いことに、ゆっくりと電車がホームに入ってくる。ステンレスの車体が群衆と私たちを遮断する。黄緑のドアがスムーズに開かれた。この国の電車は恐るべき正確さでダイヤを守るのだ。熊が出た程度では何ひとつ乱れることはない。
「行きましょう」
バレリーナが言った。まだ握ったままにしていた私の手を引いて、車両に乗り込む。バレリーナは震えていた。私は自分の着ていたタリアトーレのレディースのコートを脱ぎ、バレリーナに羽織らせた。非常にモダンな黒いロングコートに包まれて、バレリーナは幸福そうに目を閉じた。
私たちは並んで座った。まだお礼を言っていないことに気づく。
「ありがとうございます。あなたは私の命の恩人です」
言いながら、私の人生にこんな明確な「命の恩人」が現れるなんて……という新鮮な驚きがあった。
「いえ」とバレリーナは顔を赤らめてうつむいた。まだ少女のような顔立ちだ。なんとなく、憧れの教師に接する中学生めいた緊張を感じ取って、私は気分を良くした。
「お名前は?」と聞いてみる。「私はね、冗談のようだけど、熊切というの」
「熊切さん」バレリーナの顔が嬉しそうに輝く。理由のよくわからない笑顔だった。熊に襲われたやつが熊切? というのがウケた? ということ?
若い子はわからない。
「私はノリコと言います」とバレリーナが名乗る。
「ノリコさんね」
「漢字は忘れました。苗字はないです」
私はその言葉を受け止め損なった。
ややこしい環境で育った子なのだろうか。
「どうしてバレエの格好をしているの?」私はこらえきれずに聞く。もうちょっと打ち解けてからのほうが良いとは思ったけれど。
するとバレリーナの表情は暗く翳った。
「私は呪われし踊り手。ローザンヌの産み落とした最悪の忌み子。バレリーナとしては身長も技術も足らず、まるで使い物にならず、しかし100年に1人とさえ称された熊殺しの異能を認められ、殺熊バレリーナの道へ進むことを強要されました」
「殺熊バレリーナ」
聞いたことがなかった。夢でも見ているみたいだ。
しかもこのとき私は、「殺熊」という漢字を思い描けていなかった。バレリーナは「殺熊」を「さつゆう」と発している。熊の音読みは「ゆう」なのだ。
さつゆう?
頭の中はクエスチョンマークでいっぱいだった。辞書を引いて、「殺熊……! eureka……!!」と叫んだのは少しあとになってからのこと。
話がそれました。
殺熊バレリーナ・ノリコは1冊の本を取り出した。熊を殺したショットガンと同じく、手品みたいな出し方だ。
本はぼろぼろのハードカバーで、表紙にはタイトルと作家名だけが印刷されている。
バレリーナの狙撃術
リチャード・ブローティガン著
「ブローティガンをご存じですか?」とノリコは言う。
「何冊か読んだよ。昔。『アメリカの鱒釣り』とか、『西瓜糖の日々』とか」
「私がいちばん好きなのは『芝生の復讐』です」
「あー……、そう。じつは私、個々の区別はあんまりついてない。ぜんぶブローティガンだな、って思うだけで」
「それで良いと思います。ブローティガンが繰り返し書いていることはたったの一つ。人が死んで、あの世から自分の人生をなつかしく思い出している光景です。本当にそれだけなんです」
「ふうん」ぴんと来なかった。
「この『バレリーナの狙撃術』は、ブローティガンの未発表の原稿を集めたものです。今も未発表のまま。かつてブローティガンの祖母が住んでいた土地をスコップで掘り起こし、私が自ら発見しました。ブローティガンは一時期、文章を書いた端から祖母に送りつけていたのです。目の悪かった祖母は孫の原稿を一切読まず、小さく折りたたんで、次から次にコペンハーゲンの缶に収納しました。コペンハーゲンというのは噛みタバコのブランドです。長年ブローティガンの著書を愛読していた私は、彼の文章を徹底的に考察し、彼の祖母が暮らしていた土地に秘密の原稿が眠っていることを確信していました。昨年、シアトルの熊狩りに呼ばれたさい、ブローティガンの故郷であるタコマにまで足を延ばして、私はこの原稿を入手することに成功したのです」
「シアトルの熊狩り」というのは、『アメリカの鱒釣り』に引っかけた冗談か? とも思ったけど、ノリコは真面目な顔だった。
そもそも、これはいったい何の話なの?
わからない。
熊の出現以降、わからないことだらけだ。
ひょっとしたら私は、とっくに熊に殺されているのかもしれない。
ブローティガンよろしく、あの世から「私の人生ってこんなに変てこだったっけ?」と思い出している最中だったりして。
「この本は、その原稿を元に私が自費で製作しました」ハードカバーを胸に抱えてノリコは言う。
「あなたが翻訳したってこと?」
「DeepLにかけて、そこに出力された文字をそのまま印刷しています」
「なあんだ」
「私はこの本を3冊だけ作りました。そして即座に映画監督のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ氏、サックス奏者のカマシ・ワシントン氏、その二人に送りつけたのです。きっとこの本の理解者になってくれると信じたから。残念なことに、未だ返信はありませんが」
そうか。
こいつは頭がおかしい。
私は頭のおかしい女に命を救われたのか。
ようやくその事実に思い至った。
命の恩人が頭のおかしい人間だった場合、対処が難しい。
しばらく無言の時間が続いた。
「この本を、あなたにプレゼントします」どこか決然とした調子でノリコが言った。
「ごめんね」私は立ち上がる。「もう本は1冊も読まないと決めてるの」
電車が停車する。
鶯谷。私の最寄り駅だ。
「今日は本当に、どうもありがとう。助かりました」
私は丁寧にお辞儀をした。
本来なら連絡先を聞くなりして、後日改めてお礼をするところだ。
しかし私は、もう二度とこの子と関わり合いになりたくなかった。昼間に観た映画のように、すっかり忘れてしまいたかった。
ノリコが静かに立ち上がる。コートを返すためだろうと思ったが、違った。
「私も降ります」
私のアパートまでは徒歩10分の道のりだ。
バレリーナが残響みたいに私のあとについて来ている。
2分ほど歩いたあたりで不安になって、「あなたもこの辺なんですか?」と尋ねてみた。
「じつは私、家がなくて」と青ざめた顔でノリコは答える。
「うちに泊まろうとしてる?」
「いえ、そういうわけでは……」
「お金はあるの?」
「PASMOにあと198円残っています」
「今日はうちに泊まって」私はため息をついた。
「良いんですか?」
「命の恩人だからね」
6階建ての単身者向けアパート、バチルド鶯谷。304号室。私の住居。5畳間とキッチンの1K。風呂とトイレは一応セパレート。だが、はっきりいってみすぼらしい部屋だ。しかもベッドの上は洋服で山積みになっている。横たわったトトロぐらいの分量がある。私は掛け布団を使わず、服を適当に体に乗せて寝ているのだ。真冬になると、このトトロをすべて余さず体に乗っけることになる。
「あなたのような美しい方が、こんな恐ろしい部屋に住んでいるとは」
ノリコは正直すぎる感想を漏らした。
私はそれを聞かなかったことにする。
「ああ、そうだ。コンビニで何か買ってくれば良かった。私はね、家では一切飲み食いをしないの。水とビタミン剤ぐらいは飲むけれど。食事は100%外食なんだよ」
「冷蔵庫がありましたが」
「中を見てごらん」
言われるまま、ノリコはしゃがみ込んで冷蔵庫を開ける。コートはすでに私に返却していて、デコルテの大きくあいたベルチュチュだけの姿だ。白いタイツから伸びた脚はきれいだけど、全体に可哀相なほど痩せている。
よく熊なんて殺せたものだ。
ノリコは冷蔵庫の中身を、自動読み上げ機能みたいに声に出して言った。
「免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート、実印、財布、病院の診察券、眼科の診察券、映画の半券、ワン・ダイレクションのファンクラブ会員証、爪切り、耳かき……それとボルヴィック、ボルヴィック、エビアン……ボルヴィック。これだけですか?」
座ったまま私を見上げたノリコのあどけない顔が、冷蔵庫の光で照らされている。
「ごめんね、お腹空いてるよね」
「少し……。でも、大丈夫です。2週間なにも口にせずとも敵と戦えるよう訓練してきました」
「そうだ!」私は両手をいただきますの形に合わせた。「何かのときにもらったカップ麺が棚にあったな。赤いきつねと緑のたぬき」
「肉ですか?」
「いやいや……キツネとかタヌキを食べようってんじゃないよ。知らない? ♪あ~かいきつねと、みどりのた・ぬ・き」
私がCMの調子で言うと、ノリコは首をひねり、何か考えるようなそぶりを見せ、それから小さな声で歌い出した。
「♪黄色いイルカと、水色バッ・ファ・ロー」
「なによそれ」
「違いましたか? それなら……。♪白い日射しと、茶色のこ・び・ん」
「何を言っているの」
「色と物の組み合わせを歌にする遊びかと」
「何も知らないのね」
「知りません……何も知らずにゲームに参加してしまいました」
赤いきつねと緑のたぬきを知らないとは……本当に浮世離れをしている。そんなにもバレエひと筋、バレエ殺熊術ひと筋だったのか?
バレエ殺熊術ってなんだ?
まあいい。
「食べるものはあるってことだよ。安心して」そこで私は咳払いをした。「ところで。潔癖症だとか、失礼だとか思われても仕方ないけどね。コロナウイルスの流行後、私は帰宅するやいなやシャワーを浴びなければ気持ちが悪くて発狂してしまう体になってしまったの。できれば、あなたにも浴びてもらいたい」
「シャワーをお借りできるのは、ありがたいことです」
「でもね、そこで心配事がある。私がシャワーを浴びている間、命の恩人とはいえ、今日出会ったばかりの人を、部屋にひとりで置いておくのは不安です。はっきり言って。ごめんなさいね、嘘がつけない性格で」
「しばらく外に出ていましょうか」
「いいえ。命の恩人にそんなことはできない。一緒に入りましょう」
服を脱ぎながら、なかなか異常なことをしているな、と自分でも思った。犯罪の可能性がある。
巨大な獣に襲われたことで、私自身の中にも少し獣の〈気〉のようなものが入り込んでしまったのだろうか。
まあ、私はいかなる意味合いにおいてもノリコを「食べて」しまうことなどないが。そこまで見境なしの女じゃない。いろいろな問題を抱えてはいても。
ノリコが身につけていたものは、ショーツもアンダーウェアもすべてバレエ用のものだった。驚いたのは、しっとりとした栗色の巻き毛がウィッグだったこと。彼女はスキンヘッドなのだ。からだ全体が、バスルームの淡い光につるんと可愛らしく照らされている。
私たちは狭いバスルームでひしめき合うように立った。
ノリコの肉体をすばやく観察し、彼女の生物学的性がほぼ確実に女性であることをしっかり確認する。これでかなりの安心感を得ることができた。
「残念ね、髪を洗ってあげようと思ったのに」
つるつるの頭部にシャワーを当ててやると、ノリコは目を閉じたまま、水流の中から返事をする。
「私は汗を流すだけで良いです。皮膚が弱いので、いかなる洗剤も受け付けません」
「そうなの? でもあなた、とても清潔な肌だね」
「汗をかかないよう訓練してきましたので」
「それにしても細いなあ。もしあなたが強盗だったとしても、力づくで私をどうこうなんて、とてもできそうにない」
「さっきの私の戦いぶりをお忘れですか?」少しプライドが傷ついたようにノリコは言った。
「あれは銃を使っていたでしょう? あなたの体、よく引き締まってはいるけど、もろくて細い。業界用語でいうところの〈もろほそ〉ね」
「どこの業界ですか」
「〈もろほそ〉はモロゾフの語源でもある。チョコレートみたいに砕けやすいってことよ」
「私はあらゆる格闘術を叩き込まれています。素手であっても、人を苺のように容易く破壊することができますよ」
「苺を破壊するな」私は大人として、きちんとした注意をする。「私、こないだ恋人と別れたばかりなんだけどね、その恋人ってのがプロレスラーだったの。だから私、技に対する〈受け〉が強いと思う。レスラーは〈受けてなんぼ〉だからね」
「恋人……」とつぶやいてノリコは黙った。「恋人かあ」
私は自分の恋愛事情について何も聞かれたくなかったので、ノリコの全身にシャワーを掛けまくった。ノリコは指揮者のまねをする保育園児みたいな動きをして耐えた。
「よし。もう出て良いよ。髪も乾かす必要ないんだもんね。部屋で休んでいて」
「私が1人で部屋にいては駄目なのでは」
「大丈夫。もうだいたいわかったから」
「はあ」
「体はしっかり拭きなさいね。それから、肌に塗るものは塗って。若いうちからケアしておくべきだよ」
「塗るものを持っていなくて」
「洗面台にあるやつ、何でも遠慮せず使っていいよ。命の恩人なんだから」
それだけを言って私は頭を洗い始めた。
本当に変わった奴だ。
でも命のお礼に、一晩の宿と、緑のたぬきぐらいで済むなら安いもの。赤いきつねを譲るつもりはないが。
「あの」と突然ノリコの声がしたので、私は驚いて跳び上がりそうになった。
頭に手を置いたまま振り返る。目を見開いていたため、シャンプーが左目に入った。
「まだいたの」
「あの、言い忘れていたことがあって」全身をほんのり桃色に輝かせながらノリコは言った。「私が熊切さんを助けたのは偶然ではありません。熊切さん、今日映画を観ましたよね? 私はあの映画館に、対熊用の用心棒として雇われていました。それが私の現在の仕事なのです。映画館では、危険な出来事は厳密にスクリーンの内部に限られるべき、との理念から設けられた役職です。働き始めた先月の8日。その日に映画館にやってきたあなたを見て、私は一目惚れをしてしまったのです。こんなことは初めてです。熊切さんは私の理想の姿をしています。私のような〈もろほそ〉ではない、美しい大人の女性の姿。こういった言い方を許されるのなら、〈肉感的な〉と形容したくなるような。私の憧れ。この3週間で、あなたは4度、私の勤め先で映画を観ました。そのたびごとに思いは募り、ついに今日、私は用心棒の仕事を投げ出して、あなたのあとを尾けてしまったのです。熊が出なくても、私はあなたに話しかけていたはずです。あなたのことが好きなんです。今も胸がどきどきしています。痛いくらいです」
一方的に言って、ノリコはバスルームの戸を閉めた。
私が取り落としたシャワーノズルが床でお湯を吐きながらのたうち回っている。
私を尾行していた……?
怖。
怖っわあ。
ノリコが1人で私の部屋にいることが、非常に不安になってきた。
素早く全身を洗い、肌に塗るものを塗って、頭にタオルを巻くと、右手にドライヤー、左手にエビアンを持って私は部屋に戻った。
ノリコは再びウィッグを装着していた。私のベッドに堂々と仰向けになっている。そこに元々あったはずの大量の私の服はすべて床に投げ捨てられいた。しかも私の使い古しの部屋着を勝手に発掘して身につけており、あまつさえ私のワイヤレス・ヘッドフォンを持ち出し、目を閉じ、何か音楽を聴いてさえいた。
じつに良い度胸だ。
私はノリコに近づいて、勢いよくヘッドフォンを剥ぎ取った。
ノリコはゆっくりと目を開ける。
ヘッドフォンから音が漏れ出した。槇原敬之『もう恋なんてしない』。ノリコのスマホと同期しているようだ。
「へえー、あなた、世代じゃないでしょう」叱るつもりだったのに、珍しさのほうが勝ってしまう。
「いま、TikTokで流行っているのです。この曲のドリル・アレンジがバズったりして」
「急に若者っぽいこと言うのね。ドリル?」
「まあ、ヒップホップのサブジャンルですね。トラップからの派生というか。本来は銃や暴力といった、危険な内容を表現するものだったはずですが。そもそも私は、幼い頃より父親に槇原敬之を何千回と聞かされていました。車に乗ると必ず槇原敬之の最初の4枚のアルバム、その中から1枚が父によって選ばれます。そしてひたすら、槇原敬之の音楽が車内の空間を満たすのです。槇原敬之はデビューから最初の3年で4枚のアルバムを発表しました。私の父は3年分しか人を愛せない。結婚生活も3年でした」
「思い出の曲なんだね」
「思い出かどうかわかりませんが」ノリコはベッドに仰向けのまま喋り続ける。ふてぶてしい態度だなと思う。「この曲の歌詞について、父は『こんな乱暴な性格のやつ、振られて当然なんだよな。それが分かってないなんて、馬鹿な主人公だよ』とよく言っていました。父親だけではありません。その後も、この曲が話題になるたび、歌詞がモラハラだとか、そりゃフラれるだろ、などと言う意見を、リアルでもネットでもたびたび目にしました。しかし私はそのことがずっと不思議だったのです。だってこの曲の主人公は、『そんなんだからフラれた』ことを、自分自身で痛いほどわかっているはずだから」
あまりにいっぺんに喋るものだから、私は手にしていたエビアンを思わずノリコに差し出そうとしていた。でも、こいつ寝たまま飲んでベッドにこぼしそう、と思ったので、やめておいた。
「恋人の去った部屋では『紅茶のありか』すらわからなかったり、自分で作った朝食のまずさに『きみが作ったのなら文句も思いきり言えたのに』とか言ってみたり。こういった言動が横暴だと映るのでしょう。しかし私には、それは別れの原因のひとつにすぎなくて、しかもそれが別れの原因のひとつだということが、主人公にはわかりきっている、そう思えてならないのです」ノリコは天井を見たまま、機械のように言葉を発し続ける。「これに対する反論としては、当然『さよならと言った君の 気持ちはわからないけど』という歌詞が持ち出されることでしょう。ほらみろ、別れた理由がわからないと本人が言ってるじゃないか、というわけです。しかし、その直前のパートに注目してほしい。『一緒にいるときはきゅうくつに思えるけど やっと自由を手に入れたぼくは もっと淋しくなった』と槇原敬之は歌っています。ここから、イライラしていたのはお互い様だったことがわかります。2人ともが同棲生活に行き詰まりを感じていたのです。自分はたしかにワガママだったけど、こっちにも言いたいことはある。捨てられても仕方がないけど、こっちから終わらせたい気持ちだってあった。けれど、本気で別れるなんて選択肢が、2人のあいだに存在しているとは思わなかった。お互い不満を抱えながら、ケンカしながら、それでも2人で生きていくものだと思っていた。そういったニュアンスが、『さよならと言った君の 気持ちはわからないけど』という歌詞に集約されているのです。また、2番の歌詞に目を向けますと」
まだ続くんだ! と思ったけど私は口を挟まない。代わりにエビアンを口に含んだ。
「まず2番の冒頭、『"男らしく いさぎよく"と ごみ箱かかえる僕は 他の誰から見ても一番センチメンタルだろう』とありますね。しかも、『こんなにいっぱいの君のぬけがら集めて ムダなものに囲まれて暮らすのも幸せと知った』ときたもんです。これはね、未練たらたらであることの正直な告白と、世間に向けての、〈どうです、僕って可哀想でしょう、いじらしいでしょう〉というアピールを同時に行っているわけです。つまり、現在のSNSでよく見られる、同情を買って〈いいね〉を得ようとする浅ましい投稿と同質のもの。『かたすみで迷っている背中を思って心配だけど』なんて、別れても優しいオレ、を演出しつつ、『2人で出せなかった答えは 今度出会える 君の知らない誰かと見つけてみせるから』などと、聴衆に向けて〈もう吹っ切っています。新しい恋人を探しています。失恋を乗り越えて成長したんです〉と表明するしたたかさも見せつけている。『もし君に1つだけ強がりを言えるのなら』と歌ってますが、じつはこの部分だけが強がりではない。ですがここ以外のすべての歌詞が強がりです。この曲は結局のところ、自分にまるで自信のない男の、がむしゃらな恋の終わりと、自分の罪と、未練と、復讐心と、自尊心。そんなものをないまぜにした感情を、完璧に表現しきっている。そういう曲だと思うんです。未熟な恋愛、あるいは恋愛といういかなる人間をも強制的に未熟にしてしまう精神疾患。歌全体がその言い換えなんです。イントロがまた絶妙です。このイントロは〈誰もいない夕暮れのワンルーム〉みたいな情景を過剰なまでに想起させる。すべてが語りすぎなほど語っているわけです。だから、この曲を聞いて単純に、『バカだな、モラハラするからフラれるんだよ』と切って捨てた父親が、私は間抜けな人物に見えて仕方なかった。幼い頃から。私の世代では感情を剥き出しにして傷つけ合う恋愛というのが、そもそも敬遠されがちなんです。恋愛じたいが過去の遺物と見做されている面もあります。でもね、私は自分の軽蔑の対象だった父親には理解できなかったこの歌が、私の中心部に息づいているのを感じます。ちっとも今風ではない、こんな恋愛が私はしてみたい。憧れてる。正確な手順で熊を殺すだけの機械みたいな暮らしに嫌気がさしているんです」
そこでノリコは言葉を止めて私を見た。
ようやく演説が終わったようだ。
「まあ、歌詞の解釈については100%同意だけども」と私は久々に発言する。
「えっ、同意ですか?」とノリコは破顔してベッドに身を起こした。「気持ちが通じ合ったってこと? 私の思いを受け入れてくれるってことですか?」
「思いを受け入れる……とは」
「私の恋人になってくれますか? プロレスラーとは別れたんですよね? そういえば、この部屋も歌と同じく、恋人が去ったあとの部屋ですね。そのプロレスラーの知らない誰か、つまり私と、『2人で出せなかった答え』を見つけるつもりになった……ってことですよね? 付き合ってくれるんですよね?」
息継ぎもせず、身を乗り出してノリコは言う。目が爛々と輝いている。
「付き合うわけないでしょ」私はできるだけ冷たい目をして言った。「残念だけど、私、背の低い女にはまるで興奮しないの」
「そんな……理由ルッキズムじゃないですか。直球のルッキズム。身長なんて……ルッキズムの極みだ」
「こういうことで嘘をついても仕方ないから。私は誠実を信条としているの」
「熊を殺すほどの力を身につけ、しかもその力で好きな人の命を救いさえしたのに、それでもフラれることって、あるんだ……」
「そういうのとは別物だからね。恋って」
ノリコは意気消沈し、ベッドに腰掛けたまま、首の可動域の限界まで項垂れている。
私は何となく気づまりになって、ベランダに出た。タバコでも吸いたい気分だった。21の夏に禁煙して以来、もう何年も吸っていないが。
この子と一晩過ごすのか……と思うと、少々気が重い。
でも、命の恩人だし。
軽い気持ちで裸も見ちゃったし。
しかも熊を殺すほど強い。
あとで揉めないよう、明日の朝はなるべく良い気分で帰ってもらわないと。
そのとき、3階のベランダから見おろしていた暗い夜の帷に、ふと私は何か動くものを発見した。
目を凝らす。
熊だ。
熊の大群が街を闊歩している。
こんな平和な……鶯谷に?
しかもまだ夜の9時前だ。
いつのまに世界はこんな風になってしまったんだろう。
たしかに遠い国で戦争が相次ぎ、大戦前夜と言われて久しい世の中ではあるけれども。
「大丈夫、私が守りますから」
背後からノリコの声がした。ノリコもベランダに出てきている。寒かったのか、深い緑色のジャケットに身を包んでいた。このあと緑のたぬきを選ばされる運命にあるという宣告を受けた姿にも見えるが、明らかに私の洋服の山から抜き取ったミュグレーのジャケットだ。本当にいい度胸をしている。まともな教育など受けたことがないに違いない。
「じつは」どこか神妙な面持ちでノリコは言った。「熊切さんにお返ししないといけないものがあります」
「え? 財布?」
「私は泥棒じゃないです」ノリコは残念そうな顔をする。「映画館で何かを落としませんでしたか? 座席についた瞬間、かすかな、何かが落下する音がしたはずです」
私の脳裏に カタン という小さな音が蘇る。
そう、私はあのとき何かを落としてしまった。
それが何かは分からなかったけれど。
「私は映画館でずっとあなたを見ていました。スクリーンの光に照らされたあなたの顔を。あなたは座った瞬間、はっとした顔をして、すぐに座席の下あたりをまさぐりだした。そのあとでカバンの中を調べた。結局、落とし物を見つけられずに映画館を出ましたね? 私はそれを拾ってあなたの後をつけたんです。あなたの家の前で、落とし物ですよ、と話しかけて、そのままお部屋に招待してもらうつもりでした。熊なんて関係なしに」
なんかこいつ、やっぱ怖えーよ、と私は思う。
ノリコは右手を私に差し出した。軽くこぶしを握った状態で。
何かを手の中に持っているのだ。
「あなたが映画館で聞いた小さな落下音。それは……こんな音ではなかったですか?」
なんでそんな、のっぺらぼうの怪談みたいな言い方なんだ。
ノリコが手を開く。
何かが落ちる。
コ
ト ン
「どうです?」
「違うなあ」
「違う??」
「そもそも映画館の床じゃないから、同じが音するはずないよね」言いながら私は、ノリコが落としたものを拾い上げる。「何これ? 貝殻?」
どう見ても、白い小さな貝殻だった。
「ええ、貝殻です。そうか……わかった!」ノリコは勝手に何かをわかってしまった。「ここまでの話を総合すると、私にはひとつの物語が見えます。熊切さんはこの夏の終わり、プロレスラーの元恋人と海に行ったのでしょう。海岸で愛を語りながら、貝を拾った。すぐにつらい別れがやってくるわけですが。まだ気持ちを引きずっていたあなたは、思い出の貝殻をいつも持ち歩いていた。それを落としてしまったんです。つまり、映画の始まりと恋の終わりが同時に起こった。それを目撃した唯一の人間が私なんです。この事実の意味するところは……明白ですね?」
「変な考察に巻き込まないで。現実の人生だよ。サスペンスドラマじゃないんだから。もう二度と、堺雅人ぐらい喋り倒すのはやめて」私は呆れてため息をついた。「この貝殻は私のじゃないし、海なんてもう5年も行ってない。プロレスラーと別れたのだって半年も前だよ。ふったの私のほうからだし」
他の格闘家と浮気しまくっているのを見つけちゃったから。
それに、この部屋はレスラーと暮らすには狭すぎた。
傷つけ合うだけの恋愛なんて、しないほうが良いんだよ。
「そんな……」両手をだらんと下げて、ノリコは悲しそうに私を見ている。「だったら、この貝殻は何なんです?」
「知らないよ」
「意味もなく急に貝殻が登場するなんて、変です」
「なんでもかんでも、きれいな物語におさめようとしないで。そもそも私って、あなたより十は歳上だよ。もっと世代が近い子と遊びなさい。それにね、自分で言うのもなんだけどね、私はちょっとモテすぎる。きみには高嶺の花というやつだよ」
「そんなあ」ノリコは立ったまま、静かに泣き出してしまった。「何だったの今日。絶対うまくいくと思ったのに。ほんと最悪なんだけど。無理。終わった。Q.E.D.」
涙を拭いもせず、はらはらと流れ落ちるままにしている。体を駄々っ子のように揺すっているし、鼻水も少し出ていた。
可愛い。
と思ってしまった。
私の母性は二十歳を前にして完全に死滅している。もともとそっち方面は薄い女だ。しかし、母性本能のすぐそばに位置している、なにか得体の知れない別の感情が、生まれて初めて駆動し始めるのを私はかすかに感じていた。
「どうして泣いてるの?」と私は意地悪を言ってみる。
「恋に破れたからです」ノリコは素直に答えた。
可愛い!
さっきより強く思った。
「もう本当に無理なんですか?」とノリコは上目遣いで言う。
「完璧に無理だよ」
「じゃあ……じゃあ、最後に一つ。一つだけ、私の夢を叶えてください」
「いいよ。私にできる範囲なら」
と承諾してあげたのに、ノリコは激しく泣きじゃくって、なかなか言い出せない。
「憧れのぉ、しょ、昭和のぉ、あそ、遊びが、あってぇ」
しゃくり上げながら必死に言葉をつなげている。
「昭和の遊び?」
私は平成生まれなんだけど。
辛抱強く聞いてみると、どうやらノリコは、貝殻を二人で交互に耳に当てて、「海の音が聞こえるね」「そうだね、ロマンティックだね」などと囁きあうのを、一度やってみたかったらしいのだった。
「まあいいけど」
まず私が貝殻に耳を当てる。
「しますか? 海の音?」夜風にウィッグの髪をなぶられながらノリコが聞く。
「しないね、何の音も」私は意地悪を継続させる。
次にノリコが貝殻を耳に当てた。
「どう? 何か聞こえる?」
「なんにも……聞こえない」ぎゅっと目を閉じて、苦しそうにノリコが言った。
私はその痩せた背中に、そっと手を当てる。
「さ、もう充分でしょう。寒いし、部屋に戻ろう。お湯を沸かして、赤いきつねと緑のたぬきを分けあって食べるの。すごくおいしいんだよ。きっとびっくりするよ」
ノリコはいっそう大きな声で泣き出してしまった。
泣くことなんてないんだよ。温かいものを食べて、気持ちを落ち着けたら、もう一度貝殻に耳を澄まそうよ。私たちが心を合わせたら、きっと何かが聞こえるはずだよ。
ロマンティックな気分ってのは、二人で協力して、無から召喚するものだ。
ひと晩かけて、じっくりやるのが望ましい。
正しいやり方を教えてあげましょう。
誰かに好きになってもらうために、自分の力を誇示して、熊を殺してみせたりする必要なんてないんだよ。可愛いノリコ。淋しいバレリーナ。もう恋なんてしないなんて、言わないでね、絶対に。

#小説
有料ゾーンには、この小説をどのような手順で書いたかを記した、簡単な創作メモを載せています。
でも、300円払って読むような内容ではないですよ。あしからず。
ここから先は
¥ 300
