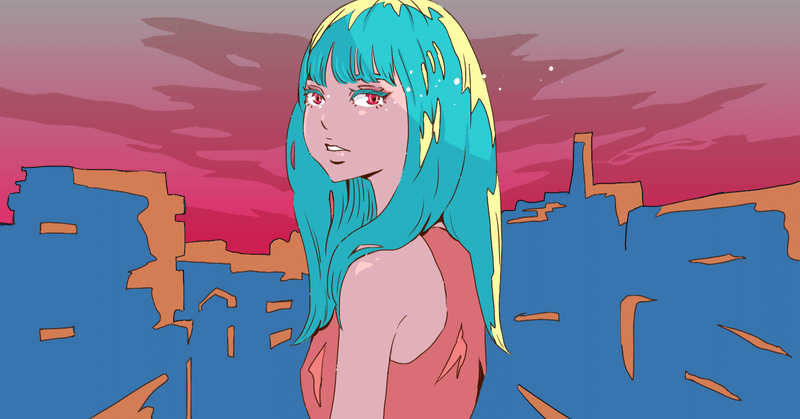
海とケーキの脆弱性(2999字)
Twitterの滅亡から20分が経過した。私の精神は1秒ごとに活気を取り戻している。だって、もう二度と「トレンドに※※ってあるから、てっきり※※のことかと思ったのに、どうやら私の知らない※※があるみたいだ」を見なくて良いし、もう二度と、自信と怯えだけは充分すぎるほど持っているのに、才能と聞く耳だけはまるで持っていない新型権力者たちの戯言を目にしなくて済むし、もう二度とTwitterだけで繋がりのあった、話したことはないけれど、なんとなく温かい気持ちになったり、行く末が心配だったりする相手に微弱な思いを同調させることもない。
要するに快適なのだ。
「仕事つらい」の変奏を4日に一度投稿するだけだった私の最後のツイートは以下の通り。
あなたは、そして私も、何者かになる必要なんてない。しかし結局は何者かになってしまう。役立たずとか、クズとか、いなくても良いやつ、みたいなものに。
助かった、と心から思う。こんな凡庸で思い上がった馬鹿丸出しのツイートを読んだのは、たぶんいても3人ほどだろうから。そして誰の記憶にも残らないだろうから。Twitterは消滅した。完膚なきまでに。
◆◆◆
「戦争はよくないって言うけどさ」私は早口にまくし立てる。「みんな好んで、自分から戦争を生み出しに行ってるよね。たとえば里と山の争いとか」
深夜2時のバスルームで悲惨なほど粉々に砕け散ったはずの私が、正午にはこうして、さっぱりした顔つきで、きのこ・たけのこ論争の無益さについて滔々と語っている。この自己修復能力には、いつもながら驚かされる。
それに、きのこ・たけのこ論争なんて、Twitterでは見るのも嫌だった話題の一つだ。
「僕たちって、きのこ派・たけのこ派に分かれてたっけ?」加賀美が怪訝そうな顔をした。
「本気で言ってる?」私は目を細める。「我々はどちらの陣営にも属していない」
私たちはお気に入りの喫茶店の、お気に入りの席にいる。道路に面した窓際のカウンター席。道ゆく人の目に、私たちは呪われた双子の人形のように映るかもしれない。二人とも髪が長く、青褪めた顔をして、クラシカルなワンピースを着ている。表情はない。
「私たちは戦争の傍観者だよ」私はコーヒーカップに口をつけたままで言う。「それに、きのことたけのこはパッケージが違うだけ。中身は同じ。味も同じ」
「別物でしょ。完全に」
「同じだよ。完全に。箱に描かれた絵や説明文が違うだけ。人間を騙すフェイクの一つにすぎない。きのこ派、たけのこ派、どちらだろうが、所属した時点で同じもの。あいつらは幻の領土を奪い合って、同族同士で戦争をしている。愚かな人類の歴史そのものなんだよ」
ふうむ、と芝居がかった調子で加賀美が不服の意を示した。
沈黙。
ささやかなボリュームで音楽が流れている。坂本龍一のバレエ・メカニック。この曲を聴くと、いつもなぜか、お正月の晴れた朝みたいな気持ちになる。
私は小綺麗なケーキをスプーンでいともたやすく突き崩した。
あまりに甘く、あまりに無防備な退廃の塊。
◆◆
私たちは同じアパートの、同じ部屋に生息している。喧嘩は絶えない。
「きのことたけのこに違いがないってこと、どうしてわかってくれないの……」
「まだ言うか」
「だって」
「きみは随分と繊細な人間のようだが」加賀美が服を脱ぎながら言う。「僕は繊細さにさして興味がない。繊細でい続けるためには、まず周囲を愚鈍化しなければならないし、愚鈍化される周囲とはすなわち僕のことだ。違うかい?」
着替えるときの加賀美の体からは南米の淫らな花のような独特の芳香が放たれる。ほんの2秒ほど。私はその瞬間が好きだ。
「きみを愚鈍だと思ったことは一度もないよ」私は加賀美に後ろから近づいて、背中に手を当てながら言った。
「どうかな。きみの繊細さは無自覚な毒のようなものだから。フグは人間を殺す毒が自分の中にためこまれていることを知らない。それと同じさ」
「フグ食べたい」と私は言った。「フグ食べたいフグ食べたい! フグ食べたあ~〜い!」
「え?」
「フグ。できればトラフグの天ぷら」
「今?」
「今」
「無理だよ。何時だと思ってる」
「クグロフ、今何時?」
現在の時刻は 02:00 am です
「現在の時刻は 02:00 am です」私はクグロフの口調をコピーして言った。
「まともなフグが食える時間帯じゃないね。海以外では」
「淡水のフグもいるらしいよ」私はスマホの検索結果を見ながら反論する。
「同じことでしょ。捌く技術がなければ毒で死ぬだけ。うちにあるもので我慢して」
「この家にはケーキしかないじゃない」
「きみがケーキ以外のものを食べないからだろう」
「じゃあ、せめて」私はフグのように頬を膨らませる。この表情の可愛さには自信があった。「フグが泳いでるところに行きたい。今すぐ」
私たちが海に着いたのは6:00 am頃。
凪いで、暗い色の、鉄板みたいに平坦な海。
この世界が球体だというのはやはり嘘で、少しだけ湾曲した土台の上に、血で血を洗う歴史というやつは繰り広げられてきたのだ。そんな幻想を抱かせるような。
ところで、ひらひらのドレスを着た私たちは壮絶なまでに海の景観から拒絶されている。あるいは未知の深海魚のように海と同化している。
「どうやってフグを見るの?」私は波打ち際の貝の破片を踏みにじりながら言った。真っ赤な・威容を誇る・厚底のレースアップシューズに海藻が絡みつく。決して交わるはずのない物体が接触する奇跡を思う。
「今でもまだ、フグが見たい・もしくは食べたい・と思ってる?」
「思ってない」私は正直に答えた。
「どの辺から思ってなかった?」
「最初から」
「きのことたけのこは?」
「別物です」
私たちは波打ち際でごく少量の水を掛け合ったりして、多少はしゃいだ。
写真は撮らず、とくに気の利いた感想も思い浮かばない。
ただ、胸の中にきれいな空気が流れるのを感じた。
こんな絵空事のような時間もそのうち終わる。忘れる。消滅する。
あとには骨も灰も残されない。
でも空想に囚われるのは簡単だ。
現実に起こったことと、夢見たことを、思い出の中で選別する必要がありますか?
加賀美の美しい髪が朝の潮風に溶けている。
加賀美を暗い海に沈めて、その確乎たる肉体を揺らめかせてみたいと思う。
目の前にいる加賀美と、過去に体験した無限のタイムラインの文字列が、波のうえに渦巻いていた。
加賀美は単なるツイートの集合体なのかもしれないし、タイムラインは私を苦しめる現実なのかもしれない。
加賀美が堤防のカモメとにらめっこをしている。私は後ろから抱きついて、レースに覆われた肩に軽く歯を立てた。
ケーキは甘く、海は苦い。
加賀美からはその両方の味がする。
もうそろそろ加賀美を私から解放してあげるべきかもしれない。
役目を終えて、忘れ去られた文字の群れのように。
◆
そんなわけで、Twitterが滅亡してからというもの、私は馬鹿のように怠惰な日々を過ごしています。一人きりで。みなさんはお元気ですか? Instagramやmastodon、その他の新興・旧態依然のSNSに、きちんと居場所を見つけましたか? あるいは自宅の・現実の・そよ風の吹くバルコニーや、居心地の良い飲食店や、木漏れ日の裏庭がそれに当たりますか?
私は何もない海岸で、誰にも聞こえない声で、今もつぶやき続けています。原因不明の不具合のように。重度の虚言症におかされたように。なにげないツイートのように。
