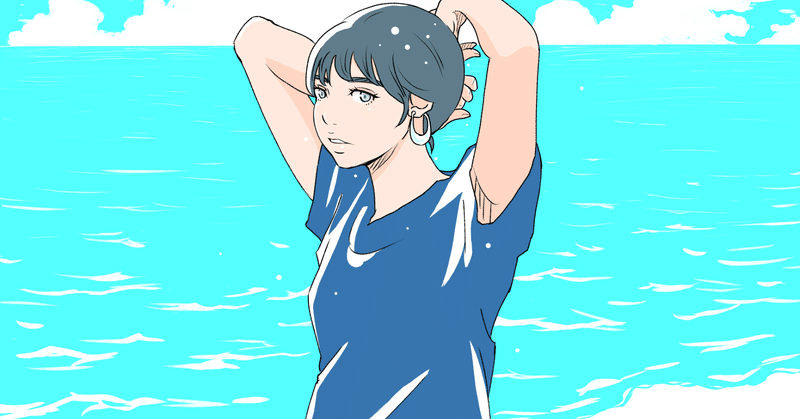
Xと夏とビデオテープ
Xが私の部屋に出現したのが13日前。
そのさらに3000日前のこと。私は唐突に歳を取らなくなった。
ごく低い確率で、人はある時点から歳を取らなくなるものだが、自分がそうなってしまうとは想像もしていなかった。とりたてて野心も特徴もない女に【不老】の特性が宿ることもあるのだ。
最初に感じた異変は食欲の喪失だった。人は食べることで老化する。当時の私は毎日記憶をなくすほど無茶な働き方をしていたから、自分が一切の飲み食いを必要としなくなっていることに、ひと月以上も気がつかずにいた。
ほどなく私は仕事を辞め、ゆかりのない土地に移る。さいわい、10年ほどであれば働かずに暮らせるだけの余裕があった。食事も社交も断てば、私の生活にほとんど金はかからない。金が尽きたあとの身の振り方など【不老】の考えることではないし、そもそも【不老】は遠い未来に不安を感じない。
【不老】はある日突然死ぬのだ。
孤独に生きることしか許されない者には、死ぬ準備など必要ないということだろうか。
世間との関わりを断った私は、1日中部屋にこもり、延々とビデオテープを再生している。
歳を取らなくなった人間は、定期的に拠点を変えるのが普通だ。世を捨て山にこもる【不老】も昔は多かったようだが、今ではそんな変わり者はほとんどいない。
華々しい生活を好み、社交会で名を馳せた【不老】もいなくはない。そういった者たちは時代の変遷期を利用して、人間関係の網から幻のように消えてしまう。そしてまた別の時代、別の場所に颯爽と出現するのだ。祖父と孫がそれぞれの青年期に憧れた少女が、じつは同一人物であったという例もある。
とはいえ、最近ではそんな徒花のような生き方も難しい。科学の進歩がすべてを変えた。何もかもが克明に記録されるようになってしまった。怪談の魅力が変質したのと同じこと。すっかりクリアになった世界には、物質的な恐怖しか残らない。【不老】はあくまで形而上的な存在なのだ。税金を払おうが、投票しようが、誰かに好意を寄せようが。
【不老】は、世間の正常な仕組みから逃れながら生きている。生活のさまざまな局面が自動的に最適化され、最後にはたったひとつの行動を取り続けるようになる。欲求を絞らなければ生きていけない。寄せては返す波のように、単純な行動を繰り返すことで正気を保つしかないのだ。絵を描き続けたり、穴を掘り続けたり、数式を解き続けたり、途切れることなく同じ文言をツイートし続けたり。新たな怪異の誕生というわけだ。
私の場合はビデオテープを観続けるという習性を備えたようだ。
ビデオテープはもともと祖父が持っていたものだ。前世紀のテレビ番組の録画がほとんどで、数千本はくだらないだろう。市販の映像ソフトは全体の2割ほど。アダルトビデオの類はなかった。もともと所持していなかったか、あったとしても、すべて処分したのかもしれない。
というのも、祖父は亡くなる前の数年間、孫娘の私と2人で暮らしていたのだ。家事の一切は私が取り仕切っていた。
とくに介護の必要も生じないまま、私が働き始めた頃に祖父は死んだ。私にとって最後の肉親だったし、祖父の葬儀を境にあらゆる親戚づきあいも消滅した。もともと疎まれていた一家だった。
【不老】となり、家を引き払う際に、私は遺品の中から大量のビデオテープと骨董品のように美しいビクター製のビデオデッキだけを引越し先に持ち込んでいた。とりあえずテープをすべて再生し終わるまではやることがある、と思ったのかもしれない。一度観たテープは破棄するようにしている。ビデオの残り本数は、私のライフゲージのようなものだった。
結果として私は外界との接触をほぼ断絶し、ビデオ再生だけを10年も繰り返している。
生きているとは言えないだろう。死んでいるとも言えない。世の理から外れてしまったとしか言いようがない。
そもそもビデオデッキの製造が中止されてずいぶん経つ。祖父がテレビ番組を録画していたのも、1980年代から90年代にかけて。ほとんど100年近く前のことだ。
必然的に、画面に映し出されるのは100年以上前の映像ということになる。
私はそれを漫然と眺めているわけでもない。ひとつだけ、目的めいたものを設けていた。
100年前の夏を探すことだ。
あるときから、私はビデオテープに記録された夏に魅了されていた。
ずっと夏を憎悪して生きてきたのに。
私の肉体や私の人生は、夏と決定的に折り合いの悪い性質を持っている。私は夏に似つかわしくない個体なのだ。そして夏に似つかわしくない個体にとって、人生というものはあまりに深刻すぎる。
夏の光は圧倒的に明瞭で、一切の逃げ場がないのだ。
ビデオテープの夏が理想的なのは、私がそこにいないという点にある。ビデオテープの中には私がいない。私のいない夏が、私は好きだ。そのことに気づかされた。
膨大な録画データに点在している100年前の夏。
100年前の髪型。
100年前の服装。
100年前の笑顔。
100年前に流行したポーズ。
100年前の愛の言葉と罵倒の言葉。
100年前の政治的な正しさ。
100年前の人々を粉々に分断した資本主義。
100年前にはまだ存在している美しい建物。
100年前にはまだ存在している謎めいた戒律。
100年前にはまだ存在している清潔な空気。
すべてが新鮮で、安全で、過去に起こったことの繰り返し。記録された磁気データの夏に入り浸り、根拠のないノスタルジーに浸っている私は、さぞかし滑稽なことだろう。
私は本物の夏をおそれている。正確には陽光を。【不老】化して以降は、夏の日差しを徹底的に避けるようになった。ずっと昔、久しぶりに見た光が恐ろしくて忘れられない。
すべてが灼けるようにまぶしかった。
夏の陽にさらされ、虚飾をはぎ取られ、何もかもがエフェクトなしに見られてしまうことが恥ずかしかった。長く生きているのに歳を取らないというのは、それだけで恥ずかしいことだ。見た目が変化しなくても、何らかの蓄積が人を変質させる。歳ばかり取った、空虚な人間であることが際立ってしまう。
そんな状態で誰かと親密に関わるのは不可能なことだ。
私は山のようなビデオテープを見て過ごす。それだけしか出来ず、それだけで満足だった。
しかし前述の通り、13日前にXが出現する。
それですべてが一変してしまった。
いつものようにビデオテープの夏に没頭していた午前11時。
突然インターホンが鳴り響いた。
最初、それが何の音なのか分からなかった。もうずいぶん長いこと、セールスや宗教の勧誘といった社会の流れ弾のような訪問すら受けていない。そういった風習は廃れたのだと理解していた。
再び音が鳴る。
ひび割れた電子音が、今度はほとんど稲妻のように私の全身を撃った。
それがインターホンの音だということを3000日ぶりに思い出した私は、立ち上がり、恐る恐るモニタを覗き込む。そこには玄関先のリアルタイム映像と、女性の姿が表示されていた。
女性は人間ではない。古いタッチのコンピュータ・グラフィックスで描かれていた。それこそビデオテープの時代に流行したような画法だ。
選び抜かれた16色の組み合わせで表現されたその女性は、口だけを動かして喋る。
「おはよう。天気も良いし、海でも行かない?」
少し考えたあと、私はモニタを切った。
いたずらか詐欺だろう。そんなものが関わってくるような社会的リンクの中に、まだ自分が位置していることが意外だった。
リビングに戻ろうとする。視界の隅に何か動くものがあった。
そちらを確認して、ぎょっとする。
玄関のドアがゆっくりと開いているのだ。
眩しい光とともに、何かが部屋に侵入してくる。
それがXだった。
先ほどの古めかしいコンピュータ・グラフィックス然とした見た目では、もちろんない。
おそらく女の姿をしていた。
おそらくというのは、Xはどのような姿にも見えるからだ。
Xの存在している座標には、無数の人物の像が、めまぐるしく移り変わりながら描画され続けている。
私が目にしているのは、その揺らぐ像の総体だ。
結果としてXは、若く美しい女のかたちを取っているように見える。
私の目が無意識に選び取っているのかもしれない。
若く美しい女の姿を。
そしてこの時点を境にして、私の姿もかつての私ではなくなっていた。
自分の外見を自由に選べるようになったことが、私には直観的に理解できている。
私もまた若く美しい女の姿を取っていた。
自分本来のルックスを、すでに思い出すことができない。
きっと、見た目に関する酷いコンプレックスがあったのだろう。想像はつく。その問題に関する苦渋の残滓が心の隅に検知されたからだ。
「どうせ暇なんでしょ」
Xは華やかな微笑を浮かべた。派手な表情の動き。100年前の化粧品のCMで女優がやっていたような。
Xは私の前に立ち、私の手を取った。ひんやりとして、少し湿った手だ。そのまま手を引かれ、私は3000日ぶりに真夏の屋外へ出る。
圧倒的な光。
でも恐ろしい光の棘のようなものは感じなかった。それこそビデオテープの夏に似た、どこかノスタルジックな明るさの洪水。
どうしてこんなに優しく感じられるのだろう?
今の私が美しい女だからかもしれない。
今の私は、夏の似合わないみすぼらしい個体ではないのだ。
「昔とは何もかもが違って見える」と思わずつぶやく。
「それは当然」Xがくすっと笑った。「ここは圧縮された夏だもの」
「どういう意味?」と問うと、Xは歌うような口調で、長く退屈な説明を展開した。まるでプライバシーポリシーに関する文書のように、私には理解できる部分とできない部分がある。
しかし、おおよその想像が当たっているのであれば、この世界はすでに私の知っている世界ではない。
私が引きこもっているあいだに、世界は少しずつ、数値と命令文の羅列に置き換えられていたのだ。
きっかけは疫病の蔓延だった。
3000日前、唐突にこの世を覆い尽くした死のウイルスは、瞬く間に殺傷能力を増大させ、人と人との交流を徹底的に断絶した。
他人との接触は即座にインターネットの回線上に移される。それでも猛威を増すばかりの疫病に対し、戦線は後退し続けた。そして結局、人類は現実世界をまるごと仮想空間に移すより他に道をなくしてしまう。死の恐慌を前にすれば、人はどんな変化もなんなく受け入れるものだ。そもそも、美しい理念で巧妙に隠されたまま、世界中の政治は完璧に独裁化していた。石器時代の昔から、権力は途切れることなく一部の人間だけに継承されてきた。何度革命が起ころうと、古い権力から完全に切り離され、自由に作り直された国など歴史上ひとつもない。すべてが記録されるようになったこの時代にだって、迫害や、ジェノサイドや、生命の仮想化が、秘密裡に、そして驚くべき速度と正確さで実行されてしまうのだ。私たちはうすうすそのことに感づきつつも、抗議の手段や意欲をほとんど奪われてしまっている。
結局、狭量な神を信じる者たちと、自分を信じすぎる者たち、そして生きる希望を失った者たちだけが、この世界から速やかに消滅した。
ろくに考える力を持たない私たちのような人間だけがのうのうと生き延びたというわけだ。権力者たちの完璧なコントロールのもとで。
まず始めに夏が完全に数値化された。事前の予測とは異なり、数値化された夏はわざわざ実行するまでもなく、数値のままで夏だといえた。他の季節とは明らかに挙動が異なっている。そのため、皮肉なことに夏だけが再生されず眠り続けることになる。
その眠り続ける夏の中で眠っていたのが私だ。
ほんの2行の数値に姿を変えて。
私は数値のまま、夏の一部として静止していた。
夏は予感のままで夏なのだ。
いつまでも始まらない、あらゆる夏の可能性を秘めた数値の群れ。
その状態でいることはなんとも心地よかった。
それが私の3000日間の正体だ。
「だったら、今ここにいる私は何?」思わずXに詰め寄る。「私の過去は本物? 私は本当に存在しているの?」
Xは出来の悪い生徒を見る家庭教師の目つきになった。
「自分が何者とか、何をするために生まれてきたのとか、もうほとんど古代人の悩みだね。メロドラマ?」
「でも、何かをしないと生きていけない。私は何をすれば良いの?」
「何もしなくて良いし、生きていかなくても良いし、死にたくても死ぬことはできない。もう世界はそうなってしまった」
「浦島太郎になったみたいだ」
「ウラシマタロウって?」Xは不思議そうに首を傾ける。彼女に連なる無数の像もなめらかに動く。
「浦島太郎を知らないの?」
「知らない。友達?」
「おとぎ話だよ」
「どんな?」
「まあ、世界中に類型が見られる説話だね。ケルト神話とか、フランスの騎士ギンガモール、中国の水経注に、竜女の伝説……ああ、リップ・ヴァン・ウィンクルもそうかな。ほかにも……」
「あなたの話って要領を得ない。ストーリーを教えてよ」
「うーん。やめておくよ。おもしろい話ではない。要するに、まともな人間らしく生きようと頑張ってみたけど、最後には何もすることがなくなって、途方に暮れる男の話、かな。今の私と似てるかもね」
「途方に暮れてるの?」
「かなり」
「どうして?」
「だって、やることがない」
「なることならあるよ」Xは言った。私の手首をまだ掴んでいる。「もう忘れた? 最初に言ったよね。海で遊ぼうって」
Xが私の手を引いて走り出した。
私は10年以上もろくに運動をしていない。足がもつれる恐怖があった。しかし、予想に反して私は軽やかに走ることができた。
目の前には驚くほど明るい街並み。
Xが手を離す。濃い潮風が私を包んだ。
海が近い。
「水着になろう」
走りながらXが言う。
走りながら私たちの衣服は水着に変化する。
Xの髪が揺れている。
Xのみずみずしい肌のうえを流星のように汗がすべり落ちている。
私の肉体も、水着の中で嘘みたいに若々しく弾んでいた。
強烈な日差しに照射されながら、私たちは海で遊んだ。私には「海で遊ぶ」ということの意味が、今までわかっていなかったのかもしれない。夏の海で遊ぶことは、夏の海で遊ぶことなのだ。そうとしか言いようのない時間の経過のさせ方だ。
はしゃぎ疲れた私とXは、ビーチの端にあるちょっとした木陰で休んだ。水着のお尻に、濡れた石畳の奇妙な感触。
Xは私のすぐ隣で、自分の足の爪を憂鬱そうに見ている。Xの親指の先は少し欠けていた。
「昔、事故で」私の視線に気づいたXが言う。「ここだけは再生しないんだ」
足の指なんて誰も見ないよ、と言いかけて、私はやめた。あまりに工夫のない選択肢のひとつでしかないと思ったから。Xがとても愛おしく感じられた。でもこの気持ちだって、何かの引用めいている。
日が暮れて、私たちは夜の街を散策した。信じられないくらい上手にパッキングされた荷物のように、小さな通りには多種多様な夜の店が入れ替わり立ち替わり現れた。
Xが選んだのは大きな酒場だ。入った瞬間に頭の中が音楽に支配された。雨のようなコンガの響き。理性のたがが外れたようなピアノ。時間を自在に伸び縮みさせるテナーサックス。世界中の音楽が鳴りっぱなしになったような狂乱だ。私たちも音楽に溶け込んで輪郭をなくし、音楽に合わせて形を変えた。お酒も加わって馬鹿騒ぎは加速する。忘我とはこのこと。奇跡のような体験だった。
ふらふらになって店を出ると、Xが膝から血を流している。
「夢中で踊ってたから。どこかにぶつけたみたい」
Xは手首で乱暴に膝を拭い、その血を舐めた。
「消毒したほうが良いよ」
「消毒?」Xは冷ややかに笑った。「毒なんて、ここには存在しない」
「放っておくのは良くない気がする」
私はかがみ込んでXの左膝を観察する。さっきよりも患部の映像が乱れていた。しゃがんだままXを見上げる。塔のようにまっすぐに伸びたXの体。その頂上に私を見おろす顔があった。美しく揺らぎ続ける百億の像の総体が。
突然、Xが私の頭を両手でおさえつけ、自分の膝に近づけた。私は目の前にあるXの傷口を舐める。Xが小さく声を漏らした。私の舌に、治癒能力とXの精神を乱す作用の両方が宿ったのがわかる。
「そのまま続けて」Xのうわずった声。「傷を食べる悪魔みたいに」
私はXの膝をかいがいしく舐めながら、手探りでXの欠けた足の親指を探り当てた。ミュールのうえにむき出しの親指をそっと撫でてやる。Xの体が軽く痙攣した。
いつしか私はXの膝にほとんど噛みついている。2人の境界が甘く滲んだ。電撃的な快感で目の前の像が揺らぐ。Xの傷は残らず私の体内に取り込まれた。Xは腰から砕けるように生け垣の縁に腰かけ、荒い息をつく。その頬は上気していて、瞳は野生動物のように鋭い。そんな女を前にしても、私は少しも気後れすることがなかった。
Xと過ごす夏は刺激的だった。
私は過去の自分と今の自分が、ほぼ断絶したような自由を味わっていた。
毎朝、目が覚めると同時に正体不明の希望が胸に充填されるのがわかる。いつも旺盛な食欲を感じていた。たっぷりバターを塗ったトーストと、ハムや卵、新鮮な野菜、果物を搾ったジュースなんかを、朝から大量に平らげる。食料も住む場所も、まるで心配がない。なんだって買えるし、どこにだって住めるのだ。
私の外見も自由自在だ。金色の巻き毛のあどけない少女のときもあれば、アマゾネスのように強靱な肉体のサーファーだったこともあるし、金属みたいに艶やかな黒い肌を持つ読書好きの女を装うこともあった。
XはXで、どんな場所でも注目の的だ。
女王のように優雅で、少年のようにやんちゃな、百億の美貌の集合体。
そのXが、いつでも私といることを選んでくれる。
私はいつだって自信たっぷりでいられた。
しかも舞台となる数値の夏は理想的なリゾートだ。
街に出れば、イベントがどこにでも転がっている。
閉ざされた夏のそこかしこで、甘い恋や小さな冒険、蠱惑的な秘密やスリリングな謎解きといったものが、美しい物語のように展開した。ささかやな収穫やほろ苦い結末に、子供は少しだけ大人になって、大人は少しだけ子供になる。開放感のある夏の始まりと、迫り来る夏の終わりが、いつも同時に持続していた。
結局、この13日間に起こったことは何だったのだろう。
Xは何も言わなかったが、おそらくウイルス対策に目処がついたのだ。世界は再度、現実化する。私が体験したのは、その直前の挙動だ。つまり、眠りにつかされていた夏が、テスト的に一度だけ実行された。
もともと期間限定のはかない夢だったのだ。
私を含めたすべての住人が数行のデータにすぎず、いくつかのコマンドの受信機でしかない。
誰もが限られた選択肢の中から、スムーズに欲求を満たす。
まるで【不老】だ。
家にこもり、100年前のビデオテープを観て過ごすのと変わらない。
変わらない?
いま、私の隣にはXが寄り添っている。
夏の範囲内での、任意の日付の21時。
私たちは街のはずれにいた。なだらかな石段の中ほどに座って、断続的に打ち上げられる花火を見ている。誰かの計算通りに夜空が構成されるさまを。
Xの右手は、私の左手に乗っている。
Xのネイルは淡い水色。
Xの肩のぬくもりと湿り気がTシャツごしに伝わる。
Xの白い脚は花火の光を一瞬の演算で反射している。
花火が終わり、周囲をやわらかな闇と静寂が満たした。
Xと私の唇が接触する。境界が揺らぐ。計算が乱れる感覚がある。
擬似的な芳香が私の鼻孔をくすぐった。
Xの手のひらが私の胸に触れる。
私の胸は弾力を帯びて、Xの指を押し返す挙動を実行する。
私たちの唇が再びふれあった。
熱っぽい、ゆっくり漂うようなXの呼気が、私の顔にかかる。
「好き」Xが潤んだ瞳で言った。
「私のことが?」
「そう」
「私のどこが?」
「自信がないんだね」
「うん」
事実、日を追うごとに私は自信をなくしていた。すべての終わりが近いことを、心のどこかで悟っていた。
「臆病な人」Xは笑いながら私から離れた。「ねえ、場所を変えない?」
「ここがいい」私はXを抱きしめる。「場所を変えると気持ちも変わりそう」
「変わらないよ。夏のあいだは」
「夏が終わったら?」
「ここには夏しかない」
「ねえ、私のどこが好きか教えて」
「本当に聞きたい?」
「いつもそのことばかり考えてしまう」
「そうね」Xは私の耳元に口を寄せた。「あなたは不幸ではない。いちども不幸ではなかった。でも永遠に幸せを感じられない人。自分のせいで」Xは私から顔を離し、私をまっすぐに見て言う。「そこが好き」
私たちは夜の浜辺を歩いた。
Xの歩く軌道が、私から少しずつ離れていく。
Xはどんどん海に入っていく。
「どこへ行くの」
私の呼びかけにXが振り返った。髪の動きが高速で処理される。水滴をまとったXの周囲に、光の粉のようなものが浮遊して見える。Xにまつわるすべての演算に滞りがない。
すなわち、健康だ。
Xはいまや腰のあたりまで海に浸かっていた。
「死ぬ気?」と私は聞く。
「いつの時代のメロドラマ?」Xは失笑した。「死なんて、ない」
「戻ってきて」
「無理かな」Xは鼻から息を漏らす。「私の力では」
「どうして」
「この眠り続ける夏は解凍され、今まさにひらかれようとしている」
「夏が終わるの?」
「これは夏ではない」Xが寂しげに言った。「夏というには無駄がなさすぎる」
Xの背後で日が昇る。透明な光が少しずつ満ちたりていく。入り江の形が明らかになり、遠くの小島の影がしだいに濃くなる。
海からの熱い風。
私の全身を包んでいる。
昨日と同じ正しい光が、みるみるうちに世界中によみがえる。
ここは完璧な夏だ。
なのにXの表情は暗い。微笑んだ形を保ったまま。見知らぬ他人を見るような目で私を見ていた。
そして私は室内にいる。
室内?
安物のラックや、テレビ台や、カラーボックスに囲まれた雑多な空間にいる。
世界の運用方式が元に戻される前に、眠り続けていた夏が一度だけ夏が実行された。
やはり、それがあの13日間だったのだ。
繰り返す無限の夏。
そのどれかひとつに私はいた。
ビデオデッキはずいぶん前に壊れている。
目の前のテレビには、真っ暗な画面が表示されていた。
突然、インターホンが鳴る。
Xが現れたときと同じように。
私はほとんど自動的に立ち上がった。
モニタは故障しているようだ。ドアスコープから外を覗く。段ボール箱を抱えた男が立っていて、宅急便です、とドア越しに告げた。
直接、人間が届けに来る?
まるで祖父の時代のようだ。
私はドアを開ける。
宅配業者の男は防毒マスクを装着していなかった。差し出された紙にサインをし、箱を受け取る。自分の手が妙に衰えて見えた。
箱を持ってリビングに戻る。真っ暗なテレビ画面に映る私は、しわくちゃの老人。しかも男性だった。
この物語は本当につまらない。
予想された中で、最も意外性のない結末だ。
自分の正体が、未来のない孤独な男だったなんて。
私が自分の人生に欠けていると思い込んでいた要素X。それを私に差し出して、その願望の無意味さ、醜悪さを私に突きつけ、苦い教訓を与えようとでも言うのだろうか。
おまえが恋だと信じたものは、ほんの短いポルノに過ぎない
私は怒りと空腹を覚えていた。
この通り、すっかり不便な人間の体だ。
食べなければ死んでしまう。
ひょっとしたら、すべては本当に一晩の夢だったのかもしれない。
私に巣食う羞恥心や、無知や、無意識の差別や、極端な被害者意識や、逃避癖や、甘えや、そんなものを煮詰めただけの。
外へ出る。街は祝賀パレードの様相。歓喜に湧く群衆を眺めているうち、私はXとの夏が、誰のものでもない特別な夏だったということを理解し始めていた。
誰も私のように素晴らしい夏を経験をしていない。
だからあんなにも無邪気に、永遠の夏の終わりを喜べるのだ。
Xと過ごした夏は、誰との共有も許さない。誰の閲覧も受け付けない。
私の中で永遠にループし続ける、たったひとつの夏だ。
あの夏を失った代償として、世界はすっかり元通りになった。
社会の脆弱性を見事に突いたかに見えた死のウイルスは、結局のところ何も破壊しなかった。
失敗した謀反は、歴史を停滞させるだけ。
何の意味もない文字情報だ。
耐えきれず部屋に戻る。さっきのダンボールを開けていないことに気がついた。
送り主も内容物も不明。箱の切れ目にペーパーナイフを入れながら、私は浦島太郎のことを思い出していた。
私のような老人が玉手箱を開けたら、いったい何が起こるのだろう。
箱がすっかり開封される。
そこには新品のビデオデッキがおさめられていた。私は壊れたビデオデッキを取り外し、新しいデッキの配線をする。ビデオテープが挿入口に飲み込まれた。再生がスタートする。
画面に映ったのは、どうやら100年前の市民プールの映像だ。
100年前の肉体の群れ混じって、Xが泳いでいる。
100年前のなつかしい笑顔。
100年前の美しい化け物。
Xの足の指は、すべてきれいに揃っていた。
ビデオテープはまだ山のように残っている。私は記録された夏を探すためにビデオを再生し続ける。
私の外で季節は巡り、私の中では停止している。生きているとは言えないだろう。死んでいるとも言えない。世の理から外れてしまったとしか言いようのない、野心も特徴もない男。過去に生きるしか術がなく、過去にいるのは空虚な自分だ。誰も私を覚えていない。私も私を覚えていない。
有料ゾーンにはちょっとした解説がありますが、100円払ってまで読むものではないですよ。お気持ちで。
ここから先は
¥ 100
