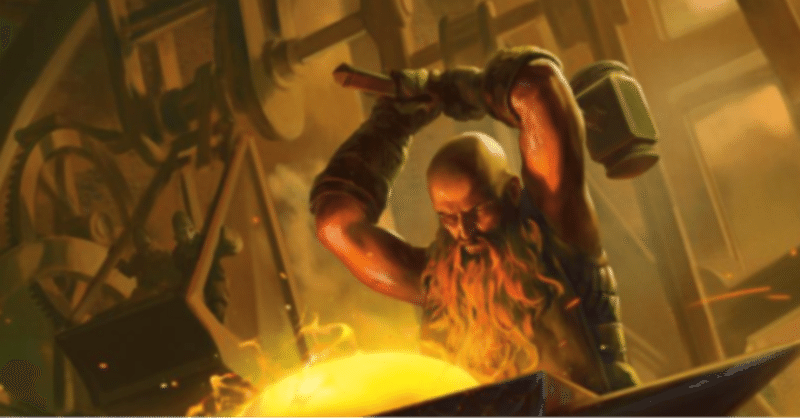
【MTG】四方山話 ~デバッグの落とし穴~
どんな強力なカードも最低1枚は使えることが売りのヴィンテージにおいて禁止カードが現れてしまってこの方、多くの人がカードパワーのインフレーションやWotCの開発能力などについてさまざまな意見を発信していたと思う。
その中で、とあるブログの記事が大変興味深かった。
https://meetsheday001.hatenablog.com/entry/2020/06/02/233700
筆者は以前に遊技機の制作に関わる仕事をしていたので、この記事で語られているようなことには心当たりがあり、なんとなく面白くなってしまった。
■ぱちんこのデバッグ
遊技機、つまりぱちんこやスロットではプレイのために金銭の投入が必要であるため、ユーザーにとって不利な不具合の類はほとんどの場合で許されないうえ、それでいて何やら不思議なシステムの関係からホール(店舗)側に不利な不具合も許されない。
2011年に発売された『パチスロ サクラ大戦3』は玉が出すぎるということでメーカー交換にいたるような不具合もあった。
さて、そんな遊技機業界での製品のデバッグだが、大抵の場合はメーカー側から最低限のチェック項目を要求される。
たとえばぱちんこでは、全ては挙げられないが、概ね
・ハズレ変動のときに図柄が揃わない
・保留玉の個数が正しい
・不正動作があったときに指定の動作をする
など、これらを詳細にしたものが多い。
当然、それ以外の演出に関連するものも多数あるが、それらに関してはメーカーというよりも機種に拠っており、ほとんどは制作をする下請け会社側で決めていたことが多かったと思う。
余談だが、全ての図柄変動の時間を合算したときに4000年ぐらいの時間に至ったことがある。これにモードや図柄の組み合わせなどを考えるとまさに天文学的な工数、人月が必要だったの途中で計算をやめ、企画者に懇切丁寧に説明し、さすがに内容を変更させた。
■落とし穴
ぱちんこのデバッグはそこそこ長い期間が必要だと感じているが、実際には演出の発生率や出玉率などは「実際に遊技しないとわからない」ことが多く、それの変更は期限ぎりぎりまで何度も繰り返されるため、精度の高まった状態になるほどデバッグ可能な時間は残されてない。
単に「図柄が[1][2][3]で止まる」、「○○予告が発生する」、「△△リーチに繋がる」などはかなり早い段階でバグフィックス可能だが、それは単発の動作での保証に過ぎず、他の組み合わせ、つまり「10時間以上遊技をしている」や「直前に□□□モードを経由している場合」などを考慮すると起こりうるパターンはほぼ無制限に存在することになる。
こういった状況において、デバッグの信頼度は「試行回数」に依存するのだが、シチュエーションを限定することで「問題はない」とみなすことが多々ある。
つまり、「仕様上こう決まっているのだがら、こうではない現象は起きない」と決め付けるのだ。当然、これは仕様外のときの動作も保証されているか、そのときの動作の仕様も存在していることが条件である。
そして、試行回数が足りない状況では、3交代制の体制で24時間回し続けることもしばしばある。その結果、「これだけやってバグはなかった」と安心するのだ。もしかしたらあと1時間で予期せぬバグが発生したかも知れないが、最早それを発見しデバッグする時間はない。
■MTGにおけるデバッグ
実際にMTGの開発においてどのようにデバッグを行っているのかはわからない。WotCによれば調整チームを発足し、入念にカードパワーを調整しているとしているが、これはおそらく同時に「決められた期限で調整を繰り返している」ことも示していると思った。
例えば《王冠泥棒、オーコ》についてはデザインの教訓として公式の記事がある。
https://mtg-jp.com/reading/pd/0033449/
《オーコ》はさまざまな環境で禁止を受け、生存している環境においても「強すぎる」と認識されていると思う。記事によればそのオーコはもともともっと不快なゲームを作り出す存在だったようだが、結局のところ「遅い時期の再デザインの間に、その純粋なカード・パワーを見失い、かなりの割合で行き過ぎてしま」ったと記事でも述べられている。
これは単に「販売スケジュールと言う締め切りがあるゲームの弊害」だと思う。
デバッグにおいて見落とされる存在は必ずあるが、2019年以降のMTGのカードについては「どのカードをどうデバッグするか」を決めてしまっているのではないかと感じる。
《甦る死滅都市、ホガーク》はモダン用のセットに登場したがモダンから追放されてしまった。おそらく墓地利用デッキという点に絞ってデバッグを行ったと思うのだが、ライブラリーアウトコンボデッキとしては一切のデバッグがされていなかったと思う。つまり、《狂気の祭壇》と組み合わされることは思いも寄ってなかったと感じている。
直近の禁止改訂でもそうだ。
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0034028/
《創案の火》について、「このカードのコストを踏み倒す効果の柔軟性により」、「環境に新しい高コスト呪文が加えられるたびに強くなり続け」ることが「判明した」と書いている。
デバッグにおいて《創案の火》の使い方を決め付けてデバッグをしていたと言っていいだろう。
■デバッグの限界
スケジュールが存在する以上はどうしようもない問題なのだが、全てをデバッグすることはやはり不可能なのだ。「オーコが強すぎるので開発期間延長」などをしようにも販売スケジュール以外にもプロツアーやグランプリなどの大会スケジュールにも影響してしまう。
可能な限りデバッグをするためには、「どのようにデバッグを行うか」を指揮する必要がある。しかし、そこからこぼれてしまったものがバグになりうる危険性は高まる。
MTGWikiの《星の揺らぎ》に紹介されるエピソードのような熱心なテストプレイヤーが多数いれば《軍団のまとめ役、ウィノータ》や《死の国からの脱出》のようなエキサイティングなカードは決して登場しなかっただろうが、2,3人はいてもいいんじゃないかと思う。
現在のMTGのカード全てを検証しデバッグすることは不可能であることは間違いないが、これからもWotCには彼らの標榜するFIREの実現を続けてほしいと思う。
■あとがき
デバッグは難しい。パイオニアやモダンというやや限った範囲であっても十分にデバッグすることは不可能だと思う。デバッグをしている間に次のセットが登場してしまう。ほとんど賽の河原に近い。
戦乱のゼンディカーブロック以降、各ブロックや基本セットで何かしら禁止カードが登場している。少なくとも今後のスタンダードについてはそうならないように祈っている。最近は新規者に勧める際に「MTGは禁止カードがあまりないので~」と言えなくなってきた。
ちなみにぱちんこやスロットのデバッグでは不正に対するデバッグが非常に多い。具体的には玉を帯電させた遊技や強力な磁気を近づけるなど、そういった不正時の挙動への対策がとにかく厳しい。なぜだろう?
それではよいMTGライフを。
ぎゃ٩( 'ω' )و
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
