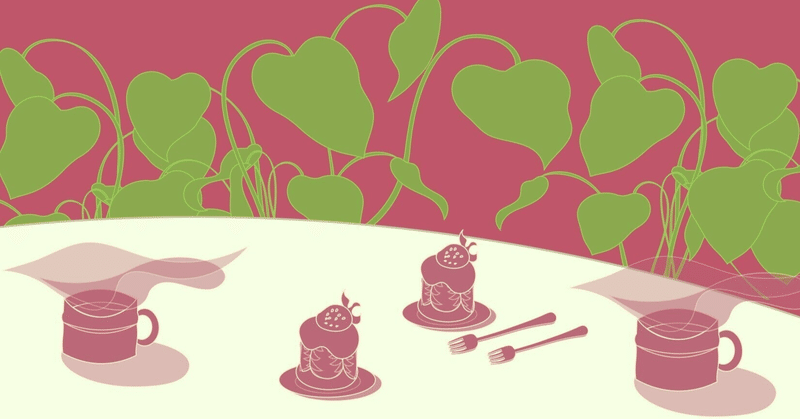
2層協議体北東西での情報共有~コロナ禍を経た居場所の情況
本日は、先月17か月ぶりに再開した、北東西協議体の会議でした。
地域資源の中でも、「居場所」のリスト造りをしていた北東西。しかし、コロナで活動中断をしていた17か月の間に中断、終了してしまった居場所もあるだろうと、この1か月、まずは、把握していた居場所の原状を確認してきて、共有しましょう、ということになっていました。
40近くあげられていた「居場所」。自分の地域のそれを各自が調べてきて、それを報告して共有しました。
コロナ禍で、居場所活動はどう影響を受けたのか
さて、その共有の結果、私個人の印象としては、「思っていたよりも、コロナ禍の中でも継続できていたな」という感じです。
ただ、課題もみつかりました。
中断の後に再開をしようと試みたところもありましたが、それまでに使用していた公民館など、「場所」の人数制限という壁です。
その関係から、比較的少人数だったところは継続できていましたが、人数が多いところは、場所の人数制限で開催ができていなかった、という報告がみられました。
他方、さすがに第五派の急激な感染情況悪化で、やむことをえず中断したところが、再開したいと思っても、もともとの人数が参加してしまうと、場所がかりられない、という形でもあらわれてくる課題です。
場所をもっていることは武器になる
コロナ禍がはじまった直後に参加した、オレンジカフェの会合では、私的な場所を使っているところはコロナ禍でも継続できているが、公の場所を借りているところは、借りられない、という理由で継続を断念したという話しがありました。
他の地域では、人数制限をこえてしまうので、コロナ禍前は月1だったものを、回数をふやして分散したという事例もありました。しかしこれは、どの居場所、団体もできることではありません。
人は食べ物があると安心して集まれる…という壁
中断を経たあとの再開を妨げるのは、「飲食」というのもありました。
やはり、「お茶会」的に集まるものが多かったので、飲食が(現在でも公民館などは禁止)できないのは、大きな壁になっています。飲食をしないことにして再開したところもありますが、「食べ物は心を開く魔法の種」です。ただ机にすわっておしゃべり、というのは、なかなかハードルも高くなります。また、もともと居場所の名前が「〇〇カフェ」だったので、カフェなのに飲食ができないのは…という壁もあるようです。
しかし、強い意思で継続、そして新設
そんな課題もみつかりましたが、この17か月に新たにはじまったところも2つ報告されました。
課題もありましたが、新たにはじめたところもあり、場所さえ確保できれば継続してきたところもあり。
多くのそれは、ボランティアです。有償・無償を問わず、中断したら生活が維持できない人もいる。QOLがさがってしまう同胞がいる。強い意思と目的意識で継続してきたことに、地域ネットワーク、支え合いの力を感じる会合でした。
画像は、みんなのフォトギャラリーで、「カフェ」で検索した中から選択して使わせていただきました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
