
若い世代の農業へのイメージは悪くない?
突然ですが、若者の動きはこれからの世の中の変化を見る上で重要な指標だと言われることがあります。
特に最近の世代はテクノロジーネイティブであり、様々な情報にさらされている分世の中の変化に対して敏感で、適応も速いと言われます。
さて、僕は最近農業にどハマりしていていろんな人を畑に連れだしているわけですが、少しずつ分かってきたことは、
「意外と若い世代の農業へのイメージは悪くないのではないか?」
ということです。(若い世代=主に20代を想定して使っています。)
そもそも、農業というと3Kや5Kの代名詞になっていたり、ダサいとか儲からないもの、というイメージが先行している。と思われがちかもしれません。確かに、マイナスのイメージがある方は多いかもしれません。
ところが、畑そのものに興味持ってる若い人って結構いるんです。一体この人たちは何に興味を持っているのでしょうか?
僕の立てた仮説は以下の三つです。(あくまでイメージについての話です。)
・世代の入れ替わりによる価値観の違い
・周辺環境の変化(情報と教育)
・産業としての変化
①世代の入れ替わりによる価値観の違い
僕たちの親世代(厳密にはもう少し上の世代)は、実家や祖父母の家が農家であるケースが多いです。(これは農家人口を見ると分かります。1960年は3400万人いましたが1990年には1300万人ほど、ちなみに今は400万人程度)
この世代が子供の時は、高度経済成長期真っ只中でした。強い日本を再構築するために多くの人が第二次、第三次産業への道を選びました。そして、この国はものづくりへの投資により凄まじい発展を遂げます。

そんな時代で、農家の息子や娘の多くが貴重な労働力として製造業や小売業に流れていきます。この人たちの中には「農家にはなるな」と農家の親に言われてきた人もたくさんいると思います。大変な仕事の割に収入は不安定で、子どもに同じ苦労をさせたくないと考える親が多かったのでしょう。中にはこのことに憤りを感じている層もいたでしょうが、工業、サービス業にお金が集まる世の中でこのような農業への強烈な思い入れを持っている層はそこまでたくさんはいなかっただろうと思います。
では、僕たちの世代はどうでしょうか?都市への人口流入は落ち着いてきたものの、「農村」の衰退によって都市と農業の分断は進みました。田舎出身でも農業とは関わりのない育ちをした人はたくさんいます。都会生まれの人は、親戚に農家がいることはあっても農業とは接点のない生活をしてきた人が多いでしょう。そのため、(農業学校は除く)大学生には、実家が農家だという人の割合はだいぶ低いはずです。

彼らの多くは、残念ながら職業として農業を志していません。その理由は日常生活とは疎遠にあるものだからです。しかし、ポイントになるのは、まだ農の世界には触れたこともない人がたくさんいるということです。
漠然とした「自然」への憧れやオフィスワーク中心の生活とは離れた生活を求めている人はたくさんいます。テクノロジーの進化が速く、ただ大企業に入れば安泰の時代は終わったので、どうやって個を強くして人生を切り開いていくか考えなくてはなりません。「生きる」とはどういうことか、漠然とした不安を抱えながら、日常生活から解放されないドーパミン疲れに悩まされます。
人生観も変わりました。お金持ちになって豪邸を立てて外車を手に入れたいみたいな話を僕はそれほど聞いたことがありません。幸せの定義がかなり変化していていて、求めているのは、小さな幸せです。個人の時代になるにつれ、家柄にも縛られず新しく自分がやってみたいことにどんどん挑戦できる環境ができつつあります。ただ働くより、自分らしい生き方、働き方を求める人は多いのです。
②周辺環境の変化
主に二つあります。教育と情報です。
世代が変わり、確かに農へのリアルでの接点は少なくなりました。しかし、若い世代は様々な形で農へのイメージを作り上げてきました。例えば、近年の日本教育。教科書のなかで「農業は後継者不足になっている」ことくらいは誰でも教えられていることでしょう。急激に下がる農業人口のグラフを見て衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか。(こちらは農家人口ではなく農業就業人口です。)
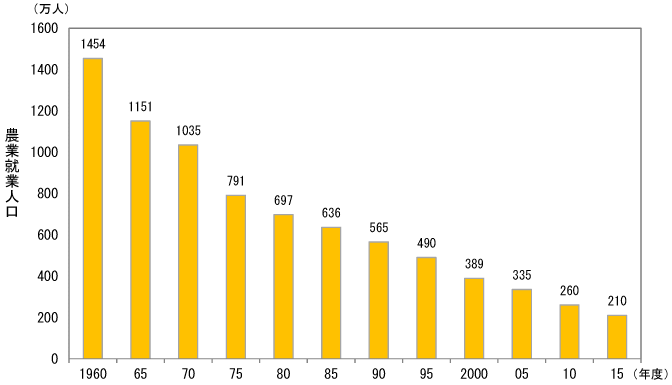
今食べているものがいつか食べられなくなるかもしれない。漠然とした不安を覚えた人もいると思います。また、入ってくる情報も増えました。テレビやメディアでの農家や農業関連の特集が以前より増えました。深刻化しつつある環境問題の暗い話が日々囁かれ、宮崎駿さんの作品で描かれる自然観を見て、人にとって「自然」とは何なのか、どうあるべきかについて考える機会も増えたと思います。しかし、先ほど申したように都市部との距離があり、農地への親近感が湧かない人も多いと思います。
③産業としての変化
昔の農業は、確かにきついものでした。優れた機械もなく今以上に労働集約型なので、繁忙期には地域の住民で協力しあってなんとか続けていました。ところが、今は機械がだいぶ増え、労働生産性はどんどん上がっています。農地の集約や販路の拡大も相まって様々な形で「稼げる農業」を実現している生産者は確実に増え、若手農家(49歳以下)の実に45%もの人が販売金額1000万を超えています。値上がりなどで設備投資が増えたとしても、これは収入も増えたことの証でしょう。

このような事例がしばしばメディアで取り上げられています。また、アグリテックへの投資が進み農業ロボットの衝撃的な動画を見て、盛り上がってきているイメージを持っている人も増えているように感じます。
というわけで、まとめます。
人と農業の距離は一度離れてしまいましたが、その反動の波として食や農への関心が高まりつつあります。なぜなら、人間と食は切っても切り離せない関係にあるからです。だからこそ食料不足に備えてあれほどまでにアグリテック、フードテックへの投資も進んでいるわけです。ずっと変わって来なかったこの業界をブレイクスルーしようとしている仲間がどんどん増え、まさに業界の変化の過渡期にあります。業界としてだけでなく、自然というものへの漠然とした良いイメージは持っています。人もホモ・サピエンスという生き物である以上インプットされている遺伝子構造を変えることはそう簡単ではないんじゃないでしょうか?
あまりまとまってませんが考えていたことを書いてみました。他にもいろんな考え方があると思うので聞きたいです。
(あくまで今回はイメージの話なので、表面的な数字などアバウトな情報しか出しておらず現場に詳しい方からすると現実はこんなんじゃない!って声もあると思います。ぜひそのような声を聞かせていただきたいです。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
