
一つの指輪:指輪物語TRPG のソロ用モジュール『Strider Mode』で遊んでみた
『ひとつの指輪:指輪物語TRPG』には2024年6月現在、未邦訳ながら『Strider Mode』というソロ用モジュールがあるという情報をいただいたので早速プレイしてみることにしました。
Strider Mode (DriveThruRPG.com)
https://preview.drivethrurpg.com/en/product/396291/the-one-ring-strider-mode
以下、プレイレポート&簡単なレビューとなります。
残念ながらロード・オブ・ザ・リングや指輪物語TRPGには詳しくありませんので物語の設定やルール運用などおかしなところがあるかもしれませんが、『Strider Mode』のご紹介が主目的となりますので、そのあたりはご容赦。
画像類はルールブック類からの引用となります。
ソロジャーナル?
『Strider Mode』は、いうなればソロジャーナル(ソロジャーナルRPG)といってよい遊び方の提案になっています。独特なのは冒頭に以下の記述があるところです。

小説のようなものを書く必要はありません(メモは役立つでしょう)。
かわりに世界、出会う人物や敵、あなたの行動を心に思い描いてください。・・・
ソロジャーナルと聞くと、
・小説めいたものを作らなければならない?
・人に見せないと書いた甲斐がないのでSNSに投稿しなければならない?
・せっかく投稿してもなかなか読んでもらえないから寂しいよね?
というような思い込みがありました。程度に差はあっても似たような印象をもつ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、この『Strider Mode』の序文は
「小説やSNSは必須ではない。頭の中で楽しめばよい」
とバッサリ切り捨ててみせます。
結局どうやって遊ぶのか謎は深まりますが、そんな序文に背中を押されて、とりあえず遊び始めてみることにしました。
キャラクターはこちら。
ビルボの遠縁にあたる若い娘とします。名前はベッカ。

イントロダクション
まず支援者を決める必要があります。6人の支援者(ビルボ・バギンズ、ガンダルフ、ギルラエン、トム・ボンバディル&ゴールドペリ、キールダン、バリン)のいずれかからクエストを受けることで『Strider Mode』のゲームは始まります。
ホビットを主人公としたので、もっとも自然なビルボ・バギンズを支援者として選ぶことにしました。ビルボのクエスト表で1d6すると4。クエストは下記となります。
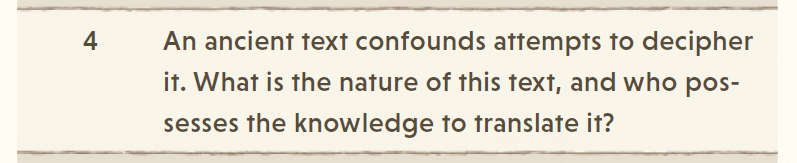
この書はどのような性質のものか?
そして翻訳には誰の力が必要か?
実際にプレイする際には必要ありませんが、プレイイメージをお伝えするためにフレーバーテキストを織り込みます。このクエストとキャラクターから次のような物語のはじまりを連想しました。
ホビット庄歴1360年の秋、当時の私は "おてんば" を絵に描いたような娘で、なまくらな小剣を振り回しては「外の世界の冒険」を夢見ていた。
そんな私にとってビルボは "実際に外の世界を冒険した英雄" だったから、私は理由をつけてはビルボの家を訪れて冒険話をせがんだ。これにはビルボもすっかり辟易しており、私はきまってすげなく追い返されるのだった。
しかし、その日はいつもと少しちがっていた。
「なあベッカ。お前さんひとつ使いをしてみないか。まぁ入りなさい」
聞けば、解読できない古い文書があるのだという。

クエストには詳細がありませんので、各種表類を使い詳細を詰めていきます。
古文書の内容は何でしょうか。ロア表(汎用キーワード抽出表。Loreは伝承や言い伝えなどの意)をつかってキーワードを抽出し、古文書の性質をあぶりだしていくことにします。
ロア表には3種類のテーマ(行動・特徴・焦点)があり、この3種類のいずれかのテーマでランダムにキーワードを抽出します。
テーマとして「特徴」を選んでダイスを何度か振るとキーワードは "危険" 。
もう少しキーワードが欲しいので「焦点」でさらに3度抽出してみます。
結果は "評議会"、"力"、 "不吉"。
相当にきなくさいキーワードになっていますが、どうまとめるか。
その文書は、はるか以前、白の会議に提出される予定だった『力の指輪の不吉な特徴』が記された書簡と、その「配達人」が身の危険を感じながら続けた長い旅の手記だった。しかし肝心の "不吉な特徴" の詳細頁が欠落しており、翻訳が難航しているのだという。
「その欠けた頁が残っていないか確認してきてほしいんだよ。ベッカ」
その欠落したページをどこの誰に確認するのか。ロア表では人名を連想するのは難しいので、スターターセットのホビット庄の書から無作為に人物を選ぶことにしました。ホビット庄からチョイスする理由は、ビルボがまだ若い娘であるベッカに "庄外への使い" を頼むのは不自然だからです。
適当にホビット庄の書を開いて吟味し、ゴーバドク・ブランディバックをチョイスすることにしました。バック郷(ホビット庄の最東端)の当時の館主にしてメリーの祖祖父にあたります。バック郷は古森が近いので小さな旅の少し危険な目的地としても申し分ないと考えました。
「ブランディバック家を訪問して残りの資料を回収すればいいのですね。それで報酬はいかほどですかな」
その珍しい鶯色の羊皮紙の束をビルボに返しながら、私は気取ってたずねた。気分だけでも "重要な任務を担った冒険者" であるかのように振舞いたかったのだ。
私は準備を整えるとすぐに東へ向けて出発した。二日ほどでたどり着けるだろう。
※ ホビット村からバック郷まで40マイル(約60㎞)。
旅のはじまり

スターターセットのホビット庄の書(10P)にはホビット庄移動イベント表という庄内を移動する際のイベントをランダムに発生させるルールがあります。使ってみることにしましょう。快調に移動できるのか、トラブルに見舞われるのか。
振ったダイスの結果は4で、疲労4:"遅延"となった。
疲労を記録して、その理由を考えます。
日暮れまでには蛙沢(かわずさわ)に辿り着き、宿に泊まることにした。
私は宿で頼んだビールと、この "ちょっとした冒険" ではしゃぎ、宿の主人と「ボフィンの香草茸スープの秘密」をめぐって遅くまで白熱した議論を交わした。というのがその日の最後の記憶で、翌日は昼近くになってやっと目を覚ました。
私はあわてて荷物をまとめると、ひどい気分で宿をあとにした。
白畔村(しろあぜむら)につく頃には日が傾いてしまったので再び宿を取り、翌朝早くからブランディ屋敷を目指した。
旅は遅れ、疲労(というより二日酔い)。
ここまで連想すると一気に終盤までの展開を思いつきました。もう少し長い話なら『Strider Mode』の各種表を使って途中の展開を抽出したり、各キャラクターの反応を調べていきたいところですが、今回は短い物語を想定していますので、勢い思いついた展開ですすめていきます。
再度宿泊しましたので、予定より一日遅れがでましたが、疲労状態は回復したものとみなしました。
バック郷につくと、何よりも先に丘の上の巨大な屋敷が目に入った。あれがブランディ屋敷だ。午後すぎにはその大きな門戸をたたくことができた。むしろ"どれが正門か"を特定する方にこそ時間がかかった。大きな門がいくつもあったのだ。ともかくも広帯翁ことゴーバドク・ブランディバックとの面談は叶った。
「よくきなさった。不自由ゆえこのままでゆるしてほしい」
翁は揺り椅子にひざかけをしていた。
彼は落ち着いたやわらかい物腰で、急な訪問にもかかわらず食事を用意してもてなしてくれたのだった。高齢ではあったが話しぶりもしっかりしており、高潔な人物にみえた。
「ビルボに譲った書簡は覚えているが、残りの文章はない。あるとすれば発見された地下の先、ということになるが、立ち入りは許しておらんのだ」
ブランディ屋敷は増え続ける大家族の住居をその地下を掘り進むことでまかなっていた。屋敷には地下道が蟻の巣のようにはりめぐらされているのだ。ある子弟が東の古森に向けて掘り進み、偶然、古森の地下洞窟につながってしまった。ゴーバドクは決してこの通路は使ってはならないとして落とし戸で封じた。封じる前に見つかったのが例の文書なのだ。

会議
指輪物語TRPGには会議というルールがあります。いうなれば説得や交渉を表現したミニゲームです。権力のある重要人物などから支援や協力を得ることができるか、どのくらい抵抗されるか、説得に利用できる時間、技能判定をもとに会議の成否を判定するというものです。
ここで「封じられた扉の開錠と探索の許し」を得るための会議をしてみます。
1)抵抗数の決定
抵抗数は会議を成功させるために必要な技能判定の必要成功回数です。
提案される内容によって必要成功回数が増減します。多ければ難しい提案ということになりますし、少なければ容易な提案となります。
資料の探索そのものはプレイヤーヒーローのみで実施するという想定のため、ブランディ屋敷の住人に負担をかけるわけではないので "穏当な提案(抵抗:3)" と考えました。
ただしゴーバドクは規律を重んじ、若者が身を危険にさらすことを好まないため(『ホビット庄の書』の人物紹介から判断した)、抵抗を1あげて最終的に(抵抗:4)としました。
4回技能判定に成功すれば会議の結果も成功となります。
2)自己紹介
自己紹介ステップの成果で会議にかけられる時間(=技能判定の試行可能回数)を決定。
自己紹介ではいくつかの交渉系技能から好きなものを選んで判定します。
ゴーバドクは真摯な人物と想像できるため、"礼儀" で技能判定しましょう。
7+1+6、希望点を使用し(+3)で大成功。
時間制限:5(次の『話し合い』のステップで5回のチャレンジが可能)となりました。
いよいよここから話し合いとなります。
1回目のチャレンジ。
私は礼を尽くしてゴーバドク・ブランディバックへかしこまった口上をのべた。
「中つ国の歴史にとって非常に重要な古文書の可能性があります。
ただ確認させていただくだけでよく、探索が終われば速やかに戻ります。
危険なときも速やかに戻ります。ご迷惑はおかけしません」
プレイヤー・ヒーローは親族であるバギンズ家の使いであり、ゴーバドクが誠実な人物であることから "親身"(+1d6)に会議に参加してくれると考えた。
また、『口上により安全に配慮した誠実な動機であることが伝わる』ものと考えボーナス(+1d6)とする。
ここでは洞察技能を使って話し合いにのぞむ。
基本ロール(1d12)+洞察技能(2d6)+親身(1d6)+ボーナス(1d6)。チャレンジするたびにロールして合計値が目標15に達すると抵抗1回分の成功。
時間制限(ロールできる回数)5回で、抵抗4回分以上成功すれば会議はクリアです。
※ 技能ロールに出目6があると成功数が1増える。
1回目:3+6+6+3+3 => 成功数:3
出目にめぐまれ(6が二つ)、一気に成功数が伸びました。もう一押しですね。
ここから2回目のチャレンジです。
「ビルボ・バギンズには幼いころより可愛がられておりました。
何卒この若輩めにビルボへのささやかな報恩の機会をお与えください」
『情に訴えかける口上』でボーナス(+1d6)として再度ロール。
2回目:0(サウロン)+4+6+1+4 => 成功数:2
また「6」に恵まれ2回目で成功数:5となりました。成功数が抵抗数:4に達したので難なく会議はクリアです。
もし会議が失敗した場合は、より危険な古森側から地下洞に入る古森ルートを考えていたのですが回避できました。
ゴーバドク・ブランディバックは厳かに言った。
「門扉の鍵を渡そう。ただし日が暮れるまでに必ずもどりなさい。
そしてすべての行いに鋭い目と心を忘れてはならん」
私は鍵を受け取ると礼をのべて地下の入り口である落とし戸へ向かった。
厳重に封鎖されている門扉を解錠して先にすすむと、すぐにあきらかな自然洞になった。この洞窟は古森に通じているのだ。油断ならない。
私はランタンを灯し、小剣を抜いて緊張しながら先に進んだ。
「小さな冒険」だから過度なイベントは不要で、比較的安全な屋敷ルートなのもあり、このあとの展開はずばり「資料の持ち主と遭遇」だけでよいと考えました。
しかし、この洞窟イベントに緊張感を加えるために時間制限は設けます。
食事をして午後も少し時間がたっていますから日没までは3時間としましょう。
ここではシンプルに3回 "捜索" チャンスがあり、1度でも成功すれば「資料の持ち主と遭遇」することにします。有利不利はなし。難易度15。
失敗すれば古森ルートを選択しなければならないものとします。
捜索技能でロールする。
1回目:7+4+6。一発で成功。
おそるおそる自然洞をすすんでいく。道はまがりくねり複雑に分岐していた。勘をたよりにすすむしかない。
急な角道をまがると不意に視界が暗くなった。
大きな人影。手に持ったランタンの光が下からあおる。
ランタンが映し出すその姿はぼろ布をまとっていたが、その合間からひどくやせこけた、なかば透き通った体がみえた。目だけは憎悪で赤黒く燃えているようだった。
その "死霊" はぼろぼろに錆びた刀身の小剣を静かに抜き放った。
「・・・クゥ・カ・エセ」
洞窟内に響いたその声は確かに共通語ではあったが、ひどくしゃがれて聞き取りづらく、またおぞましいものであった。

死霊との戦い
この物語のクライマックスの敵としてルールブックから「幽鬼」を選びました。ステータスの数値的には比較的弱めにみえたからですが、「幽鬼」は闇の住人であり、敵対者に恐怖を与え、負傷を無効にする能力があります。
ホビットは「影」の脅威に抵抗がある(恐怖に打ち克つ可能性が高い)ため相性はよいのですが、そもそも凶悪な敵を選んでしまったものです。
ベッカにはこの時点ではわかりえない情報ですが、この「幽鬼」は文書の元の持ち主で、今はビルボが持っている文書を取り返したいと考え、だれかれ構わず"文書を盗んだ者"とみなして襲います。
出会い頭で不意を打たれようですが、ベッカが驚いている間、「幽鬼」の方もランタンの炎に気を取られ、"紳士的に"文書の返還を求めてベッカの反応を待ったため、このラウンドは攻防は発生しないものと考えました。第2ラウンドから1対1の本格的な戦闘の開始とします。
「幽鬼」には炎恐怖症という特性があり、ベッカはランタンを至近距離でかざしていることになるため毎ラウンドのはじめに憎悪点を1点失います。
憎悪点とは耐久力0以下になった際に消費することで耐久力を全回復してしまう凶悪な特性ですが、実質無効にできるのは大きい。はやくも憎悪点が3点まで減少したことになります。
しかし、良いことばかりではないですね。「幽鬼」は毎ラウンド、影点3による影への抵抗をベッカに強要し、失敗すると希望点(各種判定ボーナス)を使用できなくなるし、累積影点が希望点に達するとベッカは影に心を支配されて絶望し冒険は終わってしまいます。
第2ラウンドの影への抵抗は、難易度である心力14に対して希望点も使用して9+1+5=15でかろうじて成功。
最初の攻撃。希望点を消費。難易度18に対し、5+6+2+3+3=19。3ダメージに加え、6(成功度アイコン)がでているので、ここでは重撃を選択。追加3ダメージ。
私はこの突然の遭遇にほんの一瞬たじろんだが、すぐさま「幽鬼」の側頭部めがけて小剣を力いっぱい叩き込んだ。
すべての行いに鋭い目と心を忘れてはならん。
「危険なときはすぐに戻る」というゴーバドクとの約束は違えてしまうが、私は直感したのだ。「返せ」とは件の古文書ではないか。
いま目の前にいる恐ろしい敵が何者かはわからないが、この冒険の重要な鍵を握っているに違いない。ここで怯むわけにはいかないのだ。
渾身のダメージを与えたが、当然敵からの反撃もある。
ベッカの回避値17に対し、1+2+2+1、これはなんとか回避できました。
第3ラウンド。影への抵抗は今回も希望点を使います。
心力14に対し、8+6+6=20。完全にダイスに助けられています。
「幽鬼」はここでもランタンの炎により憎悪点を失い残り憎悪点2。
以降の戦闘は長くなったので省略。辛勝。
私は腕の傷の痛みも忘れて、くずおれた「幽鬼」の亡骸をあらためた。革ひもに結ばれた筒状の容器を首からかけていた。筒の蓋を開けるとあの鶯色の数枚の羊皮紙と鵞ペンだった。羊皮紙には何が書かれているのかわからなかったが、そのうち一枚は書きなぐったようにみえた。
ベッカは目的を達成したとみてゴーバドクに挨拶し(「幽鬼」との戦闘については触れずに)帰路につきます。以降は危険もないので省略し、ビルボに報告することになるでしょう。
エンディング
羊皮紙を受け取ったビルボは私の存在も忘れて読みふけり、おそらく解読に必要であろう資料をひっくり返しては時折ため息をついて、しまいにはパイプをふかしながら厳しい表情をうかべていた。
私はその間、椅子に腰かけてものも言わずじっとビルボの様子を見ていた。
しばらくしてビルボは不意に私の存在を思い出し、用意していたボフィンの壺煮込みで私をねぎらい、また私の冒険の一部始終を聞いてひどく申し訳なさそうにしていた。私を危険に巻き込むとは想定していなかったのだ。
ビルボによると、あの羊皮紙の最後の一枚、書きなぐられた文章は「配達人」の最後の手記だったという。おそらく「配達人」が「幽鬼」と化したのではないかとのことだった。
彼女は会議への書簡を届ける旅の途中で一頭の魔狼に二日間にわたって追われ、仲間を失いながらあの洞窟に逃げ込んだのだ。彼女は命がけで文書を守ろうとしたが、結局は魔狼によって命を奪われ、文書に心とらわれたまま影の世界に身を落としたのだろう。かくして、かの文書は会議に届くことはなかった。
ビルボはその残り2枚の文書については多くは触れなかった。私もその話題には深入りしなかった。訊いてはいけない気がしたのだ。
後になって考えると、ビルボがあの文書をどこまで読解できたかはわからないが、彼はあの忌まわしい指輪の秘密をあの文書ではじめて確信したのだと思う。ビルボはあの頃から疑い深く、人を避けるようになったのだから。
その数年のち、あのやさしく力強いゴーバドクが鬼籍に入り、私もまた微かな痛みとともに"おてんば"を卒業した。

レビュー
正確な分類はともかく、ソロジャーナリングシステムやゲームマスター不在システム(OracleシステムやGMエミュレータなどとも呼ばれる)は世界的にも現在とても注目を集めていて、DriveThruRPGでは『Mythic Game Master Emulator Second Edition』が長期にわたって売り上げ上位にランクインし続けているなど、こういったソロやGM不在の遊び方、キーワードを使って物語を連想・創造していくプレイスタイルは今後も発展していく可能性がうかがえます。
『Strider Mode』は『ひとつの指輪:指輪物語TRPG』に特化したロア・マスター不在システムですが、この手のシステムの抽象化された"ある種のとっつきにくさ"に対し、”ある程度具体的なクエスト”という形で提供することで遊び手に受け入れやすくなるよう工夫していると言えます。
また、主ストーリーであるロード・オブ・ザ・リングやホビットによって、登場人物や舞台になじみがあったりイメージがわきやすいというのもこのシステムの大きな特徴であり、原作ファンやLotRファンにとってはソロジャーナリングの入門としても(未邦訳ではありますが)、うってつけのシステムとしてお勧めできそうです。
本記事のプレイでは『Strider Mode』は、冒頭のほぼイントロダクションでしか使用せず、展開を「知っている」状態でプレイしましたが、そこに至るまでに、キャラクターや世界設定資料、LotRの知識、キーワードで想像は膨らみ、物語はごくシンプルながら、その構成や整合性を考えていく過程がとても楽しめました。ゴーバドクの死没年まで調べる機会はそうはないでしょう。
このシステムには、ほかにも表類がまだまだ多数あり、当然、中盤や終盤のみならず伏線などでも使用して、遊んでいる本人も先が読めない形で遊ぶこともできます。また、キャンペーンや多数のキャラクターたちが織り成す叙事詩として練り上げたり、ロア・マスター不在で多人数プレイ、ロア・マスターの立場でオリジナル・シナリオのインスピレーションを得ることもできるなど、遊び方の応用範囲もとても広いものです。
原著PDF版は5ドルを下回る価格ですし、機会があればぜひ試してみてください。プレイした感想など聞かせていただけるととても嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
