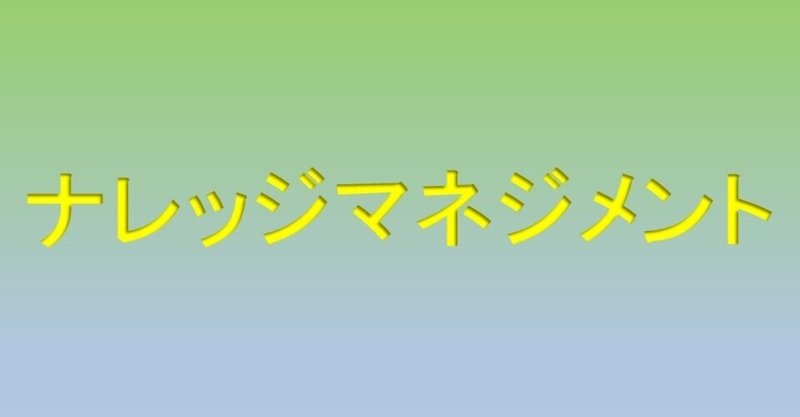
ナレッジマネジメントとは
先に開かれた経済産業ビジネススクール「二水会」第11回(2021年7月14⽇開催)は、「野中郁次郎ナレッジマネジメントの進化系『知の経営』と?」⇒知識を知恵に、知恵を知心に昇華させ利活用できるか?というテーマで、ナレッジマネジメントと「知の経営」について、深掘りされました。
ボルドリッジにも関係の深い概念でありお伝えしたいことは多くあるのですが、まず、そもそもナレッジマネジメントとは何かというとから話は始まりました。
ナレッジマネジメントの定義をいくつか見ておきます。
1)APQCの定義:
“Knowledge Management is the broad process of locating, organizing, transferring, and using the information and within an organization.”
ナレッジマネジメントとは、組織内で情報を検索、整理、移転、活用するための幅広いプロセスです。
2)アーサーアンダーセン、スティーブ・M・フォロニックの定義:
ナレッジ・マネジメントとは、組織における人々が、ビジネスの目的を達成するために、知識を修得、共有、応用していくことを可能にする手法。
3)髙梨智弘の定義:
ナレッジ・マネジメントとは、組織の目的・目標を達成するために、価値を創造する知識を発見し、理解し、共有し、活用する体系的なアプローチであり、適切な時期に適切な人が、知識をスムーズに移転し、活用できるようにする効果的な仕組みを構築し運営すること。
従来の欧米型ナレッジマネジメントの考え方は、情報の活用という意味で、形式知に注目し、知識の収集・蓄積・精製・分配・利用というナレッジ・ベース(ナレッジ・データベースとも言う)システム導入という手段をとってきました。
一方で、野中郁次郎ナレッジマネジメントは、知識創造が中心のテーマです。
ナレッジマネジメントの定義の前に、「知識」とは何か、という点でも、中身が違ってきます。
ボルドリッジがどこに位置するのか、これらに沿って、確認したいと思います。
例えば、ボルドリッジでは暗黙知も対象の一つとして捉えており、「従来の欧米型」からは進歩しています。
★★
経済産業ビジネススクール「二水会」の案内は、例えばこちら(経済産業新報社ウェブサイト)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
