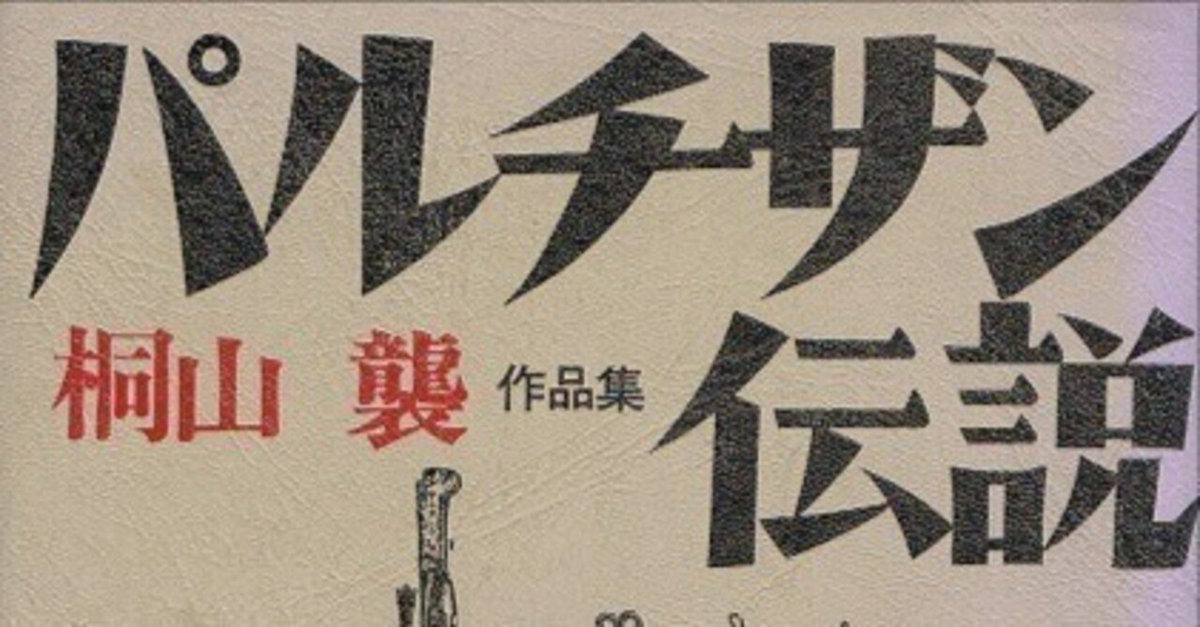
読書メモ・桐山襲『パルチザン伝説』(河出書房新社、2017年、初出1983年)
桐山襲(きりやまかさね)『パルチザン伝説』(1983年)は、数奇な運命をたどった小説である。
ある人物の、兄への手紙から始まるこの小説は、父とその息子の二代にわたる「パルチザン」の物語である。
この小説は、その冒頭にさる高貴な人物の暗殺計画について触れているのだが、そのことが発売当時、週刊誌の格好のネタとして記事にされ、それがきっかけで著者は右翼の攻撃に遭い、この小説はたちまち発禁となった。
マスコミが煽動することで、かえって言論が暴力的に弾圧されるという構造が、すでに40年以上前からこの国には存在していたのだ。
この物語は、前半で主人公や兄の反体制活動が、そして後半では父親の反体制活動の様子が、書簡や手記という形で書き進められていく。
この主人公の父親は、アジア太平洋戦争のとき、戦争を早く終結させるために、手製の爆弾を東京で爆発させるなどの、暴力的な行為を繰り返す。そして終戦の日の1945年8月15日に、ついに皇居に忍び込んで爆弾を爆破させようと試みる。
これだけ読むと、この小説はたんなる反体制小説のようにも思えるが、実際によく読めば、この国における反体制活動の限界を冷静に描いていることがわかる。
小説の後半は、Sという人物による戦時中の手記という形で、主人公の父「穂積一作」の行ったことが語られていくのだが、私が興味をひいたのはそこではない。
戦局が日に日に厳しくなっていく中、ある男が「戦争だから家が焼かれるのは仕方ないが工場が狙われるのが悔しい、それに宮城(きゅうじょう)が心配だ」とつぶやいたことに対して、Sが、
「なるほど、この国のひとびとはかつてない空爆のなかでそういうふうに考えているのか――動悸の細波が残っている胸を押さえながら、私は頭のどこかが痺れるのを感じていた。まだ焼かれ足りないのか、まだ殺され足りないのか、いや、全部焼かれ、全部殺されても、そう思いつづけているのか」
と気づき、次のように語る場面である。
「確かに私の周囲で生きているひとびとは、ただならぬ生活の混乱や肉親の死に直面しているにもかかわらず、未だ敗け足りていないように見えた。民間人だけではない、軍人もまた、真剣に降伏を考えているのは上層の極めて一部であり、それ以外は児戯に類する本土決戦の〝準備〟に我を忘れている状態だった。なるほど民は自らの水準に応じてその支配者を持つものだとするならば、知は力であるという段階を通過せぬまま権威と屈従の感覚だけは鋭敏にさせてきたこの国の民の水準に、軍部のごろつきたちはまことに適合しているのかも知れなかった」
「民は自らの水準に応じてその支配者を持つものだとするならば、知は力であるという段階を通過せぬまま権威と屈従の感覚だけは鋭敏にさせてきたこの国の民の水準に、軍部のごろつきたちはまことに適合しているのかも知れなかった」という部分の「軍部」を「政治家」に置き換えれば、まさにいまこの国が抱えている問題にも通ずる。
いまから40年前に書かれたこの小説を読むたびに、「何も変わってないじゃないか」と思う。
なお桐山襲は、1992年に42歳の若さで亡くなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
