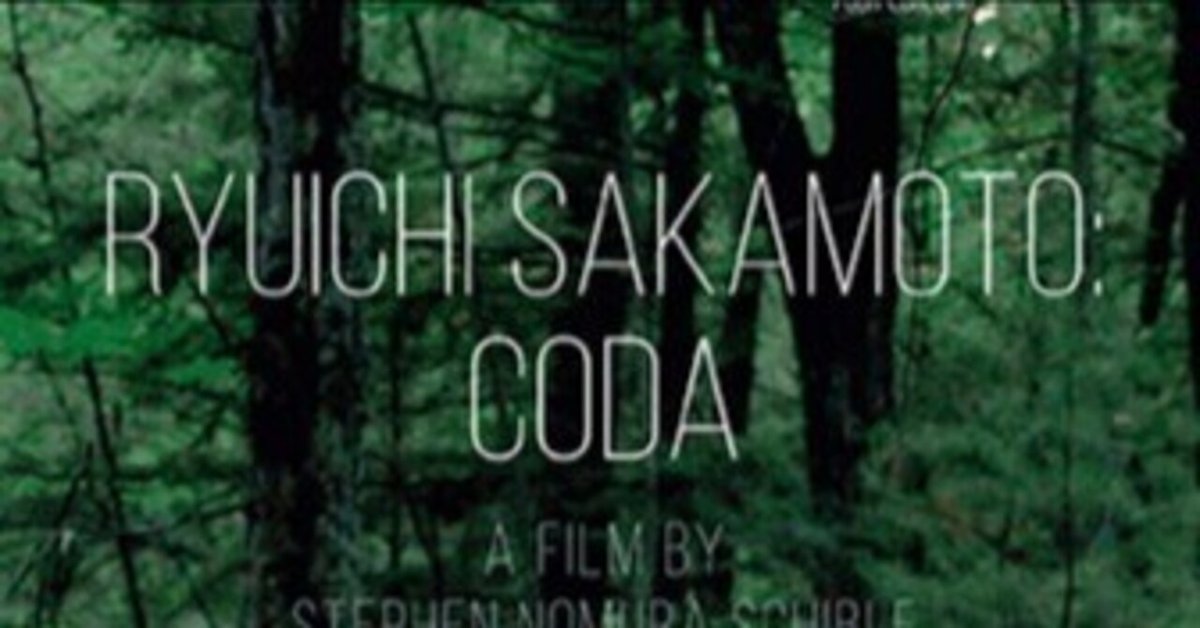
いつか観た映画・「Ryuichi Sakamoto:CODA」(2017年)
2014年3月28日は、坂本龍一さん(教授)の1周忌である。
教授について書きたいと思いながらも、想いが強すぎて、なかなか書けないでいる。さしあたり、以前に観た映画について書こうと思う。
東日本大震災以後の坂本龍一さんの音楽と人生に迫ったドキュメンタリー映画「CODA」(2017年、監督:スティーブン・ノムラ・シブル)は、震災や反原発運動などと関わって取り上げられることが多いが、私は、大病を克服した教授の「老い」をテーマにしたドキュメンタリー映画として鑑賞した。
映画の中では、若い頃、それこそ、YMOのワールドツアーの頃や、「戦メリ」の頃の映像が登場するが、若い頃の「戦メリ」のテンポは、そのときの教授がピアノで奏でる「戦メリ」とはまるで違う。明らかにテンポが落ちているのである。
ピアノを弾いている後ろ姿に、老境にさしかかった坂本龍一の、ある種の境地、といったようなものが感じられる、と観た当時は思ったのだが、後に最後のコンサートをしたときのインタビューで、「できるだけ音の響きを噛みしめたいのでゆっくりと弾いている」と言っていた。一音一音噛みしめるように弾いていたのだ。
だからそれは決して悲壮感が漂うものではなく、むしろ老いるとはどういうことか、老いてどう生きるべきかについて、考えさせられる。
教授の音楽は、この世界のあらゆるところに存在している音を音楽にしている、と私は思ってきた。…我ながらなかなかわかりにくい表現だ。
夏目漱石は『夢十夜』の中で、
「あれは眉や鼻を鑿で作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋っているのを、鑿と槌の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずはない」
と書いている。名工が仏様を木のなかから「掘り出す」ように、教授の音楽も、この世界に散らばっている音を拾いあげているのである。
…やはりわかりにくいか。
映画の中で、教授はこんなエピソードを紹介している。
ベルナルド・ベルトリッチ監督の映画「シェルタリングスカイ」(日本公開1991年)の劇伴の音楽を、いままさにレコーディングしようとしていたときのこと。
40人ほどのオーケストラを前にリハーサルをしていたら、ベルトリッチ監督が、
「そのテーマ曲、気に入らないから、今すぐ書き直してくれ」
という。
「ちょっと待ってよ。これからレコーディングをやるんだよ」
いくら何でもそれは無理だよ、と教授が言うと、
「あ、そう。でもエンニオ・モリコーネはやってくれたよ」
と返され、「モリコーネがやったんだったら俺も」と、30分ほどでテーマ曲を全然違うものに書き直し、レコーディングしたという。
「それがまた、いい曲に仕上がったんだ」
ここまでが、この映画で語っていたこと。この話は、以前にも聞いたことがある。
この話には、後日談があることを思い出した。1994年に教授のソロアルバム「スイートリベンジ」が発売された頃に、教授が語っていたことである。
最初に書いた「シェルタリングスカイ」のテーマ曲が没になったことがあまりに悔しくて、自分のソロアルバムに収録することにした。それが「スイートリベンジ」という曲である。タイトルを「スイートリベンジ」としたのは、ベルナルド・ベルトリッチ監督に対するささやかな復讐の意味を込めたからだ、と語っていたことを思い出したのである。
で、この「スイートリベンジ」も、かなりいい曲なのだが、これを没にすると決断したベルトリッチ監督も、それをまったく違う曲に書き換えてベルトリッチ監督を満足させた教授も、なんかすげープロ意識だよなあと、そのときに思ったのだった。
だんだん思い出してきた。
アルバム「スイートリベンジ」の発売に合わせておこなわれた武道館のコンサートに行った。1994年だから、まだ20代半ばくらいの頃のことである。
そのとき、高野寛さんがゲスト出演していて、「夢の中で会えるでしょう」を歌い、会場はえらく盛り上がった。そりゃそうだ、「スイートリベンジ」に収録されている楽曲の多くは、インストゥルメンタルなのだから。
高野寛さんが歌い終わったあと、教授が、
「僕の曲よりも盛り上がってる…」
とぼやいていたことを思い出した。
教授のソロコンサートに行ったのは、後にも先にもその1度だけである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
