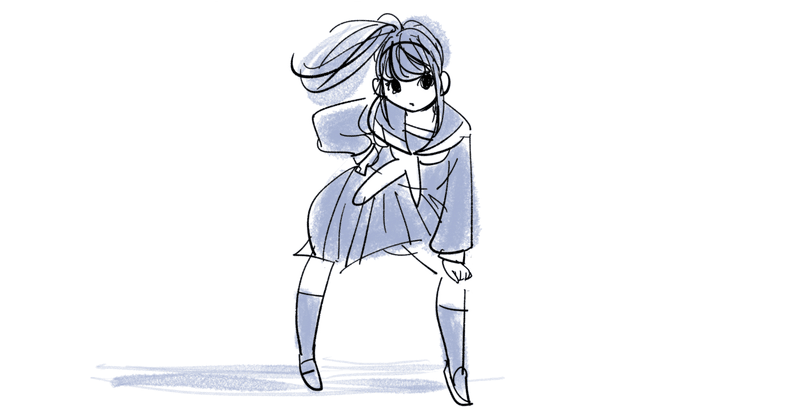
#スベり高等学校
わたしは、今、バターチキンカレーを食べている。
きっと皆様、「だからなんやねん」、と思っていらっしゃるでしょう。うふふ。物語に関係ないことを書いてごめんなさい。
青色の素敵な方が、スベる高等学校について、考えておられた。あまり書く気がなかったけど、あの方が書くのなら、と、わたしも考えることにしてみた。ちなみに、これも物語に関係のない話です。きっと、皆様、「だから、なにがいいたいねん」って思っていらっしゃることでしょう。
うるヘい! 関係ないこと書いちゃいけないのかよ、コンにゃろう!
以上、情緒不安定気味の鰯田でした。
本文です🫠↓
その平面は、永遠に続いていた。
果てなど、誰も見たことがなかった。
そもそも、ただ、滑り続ける彼にとって、この世界を形作る平面に、なんの意味があるのかも、まして、その平面に〝果て〟があるか否かなど、関係がなかった。
ただ、滑り続けるのだ。
彼は、気が付いたときから、ずっと、滑り続けていた。
いつから滑り始めたのか、なぜ滑り続けるのか、彼は、知らない。
知りたいとも思わなかった。
ただ、果てのない平面を、彼は、真っ直ぐに滑り続けるのだ。
滑り続けていると、ごく稀に、同種の、滑る高等学校に出会う事があった。
彼らも、彼と同様に、滑り続けていたのだ。
互いに真っ直ぐ滑っているため、出会うのは、いつも、すれ違う一瞬だけだった。
「よお。どこからきた」
「向こうさ」
「オレは―――
向こうからきたんだ、と言葉を終えることなく、高等学校は口を閉じた。
相手の高等学校は、もう、声の届かないくらい遠くに滑り去っていたからだ。
幾度も、幾度も、一瞬のすれ違いを繰り返す、高等学校にとって、こんなことは当たり前のことだった。
出会い、すれ違い、通り過ぎる。
これは、果てしない平面で滑り続ける高等学校たちにとって、ごく当たり前のことだった。
高等学校には、昔、長く一緒に滑り続けた〝スベ友〟というべき友がいた。
スベ友は、同種の、滑る高等学校だった。
彼らは、たまたま似たような方向から、似たような方角へ滑っていたため、互いに長く滑り合うこととなった。
「オレは、向こうから来た」
「オレもさ」
「どこに向かう?」
「向こうさ」
「オレもだ」
「そうだな」
「一緒だな」
「しばらくは、な」
彼らは、自分が、どのくらい長い時間滑り続けていたのかを語り合った。
だが、それは、互いに無意味であった。
いずれすれ違う相手に、心の底は、分かち合えないのだ。
ある時、一方の高等学校が言った。
「なぜ、オレたちは、滑り合う」
それを聞いた高等学校は、衝撃を受けた。
彼らは、気付いたときから滑り続けていた。
滑ることに、疑問など、なかったのだ。
高等学校は、言った。
「オレにも、分からんさ」
そう言って、高等学校は、スベ友を見た。
高等学校と、スベ友の距離は、少しづつ、離れ始めていた。
〝すれ違う、か〟
高等学校は、自分の胸に、何かが芽生えるのを感じた。
高等学校は、言った。
「なぜ滑り合うのか、オレには分からん。いつから、滑り始めたのかも、オレには、分からん。この滑らかな平面が、どこまで続いているのかも。滑り、出会い、別れる、オレたち高等学校は、一体、何者なのか。オレには全く分からん。分からんでもいいとも思う」
高等学校は、スベ友を見た。
互いの距離が、遠くなっていた。
すれ違いが、大きくなっている。
高等学校は、続けた。
「オレは、滑り続けて、良かったと思った事がある。それは、貴様と、出会えたことだ。貴様は、初め、生意気だった。自分のほうが校舎が大きいだの、視聴覚室を3つ揃えているだのと、先輩風を吹かしていた。だが、貴様の柱が折れたとき、オレは言った。〝死ぬな、滑り続けろ〟と。オレは、貴様の校舎の半分を切り取った。貴様は、ブチブチ文句を言っていたが、身軽になった分、オレの滑る速さに寄り添えもした」
スベ友は、遠くなる。
まだ、声は、届くはずだ。
高等学校は、言った。
「別れが辛いのは、一緒にいた時間が長かったせいだろう。オレは、貴様のことを、忘れない。オレは、常々、思っていた。貴様を、なにか、呼称するための単語があればいいと」
スベ友は、もう小さくなっていた。
高等学校は、力の限り、大きな声で、スベ友を呼んだ。
―――アキラ!
そうだ、貴様の名は、アキラだ!
アキラ!
ありがとう!
アキラに会えて、本当に良かった!
どうか元気で!
アキラ!
アキラは、手を挙げた。
高等学校の最後の声が届いたんだ。
そうして、高等学校は、また、独りで滑り始めた。
高等学校は、思った。
次は、もう、誰とも会うことはないだろう。
滑る時間が長くなればなるほど、高等学校同士を隔てる距離は、遠くなる。
高等学校は、思った。
最後に会ったのがアキラで良かった、と。
高等学校は、目を閉じた。
どうせ、もう、誰とも会わないんだ。
高等学校は、果てしない平面をぐんぐん滑っていった。
平面は、果てがなかった。
高等学校は、スピードを増していった。
永遠とも言えるほどの時間を滑って、ついに高等学校は、目を開けた。
あたりには、滑る高等学校の残骸がたくさん転がっていた。
高等学校も、もう、滑ってはいなかった。
彼は、風に尋ねた。
「ここは、どこだ」
風は、答えた。
〝果てだ〟
「何の果てだ」
風は、答えた。
〝有限なるもの全ての、果てだ〟
高等学校は、言った。
「オレをより先に、ここに辿り着いた高等学校はあるのか」
風は、指さした。
そこには、朽ち果てたアキラの校舎があった。
高等学校は、自分の体が朽ち始めていることに気が付いた。
「オレは、どうなる?」
風は、言った。
〝どうもこうもないさ。ただ、止まったんだ。全てがね〟
「アキラは」
風は、笑った。
彼は、崩れていく校舎を感じながら、自分が、滑り続けることに疲れていたことに、やっと気が付いた。
彼は、彼の意識が、バラバラと、音を立てるのを聞いた。
風が、強く、吹き、世界を形作る滑らかな平面が、波打ち始めた。
平面が、収縮を始めたのだ。
新たな、世界が、生まれる―――
「そんな夢を、オレは見たんだ」
そういうオレの前で、高校からの付き合いである[アキラ]が、ふくれっ面で、そっぽを向いていた。
ここは、アキラの親父が経営する喫茶店だ。
「なんで、わたしが、高等学校になって、あんたと滑り合うのよ。わたし、一度も、滑ったことないんだけど」
アキラは、すごく怒っていた。
「まあまあ、アキラちゃん」
そう言って、親父さんが、アキラにパフェを差し出した。親父さんは、かわいい娘に、頭が上がらない。
アキラは言った。
「しっかし、あんたも懲りないね。こんなに滑りまくって、就職活動、いつまでする気?」
アキラは、オレの不採用通知の山を呆れるように眺めた。
そうだ、こんな現実だから、変な夢を、見たんだ。
アキラになじられる情けないオレはため息交じりに言った。
「―――どこかに、すぐ就職できるところ、ないのかなあ」
オレが、頭を抱えるふりをしていると、「―――すぐそこにあるじゃん」、とアキラの小声が聞こえた。顔を上げると、アキラは、そっぽを向いてパフェを突っついていた。
「ええ?」
「すぐそこにあるっていってんの。」
「どこだよ。」
「そこって言ってんじゃん。」
「だから、どこに。」
アキラは、机を叩いて言った。
「あんた、馬鹿? こんだけ言ってもわかんねえか。だからどこにも採用されねえんだよ!」
アキラの言葉には、流石に傷ついた。項垂れていると、「―――アキラちゃんはさ、あんたに、うちで働いてほしいって言ってんのさ」と、アキラの親父さんがオレにコーヒーを差し出しながら、そういった。
「滑り続けるてめぇを、わたしの家が雇ってやろうって言ってんだよ。ありがたく思え」
と、相変わらず、ふくれっ面のアキラ。
親父さんは言った。
「ついでに、アキラの婿に、どうかな?」
ええ!?
「アキラ、あんたのこと、気に入ってるみたいだし。」
まじか。
いや、それはとても嬉しいんだけど、親父さん、アキラの前で、そんなこと言っていいの?
案の定、真っ赤になったアキラは、いちごチョコパフェの入ったグラスを親父さんに向かって振りかぶっていた。
「親父! ブッコロス!」って言いながら。
その様子を見た地元の客も、新しいスタッフと跡継ぎ問題が解消?されて手を叩いて喜んでいた。
良かったなぁアキラちゃん。
親父、結婚式はいつだ?
アキラちゃん、この兄ちゃんのこといっつも話してたもんなぁ。
兄ちゃん、早く孫を俺らにも見せとくれ。
グラスが飛び散る音を聞きながら、こんなに賑やかな喫茶店なら、きっと繁盛するだろうな、とオレは思った。
ここは、失くしちゃいけない場所だ。
オレは、ポケットに隠してあった、一通の採用通知を破り捨てた。
[おわり]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
