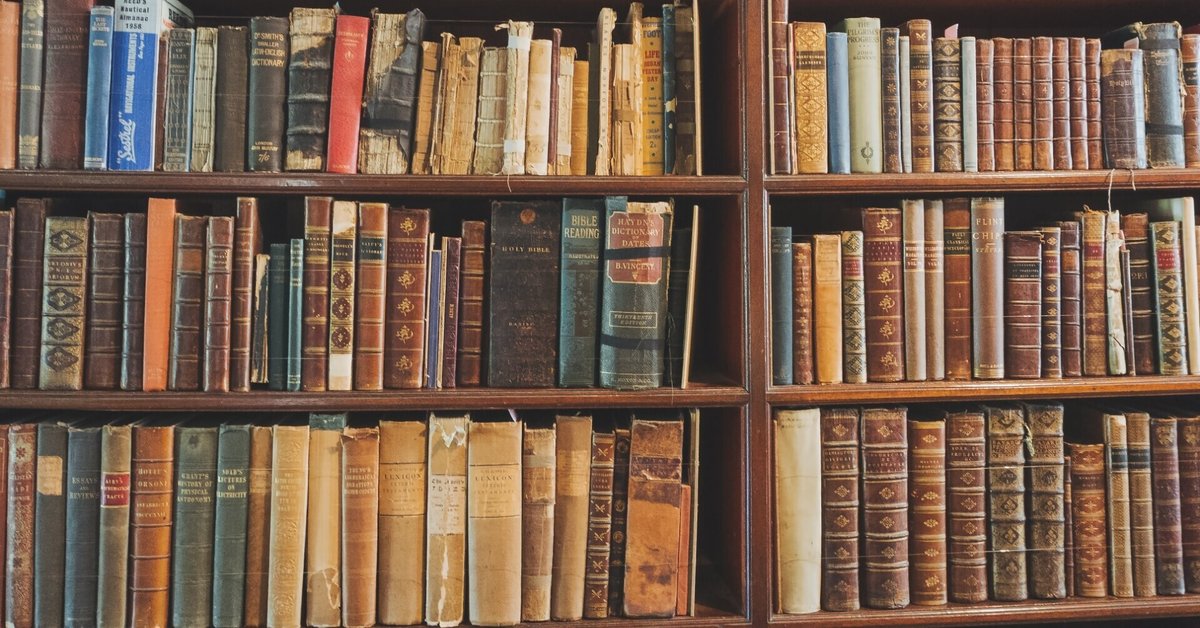
図書館史概説①~「書物」と「図書館」とは?~
はじめに
今回から、シリーズ連載(本記事含め3記事程)と言う形で「図書館史」についてまとめようかなと思います。
というのも、せっかくnote使い始めたんだし、少しくらいは真面目なものも書いてみようかなという気分で。
と、言いましても、この連載(予定)記事は過去7年ほど昔、学生時代にちょろっと卒論関係で取り扱い文書化したものを再編集と言う形でお届けしますので少し情報が古かったり、ちょっと文書が稚拙だったりするかもしれませんがそこはまあ、ご愛嬌と言うことで。
ということで第1回目の記事はそもそも「書物」とは、「図書館」とは何ぞやというところからお話していきたいと思います。
1 「書物/本」とは
まず、「図書館」について述べる前に「図書館」が収集・保管の対象とする「書物」ないしは「本」とそれらに記された文字がどのように記録されていたかについて簡単に概説、定義したい。 そもそも、「書物/本」とは何なのか。『広辞苑 第五版』は、「文字や図画などを書き、または印刷して一冊に綴じたもの」としており、「本。書籍。図書。典籍。」を同義語として挙げている。また『世界大百科事典』は「本は書物、図書とも呼ばれ、最も歴史が長い情報伝達の媒体である。形態的には、自然のままの(木の葉や竹など)、または加工した物質的材料(羊の皮、紙)を選び、その上へ文字や図を筆写または印刷したものを有機的に配列し、保存・運搬に適するよう、その材料の性質が要求する方法でひとまとめにしたものとしている。さらに、樺山紘一編『図説 本の歴史』によると、「本の定義のうちにふくみうるという点」が3つあるという。
①「音声ではなく視覚によって伝達される情報の集積」
視覚、すなわち文字と図像からなる情報・表現である。図像ばかりによって成るものを本とよべるのかという批判などもあるだろうが、古来より情報伝達においては文字と同時に図像も多用され、また文字もその発明・変化を辿るなかで表意的記号、ある種の図像的要素ももちえていた。そこを鑑みるに、図像が占める割合の多いものも「書物/本」という定義に含むことも可能であろう。
②「社会的な情報伝達の手段」
つまり、本とは他者とのコミュニケーション、情報伝達を媒介する存在であるという。しかし、そもそも他者に開陳しえない書物というものもあるであろう。それについては、秘された本・文字記録というものは確かに存在し、作成された時代においては情報の公開がなされないこともあるが、後世に至って発見され資料として調査・研究がなされていることもある。まさにその時代の人びとと、時代を超えてのコミュニケーション・情報伝達が行われているといえるのではないだろうか。
③「情報を運搬したり、保存したりするための手段」
そしてそれは、「モノ」として実体を持って存在しているもののみならず、昨今話題にもなり普及や導入が進められている「電子書籍」にもいえることであろう。
以上のことより、本記事においては「書物」と「本」、またそれに類する(とされる)ものを、「文字・図像の視覚的記録媒体」であり、「情報伝達を媒介する手段」、「情報の運搬・保存のためのモノ」という定義のもとに一括して取り扱うこととする。
2 文字と記録メディア
では、書物に記録される情報とはどのようなものが、どのように用いられていたのか、「文字」や「記録媒体」などの歴史を概観したい。
人類の歴史の中で「ことば」は情報伝達の手段として早期から用いられた。そして、人類の構築した社会の規模が大きくなり、複雑化するなかで口誦での情報交換に不便が生まれてくる。そこで、人類はことばを記号として何らかの媒体に記録することとした。それらははじめ、厳密には文字体系と分類しえないような図像的な簡略記号や南米のペルーなどで用いられた結縄(キープ)といったものであった。そして、それらが文字として発展していくことで、人びとの情報伝達の手段として視覚的記録媒体が出現、発達していくのである。
古代文明のひとつ、ティグリス川・ユーフラテス川流域でに発生したメソポタミア文明、ウル・ウルクなどの都市をシュメール人たちが築き繁栄していた。そこでは「楔形文字」とよばれる表音文字が用いられた。これらははじめ、葦の先を尖らせた尖筆と呼ばれるペンで「粘土板」に記録された。粘土板は窯焼きすることで長期間保存できるようになり、長期保存しない場合には粘土に刻まれた文字を消して再利用することも可能であった。また、粘土板以外にも石柱・石版などに「碑文」として文字記録が残されてもいた。特に有名なのはハンムラビ法典であろう。
ナイル川流域の肥沃な土壌に栄えたエジプト文明では、「ヒエログリフ(聖刻文字)」とよばれる文字が神殿の石壁や石柱などに記され、これらは碑文などに用いられる正式、神聖な文字とされた。他に「ヒエラティック(神官文字)」という文字があるが、これはヒエログリフをパピルスに書き写すために使用された文字といわれる。いわば、ヒエログリフの筆記体・速記体であろう。これも宗教的、神聖な文字であり、対して「デモティック(民衆文字)」という文字はヒエラティックをさらに簡略化し生まれたとされる。これは主に世俗的な文章、文字記録として残されているものが多い。先述の「パピルス」とは、エジプトに多く生息していた植物であり、それらの茎を短冊状に切り井桁の形状で組み合わせ加工し作られた「パピルス紙」を指す。パピルス papyrusは英語のpaperの語源であることでも有名である。これは後に、粘土板など重くかさばるものの代わりに、記録メディアとして長く用いられることとなる。特徴としてパピルス紙は軽く、また継ぎ接ぎすることで記録する情報量を増やすことが可能であった反面、脆く破れやすかったこともあり「巻子本」、いわゆる巻物(スクロール)の形で使用、保存された。
また、中国や日本などでは竹や木を「簡」(竹簡/木簡)として用いてそれらに文字を記録していた。「簡」の特徴として、表面を削り取ることで書き直しなど修正や再利用が可能であり、またその素材、形状から比較的安価に用いることが可能であった。また、これらもパピルス紙同様に紐などで繋ぎ合わせ巻子本の形態で保管された。これらの一まとまりを「一冊」とし、象形文字の「冊」がうまれたという。
その他にも、古代中国では「甲骨文字」が獣骨や亀の甲羅などに刻まれたり、インダス文明では「インダス式印章」とよばれる石製、金属製の印章に「インダス文字」や動物の文様などが彫り込まれたりしている。そして、時代が進むと「パーチメント/ヴェラム」とよばれる、動物(主に羊や山羊・子牛)の皮を使った記録メディア(いわゆる「羊皮紙」)が紀元前2世紀頃に書写素材として出現する。表面が滑らかで光沢があり、耐久性にすぐれ、また両面を使用可能であった。これらは3~4世紀にかけてパピルスに代わって用いられるようになり、それと同時に書物の形態も「巻子本」から「冊子体」へと変化していった。今日の一般的にイメージされる「書物/本」の形態は長い年月、その姿に大きな変化はなかったのである。
そして、「書物/本」にかかわる記録メディアとして決して欠かすことができず、また今日では書物のように冊子体として加工されずとも視覚情報を記録する手段として活躍する素材が「紙」である。
紙の歴史は古く、現存する最古の紙は中国で発見された「放馬灘紙(ほうばたんし)」であり紀元前150年頃のものである。そして西暦105年、蔡倫により製紙法が完成され、その技術が世界各地へ伝播する。日本へは7世紀に高句麗から渡来した僧侶、曇徴によりもたらされたとされており、また日本に現存する最古の紙は正倉院に保管された702年の美濃・筑前・豊前の戸籍用紙である。そして、751年、タラス河畔の戦いを通じてイスラム世界へ伝播し、ギリシア、ペルシア、インド、唐の文献がアラビア語に翻訳され、イスラム世界における図書館の発展に大きく貢献した。それから約400年遅れて、12世紀にヨーロッパへと製紙技術が伝来。しかし15世紀にグーテンベルクの活版印刷技術が誕生し普及するまで、羊皮紙は聖書の写本を中心として用いられていた。その後は、大量印刷の需要が増え、高価で貴重なパーチメント・ヴェラムに代わり、安価な紙の需要が増大した。
このように、我々人類は古来より様々な素材を記録メディアとして用いてきた。そしてこれら記録メディアの変遷は、記録される情報の多様化、メディアそのものの形状、そして人類の文化・文明の変化をもたらしてきた。特に「紙」は製紙技術の普及以来、その後のあらゆる時代、地域においていまなお廃れずに記録メディアの筆頭として存在している。まさに「紙」が我々の歴史の多くを記録し、生み出してきた存在とよべるのではないだろうか。そしてその代表となるのが「書物/本」である。
しかし、現在「電子書籍」の登場により「書物/本」のありようが大きく変化しようとしている。また、本だけでなく、社会が高度な情報化、電子化を需要するなかで記録メディアの扱いもまた変化し、「図書館」という存在もまた波乱のなかに投げ出されているのではないだろうか。
3「図書館」とはー「図書館」を構成するものー
「図書館」と一口にいっても、はたしていかなる定義のもとで運営され、また利用されているのか。図書館が図書館たりうるには、いったいどのような構成要素が必要となるのか。「図書館」について考察する上では欠かすことのできない問題である。
ヨリス・フォルシュティウスは『図書館史要説』において「図書館の文化的使命」は「著作物の収集保存、『人間精神の宝の部屋』となること。」、また「著作物を整理し、開陳すること。」と述べている。また、『ALA図書館情報学辞典』によるとALA(American Library Association アメリカ図書館協会)は「図書館とはサービス対象に物的、書誌的、及び知的なニーズに関するサービスとプログラムを提供できるように訓練されたスタッフを持つ組織」と定義している。また、日本において図書館の定義としてよく用いられるのは、「図書館法」の第2条の条文である。「図書館とは、図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」となっている。なお、後に詳しく述べるが、日本における「図書館法」は「公共図書館(public library)」を対象とするため、図書館全般の総括的な定義としては若干の考証が必要であろう。
さらに、上記ALAの定義や図書館法条文、その他の文献を踏まえて、高山正也・岸田和明編『図書館概論』では
「図書館とは、情報を何らかの媒体に記録した資料を収集し、整理し蓄積して随時、その記録された情報を利用に供することで、人々の精神的・知的な情報要求の充足を実現するために存在する社会的な制度」
であるとしている
以上「図書館」とは何なのかという問いに対する回答を4つ挙げたが、これらからいかなるものを図書館とよぶにふさわしいかということが導き出されるのではないか。
まず、「図書館」とは第一にその名のとおり図書、すなわち書物を集積する場所である。そしてそれらは利用者に対して開放されておく必要がある。そして書物はただ集められるだけではなく、十全な保存環境の中で、一定の規則に従い整理されておく必要がある。またそれらを管理し、利用者のニーズに応じて最適なサービスを提供する、図書館に精通した知識や技能を持つスタッフが必要不可欠だ。つまり、図書館の定義かつ構成要素となりうるのは「モノ」、すなわち集積された「書物」、情報メディアであり、それらを保存・管理しうるための「ハコ」となる「施設・設備」である。そして「ハコ」を活用しその中で「モノ」を管理し、利用者のニーズに対応する専門家たる「職員」、すなわち「ヒト」が重要である。
「モノ・ハコ・ヒト」の3つの要素が適切に機能していることが図書館の条件であり、社会に対して図書館がもちうる意義であるといえるのではないだろうか。
以上を集約すれば、「図書館」とは「情報の記録メディアを集積・保存・整理・管理し、それらの成果を利用者に提供するための専門家を有する施設、かつそれらが機能しうる制度」であるといえよう。しかし、これらはあくまで今日における図書館の機能・制度を定義したものである。
また、ここで注目したいのは「利用者」もまた構成要素である「ヒト」足りうるのではないかということである。いくら優れた蔵書があり、施設や設備が整っていようと、また専門の職員が優秀であろうと、それらを利用する人びとがいないのであれば何の役目も担うことはない。図書館としての価値、意義を果たすことはできないからである。
これについても『図書館概論』では
すなわち「蔵書・施設・職員」が揃って初めて、図書館という制度・組織が成立し、その使命(mission)を実現するための図書館サービスというアウトプットを産出することが可能となる。……図書館の機能として図書館サービスの産出が意味をもつにはその「利用者(user)」の存在が不可欠である。図書館の構成要素である利用者が……図書館サービスを要求することで、……情報提供サービスが社会的意味を有することになる。
としている。
4 図書館の機能とサービスの形
では、今日における図書館とはその利用者に対してどのような機能をもち、それをもとにどのようなサービス提供しているのだろうか。ここでは先に述べた図書館の定義をより確かなものとするため、図書館の機能並びにサービスについて述べたい。
フォルシュティウスは「図書館の文化的使命」について述べたうえで、それらによって図書館は「すべての国の価値ある図書をあらゆる立場の読者に読めるようにしておく」機能があるという。つまり、資料・情報の提供である。また『図書・図書館史』では「視点の異なった情報・知識を集積・保存し、利用に供する」機能を持ちうるとしている。
そして、『図書館概論』においてはこれらをより具体的に整理・考察し、様々な形態をとる図書館機能・サービスを大きく5つに分類している。
①情報管理機能
収集された情報群を利用者に提供すると共に、蓄積・保存することであり、目録作成や分類番号の付与などによって組織化すること
②教育機能
学校教育や社会教育、生涯学習の場において生徒や参加者を物的、また情報的に支援することである。これは図書館法の理念でもある、「教育施設としての図書館」を表しているといえる
③コミュニケーション機能
収集した情報を利用者に提供する中で、情報の生産者(送信者)と情報の利用者(受信者)との間の情報伝達を仲介する機能(レファレンス、或いはおすすめの書籍の紹介などに相当する)
④組織的記憶機能
情報や資料を蓄積・保存することによって、人類の知識や経験・思想を組織的に記憶し次代へと伝える機能
(これは特にフォルシュティウスのいう「図書館の文化的使命」における「第一に著作物の収集保存にある、すなわち継承の糸を決してとぎれないようにしておく」ことと一致する。)
⑤調査・研究機能
これは先述の4つの諸機能が効果的かつ効率的に実現されるように、調査・研究を行う機能
すなわち、「資料や情報を集積、管理、または提供」し、「人類の学問研究や学習活動を補助」すること、さらにはそうすることで「新たに生み出され、得られた情報を公開」すること、これらが図書館の機能であるといえ、そこにはもちろん利用者のニーズに応えるという前提がある。
そして、これらの諸機能を遂行し、またそれらを基盤とするかたちで図書館は利用者に対してサービス提供を行う。まず利用者は、所蔵する資料を「閲覧」することができ、必要に応じて、図書館は個人または組織・機関などの団体に対して「貸出」を行うことができる。特に「貸出」は図書館の基本的なサービスであり、利用者の多くがこのサービスを受けることを目的としているといっても過言ではないだろう。最近では多くの都道府県立図書館や市区町村立図書館が相互に協力し合い、「相互貸借」や「遠隔地貸出・返却」のサービスを行っている。また、貸出が行われない資料についても、著作権法に基づき複写を行うことができる図書館がほとんどである。また、「レファレンスサービス」も基本的な図書館サービスである。図書館では利用者の質問に対して情報提供を十分に行うために、レファレンス資料やツールを整備・活用することが求められ、また回答を得るために適切な専門家・機関などを紹介するサービスも含まれる。こうした情報提供を行う以外にも、利用者自身が資料を活用して必要な情報を得られるように「利用教育」を行う。「利用教育」とは、利用者教育・利用指導、図書館利用教育ともよばれ、図書館の使い方、資料の活用方法に関する教育を行うことである。近年日本では、これが情報リテラシー向上のためにも重要であるとして特に大学図書館で注目されている。その他にも利用者の世代別に特定のサービスを行ったり、障がい者に対しては施設のバリアフリー化や録音図書・点字図書といったものを準備したりもする。さらには、資料や情報の提供だけでなく行事や集会などの「場」を提供することもサービスの一環である。講座・講演会・展示会などを通して読書活動や図書館利用を促進している。
その他にも様々な共通サービスに加え、独自のサービスを展開することで利用促進を行い、社会的役割を果たそうとしている館も多数ある。こうした図書館機能、サービスの背景にはやはりそれを活用し、ニーズを発する「利用者」の存在が不可欠であることは自明であろう。
5「図書館」の種類
ここまで「図書館」がいったいどのような要素で構成され、またどのような機能を有するのかを説明した。ここからは「図書館」にはどのような種類があるのか、またどのように分類されるのかについて説明する。
私たちがが普段利用している「図書館」にはどのようなものがあるだろうか。県や市町村によって運営される図書館や、大学に附設された図書館、また学校や公民館、その他様々な施設にも図書室といった形で設置されている。
日本図書館協会(JLA)では図書館を利用者の種別によって
①「国立図書館(national library)
②「公共図書館(public library)
③「大学図書館(academic library)
④「学校図書館(school library)
⑤「専門図書館(special library)
及びその他の施設に設置される図書館に分類している。
外国についても図書館の分類に関して一致しており、以下この分類について解説する。
まず、「国立図書館」とは高山・岸田編、前掲書によると「国の中央図書館として、国が設置・運営し、国全体への図書館サービスの提供を目的」とする図書館であり、「国内出版物の網羅的収集・保存」、「書誌情報の記録・管理」、「国内外への図書館協力活動」といった機能を持つ。また、膨大なコレクションをもとにレファレンスサービスや、調査・研究活動、また特にアメリカなどの場合は著作権の登録制をとっているため、著作権登録局としての機能を有する場合もある。日本の場合は「国立国会図書館」がその役割を担っており、根拠法である「国立国会図書館法」には「国会議員の職務の遂行に資する」とあり、国民の利用については「両議院、委員会及び議員の必要が妨げられない範囲」において許可されているという点も特徴である。
次に「公共図書館」であるが、これについて国際的にはユネスコが公共図書館のあり方の理念と使命を掲げた
「ユネスコ公共図書館宣言 1994(UNESCO Public Library Manifesto 1994)」
が採択されている。以下、同宣言(翻訳)の「公共図書館」に関する一部引用である。
公共図書館は、その利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする、地域の情報センターである。
公共図書館のサービスは、年齢、人種、性別、宗教、国籍、言語、あるいは社会的身分を問わず、すべての人が平等に利用できるという原則に基づいて提供される。
ここに、「公共図書館」の何たるかが現れている。また、運営や管理に伴う財政、法令に関しても述べられており、「公共図書館は原則として無料」であり「特定の法令によって維持」され「国や地方自治体により経費が調達」され、「地域社会のすべての人々がサービスを実際に利用
できなくてはならないといった原則も述べられている。
なお、日本の「公共図書館」は「図書館法」により規定されており、その中でさらに「公立図書館」と「私立図書館」に分けられる。前者は地方公共団体により設置され、入館料や利用に対してのいかなる対価も徴収することを禁止している。一方後者は「日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」により設置され、国及び地方公共団体からの干渉、補助金などが禁止され、自主的な活動の下、利用に際して対価の徴収が認められる。しかし、「図書館法」の条文中に「公共図書館」の語はなく、また私立の図書館では利用や入館に(低額とはいえ)料金を徴収し運営しているものも多く有る。これは前述の「ユネスコ公共図書館宣言」の掲げる「原則として無料」、「国や地方自治体により経費が調達」という理念をはたしてはいない。多くの文献で「図書館法」が日本の「公共図書館」を規定する法律であるとされているが、これは今日の「公共図書館」のあり方とそれに対する原則・理念に対して正確ではないのではないだろうか。むしろ日本における公共図書館は「公立図書館」であり、「図書館法 第2章」によって規定されるとすることが正しいように思われる。これについては本論では研究、分析が不足しているため今後の考察、研究の課題としたい。
次に「大学図書館」であるが、高等教育機関に設置される図書館のことであり、文部科学省令の「大学設置基準」などにより「学校には、その学校の目的を実現するために必要な……図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない」と規定される。研究活動の支援や教育・学習活動の支援が主たる機能としている。また、近年は情報共有機能としてオープンアクセスのシステム構築や電子ジャーナル活用、それらに伴うメディアリテラシー教育や学生の読書推進活動なども活動の柱として取り組まれる。
「学校図書館」は初等・中等教育の学校に設置される図書館である。日本では「学校図書館法」で規定されており、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、および特別支援学校に設けられている。なお、「学校教育法」では「学校」とされる幼稚園や大学、高等専門学校の図書館はこれに含まれない。学校の教育活動の支援(児童・生徒、教職員の利用)、児童・生徒の健全な教養を育成することが目的である。読書活動の推進や「自ら学び自ら考える」児童・生徒の主体的な学習活動を支えることも大きな柱としている。
最後に「専門図書館」とその他の施設に設置される図書館について述べる。高山・岸田編、前掲書によると専門図書館とは「特定の専門主題領域に特化して、資料の収集・提供を行う」図書館であり、公益法人や企業、研究機関などが設置する。利用者は多くの場合がその設置団体に所属する者であり、一般の利用者は少ない。中には一般公開を全く行わない図書館も少なくない。収集・提供される資料の主題や種類の範囲が狭く、利用者層も限られた図書館である。
また、専門図書館に類するその他の施設図書館として、「点字図書館」や「病院図書館」、「刑務所図書館」といった一般の図書館利用が困難な利用者を対象とする図書館や、「雑誌」や「漫画」、「教科書」、「映画フィルム」など特定の種類の資料に限定して収集を行う図書館もあり、これらは「特殊図書館」と呼ばれることもある。
その他図書館には類縁施設として「文書館」や「博物館・美術館」があり、また社会教育施設としての性格から「公民館」なども含まれる。図書館はそれぞれの図書館間だけでなくこうした、類縁施設やその他団体、組織などとも密に連携を深め、ネットワークを構築することが求められる。
最後に
というわけで、ごちゃごちゃ小難しいというか堅苦しい文章をつらつらと。まあ、元は自作論文の一部の改変なので必然そうなっていくわけですけども。
今後も一応連載の形をとって投稿していこうと思っています。
次こそは「図書館の歴史」について概略していきます。
本記事参考一覧
参考文献
・『広辞苑 第五版』岩波書店、1998年。
・岩猿敏生『日本図書館史概説』日本アソシエーツ、2007年。
・大串夏身・常世田良『図書館概論』学文社、2012年。
・樺山紘一編『図説 本の歴史』河出書房出版、2011年。
・高山正也・岸田和明『図書館概論』樹村房、2011年。
・佃一可編『図書・図書館史』樹村房、2012年。
・丸山昭二郎ほか監訳『ALA図書館情報学辞典』丸善、1988年。
・ヨリス・フォルシュティウス『図書館史要説』日本アソシエーツ、1980年。
・リチャード・ルービン『図書館情報学概論』東京大学出版会、2014年。
参考雑誌
・『図書館雑誌 vol.107(No.1-12)』日本図書館協会、2013年。
・『図書館雑誌 vol.108(No.1-12)』日本図書館協会、2014年。
参考論文
・川崎良孝「最近の図書館研究の状況-批判的図書館(史)研究を中心として-」『京都大学生涯教育・図書館情報学研究 vol.8』2009年、1-10頁。
・三浦太郎「日本図書館史研究の特質-最近10年の文献整理とその検討を通じて-」『明治大学図書館情報学研究会紀要 No.3』2012年、34-42頁。
参考HP
・朝日新聞社「コトバンク」
https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B8%E7%89%A9-80626 (2015年1月20日参照)
・日本図書館協会HP「図書館とは」
http://www.jla.or.jp/library/tabid/69/Default.aspx (2015年1月20日参照)
・文部科学省HP「図書館法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html (2015年1月20日参照)
・World Digital Library “About the World Digital Library”
http://www.wdl.org/en/about/ (2015年1月20日参照)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
