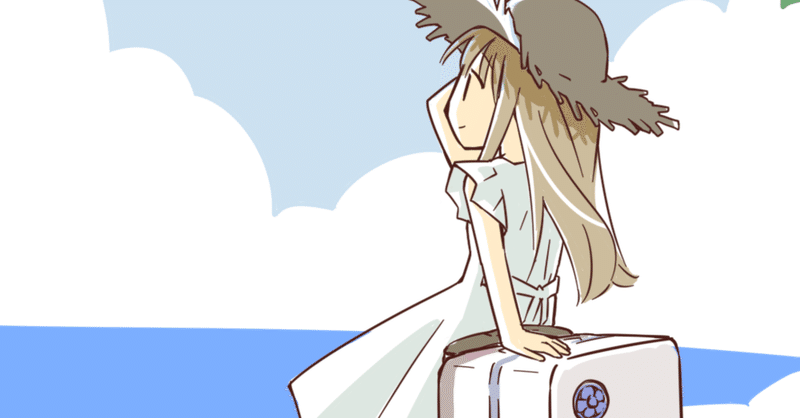
その時、小林剛だけが前を向いていた
Mリーグ2021-2022シーズンにおいて、パイレーツがセミファイナルで敗退した。レギュラーシーズンを首位で通過しながらの敗退には衝撃が残るが、全体が接戦だっただけにそこまで驚きは無い。ファイナルも同様で、上から下まで全て入れ替わっても不思議は無いくらいの僅差となっている。結末がどうなるか、一人のファンとして今から気になって仕方がない。
今回はどうしても書き残しておかねばならないと感じたパイレーツのセミファイナル最終日、小林剛を見ていて思ったことを文章に起こしておこうと思う。
見ていた人にとっては既知の事実だとは思うが、一応起きた出来事をなぞっていこう。パイレーツが挑んだセミファイナル最終日。ミッションは全体4位以内に入ることで、チームは最終日前の日程を終えた段階で4位フェニックスと約40ポイント差の5位。簡単な条件で言えば、トップと2着なら素点がマイナスにならなければ余裕で通過となる。トップ3着なら素点条件、それ以外のケースであれば、例えば連続2着且つ、同日直対となる2位、3位のKONAMIかABEMASを連続ラスに沈めるといったパターンも存在する。
まあいずれにせよ、連対が最低条件。初戦で3着を取ってしまうと次が点数条件付きのトップ、もしラスを引いたら相当厳しい条件が残るという形での1戦目、石橋の登板だった。
石橋は奮戦した。当然である。今シーズン一番の山場といっても過言ではない。簡単に沈むわけにはいかないし、出来れば緻密な条件戦での判断能力に定評が有る小林のために、素点が多少マイナスでも2着に残れば良い、そのくらいの条件を残してやりたい。俺が勝たせる、俺が決めるんだという意志、気迫を映像越しにも感じる内容だった。
既に結果が出ているので結果は簡潔に書くが、展開は終盤まで微差ながらリードしていた石橋が南3局、松ヶ瀬の七対子ドラ単騎のダマ跳という強烈な手に放銃してラス。松ヶ瀬はなんとかトップの順位点は確保して、いまだに奇跡的な条件ながら風林火山の望みをギリギリ繋ぐ大仕事。ABEMAS白鳥は終盤の勝負どころを制して、仮にハコラスでもフェニックスより上に残るという条件を作り上げ、エース多井にバトンを繋いだ。KONAMI滝沢は若干ポイントは減らしたものの最小限に留め、ABEMAS同様ラスでも大きくマイナスにならなければフェニックスより上に残せるかなり優位な位置。パイレーツは痛恨のラスで、フェニックスを逆転する7万点近いトップか、ABEMASかKONAMIを直対で逆転する点差が必要になった(ただ、これは実質的にほとんどの場合7万点以上のトップ条件を満たしている)。
一言でまとめれば、この時点でパイレーツは相当厳しくなった。奇跡と呼ぶほどの点差では無いが、ここから4位まで行くのはかなりの至難の業である。ABEMASとKONAMIは勝利にこだわる立場では無いので、序盤で先手が取れたら普段よりは一人旅が望みやすい、という大トップが少しだけ狙いやすい環境ではあるものの、先手で手が入るかどうかは流石に運頼みになるところが大きい。
この辺の事情や現実的な突破可能性も分かっていたからだろう。負けた石橋はインタビューで涙を流した。チーム戦の象徴的なシーンだなと見ていて思った。これが個人だったら、仮に一人だったら、どんなに手痛い負けだったとしても、きっと涙までは流さない。
結果論で言えば敗着となってしまったが、放銃自体は責められるものではない。トップが是が非でも欲しいところで、既に45678でドラを組み込んでいるところに過剰に引かされた5m。2枚切れの9mといえど、犠牲に出来る受け入れではないし、他に手が付けられる箇所が無かったのは事実だ。
しかしそれであっても、心に来るものはあっただろう。もしかしたら回避出来たんじゃないか、手を止められたんじゃないかと反芻したんだろうと思う。それが人間というものだ。
そしてもう一点、ここで敗退すればチーム編成の入れ替えが必須になるため、この4人での戦いは最後となってしまうことも間違いなく石橋の涙の要因になったのは、視聴者も理解している通りだ。
チーム戦らしいドラマだし、こういった人間群像のようなものが見えてこそ、プロ興行として残っていく価値があるのかもしれないな、と個人的に感じる場面でもあった。
さて、ここからは表題に書いた小林剛の話になるが、オンラインパブリックビューイングの小林の言動や行動が実に小林らしかった、という話を耳にして、改めて当日の映像を振り返って見ることにした。
既に見た人も、当日見ていた人も、もしかしたら何気ない場面だったので意識していなかったかもしれないが、是非もう一度見てもらいたいところがある。それは石橋が松ヶ瀬に跳満を放銃したシーンと、先述したインタビューでのシーンである。
石橋が5mを掴んだその瞬間、状況を考えれば切ることは皆分かっていたんだろう。朝倉の顔が曇り、瑞原は両手で顔を覆った。木下監督もしばらくして視線を落とし、画面の中に映る石橋ですら開かれた松ヶ瀬の手から目を背ける中、小林だけがずっとモニターに正対していた。そして悲鳴の後の僅かな静寂の後に、「マンガン条件か」と口を開いたのだ。起きたことは振り返っても仕方が無い。今出来る最良の戦略は、マンガンをツモって3着に浮上した上で、直対で逆転出来る相手候補を増やしつつ、トップを取ればフェニックスに追いつく現実的な位置で終えることだ。誰よりも早く冷静に状況を受け止め、そして誰よりも先に次のことを小林は考えていた。
しかしその僅かな望みも叶わず、結果ラスのまま終局した後のインタビューのシーン、控え室はやはり悲嘆に暮れていた。絶望にも近い空気の中で、瑞原が、朝倉が、木下監督がモニターを見つめる中、石橋の目から涙がこぼれたその時、小林は手元のメモを見ながら、恐らくは意図的に少し声を張って木下監督にこう要求した。
「風林火山と、ABEMAS、格闘倶楽部の点差をください」
もはやこれまでか、という空気も感じるほどの控室を、小林はこれ以上無いほどの小林らしい言葉で鼓舞した。根拠無く「まだいける」とか、「俺がなんとかする」とか、そんな空虚な言葉は残さない。そんな取り繕ったような偽りの台詞ではなく、小林は小林自身の矜持に基づいて、その時出来る最善をただ続けていた。究極の条件戦だ。事前に準備出来ることは準備しておく。それはすなわち、「全く諦めるつもりは無い」という意志の表明と共に、可能性があることをメンバーに再認識させるには充分だった。
話が突然変わるが、この場面を見て突然思い出したことがある。2000年シドニーオリンピック、女子マラソンで高橋尚子が金メダルを獲得した時、レース中の22キロ地点で高橋に直接声を掛けられる僅か数秒の場面で、故・小出義雄監督が放った言葉である。
もしかしたらご存じの方も多いかもしれないが、その言葉とは
「ロルーペ来ない、ロルーペ来ない、ロルーペ来ない、ロルーペ来ない」
である。
これはスポーツ史上に残る名場面だったと、私は断言する。
こと日本においては、スポーツとは精神性と共に語られやすい。苦境を、根性で突破する。そんな物語が好まれてきたからだろうと推察する。だからこそ、勝負どころに至っても実質的に意味を為していない言葉が飛び交う場面は未だに多く見られる。「頑張れ」「いけるぞ」「負けるな」などが代表的だろうか。こうした、具体的な意味を伴わない鼓舞が時には最後の力を振り絞るトリガーに成り得ることは理解しているし、私自身もそれを否定したくはない。しかし、そればかりにフォーカスが続くと技術や戦術の発展の妨げに成り得るなとも感じるなというのも正直な所感である。
わざと棘のある言い方をするが、日本の高校野球なんかはこの真逆をいく最悪の文化を今でもずっと引きずっている側面がある。その結果、どんなゴロでも反射的に正面に回り込む癖がついてしまったり、ファーストに不要な場面でヘッドスライディングしたり、期待値が下がる場面でバントしたり、統計的には効果が証明されている極端な守備シフトを好まず、常に一定の戦術や「基本」を重視したりする。「エラーは流れを悪くする」とか「根性を見せて勢いをつける」とか迷信めいたことを疑いも無く信奉させるのは明確に指導者としての罪である。まあ、この辺は絶対に意見が折り合わない人間が出て来ることは承知しているので深くは掘り下げないが、「自分の正義を疑わない」は人間が戦争をやめられない根本的な原因でもあるのでそれは多くの人に知ってほしい事実だ。
さて、小出監督の名場面に話を戻そう。考えてもみてほしい。愛弟子が、夢に見た大舞台で、もしかしたら金メダルが取れるかもしれない。そんな現実味が増す中で中盤戦を迎えている。ここからが勝負どころだ。「頑張れ」「いけるぞ」と声を掛けたくなるところではなかろうか。しかし小出監督はそのすべてを飲み込んで必要最小まで言葉を絞って叫んだのだ。
そんなことは言われなくたって分かっているのだ。顔が見えれば、誰よりも自分を気にかけて、胸の内で鼓舞してくれていることなど、高橋尚子の方だって確信していた。
そんなことより、既に分かり切った信頼関係を言葉にして確認する時間よりも、今この場で戦術的に必要な情報を伝える最良の言葉は何か、それを考慮して出て来た最高の選択肢が「ロルーペ来ない、ロルーペ来ない、ロルーペ来ない、ロルーペ来ない」だったのだ。
テグラ・ロルーペは当時の世界最高記録保持者であり、このレースでも前評判は非常に高かった。高橋尚子は中盤、先頭集団を走りながら、姿が見えないロルーペに不気味さを感じながらのレースを展開していた。そろそろ仕掛けて、同集団のランナーを引き離したい。そう思っていた頃合いでもあったかもしれない。
しかし、いつロルーペが追走してくるかわからない。先にスパートして、最後に脚の残ったロルーペとのマッチアップになるのは危険が伴う。その葛藤を想像すれば、スパートのタイミングで悩んでいたのは想像に難くない。
しかし実はこの日、ロルーペはコンディション不良によって後方で苦しいレースを展開していた。何をどうしたって先頭にはもう届かない位置に沈んでおり、高橋には実は後方の憂いは無かったのだ。
これを見ての小出監督が掛けた言葉が、既に書いた通りの内容である。繰り返しにも意味がある。大舞台のマラソンでは伏兵の激走が付き物だが、そういったダークホースが来そうな気配も無い。憂いはロルーペ、しかし彼女は絶対に来ないという状況を過不足無く伝えるために、ただそれだけを繰り返した。時間と状況が許すなら、どれほどの言葉を掛けたかっただろうと想像してしまう。ロルーペは来ない、だからお前のタイミングで仕掛けて大丈夫だ、信じているぞ、と。無数の含意を以て小出監督は叫んだ。生前はひょうきんで豪放磊落なキャラクター(このレースも勝負が決まった終盤には前祝いと称して酒を飲み始めたという逸話がある)もあってメディアには少し変わった人間として取り上げられる機会が多かったが、指導者としての業績ももう少し知られてほしいと私は願っている。
さて、だいぶ話が脱線してしまったので再度本論に戻ろう。小林剛の話だ。
彼は、恐らく周囲に思われているほど空気が読めないような人間ではないし、人の情緒がわからないような人間でもない。むしろ著書を読む限りは、もっと繊細な人間なのではないかと私は推定している。
実際に、最終日前日の登板で、小林はかつて見たことが無いほど所作が乱れていた。感情が「打牌選択」の領域まで狂わせていたとは決して思わないが、所作はどうしたって感情によって多少のコントロールの乱れが出る(本人は否定するかもしれないが)。この土壇場に、彼が如何に強い覚悟で臨んだのかを示す良い試合だったと感じる場面だった。
当然ながら、最終登板に賭ける想いも強かっただろう。一縷の望みを自分の闘牌に預けられた責任。そこに対して最も誠実に向き合うために、絶望が控え室を覆うかに見えたその瞬間、小林が捻りだした言葉は、「俺に任せろ」でも「なんとかしてやる」でもなく、「風林火山と、ABEMAS、格闘倶楽部の点差をください」だったのだ。
結果、小林は健闘したものの最後は届かずパイレーツは敗退した。
来期規定により編成が入れ替わる。何名になるか、などの詳細は不明だが、現状枠いっぱいの選手を使っている以上、間違いなく最低でも誰か一人は選手から外れることになる。
この編成変更ルールについても、小林は試合後に持論を淡々と語っていたのが印象的だった。
脱皮しない蛇は滅びる。よく知られたニーチェの言葉だが、そんなものを待つまでもなく、停滞がコンテンツの衰退を生むことは過去に数えきれない程の実例を以て証明されてきた。それ故、勝てない者が残り続けるような環境は良くない、という点については当然そうあるべきだ、と断言した。
本当は言いたいことはたくさんあったはずだ。偶発性の高い競技で、しかも短期決戦のセミファイナルを条件にしてしまうと、今回のパイレーツのようにレギュラーシーズンを首位で通過して再編を強いられるチームが出て来る。例えばレギュラーシーズンで2シーズン連続で5位以下、但し優勝した場合は免除など、もっとルールをブラッシュアップすることで、より良い代謝が望めるのではないか。素人目にも気の毒なくらいの形でレギュレーションの罠にハマる形になってしまったが、そんな恨み節は当然出て来なかった。
もとより、「そのルールの中」で戦っているのである。パイレーツはベストを尽くし、そして負けた。恐らく小林の中では、ただその事実が残るのみ、ということなのだろう。もし異を唱えるのであれば、勝負が始まる前に議論すべきだし、納得の上で参戦すべきだ。今の段階でそんなことは言ってはならぬ、というような、これもまた小林剛という人間の強い意志が見て取られる場面だったと思う。
今年はパイレーツのみだったが、全てのチームに枠いっぱいの選手が所属している以上、これからは再編を迫られるチームがどんどん出て来る。それが正しい姿だと私も思う。
自分が応援している選手が去ってしまうのは嫌だが、去ってしまう可能性が無い戦いを見るのはもっと嫌だ。「今の編成のこのチーム」が有限ですぐに変わり得るからこそ湧く愛着がある、というのは他のプロスポーツを見ていても皆経験があることだと思う。
パイレーツはこれからも進む。もしかしたら少しずつメンバーを変えながら、或いは小林剛を含む全ての人間が去ったとしても、文字通りテセウスの船のごとく、「パイレーツ」として存在し、航海を続けるのだろう。それこそがプロスポーツのあるべき姿であると思うし、初年度開幕メンバーが全てのチームにおいて全員去った時に残っているファンの数が、真に「Mリーグのファン」として定着した数と呼んでも過言ではない、と私は思う。
やがてMリーグが娯楽として定着し、麻雀がもっとメジャーな競技になった未来を夢想することがある。いつか来たその時に「パイレーツの小林監督は選手時代から変わり者でね、2022年にはこんな場面があったんだけど…」と懐古主義の口うるさいオッサンのように、ずっと語り続けたいと、そう感じるようなセミファイナル最終日だった。
スキだけでもとても喜びますが、サポートしていただけると執筆時に私が飲むコーヒーのクオリティが上がる仕組みになっています。
