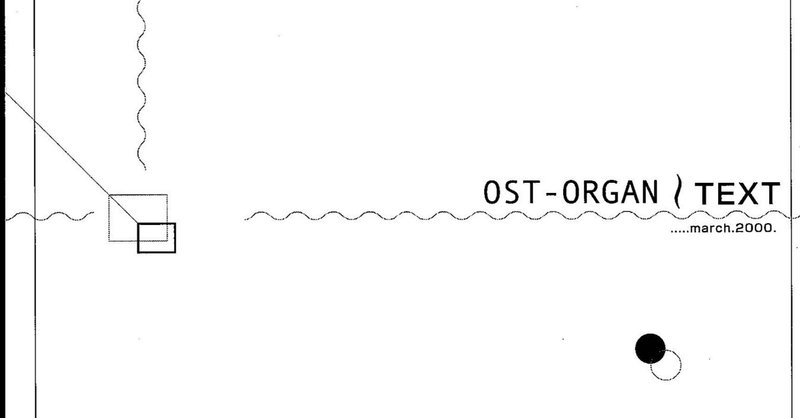
2000年3月に発行されたOST-ORGAN ≀TEXTに掲載された浜島嘉幸氏*のOST-ORGAN論です。
OST-ORGANと媒体性批判について
浜島嘉幸(身体表現)
(1)はじめに-循環論的な印象
たんに生きていくためだけでなく活動していくために重要なふたつの契機、言語と身体は行為という面で他者へと開かれている。他者へと開かれているがゆえに、たとえば演劇が成り立っているとすれば、今度は演劇の中での行為が「その他者」へと閉ざされたかたちでやってくる。そういう「その他者」へと閉ざされたかたちを内にもって、演劇という活動は観客や社会に開かれている。こうして、遅かれ早かれ「その社会」へ閉ざされている演劇行為をその内にもったなにものかがやって来る。なぜなら、そのなにものかが開かれている当のものゆえに、言語と身体が成り立っているのだから。
(2)媒体を閉じること
俳優や役者のみならずテクストを別に指示され他者の言語を身に負い自ら舞台の上に立つ者、つまり身体表現に関与する者は、身体に言語性を負うあるいは媒体的な仕方を引き受けることになるといえる。これを演者の受動面ということにしよう。一方、この受動面を介して他者について舞台上で言及し位置付け、批判することもできる。これは演者の能動面といえるだろう。「受動面を介して」といったが、他者言及-他者批判の方が先であり能動面を介して受動面が機能化し、問題化するとしても別によい。いずれにせよ、演者の媒体性は表面化し道具化すると思われるからだ。
OST-ORGANが一貫してモチーフとしてきたことは、この演者の媒体性の批判であるといえるかもしれない。声と身振りの分離といい、自己紹介による他者紹介といい、演者の媒体性をどのように批判し、演者の他者性でなく他者の他者性を演劇の上に切りおくか、つまり媒体でない演者さらにいえば演者ではもはやない例えば俳優というものを仮説するかにいつも焦点を絞っているといえなくもない。見かけ上、テープの音声を繰り返すだけの「ロボットのような」「被為的な」ありようが、演者自身の表現力動に身を委ねたような演技の仕方に対する批判と見られたり、演者の媒体性をリテラルに表面化することで逆に媒体的在り方を消去して媒体自体を絶対化つまり非媒体化しているというふうな視点で位置付けられたりするのもべつだん奇異でもないのだが、べつようにもいえるように思われる。
単純になぜOST-ORGANの上演でいつもテープに録音された自身の声を聴いてテクストを発声するのかということである。問題はいろいろあるが、これにきわめて単純に答えるとすれば、他者の声あるいはテクストの媒体にならないということ、この一点ではないのか。もちろん、媒体を介さない表現の在り方・コミュニケーションの在り方のみならず、媒体批 判を一般社会の現様に当てはめれば、その射程の広がりを伺い知ることができる。順を追うことにしよう。
今回の上演、[聴く演劇](1996年10月・七ツ寺共同スタジオ)では舞台上にコンパネの地肌そのままの囲いが使われた。この建築物状の3面の壁は左右の袖と舞台張り出しの客席面前に設置され、つまり舞台の空間を収容所のようにコの字型に閉じていて、観客には中がほとんど見えない。その正面の壁にビデオ・プロジェクターで映像がうつされる。それは歩いている俳優たちの姿でしばしば彼らの脚が重点的にうつされている。見えないが、黒いスーツを着た俳優たちが舞台内を同じように歩いている足音が聞こえる。同時にソ連抑留者の手記のようなテクストを俳優たちの声で録音されたものが流される、という具合だ。抑留者たちは過酷な環境のうちで共生を余儀なくされるというようなことばがしばしば耳をうつ。正面のいわゆる劇場の第4面のこととか、劇場は収容所であるとか、覗き見られるものとしての舞台とか、逆に観客が覗き見られジャンルとなるとかのはなしはひとまずおいておくことにしよう。ここでは映されている映像の中で歩いている俳優たちと実際に中で歩いている俳優たちのいちおう1対1の関係が重要だと思う。そのうえで、歴史的・現実的な抑留者の共生の在り方のテクストがナレーションとして耳にかさねられるようになっている。
上演チラシに同封されたコメントによれば、「『演劇と映画』は映画を透過することで演劇が多数に話しかけないことを、『演劇とTV』はTVを透過することで演劇が個人に話しかけないことを、含意してはいないか。そこでは演劇は映画であり、TVである。そうしてみると『演劇と演劇』は透過の拒否、といえなくもない。」と呼びかけられている。平易な文体だが、いつものように真意の読み取りにくい謎めいた文に仕立ててある。
思うに、映画を見るときは暗闇の中で個別に見るふうなのだが、ひとりで見るという感じはない。逆にTVを見るときは、ひとりで見るので問題はないがどうも個別に見ている感じはしない。そういう意味では、映画は個人に話しかけているふうを装っているし、TVは多数に話しかけているふうを装っている。もちろん、映画がじつは多数が話しかけTVがじつは個に話しかけているかというと怪しいものだ。要するに、個人と多数、あるいはひとりと個別という近接した社会的相関項に集約された、現実的なのだが概念的にみえる対立=矛盾のようなものの上に大衆メディアが成立しているとでもいえばよいか。とすれば、演劇とはなにか、もっとあからさまには大衆にとって演劇とはなにかというあまりに古典的な命題が演劇と映画あるいはTVと演劇をめぐって舞い戻ってくることになる。
[聴く演劇]の前半部では、上のコメントを字句どおりに、多数にも個人にも話しかけない、つまり社会的に閉ざされる在り方として演劇が映画を援用したりTVを援用したりする趣向を演劇にとっての壁=媒体として揶揄しているのだろうか。ならば、演劇は多数にも個人にも話しかけるものなのか、それとも、多数にも個人にも話しかける/多数にも個人にも話しかけないという分裂的な二項に関わるような、形而上学的にみえるがなにやら現代社会的な難題=矛盾の上に演劇を大衆メディアとして設置せしめようとするのだろうか。
壁=媒体を批判することが、媒体=壁として捉え置くことではどうというわけでもないだろう。むしろ、媒体としての第4面が自活しているようなありようは、その第4面からカメラのズーム・レンズが生き物のように客席に突き出したり、TV受像器が穴から覗いたりする場面で示されるが、このような生物学的隠喩がたとえモレキュラー・シアターへの批判だとしても強固な壁として指定できないところから媒体性の現在のありようが批判されようとしたのではなかったか。
OST-ORGANの特色は、今回は事情があり垂直的な壁面を立てて見せているが、やはり地層学的ななんらかの隠喩を含んでいるとみるべきかもしれない。地層というのは根底的な変化=断絶が起こらなければ生成しないものであり、それを地層というのだ。断層・切断面・亀裂によって地層は地層たりうる。その中間・途中・過程というのは原則的にはないに等しい。ところで、媒体というのはそのような中間的なものを指している。中間がなければ、移行ということは考えにくい。そこで、移行ということもある層の位置が別の層の位置に移動するというかたちでもって指示されることになる。これはひとつのイメージにすぎないとは言えるが、必ずしもそうではないかもしれない。地層学的な移行というのは、かつて別の層が位置していた場所に移動しそこに新たに位置を占めること、そうして全位置の意味構成を変えること、それが地層の地層たる形式であり意味内容なのだ・・・。
[聴く演劇]の前半部で、映像が位置していた観客の面前にある壁面がゆっくりと後背部に移動する。もし映像がうつされたまま移動すれば、舞台上の歩く人達と映像上のそれと前後の位置が変わるわけだが、全体の様相・形式・意味内容とも一変するのは考えるまでもない。そのとき、歴史的・社会的なコンテクストへの接続を批判的ににおわせていたテクスト=抑留者の手記の「ナレーション」は舞台上の実際の行為のナレートに接続したはずである。だから、映像(イメージ)とナレーションも、壁が前面にあって舞台内が想像(イメージ)でしか把握できない状況でしか使われないのであろう。逆に言えば、映像とかナレーションとかが壁と共に見えない領域を作っていて、文字通り想像(イメージ)の領域を決定する。それを映像というのだった。テクストがナレートするのはそこでは想像に対してであり、イメージにくさびを入れイメージの文脈をさらに想像させることである。
演劇が媒体になることを拒否するとすれば、演劇が映像 (映画・TV)の媒体になってはならず、したがって観客に対して映像=想像の前にあってはならない。いわば演劇が媒体になるのは演劇に対してであり、もとより前半部も演劇が映画やナレーションに媒介されていたのではなく、映像やナレーションに媒介された演劇に対して演劇がなされていたというべきであろう。それだけではない。演劇がいかなる意味でもテクストの媒体とならないためには、そのテクストは上演のなかに位置付けられている自ら自身の演劇でなければならない。壁の中の歩く俳優(の想像)はOST-ORGAN自身の「テクスト化した」演劇であり、それゆえに観客の眼から隔てられており、その「舞台上にあって、かつ、ない」自身のテクストを媒介して自身の演劇が批判として提示されていると思われる。要点は、媒介となるのはテクスト化した自ら自身の声や演劇であり、それが テクストであるがゆえに観客からはいったん隠されており、そうして他者のあるいは他者というテクストを媒介するものとしての媒体としての演劇や演者を自者をテクストとすることで閉じるわけである。
さて、やがて面前の壁=劇場の第4面はあとずさりして、舞台後方の第3面に位置し直すのだが、この背後のホリゾントあるいは黒い壁は劇場の「本来の」の開口部であり、想像(イメージ)の先が劇場内・演劇内に閉じないようにされている「本来」映像=想像が位置するところと考えることもできる。そのなか(その外と言うべきか)は視界からいったん隔てられ隠蔽される。つまり、字義どおりにすれば、単なる「壁」が機能する場所なのである。
(3)媒体を開く
道具/装置としての(映像) メディアは、すでに述べたように多数と個人・ひとりと個別のように近接した現実的だが概念的には矛盾=対立と思われるような社会的な相関項を背景に成り立っている。したがって、これを位置付けるとすれば、面前でなく後背地に送り返すことだろう。
ところで、道具/装置としてのメディアは、現実の事柄をなんらかのかたちで解消するとか慰撫するとか、展開せしめるとかに本質があるわけではない。メディアは現実を相対化しかつ攪乱する、と同時にそのメディア(媒体)の上に整序せしめるかのような効果を「演出」する。先日、愛知芸術文化センターで行われた[船の丘、水の舞台](1996年9月)で、映像作家の大木裕之が米井澄江らモダンダンサーや五井輝の舞踏に対してビデオカメラを持って「乱入」し、そのうえ踊り手の動きを自分の身体で不細工になぞりながら仲間のパンクふうの青年たちと右往左往したのは、メディアと媒体の或る意味での本性を露出せしめようとする意図があったのではないかと思う。攪乱し相対化しているのはカメラというメディアの武器を持っている彼ら映像グループ側であり、一種のテロルと言うべきではあるが、整序された媒体となろうとしているのはじつはモダンダンサーや舞踏家なのであって、現実に現実を相対化し攪乱したうえになりたっているメディアと媒体の性格を忘却しているのではないかというわけである。こうして彼らが対抗しジャンルとして「雑居」することで原点に差し戻すことは或る状況・場面では正当であると思われた。これもメディアを開くひとつの仕方ではあるだろう。だが、媒体やメディアの性格を露出=批判するのみでは結局その批判者みずからの優位を宣言するだけであって、アヴァンギャルド(前衛)というもうひとつの媒体性に居すわるにすぎないのではないだろ うか。だから、いったん媒 体性を閉じる方策が模索されるのではなかっただろうか。
[聴く演劇]以前からOST-ORGANの上演作品では、俳優が、録音された自らの声を聞いてそのテクストをそのまま発語するという方式を用いている。あらかじめテクストを読んでおいて、その自分の声をなぞって発声することは、脚本を覚える作業を省けるわけで合理的と言えば合理的だが、安直といえば安直である。しかし実際には、自らの録音された声と同時的に同じ章句を言うことは、逆に記憶に頼れない速度を要求され、徐々に頭の中が空白になり発語することが「自動化する」ようだ。つまり、自らの話す声もテクストたりえないという事態を招くということ。
もうすこし、細かに順をおってみよう。まず、ベケットなりのテクストがあり、それを読んで録音する。これが「自己テクスト」になり、録音された声はFM電波で飛ばされてイアホンで聞かれる。観客側からはこの「自己テクスト」の在所は直接にはわからない。これは脚本=テクストの在り方と同じである。私流にいえば「自己テクスト」が隠蔽される。これが第一の「話す私」である。これをイヤホンで聞く私がいる-これが第一の「聴く私」。そして第二の「話す私」がくる。第一の「聴く私」と第二の「話す私」は観客にはいちおうイヤホンの存在などで直接知ることができる。
だが、「話す私と聴く私の隣接」と言いながら、順番がひとつずれた「聴く私」と「話す私」が隣接しているわけだ。第一の「話す私」が隠蔽されているために、他者のテクストが直接演者をその媒体とすることを(舞台上)回避させている。隠蔽されているのは、しかし、第一の「話す私」はそもそも媒体としての演者ではなかったのかということである。そこで、第一の「話す私」は演劇の作業過程じたいに関わるもので上演=舞台上と切断されており、べつの位相にあり、簡単に言えば演劇における「練習」の不可避性に言い止めるということになるか。それでもなお、媒体としての演者はテクストの存在があるかぎり消えてなくなりはしないし、「聴く私」の第一次性と「話す私」の第二次性のずれは、先へと駆動する契機となるだろう。つまり、先へ先へと駆動していくなかでしか解消の仕方はないことになる
が、OST-ORGANの上演から受ける一種の分裂的不安のようなものは、じつはこのずれは先への駆動の中では解消しえないし、いわばずれは根源的であるということのそのままの提示からくるのではなかっただろうか。もちろん、それも前後を自己遮断することによってであり、ここで「根源的」というのも第一の「話す私」と他者のあるいは他者というテクストを隔蔽/隠蔽したところからくるのではあるが。
ともあれ、テクストを演者がそのまま身体に入れて演者が「テクスト」媒体とならずに、演者が「直接」テクストとするのは演者自身の声であり、逆に言えば演者は演者自身に話しかける。そしてさらに、分割された「俳優」は自ら自身もテクストたりえない事態に追い込まれる。その先は俳優のみならず構成・演出者も関知しない・・・。「他者」が現れるのは本当はその先のことだと言いたげに見える。だから、かつて[ハムレットマ シーンにおける受苦性の空虚に関する上演]([ハムレットマシー ン・パラタクシス]1991年)のときには、テクストは音声変換され分節されているにせよそのままスピーカーから流されているので、演者=俳優は一切「発語」せずに口をそれにあわせて動かすだけだったのだろう。声と身振り(動作)の分離・切断とはいうが、テクストは俳優によって媒介されず舞台上を動くスピーカーによって「位置付け」られ放置され、分離されているのはじつは、テクストじたいの在り方(ミュラーの『ハムレットマ シーン』とその解釈操作)と「OST-ORGANの演劇」なのだと思う。ここで成立されるのはテクストとその上演ではなく、OST-ORGANの演劇であり、さらにOST-ORGANの演劇に隣接されることによる「演劇と演劇」による<演劇>なのであろう。
さて、イヤホンで自らの声を聞き話す第二の「話す私」はじつは第二の「聴く私」でもある。説明しよう。舞台上の演者は観客の眼に晒されている。もしくは、観客の眼に晒されている舞台上にあるということを内面化して自らの行為を認知している。どれほど構成・演出によって統御されようと、舞台上の装置としてのテクストによって「自動的な」発語・動作になろうと、練習や訓練によって具体的なその場の観客の眼や反応に左右されない演技になっていたとしても、そうした基本的には「抜き差しならない凡庸な事 態」は残るといっていいだろう。いわば、身体は「聴く耳」を持っている。たとえ内面化された「自己の眼」であろうと。身体は観客の眼差しを「聴く」あるいは「匂ぐ」。だから、ふつう演者は特別な意味なしには観客を直接見ないのだろう。これには或る意味での「制度的な」枠組みが関与していることを否定しているわけではない。だから、抜き差しならない凡庸な事態と言ったのである。
ここでは、見ることは聴くことに変換されて「身体性」となっており、そのうえで聴くことは見ることであるような「身体」としてある・・・。
そこで、演者の動作や口振りが、聴く身体あるいは第二の「聴く私」に媒介されているとすれば、それが媒介している「テクスト」を舞台上に提示しておく必要があるということになるだろう。この「テクスト」は、おそらく不特定の観客の眼差しを聴くという共同主観的なものであるだろう。そこで、今回の[聴く演劇]の後半では、面前の壁がしりぞいて舞台空間が現れると、ベケットの『あのとき』を吹き込んだ自己の声を聴き発語しながら、8人の出演者は一列になった動きを始める。ところがどうやら、テクストをそれぞれの声で吹き込んだテープ面はただひとつで、そこに出演者それぞれの声で録音された全体のうち自分の声の部分を発語しているらしい。そのうえ、自分以外の俳優の声も小さな声で繰り返している。動作について言えば、長いベンチの上に座っているときは各自少しずつ違ったボーズをとっているが、突然走り出してうつぶせにスライディングしたりするときは基本的に同一の動きになっている。なにを示唆しているかはほとんど一目瞭然ではないかと思われた。「聴く私」の身体は共同的・共同主観的な「テクスト」に基づいている・・・。
第二の「聴く私」が、同一テープ面の8人の俳優の「集合的な」声と、微妙にまちまちな同一の動作によって提示されているとすれば、とうぜん第三の「話す私」が次にくることになるだろう。ベンチが舞台上手から舞台正面に移されると、そこに一列に並んだ出演者は各々隣の出演者の手にそっと触れる。その触れる所作を次々にその隣へと端のひとまで受け渡したあと、全員は3番目のテクストを喋りはじめる。それは予告されたとおり、構成・演出者である海上宏美じしんが書いたテクストの ようだ。だが、その文体は「・・・といま言おうとしていた」とか「・・・だと言ったんじゃなかったか」、「・・・だと思い出が口にした」、「・・・と言おうとしているのか」などというもってまわった言い回しになっている。要するに過去と予期にわたって、「・・・と言おうとした(が、それは私の中には見あたらない)」、「・・・と言おうとした(が、それは私が言ったとははっきりいえない)」などとなっているようだ。もはや明らかだろう。これは「テクスト」ではないと言いたいのだ。あるいは真性の<テクスト>といってもいいが、「テクスト」をこれこれだと聞いた、だれかが言ったということを喋っているにすぎないのだと。これもまた詐術である。だが、たぶん媒体を開く方法でもあるのだ。ここでは、一貫して素抜けのいわば完全な体(メディウム)でありながら、媒体にはなりえていず、媒体なのは「わたし」ではないなにものか、例えば「思い出の口」とか「追憶」とかそういう他者なのだ。それが語っている「テクスト」は、私ではないさまざまな人称やものについてのことである。きっとそのなかには「みんな(われわれ)」もはいるのだろう。
繰り返すと、一貫してテクストの媒体たることを退けると、「自己テクスト」へと閉じることになる。海上宏美が[ノンブル・パラタクシス](1992年)の「意味内容」について「OST-ORGANのメンバーが固まったということだ」とかつて言ったところまで戦略的に「自己テクスト」化は進むのだろうか(そう言われても困るけどね)。自己がテクストであることは、テクストは自己=自分だということを必ずしも意味しない。この不可逆な宙吊り状態を意志すること、この宙吊り状態を受苦することが媒体を閉じることのひとつの意味なのだろうか。だが、「話す私」と「聴く私」が先に駆動し進んでいくと、そのただなかに自己でない「テクスト」が現れることになる・・・。
これを内野儀流に「(日本では)私とは我々である」とか、別役実ふうに「(現代では)個は関係の結び目、関係自体でしかない」、あるいは吉本隆明のように「深い自己」ということも可能だが(ただし、それぞれは別々のことを言っている)、そうでなくて他者のことばを聞く身体がいずれ話すことは「・・・と聞いた」ということでしかなく、その反復のなかでその反復を話すのだということ。しかし、その反復じたいを(上演として)話すということはた だの反復ではなく、「・・・と聞いた」という 聴く身体=第二の「聴く私」が身体として自己(「自己テクスト」)ではないというところにポイントがある。そのため第三の「話す私」は「明示的に」上演中に現れていないのだが、第二の「聴く私」が「自己テクスト」にもとづかないところから、その「自己でないもの・こと」を聴くということを上演が自己のこととしてそのまま反復するまさにそのところで、第三の「話す私」は暗示されているのではなく<明示されている>と考えるべきだ。その所以は、舞台=演技空間のなかでは自己が自己自身のことを話すこと―「自己紹介」することは明示的にはできないと思われるからだ。(でもないか。ともかく、自己紹介=「上演」において部分として私的なことを指示する可能性については演技空間の枠組みと条件についての錯綜した議論が要る。そのなかには、セリフの暗唱がもたらす上演空間の中の物体の<非意味化>と、所作が再び重要性を帯びるという事態=<意味化>が含まれる。)
今回の[聴く演劇]が前作([PARATAXIS 2]1995年)にもましてOST-ORGANもしくは海上宏美じしんのモチーフが表出されているような肌触りが色濃く感じられる原因の一端はそこ(<明示>された「話す私」)にあるのかもしれない。
場面の最終部で、劇場のスピーカーからずっと俳優たちの聴いていたテープがそのまま流される。ここで上演自体が聴いているテクストが正体をあらわし、それが単純なワン・テープ、ワン・テクストの平面にすぎないことが明らかにされる・・・。そのとき、演者=出演者たちは「場面」からつまり舞台からしりぞくかのように上手前方に集まり、自分たちが演じていた場面の空間を改めて見るかのように佇んでいる。あるいは、かつての集団的な場面じたいを無視するかのように、あちこちのほうを向いている。テクストと演者の間にある葛藤=リリシズムは、リリシズム=「叙述性」に過ぎないとでもいうよう
共同性・共同主観的なものに対する今回の上演の立場は(演劇=芸術なのだから)賛否うかがいしれないのではなくて、二面的なようにわたしには思われる。二面的なように思われる というのは、わたし自身の考えの投影だともいえる(ようになっている)からだ。共同的・集団的なものに対する、あるいは「個と全体」に対する構えや扱い方・手つきの微妙さや揺れは、自らがそのなかに含まれている以上、かんたんに固定できるものではないと思う。舞台上で踊るのは、そのような微妙さや揺れなのだが、或る筋道上では強靭な構えや図式として現れざるをえない。でなければ、上演の「強度」は観客やその集団自体に対して説得力を持たないだろう。ただ、そのような「強度」をいつも要求したり、強靭な徹底した形式や構えを常時評価の基準や駆動力にするのは性急すぎるとも思われる。「この筋道をどう扱うかが現在的な問題のように思われる。」とはかつて海上じしんの書いたことであった。重要なのは、「この筋道」じたいではなく、「この筋道をどう扱うか」ということであり、だからたとえば演劇があるのだ・・・。
わたしは今回の上演を見ていて、いわば共生する集団の中の徹底した孤独のようなものを感じた。出演者の影のある顔が、単なる表情ではなく、得体も知れない視線に貫かれている深い孤独の影を刻んでいるように思われた。どのような視線=まなざしのもとでそのような顔が現れるのか、知りたいように思われた。視線が発せられているもとは、少なくとも劇場内ではもとより観客たる「私たち」なのだが、そうでない気がするところから、ひょっとしたら「作者」というのは極限でそうした得体の知れない視線とその視線に貫かれる演者の顔をつくり出すのではないだろうかと。で、観客ではない「私たち」はどうしたらいいのだろうかと。こうして、「私たち」は上演とか表現上の 身体にはおさまりきれない《受苦性》という(非)場所に戻る。
(4)おわりに-隣接と私
今回の[聴く演劇]について「批判ではない」(海上)という言にもかかわらず、演劇やそれに類する活動や「現実」の事柄を参照項として言及することで構成されており、やはり「批判演劇」として仮設されていることはわたしには明瞭のように思われた。が、そのようないわば隣接先については明白に言うのは原理的に難しいし、たんなる妄想ということにもなりかねないと思いつつ、だから思いきって「媒体性批判の演劇」という視点から分析=記述することを試みた。くどくどしいことは百も承知 の上だし、「媒体性批判」の批判先のひとつが私じしんであることも承知している。たとえば、今回の露骨なテーマになっている<共生>ということがいったい「現実」の何を参照項としているのか、わたしなりの、もしくはわたしをふくめた見当が確としてあるのだが、それを言うことはそれぞれの「項」に失礼であり、結果的に封じられていると思う。わたしにとってはこのとき、この圏域は「倫理的な」あるいは「政治的な」圏域となっており、なぜそうかというと、「現実」での演劇的批判のありように対しては隣接的にしか対応できないからだ。で、前言に反するが、今回の上演の「露骨なテーマ」が「批判ではない」ことはその通り受けとっていいのかもしれない。
結局、やはり「演劇が演劇である」ことそのもの(演劇1への言及自体)の「演劇的提示」(演劇2)でしか、現在に対する隣接(<演劇>)はありえないということだろうか。だとすれば、演劇内であろうと演劇外であろうと、現実に演劇が二つある(あるいは三つある)ことが、「現在に対する」隣接のいわば本体のように「私」へとやって来る。つまり隣接水準の移行先はいきなり《(別の)現実》、大文字の[隣接=PARATAXIS]じしんなのだ。「隣接」じたいに再帰=《反復》すること、<PARATAXIS>とはそうして隣接可能性じたいを前提とした「異なるものの共存性」に重なりあう・・・。小文字の隣接(「悪意」=批判)が、逆にその抽象形式だったとは言いすぎになるだろうか。
また、現実においてまだその《現実》は現れていないならば、この現実において演劇と演劇を隣接させ亀裂を入れること、その亀裂から逆照射されて、演劇でないようなまさにその演劇性を瞬視する「視線」がはじめて生じる、というふうに生成論的にいうことはあまりにも「演劇」的にすぎるのではないだろうかとも思われる。わたしのうちに、微妙かつ根底的な<悪意>の印象が生じるのはこのときなのである。それを比べると、(小文字)隣接の対象(悪意の相手)がどうであろうと、それは「内在論的」解釈を経由しなければ隣接にも悪意にもならない。ところで、内在論的解釈じたい隣接-批判されてきたのである。では、内在論ではなく生成論で意味付けるかというと、<外在的な隣接>が標榜されている以上、生成論的な期待にも徴妙な<内在的>悪意の影がさしてくる。再帰的な構造じたいが悪意を含んだ批判的方法論の一部となっていると同時に、この再帰的な構造じたいが隣接先/批判先になっているからかもしれない。とどのつまり、大文字の「隣接」がもとより再帰的に含意されていたとしか言いようがない--言いようがなくなるように。こうして、現実の裂開とかその《現実》への裂開というよりむしろ開裂の<現実形>が、葛藤の所在性-由来として「私」へとやって来る・・・。あるいは《演劇》が演劇》《演劇になるときにやって来るもの・・・。
ところで、一般の演劇の上演や<絶対演劇>の上演ではなく、OST-ORGANの上演でときどき自分が切り刻まれているような感じがするのは、隣接の対象のひとつが自分自身ではないかという「妄想」だけでなく、芸術対象に対する自分自身の考え方・相い対しかたが問題なのではないかということだった。というのも、上演=「表現」の一面性いわゆる表層性を極端に考えると、「作者」がその作品での内容-提示について肯定=賛同しているのか否定=批判しているのか実はわからないのではないかということに突き当たる。単純化していえば、「・・・をどう思う?」「・・・で本当にいいの?」というような提示がそのままその事柄あるいは他者への批判となると同時に(近代的)作者主体の自明性への批判にもなりうるということ。
笑い話のように聞こえるかもしれないが、この極端のさらに先端は閉じているとか開いているとかの問題でもなく、まさに断崖-奈落のようなものである。ここで「私」はまったくの「病気」のようになる。これを「芸術には裏がない」とかつて書いたが、この想定=妄想の先のひとつ、ひとつの凡庸なコロラリーは次のようなことだ。作者が設定できようとできまいと、その「作者」での内容-提示について云々しなければならないのは見手である私であって、それは「表現」の社会的・歴史的な意味とか「作品」の文化的-状況論的評価・文明論的批判のようなモダーンな「評論家的」言動や美術史家的言動とはまったく別のことではないか、ということなのである。もちろん、評論家的言動や美術史家的言動が間違っていると言っているわけではなし、解釈の多様性・受容の多元性のことを言いたいわけではさらにない。内容-提示が具体的かつ現実的な(つまり、とりわけその個人の生き方・思想に直接関係する)事柄に言及していることならば、芸術(論)的な「取り扱い方」が問題なのではなくて、その事柄に対する直截な私の姿勢や言動が明確に示される=主張されるべきなのではないのかということである。ただ、それだけが「芸術=作品」の機能・在り方だとすると「芸術=作品」が媒体だというかつての社会主義リアリズム論争ごとき問題設定に滑り込むことにもなりかねない。つまり、かなりの保留と条件がいるのだということ。だが、こんなことはすでに解決済みなのかといえば、そうではないのである。
このような意味で、たとえば上演に対するこの「私」というものが、観客(近代的観衆)だとか参加者だとか、はたまたま「立会人」だとかいうのとはまったく異なる位相で立ち現れる可能性があるのはしごく当然のことだが、隠蔽されているといえば隠蔽されており、今回わたしが書いたこのような文を含めて近代的観客の姿勢は決定的に「間抜けている」のではないかという疑念に晒されると、やはりはたと立ち止まって考え込まざるをえない。具体的な現実的事柄(問題)に対して距離をおくことで、いったん抽象的にしておけば冷静に事柄に対処できるというような効用が芸術=表現機構についてあまりにも楽天的に「正当な迂回路」あるいは「(思考-試行の)道具」だとみなされたり、媒体としての芸術=表現が忌避されるとその作品構造の「純粋度」がジャンル内自己言及的にモダニズム的在り様に結晶したり、はたまた「芸術的に優れた」バブリック・アートのように諸刃の剣のごとくに自慢げだがいずれシニカルで自身の揺れを凍結するモダニズムの自己言及性を装置として追認していたりすることではいかんともしがたい事態に「芸術的に」追い込まれることがあるということ。いわば「近代的聴取」の近代的自明性に亀裂が走るといってもいい。
そこから「折り返す」にはどうしたらいいのだろうか。OST-ORGANの上演もそのようなモダニズムのなかにある両義性の線上にあり、だからわたしは「美術的であること」をどうするのかと問うてきたのだが、むしろOST-ORGANのほうがそれをきわどいかたちで問うているとすれば、問いは直裁に私の上に折り返し降りかかっているのだと思う。反省すれば、確かでないのは、具体的に「私」に対するもの・ことへの姿勢や意見=主張であり、それは必ずしも芸術的文脈・芸術的状況に相い対するわたしの「社会的な」姿勢・思想ではない・・・。とすれば、ここでは、例えば上演はじつは芸術に相い対していることになるということも可能だ。ただ、この時点で同時に、芸術の「絶対」媒体性あるいは媒体性批判とか観客の観客性とかは「メタフォリカル」な像-行為であり、迂回路=手管にすぎるのではないかという疑念が沸く。もちろん、ジャンルの「制度的・歴史的」な条件があるかぎり、そうせざるをえない充分すぎる理由があることの具体的中身を本来確認し批判しておく必要があるのだろうが・・・。ともあれ、ここで観客批判は周到な像をむすび「私」に折り返し降りかかり、態度の変更を迫ることがあるとひとまずいっておこう。そのとき「わたしたち」はもはやすでに劇場とか芸術ジャンルの中にはいない。いやむしろ、その中という外にいるといってもいい。あまりに古典的で一歩間違えば反動的な道筋にも導かれかねないが、それは一般化すればモダニズム全域への疑義(の反復)でもありうることは確かのように思われる。ただし、だからボスト・モダニズムというモダニズムの全観客性(全-演劇=演技性といっても同じだ・・・とすることは陥穽であるとわたしは思う)への再反転あるいは「非-近代的聴取」の近代的流用もあるのだ。OST-ORGANの上演が微妙で悪意のある手つきになるのはこのためであることも確かなのだと思う。ただし、今回の上演については少し印象は違っている。そのことの一端は触れたつもりである・・・。
元に戻すが、はたしてOST-ORGAN[聴く演劇]は今回例えば「演劇と映画」、「演劇とTV」を隣接=批判先として「演劇と演劇」を構想しているのだろうか。前言に矛盾するようだが、それが<演劇>の過剰防御にならないことを願っている。「われわれ」は高速で立ち止まっているのだし、ジャンルというのも基本的にはそういう問題として見聞きできるはずだ。わたしにとっていつもOST-ORGANが刺激的なのはだからである・・・。
(1996・10・31)
P・S
以上、あまりに冗長な分析・説明(「説明演劇」!)に見えるだろうか。思っていることのひとつは、OST-ORGANの演劇もしくは<演劇>は以前からずっと一貫しているのだということであって、この点のみではOST-ORGANの擁護として書かれている。
だが、意図したことは、表層のみではないということであって、それを深層というわけではなく、「内容」と称してもいいのではないかということだった。冗長で拙いにせよ、以上の文自体がそのようなものとして書かれている。
この間身近なひとびとに手渡した草稿に加筆し、微妙な修正を施した。これでわたしを含めたOST-ORGANの<演劇>についての問題の「本質」の一端は<明示的に>突いたといちおうは考えている。このことの内実は、かんたんに<ロケーショニズム>(対象化の対象化がメタでない仕方)ということばで言えるようにも思っている。つまり、ロケーショニズムというのはテーマではなくすでに為され成されつつあるようなありよう=在り方・仕方を指すというのがわたしの主張である。だがしかし、演劇的な「政治性」とでも言えるような在り方と違うというのも、事実はどうあれ、言っておきたいと思う。これは「自負」ではない。まったくもって難しいということであって、十分だということは原理的にありえない、そういう事態であり「物件」であるのだということ。そういう事態に直面しているわけだし、そう考えるしかないということだ・・・。
手渡しした以前の原稿は破棄していただきたい。 付け加えれば、このように、「通信」ふうに特定の宛先が想定されていて一般的ないわば「公的な宛先」を第一次としていないようなありかたを、わたしのほうでは「エロス的」なありようだと考えているが、たとえば内野儀が批判し、かつ「演じて」いるような「私演劇」とも通じるものだとも思っている。
この問題の根は深く、射程あるいは「応用(悪用)」の範囲は広い・・・と思い巡らせるとまったくもって恐ろしい。だから、いずれ事は霧の中に没するだろうと楽観的に考えたい気持ちもお察しいただければと思う。(平田オリザの最近の「現実を全部演劇にする」というような言動や、「ぼくたちの演劇を守ろう」と言いたげな先の赤井俊哉の「方舟四郎丸』を見ると、そうもいかないだろうなあと思う。これは独り言だが・・・。)
〔1996末 不日〕
*
*浜島嘉幸氏 1952年生まれ。名古屋大学大学院美学美術史専攻。名古屋身体気象研究所を運営後、七ツ寺共同スタジオ他で独自の身体表現に関する活動を展開。89年月曜出勤シリーズ、93年場所論シリーズ他。
2022年11月に発行された「さくらPAPER」vol.8「特集 : 名古屋80、90年代のパフォーマンスアート ~西島、浜島、海上を中心に~」に浜島氏のインタビューが掲載されています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
