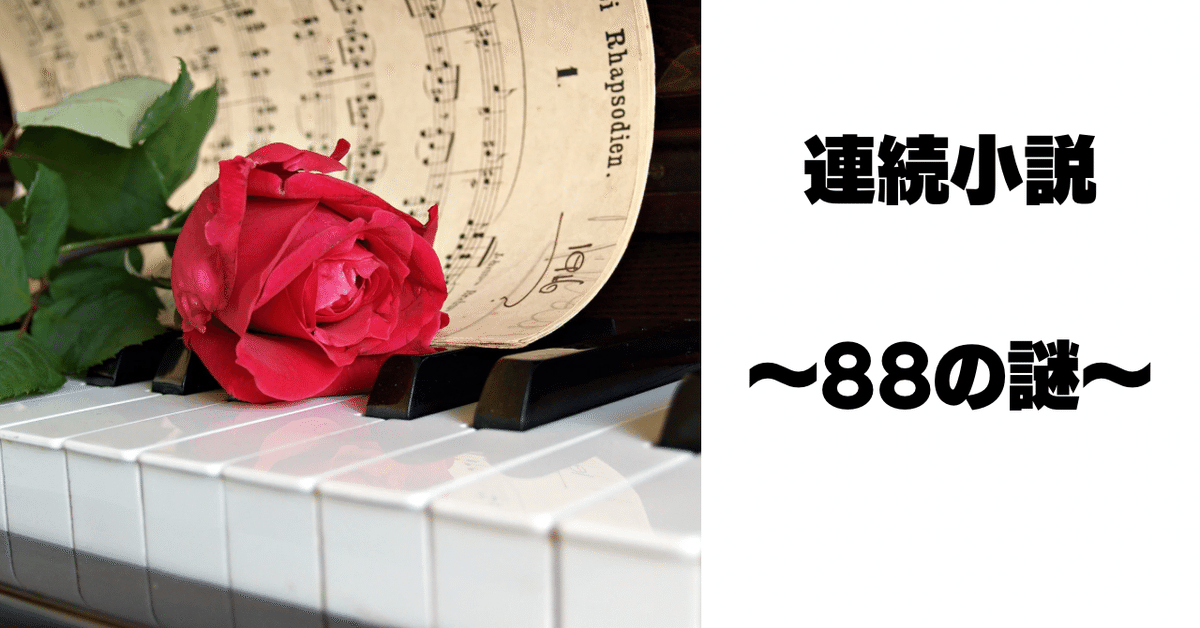
連続小説「88の謎」
第十二話 Lamentabile
軽井沢から旧国道を使い、嬬恋村と湯沢町を経由して魚沼市を越えたあたりで、ゆずを乗せた車は街並みを外れ、とあるガレージに入った。そこはゆず達の仮のアジトであり、さほど快適ではないが最低限の休息を取るには十分であった。昔の交通公園のゴーカート置き場に手を加え、いざの時の備えにしておいたのが役に立った。幸いなことにゆずの腕の怪我は簡単な治療で止血することが出来た。
「ベンツを血まみれにされちゃ敵わんからな。」
仲間の一人が悪態をつく。
「すまんかった。ただ埋めたアンプルが今の状態を保てるのは容器の性能を考えても3週間...いや2週間ちょいってとこだ。」
ゆずはタバコを吹かしながら仲間に目をやった。
「みんな、どうする?敢えてアンプルを回収しないってのも作戦だが。」
「ほう...ゆずにしては慎重な意見だな。どうした?ヘマして臆病風に吹かれたか?」
ゆず以外の3人が笑う。その中でゆずは一人表情を崩さない。
「実は…T-corporationがBYTを完成させる未来を見た...最初の発症者が出るのは福島の外れだ。」
「なんだと!?」
ガタっと椅子の音を立てて、屈強な仲間が立ち上がった。狼狽する仲間を制してゆずが続けた。
「いつもよりはっきり『先』が見えたよ。そこで俺は死ぬらしい。自分の死が見えるようになったらお終いだってTに言われたのを思い出した…」
少しの間、沈黙が続いた。
「すまん、ゆず。お前の力を当てにし過ぎて...」
「いや、こちらこそ弱気になってた。ただ今回だけはソレがいつ起こるのかは見えてないんだ。もう失うものなんてないのにな...次の目的地どうする?」
己の死、に対する予兆は近くて遠い未来であることを願いながら、ゆずは手招きをした。端末を仲間全員で覗き込みgoogle earthの航空写真にも映らない山奥の中の小屋がある場所にゆずはフラッグマークをつけた。
「ここにレジスタンスが集まってる。最近の上の情報戦の成果でT-corporationを快く思ってない組織や企業も少なくないことが分かってる。今は反勢力を集約してるところだ…後は正義が勝つか欲望が勝つかってとこさ。」
無機質な赤い三角の旗は緑に囲まれた山の麓に挿されていた。昔話に浸るクセはないが、今の内に仲間に話しておきたいことがあった。
「俺があの施設から逃げた時、山小山に隠れてた時があったんだ。その時に同じTの兵士の死体と無線機を見つけた。操作は見たことがあって理解してたから、ひたすらコールサインを出しつつ、受信するのを繰り返してた。そしたらあちらさんから、俺の能力は引き継げる、って話を聞いちまった。」
仲間の視線が一斉に集まる。
「製薬会社のフリして人体実験や臓器売買をT-corporationがやってるのはその時知った。民兵まで雇って隠し通したいワケだぜ...そしてBYTの開発。世界地図を真っ黒にでもしたいのかね。」
ふぅ、ともう一服タバコを燻らし、空を見つめた。
「本拠地に戻りたいが、俺はアンプルを回収する。それが俺の責任で、ケジメの付け方だからな。」
「そうか...なら仕方ないな。明日からまた楽しいハイキングとするか」
苦笑いしながら仲間は揃って頷いた。信頼できる仲間がここにいる。それだけでゆずは心が休まった。
過去、一度だけ本気で愛した女性がいた。逃亡後、身元が落ち着いた頃に尋ねた飲食店の看板娘だった。ゆずのようなアウトローな風体の人間にも、柔らかい笑顔を見せてくれた女性だった。もう、二度と会うことはないだろうが、彼女の笑顔をふと思い出したのだ。
「守らなくちゃな、この国を。」
ゆずは怪我をしてない方の腕で、袖のバングルを器用に操作し、位置情報を確認した。
(未練の塊か…邪魔しないでくれよ?)
ゆずは心の中で呟いた。哀れみなどいらない…ただ、未来の自分に宛てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。
思い出に浸りながらゆずが窓から見る景色は、まるで嫌がらせのようにこれからを謳歌する若い新緑だけだった。
第十三話に続く
