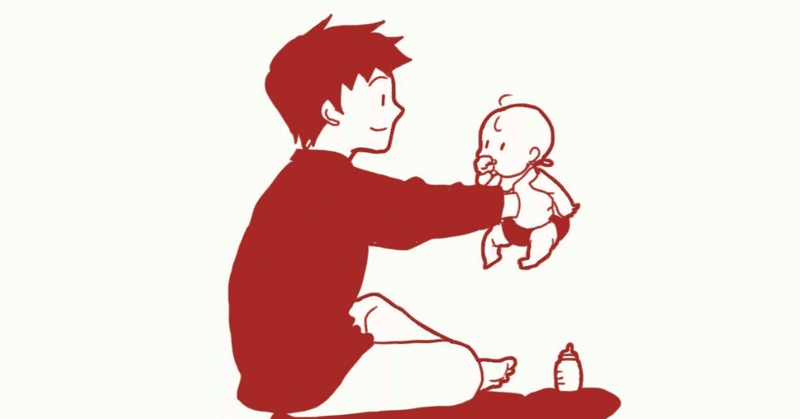
人的資本開示について思う~「男性育休取得率」の数字の罠
先週noteを始めたばかりのシンママ公認会計士河合千尋です。果たして誰か見てくれるのか??とドキドキしながら投稿した自己紹介に、多くのスキやフォローをいただき、恐縮しています。
主に女性のキャリア(→男性にも無関係ではない)について、女性公認会計士ならではの考察を交えた記事を週1目標で投稿していければと思っております。
金融庁は2023年3月期より有価証券報告書を発行する会社(ざっくりいうと上場企業)に対して「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」「男女間賃金格差」の3つの数値の開示を義務付けています。このうち開示効果や数値の意味についてかねてから個人的に疑問を抱いていた「男性育児休業取得率」について触れてみたいと思います。
こうした項目の開示が必須となった背景としては、企業の活動としてサステナビリティ(持続可能性)に関する情報を重視する風潮と、企業が経営戦略・人材戦略と連動した「人材育成方針」や働きやすい職場づくりにつとめるべきという社会の要請にこたえるため、とされています。
男性育休取得率というのは、男性の育児参加に関する企業の理解や育児休業を取得しやすい雇用環境が整備されているかを窺い知ることができ、
・女性活用促進にも意欲的もしくは実現している(というイメージを与えることができる)
・働き手不足が叫ばれる中、若手の人材が集まりやすくなる、
・男性でも育児休業をとれる背景として、業務効率化が行われていることや、周囲の理解がある等、就業環境を整備している(というイメージを与えることができる)といえます。
しかしながら開示が義務化されて1年、対象企業の現場ではさまざまな疑問や苦慮の声が上がっています。
まず私が疑義を持っていたのは、計算方法のルールが複数かつ曖昧である点です。
厚生労働省の示す計算方法は一般に2種類の定義があり、その選択は企業の裁量に任されています。
① 育児休業等を取得した男性従業員の割合
公表前事業年度中に育児休業等を取得した男性労働者の数÷配偶者が事業年度内に出産した男性労働者の数
② 育児休業または育児目的休暇を取得した男性従業員の割合
(公表前事業年度中に育児休業等+育児目的休暇を取得した男性労働者の数)÷配偶者が事業年度内に出産した男性労働者の数
実は②の「育児目的休暇」取得した男性従業員をカウントするというのは、「配偶者の出産休暇」数日程度や育児に関しての休暇をたった1日取得した者もこれにカウントされることになり、一般に世間で「男性の育児休業」(数週間~数か月以上)とはかけ離れた概念のものになってしまいます。
そして、①②とも対象男性従業員は延べ人数でカウント可能なため、同一社員が年子で2回取得したなど、場合によっては算定した取得率が1を上回ってしまうケースもあります。②の場合は対象男性労働者の全員が、各1日でも「育児目的休暇」を取得すれば「育児休業取得率100%」という、なんとも合理性に欠ける数字になってしまうのです。
また、それほど規模の大きくない企業や歴史の長い企業で、「そもそも配偶者が出産するような若い社員が少ない」「若手の男性社員はいるが結婚する者がいない」といった理由で、分母である「男性労働者のうち配偶者が出産した数」がそもそもゼロという企業が少なくないのです。こういった場合は算定不能=ゼロと記載するしかなく、今どきの社会風潮に逆らう労働環境の悪い企業というような開示となってしまい、納得がいかないという声もあがっています。
どういう経緯でこの数値が企業のサステナビリティの指標として適切だと決定されたのかわかりませんが、義務付けるのであればもう少し有益な指標にできなかったものかとこの項目を目にするたびに感じます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
記事をお気に召していただけましたら、スキやフォローをいただけますと幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
