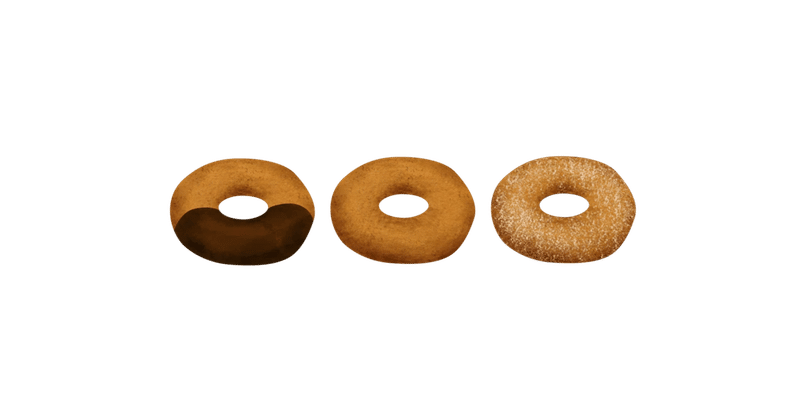
エッセイスト タケシタシノブのお気楽エッセイ(創作:約1700字)
エッセイストのタケシタシノブです。
noteにエッセイを書き続けて35年になります。光陰矢の如し。赤いリボン状の人生を指に絡める少女の如し。
その中で様々な思惑が私の脳裏に去来しました。
今日はそのいくつかに踊ってもらうことにします。
「こんなこと書いたら気持ち悪がられるかもしれない」というオールドファッション
出来れば「気持ち悪い人だ」とは思われたくないものですが、私の書きたい気持ちがいつも勝るわけで、追い抜くわけです。既に周回遅れの、常識の死骸を。
いつからか「私一人がどう思われても構わないな。読む人は読むし、読まない人は読まないだろうし」というところに逢着し、その海岸に腰かけて筆を進めています。
「こんなこと書いたらフォロワーがいなくなるかもしれない」というマカロン
フォロワーの人数というのは、誰の目にも明らかな量的尺度です。その数値は比較の土俵を作ります。それが少ないよりも多いほうが良いのではないか、そのように思い込んでしまう傾向が私の中にもあります。いや、ありました。「他者と自分」のみならず、「少し前の自分と今の自分」という関係性も浮き彫りにするこのモノサシですが、いつからか私の文具箱から消えています。これは紛失というよりもむしろ止揚です。
「涙の数だけ強くなれるよ 死線を越えたサイヤ人のように」との唄がきこえてきます。19世紀の大哲学者ニーチェは言いました。
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
「我を殺さないものは我を更に強くする」
鳥山明先生がニーチェを愛読していたか否かについては、秋の長い影が隠すしじまのためいきに埋もれてしまったようです。
「名声」という遠くの交差点で発せられたこだまによく似たガムシロップ
果たしてこの世にタケシタファンがどれだけいらっしゃるのでしょうか?
面白かったり、笑えたり、感動したり、泣けたり、そういう文章を私は意図して産むことはありませんし、きっとこれからもそうでしょう。従いまして、人口に膾炙する書物を世に生み出すことなく、文筆業を続けるという曲芸・奇芸をやっている自覚もなくはないわけです。
名声、それに憧れがないとまでは言い切れませんが、哺乳類が両生類ではないのと同じように、爬虫類が環形動物ではないという慰めがあると気付きます。
「こんなこと書いたらスキがつかないかもしれない/ゼロかもしれない」というババロア
そもそも、スキを貰えること自体が奇跡のようなものだととらえています。ありがたさを綺麗に研磨して、常に見えるか見えないかのところに置いておきたいくらいです。
さて、この世界においてスキの持つ【意味】【意義】【遠さ】【近さ】【深さ】【浅さ】【日の出】【日暮れ】【引きはがし】【巻き込み】【祈らない祈りの末路】【虎に翼に日向小次郎】は人それぞれです。その多様性を讃えます。
ですからこのババロアは、構築しない構築とでも言うべき、虚数空間の出来事であり、空き部屋に住む強くて弱い生き物だ、とも思うわけです。住んでいるのなら空き部屋ではないのではないか。その疑問には反論しません。はがれかけた「おまもりのシール」をそのままにしておくように。
「こんなこと書いたら人格を疑われるかもしれない」というフレンチクルーラー
もう無論ですよね。
緊急性がないかぎり人は焦ることはなく、後悔や遂げられなかった恋慕は触媒になります。UVランプの照射により硬化は促進し、時間性による希釈も、全て受容性/一回性に帰属しますからね。有効かもしれません。
以前にもどこかで申し上げましたが、私タケシタシノブは創作物の抱きかかえる創作性に強くて柔らかい熱を注ぎ込みます。創作物というのは創作物のことというよりもむしろ、表側の裏側のまた裏側で息をひそめる、表側に隠れる裏側の何かのことを意味します。
あるところのものではなくあらぬところのものは決して思いなしを思いなすことのないような様態で手を貸してくれるはずです。
それではまた、どこかのエッセイでお会いしましょう。
タケシタシノブ
いつもどうもありがとうございます。

