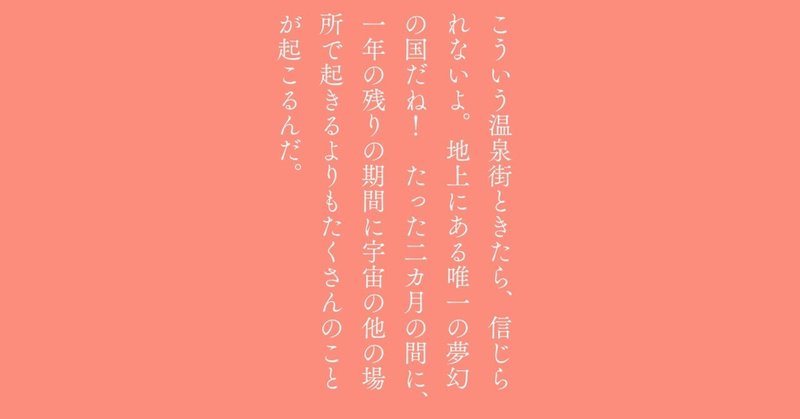
ギ・ド・モーパッサン『モン゠オリオル』訳者解題
2023年7月24日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第32回配本として、ギ・ド・モーパッサン『モン゠オリオル』を刊行いたしました。ギ・ド・モーパッサン(Guy de Maupassant 1850–93)は
ノルマンディー生まれのフランスの小説家。『オルラ』『手』『首かざり』などの数多くの短編や時評(クロニック)、『女の一生』『ベラミ』などのシニカルな作風の小説を執筆するなど、短編小説の名手として知られています。1880年、ゾラたちと発表した『メダンの夕べ』所収の『脂肪の塊』で一躍有名になりましたが、文学の流派に属さず、小説家ギュスターヴ・フローベールと詩人ルイ・ブイエから強く影響を受けたといいます。すべてを見、眼差しによって理解しようというモットーのもと、冷徹な人間観察と自然描写が際立つ作品を数多く残しました。
本書『モン゠オリオル』は、モーパッサンの数少ない長編小説のひとつ。モーパッサンが湯治のために訪れたオーヴェルニュ地方の経験をもとに書かれた、温泉地に集まるさまざまな人間模様が描き出される小説です。
以下に公開するのは、ギ・ド・モーパッサン『モン゠オリオル』翻訳者・渡辺響子さんによる「訳者解題」の一節です。


テクストの成立過程
ここに訳出した『モン゠オリオル』は、大正時代の邦訳が『湯の町の恋』、昭和に入っても『恋のモントリオル』、『秋風記』といった題をつけられていたことからもうかがえるように、温泉地での恋物語と読むことも可能であり、モーパッサン自身のオーヴェルニュ地方での湯治の経験を反映した小説でもある。1887年2月12日の「ル・タン」紙に彼は、「これはまったく優しい本にしたいと願ったものである。ほとんど意に反して書いたと言ってもいいほどだ。私を包み込み、骨抜きにし、優しい気持ちにさせたとびきりの美し国で、リマーニュ平原を一カ月間歩き回って夢見たあとで書いたものだ。かぐわしいこの地で森に身を横たえ、足元にリマーニュの青い地平線を見ながら『モン゠オリオル』を夢見て大きな喜びを感じたものだ。自分の本に、この空の深み、大地のこの香りを入れようと努めた」と書いている。
まるで自然に浮かんできたかのような書きぶりだが、実はこれより前の1885年8月、湯治のために訪れたオーヴェルニュのシャテル゠ギュイヨンから母に宛てた手紙ですでに、「ただただゆっくりと小説の準備をする他には何もしていません。この大いなる静かな風景の中の、短く、かなり単純な物語になると思います。『ベラミ Bel-Ami 』〔「ジル・ブラス」への連載は1883年〕とはまったく違うタイプの作品になりそうです」と書いている。翌八六年になると、漠然とした計画から原稿執筆の段階に入り、ルコント・デュ・ヌイ夫人宛の手紙には、次のような文章が読める。「とても高揚した、熱烈で非常に詩的な情熱の物語を書いています。いつもの自分とは違い、それで少々居心地の悪さを感じます。感傷的な章は、他の章よりずっと書き直しが多くなっています。〔…〕自分が恋愛モノに宗旨替えしてしまいそうで怖いです。本の中だけでなく、実生活においてまでもそうなりそうで」
モーパッサンと言えば、シニカルな作風が特徴であるから、「宗旨替え」という表現は見逃せない。『モン゠オリオル』のモデルになったシャテル゠ギュイヨンへは、悩まされていた消化と心臓の治療のための湯治に、1883年以来何度も滞在しており、1883年7月、時評「オーヴェルニュにて en Auvergne 」を、ゴロワ紙には 「温泉にて ロズヴェール侯爵の日記 Aux eaux. Journal du Marquis de Roseveyre 」 を書いている。ただし、後者はオーヴェルニュではなく、スイス山中の湯治場が舞台である。「オーヴェルニュにて」によれば、シャテル゠ギュイヨンの特徴は、モーパッサンが本書で「拷問」と呼ぶ治療が行われることだ。これは、作中でラトンヌがポールに得々として見せる、あの乱暴な治療に他ならず、「シャテル゠ギュイヨンはもしかするとアルジェリアのアカデミーでしかないのかもしれない。蛇や剣やその他のものを呑み込む練習をしているのだ。今ここで訓練をしている病人の一群が、この冬もし、フォリー゠ベルジェール座でデビューを飾っても、私は驚かないだろう」と手厳しい。モーパッサン自身がこの時この治療を受けたかどうかは定かでないが、85年に体験しているのは確認されている。スウェーデンの医師グスタフ・ザンダー発案の室内自転車ならぬ室内乗馬も実際におこなっているし、胃の洗浄に関しては、毎朝洗浄用の管を呑み込んでいるが、「一種の快楽を覚え始めた」と、彼らしい感想をいとこに書き送っている。シャテル゠ギュイヨンの治療所は、1878年に父親の友人でもあるバラデュックという医師が開いたもので、胃腸の病気と神経症に効くと評判だった。モーパッサンは、できたばかりのスプランディッド・ホテルに通常の治療期間を超えて滞在し、二年後に再訪している。モーパッサンは他の土地でも湯治をしていて、1885年には、イタリアとシシリアへの旅のあと、温泉治療を受けている。
「オーヴェルニュにて」には、本書の「ヴァニラの匂い」のくだりも出てくる。この地方一帯が、かぐわしい樹々によって香りづけられている、と言い、葡萄、栗、アカシア、菩提樹、樅の木、干し草、野の花と、自然を礼賛し、酔いしれている様子だ。母親に宛てた手紙には、この地に対する一種の感情の結晶作用が読める。
『モン゠オリオル』は1886年の冬から春にかけて、フランス南東のアンティーブにある友人の別荘で書かれた作品だが、現地に取材し、土地の描写を正確にするため、タズナ湖のほとりで、湖の所有者でもある城主からパヴィヨンを借り、水の音を聴きながら執筆した。スプランディッド・ホテルの女主人に毎夜、その日に書いた部分を読んで聞かせたという。経済的な問題も、施設で働く人々や湯治客の様子なども、実地で観察・研究したモーパッサンが脚色しているが、本書のアンヴァルは、ほぼシャテル゠ギュイヨンだと考えて差し支えないだろう。小説が完成したのは八六年の秋、物語の舞台ではなく、本人が所有するアンティーブの別荘においてであった。雰囲気に浸りきって客観性を失うことを恐れたのだろうか。この年の12月23日および翌年の2月6日の二回、「ジル゠ブラス」紙に掲載後、アヴァール社から出版された。
投機の物語
モーパッサンの中・長編のタイトルを見ていくと、『女の一生』(ちなみに原題では「ある一生」「一つの生」といったニュアンスで、「女の」は邦訳に固有の形容詞)、『ベラミ』、『ピエールとジャン』、『死のごとく強し』、『私たちの心 Notre cœur 』(1890)と、登場人物の名前やあだ名などの固有名詞が小説の題名になることはあっても、地名がタイトルになっているのはこの『モン゠オリオル』のみである。土地そのものの重要性は明白だ。この地名は、強欲な父子の苗字に由来する名であって、あからさまにこれを強調する役割を担っている。この新しく見出された湯の街が、資本主義の介入でどのように変わって行くか、この土地での恋愛と並行して投機物語が描かれる。『ベラミ』でもスエズ運河や新聞社の問題が出てきてはいるし、ベラミことジョルジュ・ルロワが女性を踏み台にして社会の階段を上がって行くさまが描かれているのだが、本書はより大きなスケールで構想されている。
実際、湯治場は、リゾートと健康という、19世紀における大きな関心事を併せ持つ装置であり、デパートや株式を軸に大掛かりな商売、投機の世界を描いたゾラも1884年に、このテーマで小説を書こうとしていた。〈ルーゴン゠マッカール叢書〉で第二帝政のあらゆる側面を暴こうとした小説家としては、経済的に大きな盛り上がりを見せ、建築上の高まりを示し、ある程度以上の社会階層の男女の堕落した姿を見せる湯治場は、願っても無い舞台であったはずだ。しかし、すでにモーパッサンが手がけているのを知って諦めた。
本書では、没落貴族のド・ラヴネル一家が、かすかな抵抗ののちにユダヤ人資本家ウィリアム・アンデルマットに娘クリスチアーヌを嫁がせている。このアンデルマットは、どんなものでも一目見ただけでその価値(というより、あからさまに価格)がわかるという特技を持っている。何の仕事もせず、生産せずにこの義弟に寄生して暮らすゴントランは、その才能を嗤っているのだが、ある日、自分がもし誘拐されたらいくら出すか? という、自分の値段を聞くような愚行に出る。答えるのを渋っていたアンデルマットは、空手形を出すと答えて厚かましい義兄の鼻を明かす。つまり、かろうじてまだ名誉を保ってはいるが、その実なんの力も持たない貴族と、彼らに蔑まれているものの、現実には社会を握っている資本家、実業家。さらに、その元手となる株や金銭といった実体のない富に対して、オリオル親子が土地という動かぬ富で対峙するのだ。
豊かになっても倹約家のオリオル父子は、労働しなくても十分ゆとりがあるのに依然として額に汗して働き、一方で娘二人には良家の子女の行く学校で教育を受けさせる。どこに出しても恥ずかしくない女性になり、持参金も十分な二人には、「良い結婚」をさせる。貴族階級と新興ブルジョアジーの入れ替わる図式はバルザック以来、十九世紀のフランス小説にはお馴染みのテーマだ。ここではそれが土地に根ざした葡萄農家の所有地であり、この土地を手に入れないことにはアンデルマットの壮大な計画も実現できない。まさに手も足も出ない状態で、土地と、その土地を持参金とする魅力的な娘たちが社交界の地図を塗り替えていく過程が見事に描かれた一大産業小説だ。
広告、道路整備、鉄道や天気予報など、いまでは当たり前のことだが19世紀にはまだ新奇だった戦略が見られる点にも好奇心をそそられる。
株や金も実体のない、胡散臭いものだが、水に至っては、文字通り掴みどころがない。アンデルマットは、すべては機転にかかっていて、「湯の街をつくるには、それを売り出すことを知っていなければならない」と言う。そして売り出すためにはパリの名だたる医者を巻き込まなければならないとも言う。この小説には、実際にパリが出てくることはないが、医師や教授連、株主などはすべてパリからやってくる。パリがなければアンデルマットの企む事業は成立しないのであり、やり手の実業家でありながら家庭では存在感のない婿アンデルマットが、事業を成功させるためにパリに戻ったきりで不在になるのでなければ、その妻クリスチアーヌとポールの恋も成立しないのだ。
そのアンデルマットは、ゴントランらが思うように金銭目当てでこのような仕事をしているのではない。「政治であると同時に戦争であり、外交である」大事業には「男たるものが愛するすべて」があると言うわけで、美しい妻とともにいる時間よりも、仕事を愛しているのである。
【目次】
第一部
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第二部
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
註
ギ・ド・モーパッサン[1850–93]年譜
訳者解題
【訳者略歴】
渡辺響子(わたなべ・きょうこ)
東京大学大学院(総合文化研究科)博士課程単位取得退学。パリ第三大学で文学博士号取得。現在明治大学法学部教授。専門はゾラ、サンド、モーパッサンを中心とする19世紀フランス小説。訳書にアラン・コルバン『レジャーの誕生』、『記録を残さなかった男の歴史』(以上、藤原書店)、ダニエル・ペナック『エルネストとセレスチーヌのお話』(銀の月)他。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、ギ・ド・モーパッサン『モン゠オリオル』をご覧ください。
