
氷の上は何故滑るのか?
「氷の上が滑るのは、圧力や摩擦で溶けてできた水が原因」と長く考えられてきましたが、必ずしもそうではないようです。
いえ、氷が溶けて水ができれば、水の層によって滑るのは間違いないんです。スケートで氷の上をすべると、一瞬氷は溶けて水になり、また氷に戻ります。この現象を復氷(ふくひょう)と呼びます。
ところが、圧力によって氷を解かすには、局所的な圧力が必要です。
水の三相図(気体・液体・固体)を見たことがあるでしょうか?
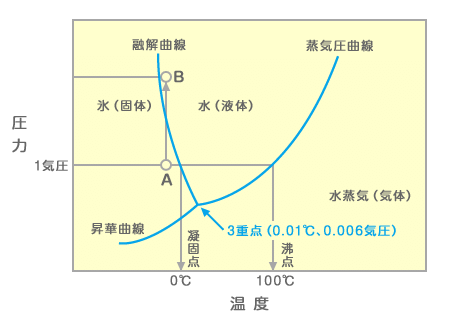
水の三相図:サントリーHP(https://www.suntory.co.jp/eco/teigen/jiten/science/01/)
図の融解曲線を見れば、氷点下で氷(固体)を水(液体)にするためには大きな圧力が必要だと分かります。
体重50~80キロの大人が氷の上にのったくらいでは溶けません。
ところが、氷の上にのれば滑ります(氷点下30℃の極寒の地でも滑ります)。
これはどういうことなんでしょうか?
14日に、マックスプランク高分子研究所の永田勇樹さんという方の講演を聞きました。
この方は、前述した謎を解いた人です。
以下は、永田さんの論文に掲載されている図です。
表面の氷を拡大すると、図の中央のように、水分子が水素結合によって綺麗に並んでいます。内部の水分子は周囲の水分子と結合していますが、表面の水分子は下の方だけ他の水分子と繋がっています。

表面の水分子は移動している(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.8b01188)
表面の水分子は内部の水分子よりも弱く繋がっているため、なんと表面を移動します(図の右側)。
水分子が次々と移動するため、氷の上の物体は滑ってしまうんです。
また、氷は-70℃から既に溶け始めているそうです。
つまり、圧力や摩擦の効果がなくても、氷の上には溶けた水の層が存在しているということになります。
とても興味深いですね。
もちろん、スケートリンクをすべるときには一時的に氷が溶けています。
スケートリンクは最も滑り易い-7℃に設定されていますが、-7℃よりも高くすると、氷が柔らかくなってスケート靴がめりこみ、滑り難くなるそうです(めりこむと言っても、肉眼では分からない程度です)。
読んでいただけるだけでも嬉しいです。もしご支援頂いた場合は、研究費に使わせて頂きます。
