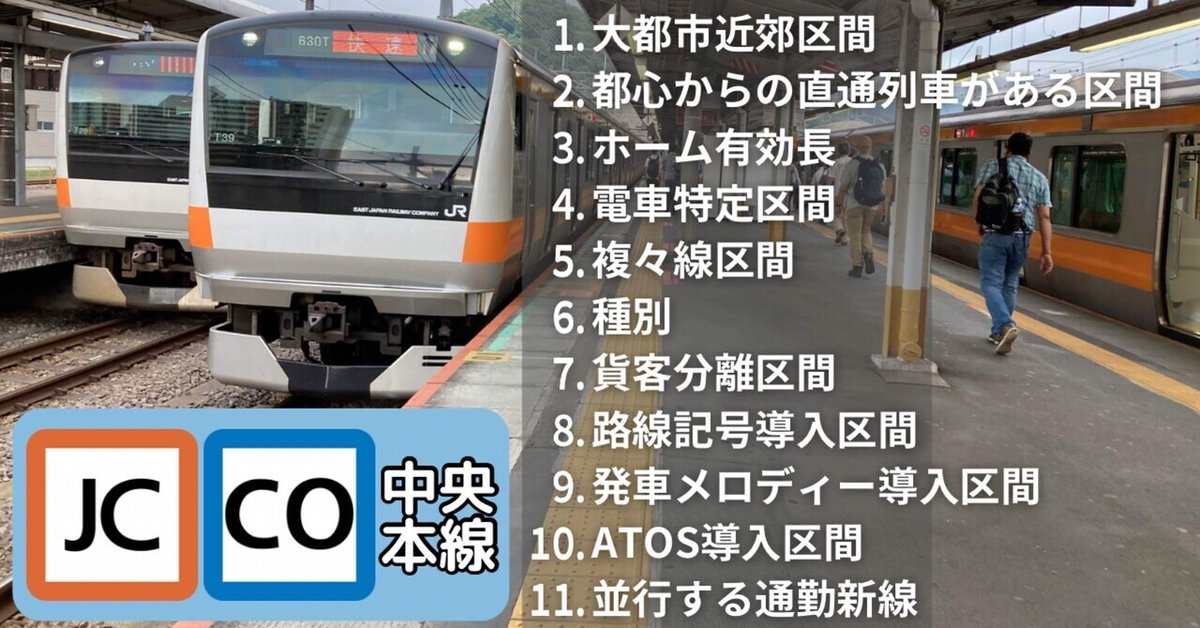
首都圏幹線路線設備まとめ⑥ 中央本線
本シリーズは特別料金不要の列車のみを対象に首都圏の幹線鉄道路線の設備をまとめるものである。具体的には、大都市近郊区間、都心からの直通列車がある区間、ホーム有効長、電車特定区間、複々線区間、種別、貨客分離区間、路線記号導入区間、発車メロディー導入区間、ATOS導入区間、並行する通勤新線の11項目についてまとめる。
※本項では便宜上、走行区間にかかわらず通勤型車両を用いる系統を中距離電車(中電)、通勤型車両を用いる系統をE電と呼ぶ。
概要
中央本線は本来は神田~名古屋間を結ぶ路線であるが今回は東京~塩尻間として扱う。現在電車特定区間内に中距離電車は(立川〜高尾間の数本を除き)存在しないが、かつては青色の普通列車があった。
設備詳細
大都市近郊区間•都心直通区間•ホーム有効長
大都市近郊区間:全区間
(塩尻•長野まで)都心直通区間:高尾•河口湖•青梅まで
(廃止:塩尻•松本•奥多摩•武蔵五日市)12両対応区間:大月•青梅まで
8両対応区間:塩山まで
大都市近郊区間は関東はおろか首都圏ですらない長野県まで伸びており非常に長いが、これは21世紀以降原則としてSuica対応区間は全て大都市近郊区間とするようになったからである。
複々線区間の快速線(厳密には急行線)にはかつて新宿始発の中距離電車と東京始発のE電が混在しており、E電は電車特定区間内(高尾まで)の運転で中電は甲府や松本方面まで走っており、現在の常磐線に近い形態であった。しかし1993年に中電の新宿〜立川間が廃止されE電のみとなる。しかしその後一部のE電(中央快速線)が電車特定区間を越えて大月や河口湖まで直通するようになった。
中距離電車が廃止された理由は、大月以西のホーム有効長が8両(一部駅は6両でドアカット)しかないため中電は8両編成までにする必要があるが、それが都心部で輸送力不足となってしまうためである。
このような経緯から他の幹線とは異なり県庁所在地(甲府)への直通列車が存在しない。
電車特定区間•複々線区間
電車特定区間:高尾まで
複々線区間:三鷹まで
(計画中:立川)
快速線のE電の中には高尾へ向かわず途中の立川から青梅線に乗り入れて青梅へ向かう列車も存在する。かつては奥多摩・武蔵五日市(五日市線)・高麗川(八高線)へも乗り入れていたがワンマン化による系統分離で廃止された。
電車特定区間は高尾までであるが、実際はそこから先の大月・河口湖(富士急行線)までE電が乗り入れている。これは先述した中距離電車の廃止による代替処置である。なお、富士急行線へは中電の211系も乗り入れている。
なお、E電(中央快速線)のE233系0番台は本来通勤型車両だが、近年になってトイレ設置工事やグリーン車連結が行われており、近郊形車両とのサービス上の差異がなくなっている。なお以前はボックスシートがあるというのも近郊形車両の特徴であったが、E235系1000番台が採用しなかったことで条件から外れた。
種別
中央本線では現在以下の種別が運転されている。
中電...なし
※立川以西のみ中電の普通列車が存在(事実上のローカル列車)。立川以東に普通列車が存在した時代の停車駅は中電普通>E電全種別(特快•快速 など)であった。
上記内容はWikipediaを参考にしているが、今後時刻表で調べ、確実な情報が分かれば本記事を更新する。
E電...各駅停車(緩行線)、快速(快速線)、通勤快速(快速線)、中央特快(快速線)、青梅特快(快速線)、通勤特快(快速線)
※高尾以西は普通に種別変更。
かつては中電に以下の種別が存在した。
普通、快速
※E電快速とは異なる
貨客分離区間
貨客分離区間:なし(国立まで)
直接の貨物別線は存在しないが、貨物列車は全て武蔵野線(又は南武線)経由である。
千葉方面からは京葉線経由で、東北・新潟方面からは大宮操車場〜西浦和間の連絡線経由で武蔵野線に入り新小平〜国立間の連絡線を経由して中央本線へ乗り入れる。東海道方面からは品鶴線経由で新鶴見信号場から武蔵野南線(又は川崎貨物駅方面から南武支線経由で南武線)へ入り、府中本町〜立川間で南武線を経由して中央本線へ乗り入れる。
路線記号•発車メロディー
路線記号導入区間:小淵沢まで
発車メロディー導入区間:小淵沢まで
※臨時駅の偕楽園は未導入ATOS導入区間:甲府まで
路線記号の導入区間は都心直通列車が存在しない小淵沢までとなっており、東北本線や常磐線などと比べ桁違いに長い距離である。但し中央快速線としてのナンバリング(JC)は大月までで以西は中央本線(CO)のナンバリングである。これは大月以西にナンバリングが与えられる以前に青梅線•五日市線でJCのナンバリングを使用してしまった結果番号の重複が発生するためであると考えられる。JR東日本管内で首都圏以外に駅ナンバリングが設定されているのは中央本線と大糸線のみである。
ATOS区間も甲府までとかなり長くなっている。
発車メロディーが全駅に導入されているのは小淵沢までであるが、実際は小淵沢から先、長野(松本•篠ノ井経由)までの区間も主要駅では導入されている。
現在は立川以西のローカル運用を担う中電のラインカラーは青である。快速線のE電はオレンジである。
通勤新線
なし
計画中:京葉線(三鷹まで)←中央開発線(武蔵境まで)
新五方面作戦では東京(汐留貨物駅付近)〜立川間の中央開発線が計画され、総武開発線と直通運転をすることとなっていた。その後計画区間は武蔵境(三鷹とする資料もあり)までに短縮された。
総武開発線は形を変えて京葉線として実現したが、中央開発線は実現しておらず現在は新宿〜東京〜三鷹間の京葉線延伸計画として残っている。中央開発線では途中駅(方南町/新浜田山)が建設されるはずであったが京葉線延伸計画では東京を除き途中駅は設置されず全区間が地下線となる予定である。また、三鷹〜立川間の複々線化計画と一体となることが想定されており、実際は蘇我〜立川間で運用されることが考えられる。
まとめ
設備まとめ
大都市近郊区間:塩尻•長野まで
都心直通区間:大月•河口湖•青梅まで
(廃止:甲府•松本•長野)12両対応区間:大月まで
8両対応区間:塩山まで
電車特定区間:高尾まで
複々線区間:三鷹まで
計画中:立川まで中電種別:なし
※立川以西には普通列車がある
廃止:普通、快速E電種別:各駅停車(緩行線)、快速(快速線)、通勤快速(快速線)、中央特快(快速線)、青梅特快(快速線)、通勤特快(快速線)
貨客分離区間:なし(国立まで)
路線記号導入区間:小淵沢まで
発車メロディー導入区間:小淵沢まで
ATOS導入区間:甲府まで
通勤新線:なし
計画中:三鷹まで(京葉線)
特徴まとめ
電車特定区間内には中距離電車は(立川〜高尾間の数本を除き)廃止されて存在しない。
大都市近郊区間が長野県まで伸びている。
E電の快速が電車特定区間外へ直通する。
大月以西のホーム有効長は8両分しかない。
甲府は県庁所在地であるにもかかわらず、都心からの直通列車が特急を除き存在しない。
E電快速の車両は改造によってトイレやグリーン車が設置されたため近郊形車両との差異がほぼなくなった。
かつてはE電と中電に同名で停車駅が全く異なる2種類の快速が存在した。
駅ナンバリングは小淵沢までと導入区間が長くなっている。
駅ナンバリングは大月を境に変わっている。
発車メロディーは全駅(偕楽園除く)導入されているのは小淵沢までだが、実際は塩尻まで多数の導入駅が存在し他路線よりも積極的である。
通勤新線は各方面の幹線で唯一現在も計画途中である。
参考サイト
出来る限り信頼性のある情報を使用していますが、一部でWikipediaや個人サイトを利用しています。
路線概要
大都市近郊区間
ワンマン化による系統分離
https://www.jreast.co.jp/press/2021/hachioji/20211217_hc01.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2022/hachioji/20221216_hc01.pdf
電車特定区間
複々線区間
路線記号
https://www.jreast.co.jp/press/2016/20160402.pdf
発車メロディー(発車ベル使用状況 様)
ATOS
通勤新線(草町義和 様/一般社団法人建設コンサルタンツ協会 様)
https://www.jcca.or.jp/infra70n/files/PJNO_06.pdf
最後までお読み頂き有難うございました。このシリーズではこれまで東海道本線、東北本線、常磐線、総武本線を紹介してきましたが、今回が最終回となります。読んで頂きありがとうございました。
今後は未定ですが、私鉄編をやるかもしれません。引き続きガサキ鉄道のnoteを宜しくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
