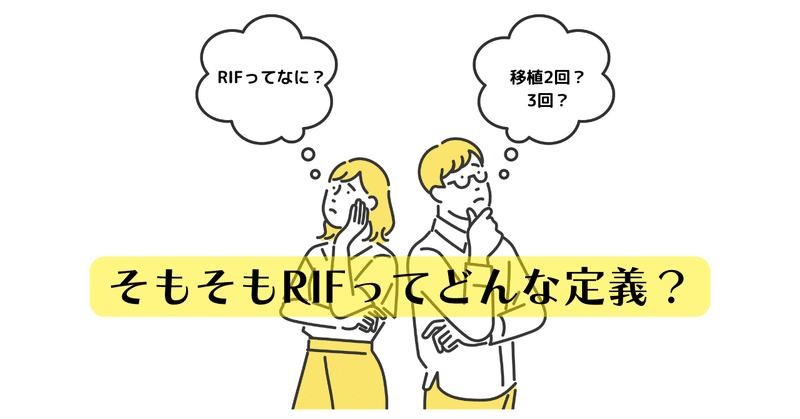
RIF(反復着床不全)って誰が決めたのという話
以前からERA検査が妥当性がどうだ!ということで、標的にされています。
個人的には、ERA検査なのか?ということを感じていて、
そもそも反復着床不全(RIF)って何なんだろう、というところを感じていました。
PGTを行わない場合、形態的な良好胚を移植した時の妊娠率が40%だとした場合、2回連続で移植に失敗すること自体はそんなに稀じゃないはずです。
4割バッターが今日は5打数無安打、みたいなことはどうしたってありえるのと同じことです。
PGTが進まない状況の中で、子宮内膜の環境に活路を見出そうとした結果、過剰に評価されてきた可能性は否定できないと思いますし、でもそれで誰が悪いということじゃないのかなと。
実際、その検査を行い、妊娠された人も「有意差」が出ないとしてもいるわけですし。
ただ、これだけいろんなデータが出てきた中で、冷静にもう一度反復着床不全の定義を決めていくべき時なんじゃないのかなと思うのです。
そんな中で、まさにそうした提案をしている論文に出会ったので紹介します。

なかなか刺激的なタイトルですね。
生殖医療の国際専門家が2022年7月1日にスイスのルガノで集まり、RIFのさまざまな側面を検討し、診断とその適切な管理を定義したというのが、このLugano Workshopというもののようです。
このようなワークショップが開催された背景には、
いささか、RIFというものが、過剰に評価され、治療や検査をされてきたという風にこの有識者たちは考えているようです。
実際に、本当の意味でRIFとなりうる方は、不妊症患者の5%ほどであろうとこの方々は定義しており、3回正倍数性の胚盤胞移植を行っても妊娠しない場合にRIFと定義すべきではないか、と言われています。
日本では、ようやく先進医療BでPGTが行われようとしている中、どのように3回の正倍数性移植を行えば良いのかは疑問ではありますが、曖昧とされてきた定義が見直されるきっかけとなるかもしれませんね。
かなり細かく調べられている論文なので、詳細を今後紹介していきたいと思います。
よろしければサポートをお願いします! 主に、不妊治療や若年がん患者の方の妊孕性温存に関する情報収集の書籍代や活動費用に充てさせていただきます。
