
長崎観光入門②長崎の文化
「観光」はもともと、その地の文化と切り離せない。長崎は京都のように壮麗な建築物が多数残っているわけでもなく、富士山のような自然景観に優れているわけでもなく、ただその歴史と文化がよりどころ。
今回の講義の狙いは、最初のスライドで示したとおり。

長崎の文化の基本構造
長崎の文化を「和華蘭(わからん)」文化と呼んだりする。長崎市公式観光サイトでも次のように記されている。
「鎖国時代が始まってからも、長崎(和)だけはオランダ(蘭)と中国(華)との交易が許されていたことから、それぞれの国の文化が混ざり合って、独自の文化が育まれてきました。異国情緒あふれる雰囲気は今に引き継がれ、「和華蘭(わからん)文化」とも呼ばれています。」
https://www.at-nagasaki.jp/education/article/learning/culture
前回と同じように、人工知能にまとめてもらってみた。
和華蘭文化とは、日本(和)、中国(華)、オランダ(蘭)が交わった長崎独自の文化です。鎖国下でも日本唯一の海外との交易窓口であった長崎は、西洋や中国などの影響を受けた独特な文化を育んできました。
By Google Gemini
※ 「長崎観光入門」の参考書として推奨しているのがまさに「わかる!和華蘭」
「和」
和華蘭の「和」は日本。開港以前の長崎は当然ながら、和の要素のみ。ベースの姿は近隣地域に残る。

長崎近郊には、長崎開港前から連綿と繋がる民俗文化が息づく。これらは佐賀や福岡、熊本など長崎の近隣地域に広がる和の文化と同じ系統のもの。和華蘭文化というが、基盤である「和」の部分が本体であって、その上に華や蘭が乗っかっている。
「和」は日常の何気ない部分に埋め込まれているので目立たない側面もあるが、他方で、「和」には奇抜な伝統もかなり多い。長崎でも、手熊や柿泊には、「モットモ」という行事がある。モットモの起源を示す文献などはないが、「日本の節分行事の地域的特色や変遷を理解する上で注目される」として、2015年に国の無形民俗文化財に採択された。
長崎新聞ウェブサイトより
NCCウェブサイトより
「奇祭」と言われるこの行事、長崎県内には他にも「奇祭」が多い。五島の「へトマト」など奇祭の代表例だ。
五島市観光サイトより
長崎だけが異質なのではなく、「和」は普段着の部分から、「奇祭」のような特別な日の部分まで変動幅が大きい。江戸時代の天保年間(1830年代)には「蝶々踊り」が流行した。(下記大阪歴史博物館ウェブサイト参照)
「華」
長崎の「華」(チャイナ文化)の部分は、「和」の基盤の中に染み込んで一体化したもの。葬祭にも色濃く及んでいる。長崎(中心地)の墓地は、「金文字、土神さん」が多い。金文字の墓(私の家の墓の画像参照)は、長崎とその近隣地域(北部九州にまだら状)に広がる。また、墓の横に「土神」さんをまつってある墓地も多い。これらはチャイナ文化の影響だ。

これは、他の地域の墓地と比べるとよくわかる。各地に広がる親族の墓地を並べると、金文字などひとつもない。

現代中国の墓地を調べてみると、石材店さんのウェブサイトで紹介しているものがあった。これをみると金文字のものもあり、チャイナ文化の一系統であることがわかる。
長崎ではお盆に墓地に親族が集まり花火をしたり、精霊船の進む道に爆竹を投げて邪気を払ったりしているが、これも影響を受けている。
「蘭」
さて、「蘭」である。「蘭」は文字通りに捉えれば、オランダ(阿蘭陀)のことだ。しかし、オランダは最初から出島に限られていたので、長崎文化への影響は「華」に比べて顕著に少ない。食文化などにはオランダ以前に交流が深く、長崎開港にかかわったポルトガルの影響が残る。
これは、ポルトガル人は長崎市中に雑居していて日常的な接触があった時代もあったのに対し、オランダはポルトガル人を収容するために建設された人工島・出島に最初から居住していたためだ。幕末開港の後は英国その他のヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国の人々も来たため突出せず、「蘭」=オランダの要素は「和華蘭」のうちでも薄い。

ラーメンで言えば、基盤となる「スープ、麺、チャーシュー、ねぎなどの薬味」という基本構造(和)に、ふつうと違う風味の豚骨スープ(華)がゆきわたり、ごまとスパイス(蘭)がぱらぱらっと振りかけられたかたちが和華蘭文化のそれぞれの割合に近いように思う。
わずかに残る東南アジアの面影
「あごばた」とよばれる、現在の長崎のハタは、1600年代前半に出島にやってきたインドネシア人から伝えられたと言われており、ハタの文様も白と青と赤の3色、オランダ船の船旗や信号標識旗をデザイン化したと思われるシンプルなものが多く、異国との唯一の窓口であった長崎の特色を出しています。(長崎市「長崎Webマガジン『ナガジン』」より)
インドネシアと隣接し、ポルトガルやオランダが拠点としていたマレーシア・マラッカの凧をみると長崎の「ハタ」と似た形をしており、文化的遺伝子があるのではないかと気になります。(下記「マレーシアの凧」のサイト参照)
これらの「東南アジアの面影」は、ヨーロッパが東南アジアを通って長崎までやってきたこと、長崎から東南アジア各地に人や船が出向いていた時期があったことが背景にあり、前回講義「長崎の歴史」で述べた世界とのつながりがある。



https://aseanpedia.asean.or.jp/partnership_history/

食文化(缶詰、パン、等々)の長崎事始めは非常に多い。
年中行事
再び戻るが、長崎の「和華蘭」文化は年中行事に色濃く残り、また、和の要素が中核にあることがよくわかる。















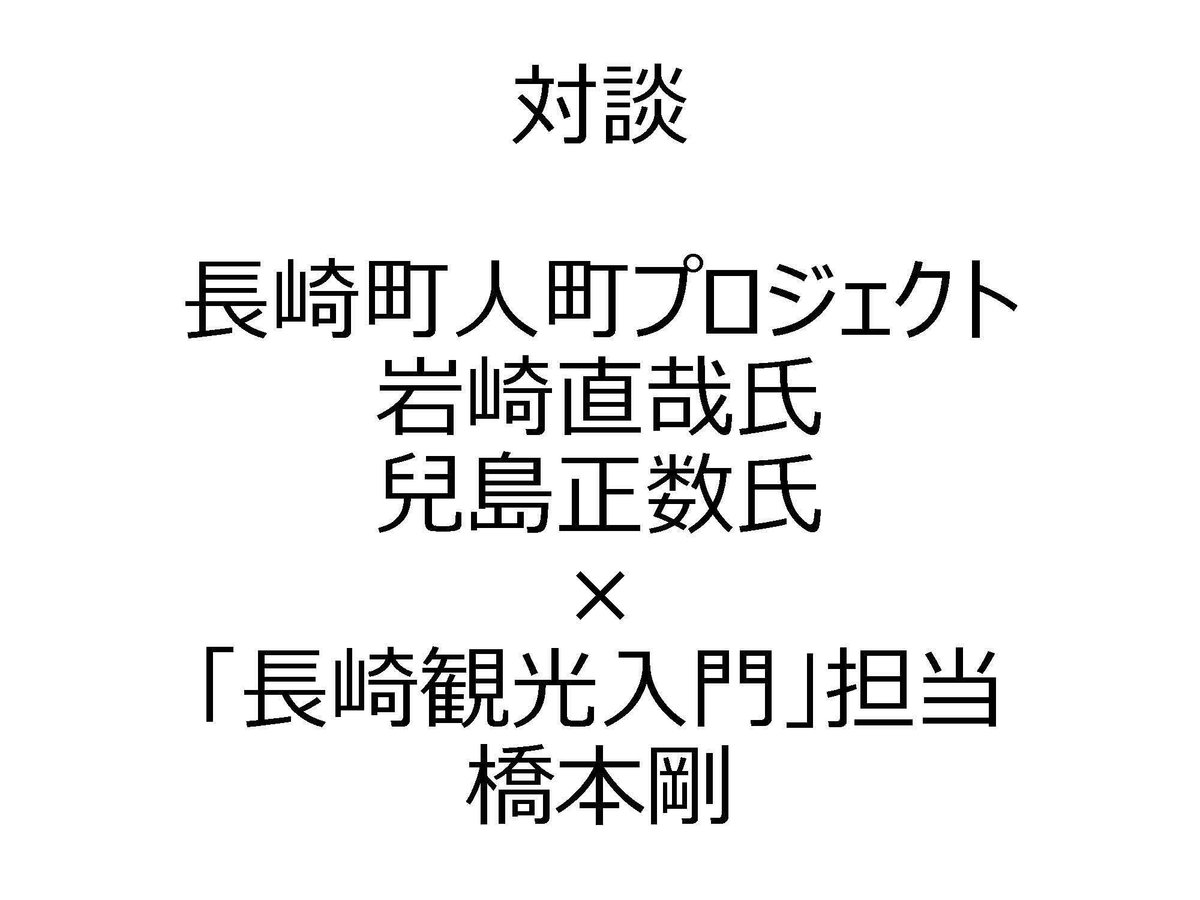
「長崎の文化」の講義では、後半に「長崎町人町プロジェクト」の岩崎直哉氏と兒島正数氏を交えたパートとした。「長崎町人町プロジェクト」は、2012年に発足したプロジェクト。和華蘭と呼ばれる長崎の伝統的な文化を体現するエリアのうち、「華」は中華街、「蘭」は出島や居留地といった明確な地理概念もあるのに、「和」は色濃く残しているエリアすら「寺町、中通り、中島川…あたり?」とネーミングもない。町人が暮らした町という意味でもあり、町と町の間に「人」がいるという意味も込めて名付けたプロジェクト名だ。エリアのことに触れたが、当初から「マップではなくカレンダー」と言い続け、「長崎歳時記」を展開している。


岩崎直哉氏から、長崎の文化文化面からみた広がりについての話が冒頭あった。長崎というまちは、その中心に、くんちの踊町だった「77ヶ町」と、遊郭があった「寄合町・丸山町」、それに人工島「出島町」の計80ヶ町から構成される中核部分があり(くんちも77ヶ町が7年に1度、11ヶ町出ていた。出島町は外国人だから出ず、寄合町・丸山町は交代で毎回出ていた)、その外側に小島郷その他の「神輿守町」が広がり、それらが徳川家直轄領としての天領長崎を構成していたこと、宝町以北の浦上エリアは「大村」の領地だったこと、長崎女子短期大学が所在している弥生町が小島郷の一番外れで、バス停の名前になっている「早坂」は島原藩が経営している土地だったことなど、意外な話をいただいた。
実際、江戸期は海だったところが今の平地なので、銭座町付近で山が迫っているエリアが「岬」、その向こうには浅瀬が広がり(浜口、川口)、大村藩の経営する浦上村が遠望できたのだろう。ごく最近まで、その境界の土地に三菱重工業幸町工場があったため、浦上と長崎は電車通り沿いのわずかな市街地で繋がる、くびれの大きいひょうたんのような構造として繋がっていた。これが今、ジャパネットたかた社による都市開発でスタジアムシティができようとしていて、数百年にわたる「長崎と浦上」の境界がつながり、はじめて市街地として一体化する歴史的意義もあると感じている。
岩崎直哉氏・兒島正数氏からは年中行事について解説頂いたが、残念なことに時間切れとなり、端午の節句の唐あくちまきまでで終了となった。長崎観光入門の授業のどこかを使って残りの話もできればと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
