
《新古小説十二題(二)》田山花袋『蒲団』:画文の人、太田三郎(11)
1 芳子の帰郷
『ハガキ文学』第4巻第2号(明治41年2月1日)の口絵木版、《新古小説十二題》の2回目は、田山花袋の『蒲団』を取り上げている。
『蒲団』は、雑誌『新小説』の明治40年9月号に発表された。太田はこれを読んで、《新古小説十二題》に取りあげたものと推測される。
中年にさしかかり人生に迷いを感じ始めている竹中時雄という小説家が『蒲団』の主人公であるが、文学を学びたいという希望を持つ横山芳子という若い女性を下宿させることから、単調な生活に波乱が起きることになる。
竹中は、芳子の保護者としての役割を担うことになるが、徐々に芳子に惹かれてゆくことを自覚する。芳子はやがて、田中という大学生と恋愛関係になり、竹中は芳子の父にそのことを連絡し、結局芳子は帰郷することになる。
この小説が話題になったのは、その結末で、新橋駅まで帰郷する芳子を見送りに行った竹中が、帰宅すると芳子の生活していた二階に上がり、芳子の使っていた蒲団を取り出して残り香をかぐという場面が描かれたことが大きく影響している。
隠しておくべき事柄があからさまに描かれたというように読者は感じたのである。
しかし、いま読み直すと、結末の場面よりも、竹中時雄がどうしようもない俗物であるのにもかかわらず、西欧の新文学思想の理解者を気取っているという矛盾にたちどまらざるをえない。
太田三郎が絵にしたのは、「十」の父が迎えに来て、いよいよ芳子が帰郷する支度をしている場面である。太田の添え書きとは若干文言がことなるが、『蒲団』の引用は、以後も岩波文庫版『蒲団・一兵卒』(2005年5月6日、5刷)によることとする。
三年前、青春の希望湧くがごとき心を抱いて東京に出て来た時のさまに比べて、何等の悲惨、何等の暗黒であろう。すぐれた作品一つ得ず、こうして田舎に帰る運命かと思うと、堪らなく悲しくならずにはいられまい。
引用の直前には、「東の窓を一枚明けたばかり、暗い一室には本やら、雑誌やら、着物やら、帯やら、罎やら、行李やら、支那鞄やらが足の踏み度もない程に散らばっていて、塵埃の香が夥しく鼻を衝く中に、芳子は眼を泣腫して荷物の整理をしていた。」とあって、かなり忠実に再現した画像となっていることがわかる。

『ハガキ文学』第4巻第2号(明治41年2月1日)木版口絵
この日の午後6時発の神戸行き急行で、芳子は父に付き添われて帰郷することになっている。恋愛の相手の大学生田中が面会に来るが、芳子に会うことは許されない。
保護という名のもとで、父の娘に対する支配が際立つ場面である。
2 竹中時雄の二重基準
食事をとることを勧めたとき、泣き始めた芳子を見て、竹中は次のような感懐を抱く。
時雄も胸を衝いた。師としての温情と責任とを尽したかと烈しく反省した。かれも泣きたいほど侘しくなった。光線の暗い一室、行李や書籍の散逸せる中に、恋せる女の帰国の涙、これを慰むる言葉もなかった。
このように、『蒲団』では、竹中時雄の内面に踏み込んだ描写が多く見られる。竹中の主観が偽りのないものかどうかはよく考えてみなければいけない。竹中は芳子の無念さに共感し、また「師としての温情と責任とを尽したかと烈しく反省した」というが、これは世間の視線に対してよい人として受け取られるような演技をふくんではいないだろうか。
竹中は、かつては芳子に次のようなことを述べている。
「女子ももう自覚せんければいかん。昔の女のように依頼心を持っていては駄目だ。ズウデルマンのマグダの言った通り、父の手からすぐに夫の手に移るような意気地なしでは為方が無い。日本の新しい婦人としては、自ら考えて自ら行うようにしなければいかん。」
芳子に自立を勧めながら、いざ芳子が自由に振る舞うと、竹中は「父の手」に芳子を返す動きに加担する。
「ズーデルマンのマグダ」とあるのは、ドイツの作家ヘルマン・ズーダーマン(Hermann Sudermann 1857−1928)の戯曲『故郷』(1893年)のことである。退役陸軍中佐シュワルツェの先妻の娘マグダは、親の勧めた結婚を拒絶して家を出る。マグダはオペラ歌手として自立し、シングルマザーとして子どもを育てている。マグダは帰郷して父と再会するが、父シュワルツェはマグダを赦すことはできない。
マグダは芳子とはまったく異なる生き方を選んでいる。もし、竹中が本気でマグダの生き方を推奨するならば、芳子の父を説得し、芳子と田中の恋愛の後押しをしなければいけないはずである。
だが、竹中は保守的な芳子の父親に同調するばかりだ。
また、「神聖な恋」、すなわちプラトニックな恋愛をのみ認めて、霊肉をともに許す恋愛を認めないという竹中の思考は、当時の規範意識の影響を受けているとしても、偏執としか言いようがなく、見事に芳子を抑圧する根拠としてはたらいている。
竹中には、西欧文学から得た新思想を称揚しながら、芳子の恋愛は認められないという二重基準の欺瞞があった。語り手はそのことをあらわにするが、登場人物の竹中はそのことに無自覚であるように描かれている。その描き方に花袋の手腕が発揮されている。
3 芳子を描くという選択
《新古小説十二題》は、木版挿絵を1枚作り、そこに作品の一節をそえるという画文共鳴の試みであるが、『蒲団』では、竹中時雄ではなく、横山芳子を描いている。
最も内面が描かれる登場人物である竹中を描くという選択は自然であるが、どの場面にするかというとなかなかむずかしい。よく知られたラストシーンは検閲のことを考慮しなければならない。
新橋駅の場面は、すでに先例がある。雑誌『新小説』明治40年9月号の口絵は、『蒲団』の新橋駅の場面を描いている。
『明治文学の彩り 口絵・挿絵の世界』(日本近代文学館編、責任編集出口智之、2022年8月、春陽堂)に図版が掲載されている。二等待合室にいる芳子と父親を室外から見る竹中、その背後にそっと見届けに来ている田中の立ち姿が描かれている。口絵の解説では次のように記されている。
師の時雄から破門を言い渡され、汽車で郷里に帰る芳子と父親、それを見送りに来た時雄、その後方の雑沓のなかに佇む芳子の恋人、田中を描いている。 芳子に対して都合のよい「空想」を一方的に投げかける時雄は、実は芳子が自分の背後にいる田中を見ていることに気がつかない。また、芳子の内面がはっきりと記述されない、時雄視点の小説であることに見事に照応して、芳子の表情は隠されている。登場人物の関係性を象徴する口絵となっており、豊かな含意をみるとやはり作者花袋の指示のもとに描かれたものと考えられる。
この口絵の作者は、小林鐘吉(1880-1946)。東京美術学校西洋画選科に明治32年入学、明治36年卒業。白馬会原町洋画研究所の指導を担当し、田中恭吉や藤森静雄を教えた。『画行脚』(明治41年5月、彩雲閣)という、紀行文と挿絵を合わせた本を出している。
岩波文庫版『蒲団・一兵卒』のカバーにモノクロであるが、口絵が載っている。
小林はさすがに洋画育ちらしく、駅構内の奥行きを立体的に表現している。
複数の主要人物を配しているのは、物語を見渡すという口絵の機能を意識した結果であろう。
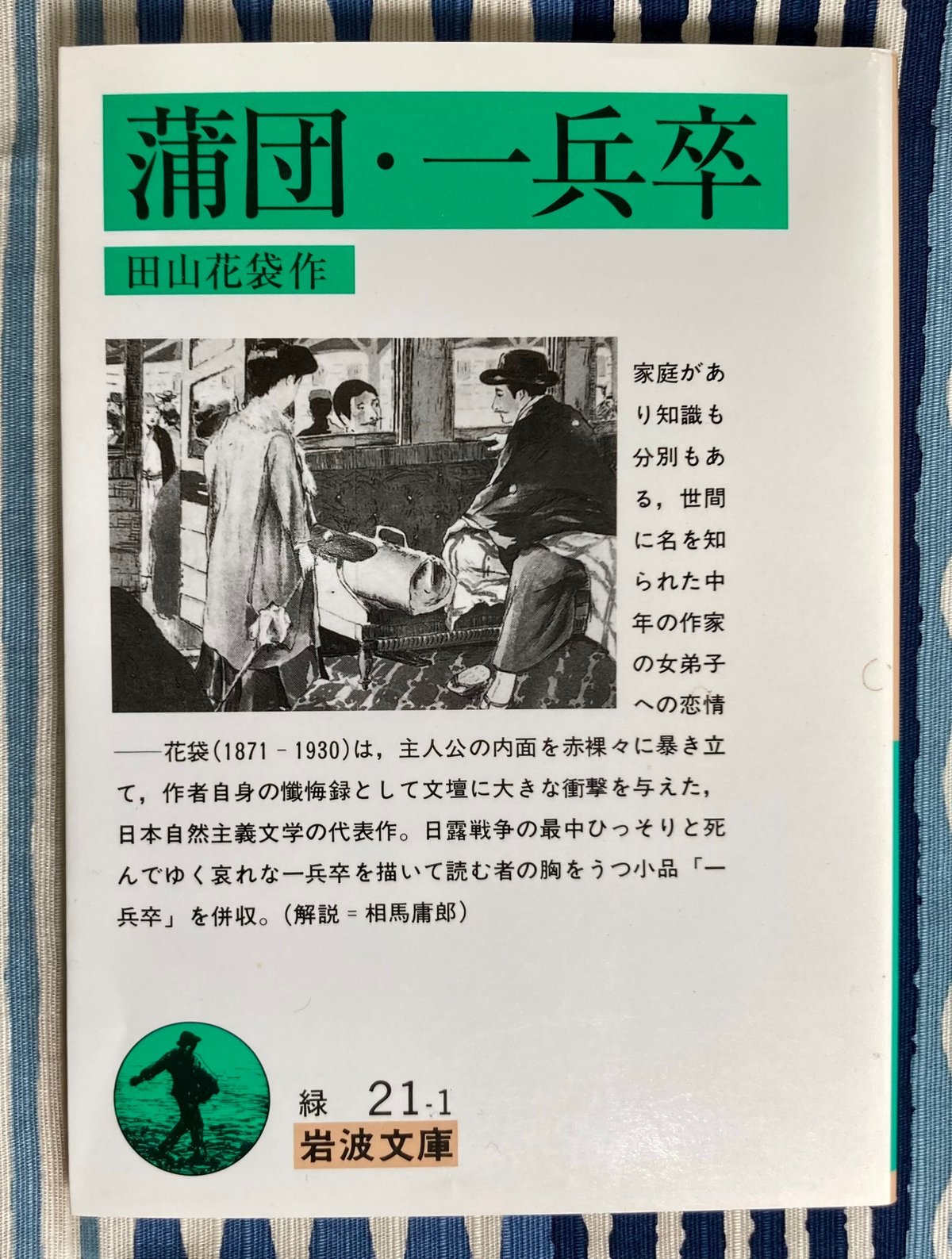
太田はおそらくこの口絵を見て知っていたのであろう。『蒲団』が収録された『花袋集』(易風社)の刊行は明治41年3月であり、太田は初出の『新小説』で読んでいる可能性が高いからである。
竹中を描かず、また複数の人物も描かずに、翼が折られた芳子だけを描くという太田の選択は、それなりの見識を示している。
竹中の二重基準の犠牲になって、芳子の翼が折られたと見ることもできるからである。
芳子の顔は隠されている。〈泣き伏す女性〉というモチーフは繰り返し使われた定番化した画像である。
以前《渡辺与平と竹久夢二》というブログ記事で、コマ絵の〈泣き伏す女性〉モチーフを取りあげたことがある。
芳子の悲劇が、ステレオタイプの〈泣き伏す女性〉に帰結するというのも、一つのアイロニーを示しているのかもしれない。顔を描かないのも、非個性的な悲劇であることを語っている。
太田の画像の作り方を見ていると、挿絵の描き方の文法のようなものが見えてくる。映画のカメラにたとえて考えてみよう。カメラ位置は、部屋を若干ななめからとらえている。そのほうが変化が出る。積まれた雑誌、卓上の書物は芳子の文学への夢の痕跡を示している。
カメラの高さは意外に低い。立った視点ではなく、座った視線からとらえられているような感じがする。
芳子の足袋の足先の表現が気になる。もしかしたら、浮世絵の伝統に従っているのかもしれない。
色数は3色か。薄い黄色(鳥の子色)で地を刷り、薄い緑(柳色)で着物などを表現。黒で卓や輪郭線を表している。褐色に見えるところは、色を抜いた紙の地色の部分だと思われる。酸化のため褐色に見えるが、もとはもっと白みがあったと推測される。
最後に一つだけ深読みを示しておこう。泣く芳子を描いた太田の絵に、じつは竹中が存在しているのではないかということである。
映画の手法に主観カメラというのがある。登場人物の視点で映像を撮るのである。
主観カメラを応用すると、太田の絵は、竹中の視点から見た芳子をとらえているとも理解できる。
太田が絵に添えた引用では、「すぐれた作品一つ得ず、かうして田舎に帰る運命かと思ふと、堪らなく悲しくならずには居られない」とあるが、原文は「居られまい」という否定的推量で終わっている。「居られまい」という表現は語り手が竹中に寄り添った表現であり、泣く芳子を見た竹中の感懐ととることもできる。
それは同情を示しているようで、じつは白々しい酷薄さを隠している。帰郷する以外のほかの選択肢、別の道に向かう未来が封じられていることをやすやすと受け入れてしまっているからである。
竹中の視線によって芳子がとらえられていることを意識すると、人々が従っている規範的観念が覆い隠すものの大きさということに、思いが至る。
自分は一貫して誠実だと信じてやまない竹中の二重基準が読者にはあらわにされるが、〈泣き伏す女性〉というわかりやすい類型的イメージの向こう側に固有の悲しみが隠蔽されてしまっているという気がしてならないのである。
*ご一読くださりありがとうございました。
